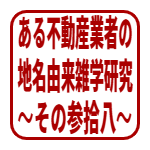


[水戸徳川家や徳川慶喜の食に関して・その一端]
徳川慶喜は、生後7カ月の頃から、父・徳川斉昭(※烈公のこと)の教育方針によって水戸で養育されたため、当然に水戸徳川家の「食育」と云うものが、この人が口にする食べ物に影響してまいります。
そして、この水戸徳川家(水戸藩)は、代々・・・現在の茨城県常陸太田市折橋町の山中で、「牧場経営」や「林業経営」をしており・・・実際に、海外から輸入した牛を飼育して、その牛から搾乳した牛乳を飲んだり・・・発酵させたバターを作って、それを食すなど、全国諸藩の中でも珍しいお家柄だったと云えます。・・・これらも、遡れば徳川光圀(※義公のこと)に辿り着く訳ですが。
江戸時代を通じて観ても、「牛乳」や「バター」は、当時ほとんどの日本人には縁が無かった訳です。当然に、オランダなど諸外国との窓口とされていた長崎出島や、その関係者、関係各藩などは除外されますが。
徳川慶喜の曾孫に当たる徳川慶朝氏の著書『徳川慶喜家の食卓』では、水戸徳川家の関係者が、当時は貴重品とされていたものを、ごく日常的に食していたことが分かります。
・・・何でも、“徳川慶喜の異母妹・八代姫(やちよひめ?:※徳川斉昭と側室・松波貞子の娘で、鳥取藩主・池田慶徳や岡山藩主・池田茂政の妹、後の伊達孝子のこと)が、乳牛とその世話係(≒飼育員)とともに、陸奥仙台藩主・伊達慶邦の継室に嫁いだ”とか。・・・尚、この「八代姫」の写真も現存していますが・・・当時、「徳川美人三姉妹の次女」として持て囃(はや)されたとか。これには、もちろん水戸徳川家(水戸藩)としての対面上も、箔を付けるという意味合いもあったのでしょうが・・・きっと、牛乳を良く飲んで、骨格頑丈となり、今に云う「健康美人」になられていたのかと。・・・残念ながら、伊達慶邦の継室となった「八代姫」こと「伊達孝子」は、28歳の若さで亡くなって、子は為さなかったようですが。
・・・いずれにしても、水戸徳川家の家風としての「食」に対する拘(こだわ)りがあって、更に儲けた子女が37人と謂われる父・斉昭の哲学思想などによる教育方針が加わる訳です。
その父・斉昭の「食」に関しては・・・斉昭は、鯨肉を食べるなど、大の肉食家として知られ・・・彦根藩から「近江牛の味噌漬け」を贈られた際には、返礼状を出していたり(※当然に「安政の大獄」が起こる以前のことですが)・・・他にも、“徳川斉昭本人が実際的研究によって親撰して記した”とされる、江戸時代の料理レシピ集『食菜録(しょくさいろく)』の原本が、水戸彰考館に大切に保存されており、上、中、下の三巻から成るとのこと。
また、この書本は・・・「斉昭公の多年の心血を注ぎ纏められたもので、当時の調理法(≒レシピ)三百種ほどが記載せられ、未だ世に公にされざる誠に得難い貴重なる文献である」・・・と、石島績(いしじまいさお:※茨城県下館保健所〔現茨城県筑西保健所〕の初代所長などを務めた郷土史家)氏が著した『水戸烈公の医政と厚生運動 下巻(日本衛生会・1943年〔昭和18年〕9月)』の評価もありますが・・・
『食菜録』の中で、斉昭は「牛乳は精力剤である」と説明し・・・また、“自らの庭(※おそらくは、江戸屋敷と水戸城の区別無く)にて乳牛を飼って、健康のため、搾乳された牛乳を、ギヤマン(※江戸時代から明治時代初期頃に掛けて用いられたガラス製品を意味する外来語であり、別名は切子とも)の器に入れて飲んでいた”とか。
・・・これらのレシピと云いますか、研究成果? 料理指南? が上・中・下の三巻を通じて、ちょうど300項目あるのですが、表現方法が豊かなことなど、これはこれで、とても興味深いので・・・概ね前述の「石島版食菜録」を元に、以下に「備忘録」として残します。常陸那珂川を遡上する「鮭」に関する記述も多く、他にも「へぇ~」と想えるものが多々ありますが、中でも「パンの法 中濱萬次郎咄」なんていうのもありますよ。もちろん「中濱萬次郎」とは、あのジョン・萬次郎のことです。料理方法や水戸徳川家(水戸藩)、徳川斉昭、徳川慶喜研究の史料として、是非ご利用下さい。尚、現代では入手困難、若しくは入手を禁じられている食材もありますし、料理画像も付きません。・・・あくまでも、私(筆者)の解釈等を含みますが。(↓↓↓)
上巻1【正宗流(しょうしゅうりゅう) 鮭(さけ)の鮨(すし)】・・・ここにある「正宗流」を、つい「まさむねりゅう」と読んで、当時の刀鍛冶や包丁鍛冶、料理流派の一派のように捉えてしまいそうになりますが・・・私(筆者)は、“現茨城県常陸太田市増井町にある正宗寺(しょうしゅうじ)など常陸太田周辺で培われた伝統的な料理等などを、著者・徳川斉昭が敢えて表現したものだ”と考えます。この「正宗寺」は、元々は常陸佐竹氏との関係が深い寺院ではありますが、徳川斉昭が敬愛するご先祖・徳川光圀が暮らした隠居所「西山荘」や水戸徳川家の墓所「瑞龍山」がありますし、初代藩主の頼房以来、歴代の水戸徳川家当主からの尊崇も厚く、水戸藩領内における有力寺院となっていたからです。また、常陸那珂川を遡上する鮭に関する料理を、この『食菜録』の一番目に掲げるところなどは、水戸藩士や領民達に向けて、実践的で役立つ情報をご当地グルメ雑誌的でも構わないので、読んで貰いたいとの著者の気持ちが伝わってまいります。おそらくは、徳川斉昭が敬愛するご先祖・徳川光圀が作製させた家庭療法本『救民妙薬(きゅうみんみょうやく)』にも通じる哲学があったのだろうと考える次第です。
「新しき鮭(さけ)三枚におろし、一日一夜塩押(しおお)しをして(=一日一夜の間、塩をふり重石を載せて漬けておいて)
、明日鮨(すし)に漬(つ)け申し候。右(=鮭を)
塩水にてよく洗いあげ、上白米常の食よりは(=上白米を普段食べる米飯よりも)
、少しこわめに致し(≒少し固めに仕上げて)
、米五升に糀(こうじ)二升二合の割合に混ぜ合わせ、酒五合、食(しょくすは)、糀(こうじ)へ合わせ、魚のすり(=摺り)合い申さぬように、飯たくさんに置き申したるがよく候。重(おも)しは大方(おおかた)常の加減に候。重(おも)しの上へ、塩水に酒を少しく加え、この水を溜めて置き申し候。鮨乾き申し候えば、悪(あ)しくなり申し候。醤(ひしお)も入れ申し候。取り出し候て後、蓋(ふた)重しをして、又(また)右(=塩水に少し酒を加えておいた調理用)
の水を溜め置き申し候。」
上巻2【同(※上記にある 正宗流のこと) 鮭(さけ)の黒漬(くろづけ)】・・・仙台風? もとい、正宗流・鮭の黒漬か?
「鮭(さけ)の新しきを三枚におろし、又(また)二つ三つに切り候ても、そのままにても五日程、塩押し(※塩をふり重石を載せて漬けること)にして、その後、玄米を蒸して漬(つ)け申し候。米一斗に、糀(こうじ)二升入れ、よくもみ(=良く揉み)
合わせ、飯一通り、鮭一通り置き、その上へ薄霜(うすじも)の加減に塩をふり(=振り)
、飯をたくさんに入れ漬け申し候。重(おも)しも常の鮨よりは、重く置き申し候。 来年までも耐(こた)え申し候。春の末、夏秋の時分、右のこと(≒前述した一連の作業を)
当座当座に鮨に直し遣(つか)わし申し候。鮨に漬け候時、鮭食べ候て見候て、塩辛くば塩を出し申すべく候。」
上巻3【鮎(あゆ)の鮨(すし) 但し、美濃漬の流(ながれ)】
「新しき鮎(あゆ)を腹をあけ(=開け)
、少しも洗い申さず、そのまま一日にても、一夜にても塩押し(※塩をふり重石を載せて漬けること)にして、明日(=翌日に)
その塩水にてよく洗い、その時、えら(=鰓)
を取り、その上を一遍(いっぺん:=一度)
よき水にて洗い、焼き見候て、少し塩辛めなるがよく候。上白米の飯、冷え候ほど冷まし、腹へ成程(なるべく)よく込(こめ) 申し候。飯を握り、腹へ入れたるがよく候。その外(ほか)の飯をば一遍(=一度)
洗い、雫(しずく)をよくたらし(=水気を良く切り)
食たくさん(=沢山)
に漬け申し候。早く食べ候わんと存じ候えば、少し軽めに重(おも)し置き申し候。又(また)少し久(ひさ)しく置き申し候には(≒また少し長持ちさせる際には)
、重(おも)しを強く置き、蓋(ふた)の上に塩水を溜め候て押し申し候時、塩水をあけ(=開け)
取り出し、蓋(ふた)をし、重(おも)しを置き、又(また)塩水を溜め置き申し候。」・・・「鮎」も水戸藩領の那珂川や久慈川水系で良く獲れましたし、“美濃漬の流れ”とされていることも納得できますね。
上巻4【白魚(しらうお)の鮨(すし)】
「白魚一夜塩を仕(つかまつ)り候。但し、重(おも)しは仕(つかまつ)らず候。鮨に仕(つかまつ)り候時、右(≒重し無しで一晩置いた塩ふり白魚を)
塩水にて洗い、雫(しずく)をよくたらし(≒良く水気を切って)
、飯は上白米、常より強(こわ)めにいたし飯を洗い申さず、白魚を飯ともみ(=揉み)合わせて 、桶(おけ)に入れ、重(おも)しは成程(なるべく)つよく(=強く)
置き申し候。この鮨は久(ひさ)しくは居(お)き申さず候(≒この鮨はあまり長持ちしないので注意すること)
。」
上巻5【うなぎ(=鰻)のすし】
「鰻(うなぎ)をよく洗い、雫(しずく)をたらし(=垂らし)、三つ四つほどに短く切り、一夜酒に塩を喰い塩(くらいじお)より辛めに混ぜ、これにひたし(=浸し)
、明日飯に塩を喰塩に混ぜ(≒翌日の飯に適量の塩を混ぜて)
、飯を洗わずに、常の如く漬け申し候。重(おも)しは、中の位(くらい)に掛け申し候。」
上巻6【鮒(ふな)の鮨 但し、近江(おうみ)の流】・・・琵琶湖周辺で食される伝統食「鮒ずしの作り方」です。
「寒の内(かんのうち)に、鮒(ふな)を漬け申し候。えら(=鰓)
を取り、えら(=鰓)
より内臓を抜き、頭(かしら)を打ち拉(ひし)ぎ、盆(ぼん)なりとも、重箱(じゅうばこ)なりとも、塩たくさんにため(=溜め)、裏表より蓋、塩の上へ押し付け、つく(=搗く)
ほど塩をつけて(=付けて)
、鮨に漬け申し候。めし(=飯)
は玄米を強めに致し、よく冷まし、飯にも塩を食塩(くらいじお)に混ぜ合わせ、たくさんにつけ(=漬け)
申し候。初めは成程(なるべく)重(おも)しをよく置き、二十日程過ぎて、重(おも)しを常の鮨の加減程に(≒重しが効いた頃合いを観て)
、弱く置き申し候。七十日程過ぎてよくなり候。いつまでも耐え申し候。来年夏秋の時分もきつく香味よく(≒翌年の夏秋の時分には、極めて香味が良く)
、骨も一段と軟(やわ)らかになり申し候。これも重(おも)しを緩(ゆる)め申し候時分に、塩水を蓋(ふた)の上に溜め置き申し候。取り出し候て後、うちの(≒容器内の)
魚飯の肩下がりになきように直し、蓋重(ふたおも)しをいたし、又(また)右の水(=蓋の上に溜まった塩水)
を溜め候て置き申し候。」・・・文頭部分にある「寒の内」とは、「小寒(しょうかん:※寒の入りとも。現在の暦では1月5日頃のこと)」から「節分(せつぶん:現在の暦では2月3日頃のこと)」までの期間を云います。・・・ちなみに、「大寒(だいかん:※現在の暦では1月20日頃のこと)」から2月初め頃までが、人が最も寒く感じる季節であり、また一般的にも「農閑期」となります。
上巻7【雁(かり) 鴨(かも)のたたき(=敲き)
】
「鳥の身も、骨も、細(こま)かにたたき(=敲き)
申し候。鷹野(たかの)にて(=鷹狩りの際に)
仕(つかまつ)り候時は、溜り血(たまりち)をそのまま、その身、骨にかけ(=掛け)
よく混ぜ申し候。締(し)め鳥ならば、背骨に固まり候血をとりて(=取りて)
混ぜ申し候。大鳥(おおとり)にても、小鳥(ことり)にても、としり(=鳥尻)
を切り捨て、腸(わた)もよけ(=除け)
、丸(たま:=弾丸)
はもっとも(=最も)
取り申し候。鳥の分量一升あらば塩を五合混ぜ、手にてよくもみ(=揉み)
合わせ、塩へ入れて、十日程も過ぎて、又(また)取り出し、糀(こうじ)を入れ申し候。(味噌の)
溜(たま)りを入れ候わば、糀(こうじ)二合、さもなくば五合加え申し候。右の糀(=利用した糀)はなおよくもみおとし(=尚良く揉み落とし)
、糀(こうじ)の粕(かす)をこげ色(=焦げ色)
に炒(い)りて臼(うす)にて引き、はな(=糀)と一つにいたし、鳥の中へよく混ぜ、古酒(こしゅ)を少し加え、又(また)よくたたき候て、ひしお(=醤)
の汁さほどに仕(つかまつ)り、又(ま)た壺へ入れ、風のひき候わぬ様に(≒あまり風に当たることがないように)
、口を仕(つかまつ)り七八日程過ぎて、よくござ候。又(また)小鳥も同じ事にて候。雁、鴨新しきを料理に遣(つかわ)し、その胴殻(どうがら)を不断にいたし候てよく候。」
上巻8【雁 鴨の炒り鳥】
「常の如くに身をつくり、古酒(こしゅ)と醤油と等分に合せ、鳥を鍋に入れ、右の汁(≒古酒と醤油とを等分にした調理液は)
ひたひた程か、又(また)鳥に油すくなく(=少なく)
候はば、それは少し控え、炭火(すみび)にて煎り鳥に仕候(つかまつりそうろう)。」
上巻9【小鳥のいりとり】・・・「鶉(うずら)や雀(すずめ)など小鳥の炒り鳥」。
「酒と醤油と水と、等分に混ぜ、花鰹(はながつお:※鰹節を薄くけずったもの)
少し入れ、鍋へ入れ候て、鳥とひたひたほどにして煮申し候。」
上巻10【鳩(はと)のはふじいり】・・・「はふじいり」とは、「焙じ炒り」?
「鳩はと)にても、又(ま)た何(いずれ)にても、骨をたくさんにたたき(=敲き)
入れ、花鰹(はながつお:※鰹節を薄くけずったもの)
を入れ、酒と醤油と等分にして、汁を少なめに、血と腸(わた)付き候程に炒り上げ、又(ま)た他の鍋に、山葵味噌(わさびみそ)をあたためて(=温めて)
置き、そのまま煮ても、又(ま)た物にかけても(=掛けても)
、給(たまい)し申し候。」
上巻11【小鳥だんご(=団子)
の仕様】・・・「小鳥」とは、上記の 上巻9 と同じく、鶉(うずら)や雀(すずめ)などのことです。
「何鳥(なにどり)にても、小鳥を成程(なるべく)細(こま)かに、たたき(=敲き)
、餅の粉、小鳥と等分に混ぜ、摺鉢(すりばち)にて摺(す)り合わせ、湯煮(ゆに)をして、煮物の中へ入れ申し候。団子の大きさ心次第に候(≒団子の大きさはお好みで良いのです)
。」
上巻12【鳥もちの仕様】・・・「(いろいろな)鳥肉」と「お餅」とのコラボレーション料理。「栃もち」ではありません。
「小鳥(ことり)にても、大鳥(おおとり)にても、細(こま)かにたたき(=敲き)
申し候。小鳥は骨をも入れ申し候。味噌にても、又(ま)た醤油や酒にても、余り汁気(しるけ)なきよう(=無きよう)
に炒り上げ、餅をよく焼き、いかにも(=如何にも)薄き薄たれ(※薄味仕立ての味噌だれのこと)
にて、さっと煮て、右の(=料理した)
小鳥を椀(わん)の中にて、餅に掛け申し候。」
上巻13【鳥こくせう】・・・鳥を主に濃漿(こくしょう:※味噌で濃厚に仕立てた汁物のこと)で煮た料理です。
「味噌いかにも(=如何にも)
よく摺(す)り、水にて延べさまに、酒を三分一混ぜて、味噌を延べ、鳥の細(こま)かなるを入れ、よく混ぜ合わせ、鳥と味噌と等分か、少し味噌を多きかと申すほどにいたし、鍋に入れ、炭火(すみび)にて煮申し候。山椒(さんしょう)を入れてよし。その外(ほか)何(いずれ)にても入れ申し候。花鰹(はながつお:※鰹節を薄くけずったもの)
短く削(けず)り加え申し候。煮たててうち(≒煮立てて、すぐに)
、箸にてかき(=掻き)
回し申し候。」
上巻14【◇、白鳥、雁、鴨 塩の仕様】・・・「◇」の部分は、判読不明部分となるのですが、「鶴(つる)」のことかな? と想います。水戸の千波湖周辺には「鶴」も飛来したと考えられますし、「鶴は千年」などと珍重されましたので。
「料理に遣(つか)い候様に(=料理に使う食材に合わせて)
、毛をとり(=取り)
、鳥尻(としり)を切り捨て三つにおろし、胴殻をのけ(=除け)
、尤(もっと)も油皮(あぶらがわ:※鳥皮部分など油分を多く含む部位のこと)
を付け、脚をも付け候て、塩に仕(つかまつ)り候。塩俵(しおだわら)にまき(=巻き)
候て置き候もよく候。又(ま)た遠道(えんどう)へ遣(つかわ)し候には、すし(=寿司)
を付け候ように、鳥のすれあい(=摺れ合い)申さず候様に、塩にて桶(おけ)に漬け申し候。料理の時分は、そのままあらい(=そのまま洗い)
油皮(鳥皮部分など油分を多く含む部位)
をつけ(=付け)
ながら塩を出し申し候。」
上巻15【くじら(=鯨)
の塩漬】
「寒の内の鯨(くじら)新しきを食うて見て、軟らかなるをつけ(=漬け)
申し候。身鯨(みくじら:※鯨肉のこと)
は、手のひら(=平)
程ずつに切り、皮は四分程になりとも、それより細(こまか)くなりとも切り、いかにも(=如何にも)
塩をたくさんにすれ(=摺れ)
合わせ申さぬように、すし(=寿司)
を漬け候如くおしつけ(=押し付け)
、蓋(ふた)の上に重(おも)しを置き申し候。身鯨(みくじら:※鯨肉のこと)
と皮とは別の桶に置きつけ申し候。塩水たまり(=塩水溜まり)
申し候ものにて候。その時重(おも)しゆるめ(=緩め)
候ても、そのままにても、苦しからず候。取出し候時、竹箸(たけばし)にて取り出し申し候。中へ手を入れ候えば、桶の鯨、色替り申し候。塩水少(すくな)く候わば、塩水して入れ申し候。」
上巻16【くじら(=鯨)
の料理】
「生鯨(なまくじら)良き加減に切り、酒にて一遍(いっぺん:=一度)酒いり(=酒炒り)
のように煮申し候。酒を捨て、その後味噌へ入れ申し候。塩鯨(しおくじら:※塩漬け鯨肉のこと)
ならば塩を出し候て後、右のごとく(≒前述した工程のように)
酒炒(さけい)りにして、その後料理申し候。自然塩鯨(しおくじら:※塩漬け鯨肉のこと)
色赤く候わば、上を切除(きりのぞき)申し候。」
上巻17【松前焼(まつまえやき) 鯨(くじら)の料理】
「焼き鯨(やきくじら)を短くいたし候(≒細かく切って)
、三日ほど水に漬け、よくよく水を再々に替え申し候。三日、四日過ぎ候えば、やわらかになり(=柔らかに成り)
申し、その時薄く切り、鍋に糠味噌(ぬかみそ)をたて(=立て)
、煮申し候。よく煮え候時、刺身にも、汁にも仕(つかまつ)り候。まず、ふだん右のこしらえにいたし(≒普段は前述した工程に従って)
、糠味噌(ぬかみそ)にて鯨を水にて洗い、ざっと日に干して置き候えば、久しく置き候ても苦しからず候。用の時はぬる湯(=温湯)
にて、ほどはがし(=程剥がし)
申し候。急の用にも立ち申し候(≒急ぎの際にも役立ちますよ)
。」
上巻18【雉(きじ)の汁山かけ】・・・「雉の汁山掛け」。
「雉(きじ)をいかよう(=如何様)
にも切り、酒をひたひたに入れ、火を細(ほそ)くして、酒臭くなきように煮申し候。その上へ水を入れ、煮たて塩を入れ申し候。汁軽過ぎ候わば、ちと(≒少々)
醤油を加え候。煮汁(だし)は少しも入れ申さず候(≒だしは必要ない)
。」
上巻19【きじすり汁】・・・「雉摺り汁」。
「雉(きじ)を細(こま)かに切り、筋と骨とを取って、摺鉢(すりばち)に入れ、成程(なるべく)こまかにすり(=細かに摺り)
、又(また)酒を加え、摺(す)り延べ、田楽味噌(でんがくみそ)の加減にいたしおき(=致し置き)
、汁は納豆汁(なっとうじる:※ネバネバ納豆を具材にした味噌汁のこと)
の如くにいたし候。葱(ねぎ)をざくざくに切り、入れてもよし。おおかた(=大方)
煮たて候時分、納豆を入れ候ように、右の摺(す)りたる雉(=前述した工程を経た雉肉)
を入れ申し候。雉のたくさん(=沢山)
なるがよし。」
上巻20【鯛(たい)しらしほ煮】・・・「しらしほ煮」とは、「しら潮煮」?
「身も、骨も常の如く切りて、古き酒をひたひたに入れ、火を細(ほそ)くして煮申し候。 酒の匂(にお)い是(これ)なき時、その上へ水を入れ、塩ばかりにて仕立て申し候。 鱸(すずき)などの汁は、醤油少し加えてよし。」
上巻21【かき(=牡蠣)
の吸物】
「なべに塩をいり(=炒り)
、その塩をとりあけ(=取り上げて)
、牡蠣を二つ三つ程鍋へ入れ、すりつぶし、牡蠣に水をひたひたに入れ、一たん煮たて、右の塩(=炒っておいた塩)
を加え申し候。時によりいかにも、少し醤油を加え申候、又酒、塩もさし申候。」
上巻22【うけいりとうふ】・・・「うけいり」とは、「受け要り」? 必ず人気が出るとのネーミング?
「山の芋と豆腐と等分。何(いずれ)にても、魚等分よりは少し控え、面々にすり(=摺り)
、その後一つにすり(=摺り)
混ぜ、塩少し混ぜ申し候。すまし(=澄まし)
の汁へなりとも、又(また)煮物へなりとも、杓子(しゃくし/しゃもじ)にて、つみ(=摘み)
入れのようにいたし入れ申し候。薄たれ(※薄味仕立ての味噌だれのこと)
にて、葛たまり(くずだまり:=葛溜:※葛餡のこと)
、又(また)
鳥味噌(とりみそ)程かけて(=掛けて)
もよし。」
上巻23【さけ(=鮭)
のいりもの】・・・「いりもの」とは、(鮭の)白子や内臓のことか?
「鮭の腸(わた)、同じく中うち(※中にある骨部分のこと)
こそげて摘みいり(≒そぎ取って)
、鮭の薄み細(ほそ)くつくり(=鮭の身は薄い細づくりとして)
、腹子(=筋子)
半分はそのまま、半分は摺(す)りて、さて煎り酒(※別項目に2種類の記載あるため、注意を要す。この場合は、食材が魚類のため、本書下部にある「いり酒」となります)
に水を混ぜて煮やし、その中へ右の色々(≒鮭の身や腸など全てを)
入れてとり(=取り)
、濃醤(こくしょう)もし、ねばりなく候わば(≒粘り気がないと感じるならば)
、葛粉(くずこ)を少し入れてよし。酢を加え申し候。」
上巻24【こたくみの仕様】】・・・「こたくみ」とは、「子巧み」? あるいは「小巧み」? ・・・いずれにせよ、鯛のアラや中落ち部分など旨味成分が強い内臓部分かな? と想います。
「常に世の中にする如く、されども鯛の中落ち(※骨の周りに付いた部分など)
を焦げぬように、遠火(とおび)にあぶり(=炙り)
、上の香色に成候時分、骨に付きたる身を竹箸(たけばし)にてむしり(=毟り)
落とし、細(こま)かに刻み、摺鉢(すりばち)にてよく摺(す)り、これを加え候えば、香味(こおみ)猶(なお)によし。」
上巻25【やきとり(=焼き鳥)
の仕様】
「鳥を串(くし)に刺し、上へ薄霜(うすじも)の降りし程に塩をふりかけ焼き申し候。よく焼け申し候時分、醤油の中へ、酒を少し加え、右の焼鳥(≒前述した焼き鳥を)
につけ(=付け)
、又(また)一辺(いっぺん)つけて(≒一度または二度付け足して)
、醤油の乾かぬ内に、座敷(ざしき)へ出し申し候。雉(きじ)ばかりは(=雉に限っては)
初めより掛け汁を付けて焼き申し候。」
上巻26【たたき鮑(あわび)】・・・「敲(たた)き鮑」。
「鮑(あわび)の上、香色なるがよし。貝殻を離し、腸(わた)を取り臼(うす)にて搗(つ)きてよし。又(ま)た板の上にて摺(す)り、木にて敲(たた)きてもよし。その後田楽(でんがく)の如くに焼きて、煮物にてよく御座候(ござそうろう)。」
上巻27【鳥のほろみそ】・・・「鳥のほろ味噌」。
「寒の内に雉(きじ)、鳩(はと)にても、その外(ほか)小鳥(ことり)にても身は、いかにも細かに(=如何にも細かに)
作り、骨はなるほど細(こま)かにたたき(=敲き)
、味噌よく摺(す)りて、酒と水とにてゆるゆると延(の)べ、鳥と味噌と等分に混ぜ、鍋へ炭火(すみび)をゆるく(=緩く)
して、そろそろとかき(=掻き)
回し煮るなり。若山椒(わかざんしょう:※少し早く収穫する若摘みの実山椒で、さわやかな辛さと清々しい香りがある)
、黒胡麻(くろごま)、その外(ほか)何(いずれ)にても加え申し候。二時も三時も(≒4時間も6時間も)
いかにも、しずかに煮あげ申し候(=静かに煮上げ申し候)。油断なく焦げぬように仕り候。その後、ぼろぼろと成り申し候。おおかた(=大方)
水気乾き申し候時分、取り上げ申し候て、よく冷まし、壺(つぼ)へ入れ置き申し候。来年夏までも、こたへ申し候(≒翌年の夏まで持ち堪えるますので)
。」
上巻28【鳥のあぶらの取様(とりよう)】・・・「鳥の油の取り方」。
「白鳥(はくちょう)、雁(かり)、鴨(はと)にても、としり(=鳥尻)
の内の、両わき(=両脇)
に油が溜まりて有る物にて候。その油を取り出し、又(ま)た細腸(ほそきわた)の油を、竹の箸にてしごき(=扱き)
、何(いずれ)も鍋へ入れ、一あわ(=一泡)
、煎じ(=煮て)
、おおかた(=大方)
冷め候時盆(ぼん)へ入れ、蓋(ふた)をあけて(=開けて)
、よく冷まし候えば、蠟(ろう)の如く固まり申し候。としり(=鳥尻)
のわき(=脇)
少しにても入れ候えば、臭(くさ)く成り申し候。内の油ばかりにて候。」
上巻29【魚の塩取やう】・・・「(塩漬保存された)魚の塩分の取り方」。
「鯛(たい)にても鱸(すずき)にても、その外(ほか)何(いずれ)にても、三枚におろし、紙包み、上を水にて濡(ぬ)らし、日かげ(=日陰)の湿気(しめりけ)有る土に、一夜埋め申し候。ことのほか(=殊の外)塩辛く候わば一日一夜にても、二日も置き申し候。おおかた(=大方)
薄塩程に成り申し候。」
上巻30【あえまぜの仕様】・・・「あえまぜ」とは、「和え混ぜ」のこと。
「干物(ひもの)色々けずり物(=削り物)
にして、精進物(しょうじんもの:※多くの仏教宗派で禁じる肉や、魚介類、卵類、乳製品以外の食物のこと)
を取り混ぜ、精進(しょうじん)の煎り酒(※別項目に2種類の記載あるため、注意を要す。この場合は、「精進の」とありますので、本書下部にある「煎酒」となります)
に水を混ぜ、酢を加え、膾(なます)の如く和(あ)え申し候。魚の煎酒(※この場合は、例の如く「いり酒」となります)
よりは、精進の煎酒増し申し候。煎酒に酢(すっぱ)き味有る物に候間、酢は加え候わねどもよく候。」・・・「なます」とは、元々生肉や魚介類を細かく刻んだ料理のことを指しており、「なます切り」や、時代劇などの台詞(せりふ)で「なます斬り」って使われたりしますね。
上巻31【鰹(かつお)の刺身の仕様】
「鰹(かつお)常の如く、湯を掛けてなりとも、またそのままなりとも作り、古酒(こしゅ)に塩を如何(いか)にも少し加え、作りたる魚に掛け、ひと時も(≒2時間も)
置き取り出し、盛り申し候。また、右の如く(≒前述した通りに)
酒に漬け置き候えば、二日程も魚、さがり申さず候(≒悪くなりません)
。」
上巻32【鯉(こい)の川つくりの仕様】・・・「川つくり」とは、「洗い」のこと。
「子(=魚卵)
の無き鯉(こい)如何(いか)にも薄く、刺身に作り、くみたての(=汲みたての)
水に塩を少し入れ、二、三返(に、さんべん)も洗い、鯉の身の弾(は)ぜ候ほど洗い、水気を絞り身の縮むようにいたし、煎酒(※この場合は、例の如く「いり酒」となります)
にても、からし酢(=芥子酢:※酢に和芥子を加えたもの)
にてもよし。」
上巻33【魚のなまひ(=生干)
の仕やう(=仕様)
】
「鯛(たい)にても、鯵(あじ)にても、その外(ほか)何(いずれ)にても、三枚におろし、魚の目を抜き、水に喰塩(くらいじお)より辛めに塩を混ぜ(≒水に通常の塩分量を超えた量の塩を混ぜて塩辛くして)
、それにて一返(いっぺん:=一度)
洗いそのまま日に干し、焼物に仕(つかまつ)り候。」
上巻34【干し鯛(たい) 干し鱈(たら) やわらげやう(=和らげ方)
】・・・上記の 上巻29 にある 「魚の塩取やう」 と似ていますが、こちらは干物を利用する際のコツの伝授か?
「右の干物(≒干し鯛や干し鱈)
を水にひたし(=浸し)
、再々に水を替、え三日程置き、取あげ(=取上げ)
、やき物(=焼き物)
によし。余り塩ぬけ(=塩抜け)
申し候わば、酒の中に塩を入れ候てなりとも、醤油をつけ候てなりとも、焼き候えば、やわらかになる物(=柔らかに成る物)
にて候。また右のやわらぎ候干物(=前述した工程で柔らかくなった干物)
を、水の中より取り出し、水気をよく取り、酒の糟(かす)に漬(つ)けてもよし。」
上巻35【切卵(=切玉子)
の仕様】
「(鶏)
卵を潰(つぶ)し、よくよくとき混ぜ(=よくよく溶き混ぜ)
、(鶏)
卵五つ程ならば、火を如何(いか)にも、ゆるゆるとして、葛の粉濃い茶一服程入れ、麩(ふ)の焼きに(=お麩を焼くように)
焼くなり。(鶏)
卵を少し入れ、成程(なるべく)薄く焼き候。蕎麦切(そばきり)の如く細(ほそ)く切り、煎酒(※この場合は、例の如く「いり酒」となります)
にて、刺身にも、煮物にも、膾(なます)にも、混ぜ申し候。」
上巻36【玉子ふわふわの仕様】・・・「玉子ふわっふわっ」との魅力的な表現となっております。
「鶏卵を潰(つぶ)し、水醤油か、出汁醤油(だしじょうゆ:※徳川斉昭が当時の板前さんのように出汁を煮出して予め用意した?)
かを入れ、常の如くふわふわに仕り候。酒を入れれば悪(あ)しく候。酒を入れ候えば、鍋肌(なべはだ)つよく(=強く)
焦げつき(=着き)
申し候。また煎酒を加え候得ば、よくできた時分、鍋の中の鶏卵に、あそこ、ここに、穴をあけ(≒玉子のあちらこちらに穴を開けて)
、煎酒(※この場合は、例の如く「いり酒」となります)
を水にて薄く延べ、上へつぎ(=注ぎ)
込み、少し煮てよし。」
上巻37【巻きたまごの仕様】・・・蒲鉾と玉子焼きの中間的な料理かな? と想います。
「たまごを、麩(ふ)の焼き(=お麩を焼くよう)
にして、何(いずれ)にても魚のくずし(≒どんな魚のすり身でも)
を中にぬり(=塗り)
、麩の焼きをきりきりと巻き、干瓢(かんぴょう)にて括(くく)り、煮申し候。その後いかようにも(=如何ようにも)
切り申し候(≒どのように切っても良い)
。」
上巻38【夏のこごり(=凝魚)
の仕様】
「鯉(こい)、鮒(ふな)とても、又(ま)た精進物(しょうじんもの)にても、たれ汁(≒煮汁)
にて煮申し候。煮さま(=煮様)
にその中へ、ところてん(=心太)
を入れ申し候。煮汁一升程の中へ、ところてん(=心太)
の四角なるを、五つ程入れ申し候。よく煮候て、鉢(はち)に入れ、水にて冷やし申し候。」
上巻39【あさり(=浅利=鯏)
のたたき(=敲き)
の仕様】
「寒の内に、あさり(=浅利=鯏)
の剥(む)き身をそのまま雫(しずく)をたらし(=水気を切り)
、あさり(=浅利=鯏)
の身一升あらば、塩五合、糀(こうじ)五合よく混ぜ、桶の下に、右の塩を(=塩を五合分)
ふり、あさり(=浅利=鯏)
を置き、又(また)塩を置き鮨(すし)を漬(つ)けるようにいたし、上に重(おも)しを、如何(いか)にも強く置き、二十日ほど過ぎて、半分程重(おも)しをゆるめ(=緩め)
申し候。」
上巻40【はまぐり(=蛤)
の吸物(すいもの)の仕様】
「蛤(はまぐり)のむきみ(=剥き身)
を、手の内にて少し汁を絞り捨て、さて酒と水等分に、酒臭くなき程によく煮申し候。いり塩(=炒り塩)
にて仕立て申し候。」
上巻41【かわらけやき(=土器焼き)
の仕様】
「鳥こくせう(=上記の 上巻13 鳥こくせう)
の如くに、味噌と鳥、等分程に混ぜ、鰹(かつお)、もみ(=揉み)
鰹にして煎酒(いりざけ)を加え、土器(かわらけ)へ入れ、炭火(すみび)の上にて、すきやき(=鋤焼き)
の如くに致し候。魚をも加えてよし。」
上巻42【いり酒の方】・・・「いり酒の用い方」。ここは、要注意項目です。下巻27に、これと同じように「いりざけ」と読む項目があります。そちらとの違いは、食材の違いと、「精進もの」と呼ばれた料理に該当するか? 否か? の違いによります。この「いり酒」の場合は、鰹節を利用していますので、“精進ものの料理”には使用しないこととなります。・・・さらに、もう一点、注意せねばなりません。ここにある項目レシピは、いわゆる「料理酒」なのですが、以下原文中にある「古酒」= 日本酒(清酒)を長期間熟成させたお酒。但し何年熟成させれば古酒になるという明確な決まりは特に無い = 発酵や醸造の要因となる酵母菌の働きが一定程度落ち着いた状態の酒 ≒ アルコール度数が20度以上のお酒 を、仮に使用せず、うっかりアルコール度数が20度未満のお酒を基にして、この項目レシピを実験的に造ろうとすれば、発酵や醸造の要因となる酵母菌が活性化してしまうため、現在の「酒税法」により“新たな酒を造ること”に該当してしまい、結果として「違法行為」となるのです。
・・・尚、次のものを混ぜて、新たに自家製のお酒を造ることも、「酒税法」により禁じられているため、さらに注意を要します。
・・・1.米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ・・・
・・・2.ぶどう(やまぶどうを含みます。)・・・
・・・3.アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす・・・
したがって、この項目の【いり酒の方】など「お酒の造り方」は、“仮に知ったところで、むやみやたらに行なえない事柄”となる訳ですが、『食菜録』著者・徳川斉昭の探求心? と申しますか、彼の情熱を理解するため、以下に訳文を掲載する次第です。
「一、古酒(こしゅ)三升 一、醤油五合 一、鰹節一升、いかにも細かに(=鰹節一升を如何にも細かに)
削り、水にてさっと洗い、はかる(=量る)
、又(また)水にて洗い申さず候わば二升入る。右三色(=古酒三升、醤油五合、鰹節一升の全てを)
よく混ぜ、炭火(すみび)の上にて沸(わ)かし、酒の匂い退(の)き候まで煮るなり。大方(おおかた)煮え候時分、煎酒入り加減をいたし候。又(また)酢をも心次第に(≒また、酢の加減はお好みで)
加え候。何(いずれ)も煮え候内、又(また)梅干(うめぼし)を入れ候わんと存じ候えば、梅二十程よく候。よい加減の時、鰹そのまま、漉(こ)して取り申し候。久(ひさ)しく置き候えば、鰹臭く成り候て、悪(あ)しく候。この煎酒は、はやわざに、でき申し候(≒この煎酒は、早業にて、出来てしまう)
。」
上巻43【しほとりのいりとり(=塩鳥の煎り鳥)
】
「塩鳥(※塩漬けした鳥肉のこと)
を成程(なるべく)よく塩を出し(=塩出しして)
大(=大きめに)
に切り、いり鳥(=炒り鳥)
鍋に、鳥の油を少し入れ、はじらかして(=油を十分に加熱して)
、酒を多め、醤油を少しよく煮やし、右の塩鳥(=前述した工程を経た塩鳥)
を入れて少し煮申し候。この中へ、赤貝(あかがい)、麩など加えてもよし。」
上巻44【塩鳥のかきあへ】・・・この『食菜録』の原文中に「塩鳥の」とありますが、正しくは「塩魚の」となります。尚、「かき和え」とは、薄塩の魚や貝を主材料にし、瓜(うり)や蓼(たで)などを取り合わせ、短冊や千切りにして器に盛り、出す間際に酒に煎り酒を加えて塩で塩梅した調味液をかけ、さっと和えて出す料理のことです。
「塩鱈(しおだら)にても、塩鯛(しおだい)にても、よくよく塩をおし(=押し)
、刺身の如くに作り、水にて洗い、鰹節を大きに削り、一つに混ぜ煎酒に酢を少し、水を加えて、膾(なます)の如く和(あ)え申し候。」
上巻45【鮒(ふな)のなます】
「子(=魚卵)
をつけぬ先に(≒鮒の魚卵は除いておいて)
、酒を少しかけ(=掛け)
、それにて一返和え(=一度和え)
、その酒をしたみ(=その酒の水気を切り)
申し候。土香(つちか:※泥臭さのこと)
を取り申すべきために候。その後、酢、煎酒、塩にて和(あ)え、焼き骨、子(=魚卵)
は、後に混ぜてよし。」
上巻46【鯉(こい)のなます】
「子(=魚卵)
をいりて(は)
悪(あ)しく候(≒鯉の魚卵を煎る事は絶対ダメです)
。湯煮(ゆに)をして、水気をしたみ置き(≒水分を切り、しばらく置いて)
申し候。之(これ)をば、成る程(なるべく)細(こまか)く作り、酒をぬるく温め、煎り酒ばかりにて和え候。山葵(わさび)をたくさんに入れ、栗、生姜など入れ、酢を少し加え、盛りざまに、子(=魚卵)
を混ぜ申し候。」
上巻47【あえて久敷損ねぬ膾(=敢えて久しく損ねぬ、なます)
の仕様】・・・食材の腐敗や酸化を遅らせる方法?
「何(いずれの)魚にしても(≒どんな魚でも)
、塩と酢とばかり(=塩と酢のみ)
にて和(あ)え、その酢の中へ、そのままひたして(=そのまま浸して)
置き候えば、半日過ぎても、苦しからず。おしさまに(≒一度浸し置いた後に)
、酢をひたひたよりは、少なめにして、酒をたくさんにさし(=注し)
、時により水を加えてもよし。又(ま)た酢の中より、魚を皆(みん)な取り出し、酒ばかりにて和(あ)えてもよし。」
上巻48【ふなもどきのなます】・・・「ふなもどき」とは、「海鼠(なまこ)」のことだそうです。その大きさ・サイズ感から、こう呼んだのではないでしょうか?
「海鼠(なまこ)、なる程(なるべく)細(ほそ)く作り、煎酒ぬるく温め、それにて何にても(≒何が何でも)
、魚のへぎ骨にして、山葵(わさび)を混ぜ和え申し候。酢を加え申し候。」・・・「魚のへぎ骨」とは、“平たい骨だけのような状態まで薄く細かくする”との比喩表現です。尚、「へぐ」とは、「剥(は)ぐ」の方言で、訛(なま)りがあります。北関東人は親近感が爆上がり?
上巻49
【なまこほそづくり】・・・「生海鼠細造り」。別名は「海鼠湛味(こだたみ)」とも。
「海鼠(なまこ)を、二つ、三つにへぎ(≒二つ、三つに剥いで)、成程(なるべく)細(ほそ)く作り、酒にて和(あ)え、その煎酒を捨て申し候。粘りを取り候わんためなり。又(また)他(よその)の煎酒を掛け、一遍(=一度)
和(あ)え候えば、さらりとなり申し候。山葵(わさび)入れ、はな鰹(はながつお:※削り節の一種、鰹節を薄く削ったもの。花鰹とも)
、上(うわ:≒上側にそっと)
置きに仕(つかまつ)り候。但(ただし)ぬる湯(=温湯)
にて、さつと洗い(=サッと洗い)
候へば、ねばりとれ(=粘り取れ)
さらり(=サラり)
と成(なり)よく候。」
上巻50【なまこなますのしやう】・・・「生海鼠鱠の仕様」。
「酢に、魚の骨を入れ、煎(せん)じ出(いで)し(=煮出して)
、骨を取り、酒を加え、塩を入れ、はな鰹(=花鰹)
も入れ、ぬるく(=温く)
冷まし、魚、なまこ(=海鼠)
、鳥のももけ(※鳥のもも肉か?)
、何(いずれ)も細(ほそ)く作り和(あ)え申し候。」
上巻51【鳥なますのしやう】・・・「鳥膾の仕様」。
「雁(かり)にても、鴨(かも)にても、身を二つ、三つにへぎ(≒身を二つ、三つに剥いで)
、油皮(※鳥皮部分など油分を多く含む部位のこと)
を取り、なる程(なるべく)細(ほそ)く作り、温め酒(ぬるめざけ)にて一返洗い(=温め酒にて一度洗い)
、酒を捨て、酢は鳥のどうがら(=胴殻:※鳥ガラのこと)
を入れ煎じ(=煮て)
、少し冷まして、右の鳥(≒前述した工程を経た鳥肉)
にかけあえ申し候(≒掛け和えに致します)
。わさび(=山葵)
を入れ申し候。花鰹(はながつお:※鰹節を薄くけずったもの)
を少し混ぜてもよし。冬のなます(=膾)
は、温めても、温めずにも、少し煎り酒をさしたるがよし。夏のなます(=膾)
は、鯉(こい)鮒(ふな)の外(ほか)は、煎酒少しでも悪(あ)しく候。水ばかり(=水のみを)
加えてもよし。」
上巻52【かまぼこのしやう】・・・「蒲鉾の仕様」。
「出汁(だし)にしても、酒にても、混ぜ候事悪(あ)しく候。ゆるくいたし度は(=緩くしたい際には)
、水がよく候。まえかどに(=事前に)
すり(=摺り)
、塩を混ぜて置き申し候こと塩魚になり候故、これまた悪(あ)しく候。牡蠣(かき)鯛(たい)の如くにして置き焼き候時、すり塩(=摺り塩)
を混ぜ、そのまま焼き申したるはよく候。かまぼこ(=蒲鉾)
焼きて、中ぼろぼろといたし候わば、塩混ぜて置く故(ゆえ)なり。」
上巻53【いかのこの煮もの】・・・「いかのこ」とは、烏賊の白子のことか?
「いか(=烏賊)
の腹をあけてみれば(=開けて観れば)
、白く固まりたる物(※いかの子、白子のこと)
あり。これを取り出し、二つ、三つに切り、煮物に(は)一段(と)よきものなり。」
上巻54【いかのまる煮】・・・「烏賊の丸煮」。
「いか(=烏賊)
の黒身のみつの如くなる(※黒蜜あるいは黒い水、いか墨のことか?)
を洗い捨て、殼をぬき(≒おそらくは、軟らかい骨を抜いて)
、固まりたる黒身をば、そのまま置き、切らずに、うすたれにてよく候。煮て取り出し、筒切りにして、そのままも、又(また)右の汁の中へ入れてもよし(≒再び煮汁に戻しても良し)
。」・・・そもそも保存方法に限りある時代なので、「固まりたる黒身をば」とする時点で、既に“いかの沖漬け状態のもの”を使用していた可能性があります。・・・また、文中の「うすたれ」とは、薄味仕立ての味噌だれのこととなりますが・・・但し、いかが沖漬け状態だった場合、浸透圧の作用にて、いかに含まれていた塩分濃度は薄まる筈であり、当時の人々の塩味(えんみ)感覚では、これで良かったのかも知れません。料理って健康科学ですね。
上巻55
【たこなんばん煮】・・・「蛸南蛮煮」。
「蛸(たこ)を常の如く洗い、板の上にて摺(す)り、木にて、よくたたき(=良く敲き)
、軟らげ、心次第に(=お好みで)
切って、酒ばかり(=酒だけ)
にて、久(ひさ)しく煮候えば(=長時間煮ると)
、成程(なるべくして)、やわらかに(=柔らかに)
成り申し候。その上へ、醤油をさし(=注し)、又(また)煮てその後取り出し、心次第に(=お好みで)
切り、汁なし(=汁無し)
に座敷(ざしき)へ出し候。山葵酢(わさびず)、生姜酢(しょうがず)かけてよし(≒山葵酢や生姜酢を掛けるのが良い)
。」・・・生姜を使う料理だから南蛮煮?
上巻56【ゆで鳥】・・・「茹で鳥」。
「雁(かり)、鴨(かも)水ばかり(=水だけ)
にて煮て、取りあけ(=取上げ)
、よき加減に切り、熱き内に山葵味噌(わさびみそ)なりともかけ(=掛け)
、又(ま)た塩ばかりにてもよく候。鰯(いわし)は生塩(きじお)よし(≒鰯は生塩が合います)
。」・・・「茹で鳥」と云いながら、「茹で鰯」も追加しています。
上巻57【煮とり】・・・「煮鳥」。
「雁(かり)、鴨(かも)薄たれ(※薄味仕立ての味噌だれのこと)
にて、よく煮申し候。その上へ醤油をさし(=注し)
申し候。敷鰹(しきかつお:※薄く削った鰹節のこと)仕(つかまつ)り候(≒敷鰹をふり掛けてね)
。」
上巻58【小鳥なんばん料理】・・・「小鳥南蛮料理」。
「小鳥(ことり)の腹の内へ、かまぼこ(=蒲鉾)
を入れ、油揚げにして、その鳥の如くに(≒その鳥の種類によって)
煮るなり。」・・・「かまぼこ」は、魚のすり身なのか? 海老のすり身なのか? が不明となりますが、おそらくは小鳥の種類によって変えていたかと想います。尚、小鳥の胸辺りの骨を除く描写が無いので、「骨まで食べてね」ということかと。・・・また、味付け方法についても不明なのですが、小鳥肉の中に何かのすり身を入れて油で揚げているため、どこか中華風に感じますし、そもそも小鳥(≒野鳥)には独特な臭みがありますし、徳川斉昭は南蛮料理と云い切っていますので、鷹の爪などの香辛料を使用したものだった可能性が高かったかと想います。
上巻59【鮎(あゆ)の刺身】
「一寸、二寸、三寸ほどの鮎(あゆ)を、頭をとり(=取り)
、三枚におろし、中うち(※中にある骨部分のこと)
を捨て、酢に塩を少し入れ、それにて洗いたて、酢味噌か、辛し酢味噌にてよし。三枚におろしざまに、その刀を(≒その包丁を)
はなさず、中うち(※中にある骨部分のこと)
をとりてよし。」
上巻60【切うるかのしやう(=仕様)
】・・・「うるか」とは、鮎の塩辛のことです。
「鮎(あゆ)をよく洗い、成程(なるべく)薄く、背ごしに切り(≒頭や、ひれ、はらわたを取り除いて、中骨のあるまま、ぶつ切りにすること)
、頭、尾先(おさき)はのけ(=尾先を除いて)
、腸(わた)も、子(=魚卵)
も、そのまま置き、その鮎のかさ(=その鮎の量が)
一升あらば、塩を五合混ぜ申し候。塩に少しも、水気なきがよく候。手にて何べんも(=手によって何度も)
、むらなきように(=ムラが出ないように)
もみ(=揉み)
合わせ、その後大きなる桶(おけ)に、おし(=押し)
付(つけ)置き申し候。切りうるかたくさん(=沢山)
につけたるほど(=漬けたる程)
よき物にて候。」
上巻61【とりまぜ うるか】・・・「取り混ぜ うるか」。上記にある 鮎の塩辛や、内臓、白子、栗子(=魚卵)を使った料理なのですが、食材の違いと云えば、白子を使用すること位しかないようにも想えます。但し、こちらの方が塩分控えめで、味も多少なめらかにはなるかと。
「腸(わた)と、あわこ(※鮎の魚卵のこと)
とは、ひとつにして、白子は摺鉢(すりばち)にてよく摺(す)り、腸(わた)、あわこ(※鮎の魚卵のこと)
によく混ぜ、そのかさ(=その量が)
一升あらば、塩四合ほど混ぜ、壺(つぼ)に入れ押付け申し候。」
上巻62【こいわしのなます】・・・「小鰯の膾」。
「田作(たづくり/たつくり)より、小さき鰯(いわし)よく候(≒田作より小さい鰯が良い)
。尾先を持ち、逆さまにし、こき候えば(=扱〔しご〕くようにすれば)
、うろこ(=鱗)
、はらわた、頭(かしら)までとれ申し候。それをよく洗い、頭に塩を混ぜ、よく洗い申し候。」・・・「田作」とは、片口鰯(かたくちいわし)の幼魚を乾燥させたもので、「祝い肴」とされ、別名は「ごまめ」とも。
上巻63【塩鯉の持様(もちよう:=持たせ方≒保存方法)
】・・・これもまた「塩鯉」と原文中にありますが、明らかな誤記です。正しくは「塩鮭」です。
「塩鮭、春に成り候えば、塩吹き出し申し候(≒塩鮭は春になると、自然に塩が沁み出てまいります)
。そのまま置き候えば、それから腐り申し候。はやく(=早く)
白水(※米を研ぐ際に出る水のこと)
にて、腹の内も外もよく洗い捨て、風隙(ふうげき)に(=風がよく当たる処で)
干して置き申し候。身堅(かた)きは、鯖(さば)の如くに引き裂き、酒をかけて(=掛けて)
よし。」
上巻64【鯖(さば)の汁の仕様】
「鯖(さば)の骨も身も、よくかんに(≒良い加減で以って)
切り、よくよく塩を洗い捨て、さっと干して、その後又(また)水にて洗えば、なすび汁へも、にんじん汁へも、入れてよし。」・・・文中の「にんじん汁」とは、実際に人参を使った汁ではなく、人参を切るように切った、つまりは大きめに輪切りとした大根汁のことを指すとのこと。また、現代の鯖缶料理のように、骨までいっしょに食べたようです。・・・「旨い骨髄部分まで摂取しましょう」との、徳川斉昭の声が聞こえるような?
上巻65【鯨(くじら) 鮒(ふな)の汁の煮様】・・・「鯨や鮒を煮て汁物に仕立てる方法」。
「この二色(≒鯨と鮒)
は、古酒(こしゅ)をひたひたに入れ、酒ばかりにて煮候て、酒の無き時分味噌をたて(≒酒が煮え切って蒸発しきった頃に味噌を入れて)
、さして(=注して)
足し(≒再び酒を適量加えて)
、袋(※味噌を入れた木綿袋のことか?)
を入れ申し候。味噌濃すぎ候わば、取り酒をさし(=注し)
申し候。味なくば、少し醤油さし(=注し)
てよし。」・・・鯨肉や鮒特有の臭さを抑えるために、醸造が進んでいる古酒を使ったようです。臭いには、匂いをということですね、きっと。
上巻66【越後のあまづけ(=あまご漬)
】・・・「越後流・生いくらの塩漬」。
「鮭の子(=鮭の魚卵)
のよく詰まりたるを、如何(いか)にも疵(きず)のつかぬように、袋(※鮭の魚卵を包む卵巣膜のこと)
ともに取り出し、うす霜のふる程に(≒薄い霜が降るように)
、塩をつけ、壺へ入れ、ろく(=陸)
にならべ(=平らに並べ)
置き申し候。久(ひさ)しく置き申し候には(≒しばらく長い期間保ちたい場合には)
、うす霜よりは塩をまし(=増し)
申し候。さりながら、塩事(こと)の外(ほか)きくもの(=効く)
にて候(≒とは云っても、案外と塩が効いてしまうので、要注意)
。」
上巻67【奥刕(=奥州)
子籠(こごもり)】・・・「奥州流・子籠」。「子籠」とは、“菰(こも:※水辺に生えるイネ科の多年性植物を乾かして、粗く編んだむしろのこと)や笹の葉を使用し、魚卵を鮭の腹に詰めた塩漬保存食”のことです。
「如何にも(≒まさしく)
新しき鮭(さけ)を腹を割り、よく洗い、内外(うちそと)へ塩をよくよくいたし、菰(こも)に笹の葉を敷き、包み置き、これは七日過ぎ八日目に取り出し、腹も子(=魚卵)
も鮭も、水にて洗い、腹へ一盃、子(=魚卵)
を詰め申し候。その後、うすみの所をわり候てぬい(≒腹の身部分で薄い部位を割いた後に糸で縫って)
、七日風をひかせ(≒七日も風に当てて)
、又(また)菰(こも)に包み置き申し候。家の内につり候て(≒屋根下に吊って)
置き申し候。鮭一つの子(=魚卵)
にては少なく候故、鮭一つに二、つ三つの子(=魚卵)
を取り集め、詰め申し候(≒鮭一尾の魚卵の量では、どうしたって少なすぎるので、鮭一尾に対して二尾三尾分の魚卵を集めて詰めると宜しい)
。」・・・尚、徳川慶喜の異母妹・八代姫(※徳川斉昭と側室・松波貞子の娘で、鳥取藩主・池田慶徳や岡山藩主・池田茂政の妹、後の伊達孝子のこと)が乳牛と世話係(≒飼育員)とともに陸奥仙台藩主・伊達慶邦の継室に嫁いだことと、ここにあるような奥州陸奥仙台藩の秘伝とも云える保存食や特産品の製造工程が徳川御三家・水戸家に伝わったことは、決して無関係では無いと私(筆者)は考えております。つまり、食や流通、経済に関わる物産情報の交換(=情報トレード)などが、江戸時代後期の大名家藩主達にとっては、婚姻関係を結んで友好を保つためにした列記とした手段の一つだったからです。当然に、情報は人が人に伝えるものですし、特に水戸藩は諸々の事情により財政状況が長い間逼迫していたので、国内の外様大名で大藩と云える伊達家と婚姻契約を結んだことは、一時的だったとは云え、今で云えば食料安全保障上の同盟関係を結んだに等しく、とても大きな出来事だったと云えるからです。そもそも水戸藩は、伊達家や佐竹家、上杉家など外様大名達が居残る東北地方を見張ったり、江戸を守る防衛拠点としての役割を課されて立藩されておりますので。また、越後地方の物産品の記述が観られるのも、水戸徳川家と越後の旧主・上杉家や当時の藩主・堀家などとの関係構築の成果だったと考えても良いのではないかと想います。
上巻68【奥刕流(=奥州流)
子無(こなし:=魚卵無し)
の鮭引(さけびき)の仕様】・・・「奥州流・子無鮭引の仕様」。上記項目と類似していますが、こちらは「子無の鮭」を使用したものです。
「これは内外(えちそと)より、塩おしして(=塩押し〔※塩をふり重石を載せて漬けること〕して)
、これも七日置き、八日目に、塩を洗いおとし、家の内につり置き申し候。塩引(しおびき)をかたく(=堅く)
致し候には、風をひかせ申し候(≒風に当てるのです)
。柔(やわ)らかに致し候には、菰(こも)に包み申し候。」
上巻69【正宗流(しょうしゅうりゅう) 生かい(せいかい)の料理】・・・「正宗流・鳥肉と鳥皮の料理」。「生かい」とは、「生介」と書いて、雁肉や鴨肉など相性が良い食材同士を使った料理を例える言葉のようです。
「雁(かり)にても、鴨(かも)にても、油皮(※鳥皮部分など油分を多く含む部位のこと)
を付けながら、成程(なるべく)細(こまか)く作り候。身の厚き所はへぎ候ても(≒肉厚な部分については削いで)
、細(こまか)く作り申し候。 鍋に、だし醤油(※徳川斉昭が当時の板前さんのように出汁を煮出して予め用意した?)
、酢にても、酒にても、少し、これをさっと煮やし、よく煮え候時、火上をあけ(≒火力を上げて)
、右の鳥を(≒前述の工程を経た鳥肉を)
入れ候。 汁は、ひたひたの加減に成る程に(≒汁はヒタヒタの加減になるように)
、初めに鍋へ入れ申し候。鳥を入れ候てよりは煮候わず候(≒汁よりも鳥肉を先に鍋へ入れると煮物として固くなり失敗するので要注意)
。 わさび(=山葵)
を、たくさん(=沢山)
に入れ、かき(=掻き)回し候。鳥、いか(=如何)
にも薄く細(こまか)く候故よい加減に、柔(ゆわ)らかに煮え申し候。」
上巻70【越後の子籠(こごもり)仕様】・・・「越後流・子持ち鮭塩引きの作り方」。
「新しき鮭(さけ)、拾本に付(=十尾に付き)
塩一斗、水一斗を桶の中に入れ、よく揉(も)み砕(くだ)き、塵(ちり)を漉(こ)して取り、この水一斗になり候ほど、煎じ(=煮て)
、よく冷まし、冷え候時、この水の中へ、鮭をつけ(=漬け)
申し候。鮭の腸(わた)をとり、子(=魚卵)
少なくば、他の子(よそのこ:≒別の鮭の魚卵)
を混ぜ、子の抜けぬように(≒魚卵が零〔こぼ〕れ落ちないように)
、腹もの所を糸にて縫い(≒腹部分を糸で縫って)
、右の水の中へ(≒前述した工程で冷ましておいた塩水の中に)
、七日七夜(なのかななよ)付け、その後鮭(さけ)を取りあげ(=上げ)
、三所ほど(=三カ所ほどを)
、細縄(ほそなわ)にて結(ゆ)い候ても、又(また)くるくると、如何(いか)にも荒く巻き候てもよし。口にも縄をつけ(=付け)
、日かげ(=日陰)
につるし(=吊るし)申し候。柔(やわ)らかにいたし候わんと存じ候えば(≒柔らかな食感にしたければ)
、十日程にてもよく候。かたくいたし候には(≒堅い食感にしたければ)
二十日も、三十日もつるし(=吊るし)申し候。」
上巻71【越後の鮭(さけ)のひらき(=開き)
様】・・・「越後流・塩引き鮭の作り方」。
「水一斗二升に塩一斗入れ、揉(も)み砕(くだ)き、水一斗に成り候程煎じ(≒水が一斗程になるまで煮て)
、よく冷え候ほど、冷め申し候時新しき鮭(さけ)をひらき(=開き)
、右の塩水(≒前述した一斗ほどになった塩水)
の中へ入れ、四、五日程置きその後取り上げ、日かげ(=日陰)
にかたまり候程(≒日陰におくと固まってくるので)
、つり(=吊り)
置き申し候。早く食べ申し候には、三日程塩水につけ(=漬け)
申し候。」
上巻72【越後筋子(えちごすじこ)の仕様】・・・「越後流・筋子の仕様」。「筋子」も、鮭の魚卵のことですが、こちらは鮭の卵巣膜を利用したものです。上記にある 【越後のあまづけ】 と比べても、同じような塩漬けになるのですが、きっと見た目の違いにより、記述される表現が変わったものだと想います。
「これも右の如く(≒上記にある越後の鮭のひらき様のように)
、塩水を煎じ(=塩水を煮て)
、はらの子の袋の(≒鮭の魚卵を包む卵巣膜を)
損じ候わぬようにいたし候(≒傷付けないように丁寧に取扱います)
。右の塩水(≒前述した作った塩水)
にて漬け、二時ほど置き(≒四時間ほど置いて)
、そのまま取上げ、壺(つぼ)に入れ、二、三日も置き、そのまま置き候得ば固まり申し候。その時薄く藁(わら)を敷きて、風ふきに置き(≒風当たりの良い処に置くようにして)
、料理の時切りて、酒をかけ(=掛け)
出し申し候。」
上巻73【小鳥(ことり)かうじ漬(=糀漬)
の覚(おぼえ)】・・・「小鳥糀漬けの覚(え書き)」。
「糀(こうじ)三合、塩二合、
右(≒糀三合と塩二合とを)
よくよくかき(=掻き)
合わせ、小鳥(ことり)一つならびに置き(≒鶉〔うずら〕や雀〔すずめ〕などの小鳥と、前述した塩糀〔しおこうじ〕とを一対に並べて)
、右の糀を(≒前述した塩糀を)
小鳥のあいだあいだに置き(=小鳥の間、間に置き)
、鮨(すし)の重(おも)しよりも(≒鮨一貫の重さよりは)
、軽めに置き申し候。小鳥はよく毛をむしり(=毟り)
、背(せ)を割り、内の物を取り(≒内臓などを取り除いて)
、頭(かしら)をも割りて漬(つ)け申し候。」・・・この料理もまた、小鳥特有の臭みを消すために発酵調味料の塩糀を使ったようです。科学ですね。
上巻74【子籠鮎当座鮓仕様(こごもりあゆとうざすしよう)】・・・琵琶湖周辺で食される伝統食・鮒ずしの子持ち鮎版か? と想います。
「鮎(あゆ)のささめ(=莎:※しなやかな草の莎〔ささめ〕で、獲れた鮎を刺したり包んだりして持ち運びました)
かき(≒獲れたての生の鮎を掻いて)
、腸(わた)取り(=腸を取り除いて)、成程(なるべく)つよく(=強く)塩仕(つかまつ)り候て、二日指し置き鮓(すし)(≒二日ほど置いて鮓として)に仕(つかまつ)り候時、鮎(あゆ)成る程(なるべく)よく洗い、水気少しもなき(=無き)ように拭(ぬぐ)い、食は(=飯は)鮎十に付き、白米一升の積(つも)り、成る程飯を炊き干しに(≒なるべく、米を煮てから蒸らすという、当時の一般的な炊飯方法によることとし)、こわめ(=強め)
に仕(つかまつ)り候(≒固めに仕上げるようにして)
、重(おも)しは如何(いか)にも、つよく(=強く)
掛け置き、五日程指し置き申し候。」・・・著者の徳川斉昭が、「鮨」とは書かずに「鮓」としたのには、これが江戸前握り鮨のように酢飯を合わせたものとは違って、“発酵の力を利用した伝統的な製法によるものである”との考えがあったからに違いありません。
上巻75【鮎こたべ付の仕様】
・・・「鮎っこ(※鮎の生漬:※鮎の塩漬のこと)と玄米を使った料理とその取扱い方法」。徳川斉昭が何故に、この料理名としたのかは不明なのですが・・・下記の調理方法を観ると、鮎の頭(かしら)などを捨てずに、全てを丸ごと食べるもののようなので・・・おそらくは、玄米を使用して精米の手間を省けるだけではなく、脚気(かっけ)などのビタミン不足による病気の予防に役立つ薬膳的な料理として、彼が抱いていた世の中にこれを広めたいとの意気込みと、ネーミングセンスを同時に感じます。
「鮎(あゆ)生漬(きつけ)三日仕(つかまつ)り、鮎(あゆ)の塩出し申さず(≒塩漬鮎は塩抜きをせずに)
、そのまま食は玄米(≒飯は玄米のままとして)
焚(た)き干し(≒煮てから蒸らすという、当時の農村部では一般的な炊飯方法によることとし)
、成る程(≒可能な限り)
こわく(=強く)
仕(つかまつ)り(≒堅めに蒸らして)
、米の積(つも)りは(=米の量は)
、右の如くに候(≒上記にある 上巻74 子籠鮎当座鮓仕様にて前述したものが目安となるのだが)
、重(おも)し強く掛け置き、遣(つか)い申し候時分は、右の当座付の如く(≒これも、上記にある 上巻74 子籠鮎当座鮓仕様に前述したもののように)
仕(し)なおし(=直し)
申し候。」
上巻76【魚もたせの様の事】・・・「塩や酢、酒を使用した魚の保存方法について」。
「塩二盃、酢一盃、酒三盃、
右合わせ(≒塩二盃と酢一盃、酒三盃を合わせて)
、さわさわと煮て、この水に魚を三枚におろし入れ置き候得ば、六月にても、十日、十五日は新しき候ており(=居り)
申し候由、井上筑州(いのうえちくしゅう)へ吉利支丹(キリシタン)相(あ)い伝え申し候よし(≒ ~と、当時の井上筑州がキリシタンから伝えられていたとの事)
。」・・・文中の「井上筑州」とは、江戸初期の禁教政策の中心人物とされる「井上政重(いのうえまさしげ)」のことであり、江戸幕府「宗門改役」を務めた「下総高岡藩初代藩主」です。
上巻77【松平與兵衛(まつだいらよひょうえ)殿より参じ候(≒松平與兵衛殿から伺った話によれば)
鰹たたき(≒鰹は敲き)
塩をはぜたたく也(≒塩は爆ぜ敲くそうだ)
】
「鰹(かつお)一本たたき(≒鰹一尾を敲きとし)
、喰塩(くらいじお)に仕(つかまつり)り候(※通常の塩分量で良いとの意味か?)
。板につけ(=付け)
塩の加減、焼きて食(くら)い見申べく候。糀(こうじ)は三分一ほど、塩の時分に入れて、鉢になりとも、桶になりも入れ申し候。八分め程入れ候得ば、一杯になりあがり(=成り上がり)
申し候。その時分竹にて上下へかき(=掻き)
合わせ、日に干し申し候。六、七日程かき(=掻き)
候得ば後はなり(=成り)
申さず候。その時分(じぶん)は取り入れ申し候。なり(=成り)
申さず候内は蓋(ふた)をあけ置き> (=蓋は開けて置いて)
、いきり(=熱〔いき〕り≒熱気や湯気があるような様)
の、こみ申さず候様に(≒発酵過程で発生する熱やガスが充満することが無いようにして)
冷まし申し候。六月はその日の内に成り申し候。寒時は、おそく(=遅く)
なり申し候。夏冬ともに日にあて(=当て)
申すべき候。」・・・この料理は、比較的簡単な鰹の保存方法や簡易な鰹節製法のように感じられます。尚、上記にある 上巻76 【魚もたせの様の事】 の次に記述されているため、「松平與兵衛」は・・・下総高岡藩や常陸下妻藩(※どちらも井上家)の重臣だった可能性が高いのではないか? と考えます。
上巻78【小米(こごめ)酢の法】・・・「米」や「糀(こうじ)」、「水」、そして「きじ」を、連想させるような何か? を使用した簡易な米酢製法?
「小米(こごめ)三升めとを去る(≒三升の小米を目途とするならば)
、糀(こうじ)九合、水六升、
小米、砂を去り、水にて洗い、ざる(=笊)
へ入れ、水を乾かし、こわめしの如くに(≒堅めに蒸し上げた米飯のように)
、ふかし(=蒸かし)
、糀(こうじ)を水へ入れ、冷めざる内にかき(=掻き)
回し、きじのおそね(※何かを形容しているようであり、意味も不明となりますが、後述します)
一本、堅炭(かたずみ)一つ、はし(=箸)
にてゆいすすぎ(=結い濯ぎ)
、桶底(おけぞこ)へ入れ申し候。」・・・「きじのおそね」についてが、いまいち、その意味が読み取れないのです・・・が、「おそね(=小确)」という言葉は、元々“石まじりの痩せた土地”を意味するため、鳥の雉の足部のことを連想して「きじのおそね」と呼んでいたとしても、何ら矛盾しませんが、ここは“キジ違い”で、「生地」のことだろうと想います。そして、この「きじのおそね」を、「堅炭と結い濯いで桶底へ入れる」という文章から、私(筆者)は“木綿製の組み紐”を連想いたします。炭はアルカリ性ですし、桶の中を酸性から中和して、アルカリ性の液体に変化させ、中和に役立つ成分を吸着させるという目的で、木綿製の組み紐一本を入れたのではないでしょうか? これも科学です。
中巻1【寒さらし餅の方(ほう)】・・・「寒さらし餅の用い方」。「寒さらし餅」とは、「寒晒の餅」のこと。餅米(もちごめ)を水に長期間浸け置きし、後に陰干しするものであり、脂肪分が減って、粒子が細かくなるのが特徴。・・・尚、ここから中巻に入り、日持ちのする餅類や菓子類、滋養効果があると考えられる食品などに関する記述が続きます。
「餅上白米を(=餅米を上白精米したものを)
寒三十日、水にひたし(=浸し)
、一日一夜に一度ずつ替え、三十日過ぎて、取上げ日によく干して紙袋に入れ置くなり。餅にいたし候時は右の米を(≒前述した良く干した上白餅米を)
水にて湿(しめ)し、臼(うす)にて叩き(=搗いて)
、絹篩(きぬぶるい:≒細かな粒子になるようにふるいに掛けて)にて、よくふるい(=良く篩い)
、いかにも(=如何にも)
熱き湯にて捏(こ)ね申し候。初めは熱く候て手さえ入れられず候を、箸(はし)にて廻(まわ)し、少し冷め候てより、手にて成程(なるべく)捏(こ)ね回し候えば、搗(つ)きたる餅のように成り申し候。よき加減にちぎり(≒良い加減で千切って)
、鍋に湯をたて、その中へ入れ、煮申し候えばあがり申し候(≒煮てしまえば出来上がりにござる)
。その時取り上げ、 豆の粉(=きな粉)
へなりとも、又(また)小豆(=あずき餡)
へなりとも取り申し候。味噌にて煮候わんも存じ候えば、湯になしに(≒湯で煮たりしないで)
、すぐに(=直ぐに)
ふくさへ入れ申し候。」・・・文中最後にある「ふくさ」は、漢字で書くと「袱紗」となり、絹、縮緬(ちりめん)などで一重または表裏二重に作り、無地や吉祥柄などの刺繍を施したもののことです。物を包む「包み袱紗」や、進物の上に掛ける「掛け袱紗」がありますが、この文中にあるのは、“掛けるタイプ”のものではなく、包んで置くための「包み袱紗」。いずれにしても、方形の儀礼用絹布のことです。
中巻2【茂(も)ろこし餅】・・・「もろこし餅」のこと。「もろこし」は、「とうもろこし」と良く混同されてしまいますが、イネ科の一年草の穀物であり、漢字で書くと「蜀黍」や「唐黍」となり、別名としては「高黍(たかきび)」があります。日本列島に伝来した時期等については、“室町時代に中国を経由して齎(もたら)されたもの”と考えられています。
「寒の中にても、何(いずれ)成りとも、蜀黍(もろこし)を洗皮(せんぴ)を(≒蜀黍の皮部分を洗って)
石臼(いしうす)にて、ひきすて候て(≒挽き捨ててもらって)
、その後又(また)よき所を、石臼(いしうす)にて成程(なるべく)細(こま)かにひき(=挽き)
、蒸籠(せいろ)に掛け申し候。さて下り申さず候を何べん(=何返も)
もひき(=挽き)
、せいこうに(=精巧に)
掛け申し候。水にてかきたて(=水にて掻き立てて)
、木綿の袋へ入れ、水の中にて、もみ(=揉み)
出し、水を三返(さんべん)も替え(=その水を三度程入れ替えて)
、あく(=灰汁)
を取り下(くだし)にいさせ(≒灰汁は取り除いて)
、上の水を捨て日に干し申し候。餅の時は固まり候を粉にいたし、熱き湯にて捏(こ)ね、湯におして(=湯煮をして)
、浮き上がり候時、豆の粉へなりとも、小豆(あずき)へなりとも取り申し候。餅の粉入れ申さず候ても、苦しからず候。餅の粉入れ候時は、餅の粉三分一入れ申し候。」・・・尚、この当たりから、暫らく甘味やお菓子系統の項目が続きます。
中巻3【粟餅(あわもち)の仕様】
「粟を臼(うす)にてはたき(≒粟を臼で搗〔つ〕き)
、あら皮(=粗皮)
を取り候て捨て申し候。その後、石臼(いしうす)にてひき(=挽き)
、絹篩(きぬぶるい)にてふるい(≒絹篩で篩って)、餅米(=上記にある 中巻1 寒ざらしした餅米粉 のこと)
を、三つ一分混ぜて(≒三つに一つを目安に)
、ばらばらにこね(=捏ね)
、蒸籠(せいろ)にてよく蒸(むら)して、臼(うす)に入れつき申し候(≒臼に入れて搗くのです)
。さて小豆(あずき)にても、豆の粉にても取り申し候(≒これはこれで小豆餡でも、きな粉でも箸がススムのだ)
。」
中巻4【水飛餅(すいひもち)の仕様】・・・「水飛餅」とは、上白の餅米粉の水分を干して蒸発させるなど、火を使わずして長期保存できる餅を作る方法のようです。・・・おそらくは、時代が時代ならば「戦さ飯(いくさめし)」とされる代物ではありますが、江戸時代に頻繁に起こった飢饉に対策するための食品と云って良いのではないでしょうか? この「水飛餅」のように「水飛」させて作る食品には、伝統的な食品として「凍みこんにゃく」や「凍み豆腐」が挙げられますが、現在の茨城県常陸太田市より北部の地域は、気温の寒暖差が大きい処と云えますし。
「上白の餅米を、水にほどはかし(≒ただ水煮とするように湯で沸かして)
、摺鉢(すりばち)にて摺(す)り、木綿の袋へ入れ、水の中にてもみ(=揉み)
出し、上水(うわみず)を捨て、日に干して、寒晒(かんざら)しの餅の如くに(≒上記にある 中巻1 寒さらし餅の方 と同じ様に)
、こしらえ(=拵え)
候。但し、寒晒(かんざらし)の米を、水飛(すいひ)にいたし候てもよく候。さりながら、寒晒の米は只(ただ)の米程、餅白くこれ無く候(≒しかしながら、寒晒の米は只の米とは異なるので、餅は白く仕上がりません)
。」
中巻5【やうかん(=羊羹)
の仕様】
「小豆(あずき)一升、葛(くず)二号七勺、黒砂糖二百五十匁、
黒砂糖ちりをよく取り(≒黒砂糖は、そこに含まれる塵をよく取ってから)
、その中へ、木綿の袋に入れ候。小豆(あずき)の粉を、砂糖の分量大栗(おおぐり)ほど入れ申し候(≒大栗を甘く煮詰める際のように砂糖を入れるのです)
。されども砂糖固く候わば、大栗ほど(=大栗程)
又(ま)た入れ申し候。かき(=掻き)
回し候えば、砂糖ゆるやかに成り申し候。その時、綟(もじ:※麻糸で織った目の粗い布のこと)
にて念を入れ漉(こ)し、塵(ちり)、かす(=滓)
を、捨つるためなり(≒捨てる為なのです)
。右の小豆(≒前述した工程を経た小豆を)
よく煮て、その後摺鉢(すりばち)にて摺(す)り、水嚢(すいのう:※曲げ物の底部に、馬の尾の毛や銅綱でできた細かい網を張った濾〔こ〕し器・篩〔ふるい〕の一種)
にて(豆の内)
皮を取り、よく漉(こ)し、又(ま)た汁を木綿の袋に入れ絞(しぼ)り申し候。水気をよく取り申し候。その中へ葛(くず)、砂糖を混ぜ、さてなりはいかようにもして(≒成形については適宜で構わないので)
、竹の皮にて包み、その上を木綿にて包み、蒸籠(せいろ)に入れ蒸し申し候。加減は、蒸籠の内へ生なる豆少し入れ、その大豆の食われ候ほどの間、蒸し申し候(≒蒸し加減については、生の豆を蒸籠に少し入れて、大きめの豆が食べられる程度の固さまで蒸らすと宜しい)
。その後、取り出し、よく冷まし、竹の皮ともに切り申し候。」
中巻6【あんだんごの仕様】
「常の団子の如くに(≒普段食べている、だんごのように)
、捏(こ)ねて中へ餡(あん)をいれ、蒸籠(せいろ)に置き蒸し申し候。蒸し加減は、餅に、ひかり色出で候程蒸し申し候(≒蒸し加減は、餅に光沢やツヤが出るようになるまで蒸し上げるのが宜しい)
。餡(あん)は、羊羹(ようかん)の如くなり(≒上記にある 中巻5 やうかん〔=羊羹〕の仕様 のようにすること)
。しぼり粉の餡(あん)を入れ申し候(≒小豆を搾って、滑らかになった餡を入れるのです)
。」
中巻7【とち餅(=栃餅)
の仕様】・・・ここで、「鳥もち」ならぬ、「とち餅」が登場しますが・・・これも、飢饉対策用食品と云っても良いのではないでしょうか?・・・灰汁抜きが、大変ですから。
「餅米一升、栃(とち)の粉三合(栃の毒〔あく:=灰汁〕
を取り、粉にはたく〔≒粉状になるまで搗くようにすること〕
)
右餅米を(≒前述した一升の餅米を)
、さっと湯煮(ゆに)をして、笊(ざる)へ上げ、栃の粉をふりかけ(=降り掛け)
、混ぜ合わせ、水を注(そそ)ぎ、手に握り候えば、手の内にて固まり申す程に、水を注(そそ)ぎ申し候。その後、よく蒸して常の餅の如く(≒その後、良く蒸らして普段食べる餅のように)
、つき(=搗き)
申し候。蒸し加減は成る程(=可能な限り)
よく蒸したるがよし。つきたて(=搗きたて)
をそのままも食べ申し候(≒搗きたてをそのまま食しても良い)
。又(また)かき餅も仕(つかまつ)り候(≒また、かき餅とすることもできますよ)
。」
中巻8【たいりちまきの仕様】・・・著者・徳川斉昭は、京都御所などを連想させる「内裏(だいり)」という言葉を用いて、ネーミングしています。きっと、「うるち米」や「餅米」を上白精米した最高級米粉を用いる「ちまき」だったからだと想います。水戸徳川家とは、何かと縁の深~い都だった訳ですし。
「粳(うるち )の上白米一升、餅の上白米二升、
水に加(か)し叩(はた)き候て(≒米を水洗いし、水を切ってから、臼で搗いたものは)
、二色ながら(≒粳米と餅米の違いはあるけれども)
絹篩(きぬぶるい)にて篩(ふる)い申し候。 右水一升に、砂糖半斤入れ、よき加減に捏(こ)ね申し候。又(ま)た黒砂糖にて、同じ如くに捏(こ)ね、二色に作り(≒白色と茶色の縞柄状になるように)
、黒砂糖にて、捏(こ)ね候を筋(すじ)に付くように混ぜ、熊笹(くまざさ:※笹の葉の一種)
にて包み、畳のりにて巻き、蒸籠(せいろ)にて蒸し申し候。」・・・最後の文中にある「畳のり」とは、おそらくは畳表(たたみおもて)や縁(へり)の部分を縫い上げるために用いる畳糸のことであり、丈夫で耐久性のある「青麻」で作った糸だったのではないか? と想います。・・・これを、当時の水戸徳川家(水戸藩)が、独自に入手できたとするならば、その生産候補地は・・・藩領内で海に近い地域かな? と想います。
中巻9【けんひんのやき様】・・・「けんひんの焼き方」。
「うどんの粉へ(=小麦粉へ)
、白砂糖をよき加減に入れ水にて、どろどろと」・・・この「けんひん」なるものには、諸説あるのですが、本文にあるように「~入れ水にてどろどろと」という処で、原文が終了しています。したがって、この後に著者・徳川斉昭が加筆しようとしていたのに、何らかの事情によって、それが出来なかったのか? などは、分からず仕舞いとなっています。・・・ただ、この文章の前後を観れば、斉昭は「けんひん」を、甘菓子の一種であると考え、この項目名で「焼き様」としているので、今風に云えば・・・「卵が入っていなくて、甘いクレープ」・・・と云えるのではないか? と想いますし・・・また、この当時、精製された「白砂糖」を入手できたのは、ごく限られた人達だったのではないか? とも想います。
中巻10【らくがんの仕様】・・・「落雁の仕様」。
「白砂糖、水ひたひたに入れ湯になり候時、木綿にて漉(こ) し、石の鍋にて、又(また)一泡(ひとあわ)立て、冷まし、さて道明寺(どうみょうじ:※水に浸し蒸した餅米を乾燥させて粗めに挽いたもの)
の糒(ほしいぃ:=干飯)
少しいりて(≒ ~から、餅米を、まず水に浸し、蒸し上げてから乾燥させた米粉〔=道明寺粉〕を、少しばかり炒って)
、右の砂糖の汁にて(≒前述の木綿で漉した白砂糖汁を)
、捏(こ)ね固め、成りはいかよう(=如何よう)
にも致し、内に干し申し候(≒屋根下で干すと出来上がり)
。」
中巻11【あるへいとう】・・・「或る平糖」、若しくは「荒平糖」か?
「砂糖水ひたひたに入れ、木綿にて漉(こ)し、塵(ちり)を取り、火をゆるゆるして、煎じ候えば(≒煮詰めていくと)
、ねばり(=粘り)
出て来申し候。箆(へら)にて付け、水へ入れ扱(しご)き見候えば、冷めては折れ申すものに候(≒冷めると折れ易いものと成る)
。その時、鉢に入れ水せんにして(≒鉢に移し替えて、水にくぐらせて)
、ぬるく冷まし、飴の如くに、ちと固まり候時(≒少し固まってきたら)
、手にてなるほど引き延ばし(≒人の手によって、できるだけ引き延ばし)
、薬練(くすね:※松脂〔まつやに〕を油で煮て練りまぜた接着剤。粘着力が強力で武具製作などにも使用するもの)
を致し候様に仕(つかまつ)り候(≒薬練を準備する際と同様に致すのだ)
。白く成り申し候(≒=白くなってまいります)
。成りは如何(いか)ようにも心次第に候(≒形状はお好みのままで良い)
。白砂糖よく候(≒白砂糖との相性が良い)
。氷砂糖にては猶々(なおなお)よく候(≒氷砂糖とした場合には、これまた絶品と成る)
。」・・・ネーミングに現れていますが、「金平糖」が意識されいるようです。いずれにせよ、飴を練り上げた菓子です。
中巻12【かすてらほうろ】・・・ネーミングは「カステラ・ボーロ」とされています。“堅めのカステラ”と云うより、「ビスケット」と云ったところでしょうか?
「白砂糖百六十目、たまご(=鶏卵)
十六、うどんの粉(=小麦粉)
百六十目、
右(≒上記の食材全てを)
鉢(はち)にてよく捏(こ)ね合わせ、菓子鍋に油をひき、右を捏(こ)ね申し候を焼き申し候。焼き候時は、炭火(すみび)をあまり強くこれなきように(≒炭火の火力は弱火として)
、上下に炭火(すみび)を置き申し候(≒上下に炭火を置いて熱を掛けるのです)
。さて焼き加減は蓋(ふた)をあけ(=開け)
、焦げぬほどに焼け申し候時よく候。右捏(こ)ね申し候を二度に焼き申し候(≒上記の食材全てをよく捏ね合わせたものを、菓子鍋に油をひいて弱火で二度焼きとするのです)
。」
中巻13【こうらいせんべい】・・・「高麗煎餅」とのネーミング。
「一、白さは(≒白きものは)
常の如く米をつき、白砂糖をよき加減に入れつき(=搗き)
合わせ、煎餅を焼き候物にて、焼き申し候。
一、黒きは(≒黒きものは)
黒砂糖にうどんの粉(=小麦粉)
を混ぜ、右の如く(≒前述したように)
捏(こ)ね合わせ、焼き申し候。」・・・白いこうらいせんべいの食材は、うるち米と白砂糖で甘いもの。二度焼きするようなので、相当に堅く、焦げ易かったかも?・・・黒いこうらいせんべいの食材は、小麦粉と黒砂糖で、これも甘い煎餅。但し、こちらの方は、白いこうらいせんべいよりは、堅くなく・・・南部せんべいのような感じかと想います。
中巻14【葛餅(くずもち)、但(ただし)、湯煮(ゆに)をする餅なり】・・・「葛餅、但し湯煮する餅なり」と、但し書き部分を強調しています。
「葛(くず)の粉一盃、但し、おろし申さぬくずを(≒下〔お〕ろしていない葛を)
白砂糖一盃、水一盃、三色ながら同じ(≒葛粉と白砂糖、水の三種があるが、全て同じ分量とし)
、秤物(はかりもの:※天秤など物の重さをはかる道具のこと)
にて秤(はか)り申し候。
右三色よくよく捏(こ)ね合わせ、竹の筒へ入れ申し候。但し、竹節(たけふし)の跡先(あとさき:=後前)
にこめ(≒但し、竹節の後前に、これを込めて)
、上を成る程(≒その上側部分をできるだけ)
、うすく成り申す程削り(≒薄くなるように削って)
、一方の節に穴を空け、その口より葛(くず)を流し入れ、鍋に湯をたて半時程煮て(≒鍋に湯を沸かして一時間程煮て)
、その後、水につけ(=浸け)
、竹を割り取り出し申し候。如何(いか)ようになりとも切り申し候(≒どんな形状と成っても構わないので切って食すのだ)
。」
中巻15【ういろう餅の方】・・・「ういろう」を漢字で表すと、「外良」や「外郎」となりますが、蒸し菓子の一種です。
「うる上白米七合粉々にして(≒上白に精米したうるち米七合を粉々とし)
、餅上白米三合、白砂糖少し、右二色の米一つに合わせ(≒前述した上白うるち米七合と上白餅米三合を一つとしたものを)
、半分ずつ取り分け、一方はくちなしの汁にて(≒一方は梔子の汁を使って)
捏(こ)ね、はらはらの加減にして(≒小さいものや軽いものが、静かに続けて落ち掛かるような絶妙な加減とし)
、一方は水にて捏(こ)ね、米通しのあらきにてふるい(≒米研ぎに使用する粗目の笊〔ざる〕にて篩〔ふるい〕に掛けるように繊細に)
、蒸籠(せいろ)に入れ蒸し申し候。黄色と白色との間に、箕(み)のすりかき(≒箕で編んだ農具のように)
うすくへぎ(≒薄く平らな形状に成形して)
ならべ申し候時、蒸籠(せいろ)より上板の上にて冷まし、切り申し候。」・・・文中の「くちなし」は、単に食材を黄色に色付ける着色料ではありません。薬効成分が認められている「生薬」でもあります。ここにある「くちなしの汁」は、くちなしの果実を水で煮だして抽出した液体のことであり、人の胆管や腸管の狭まりを拡張させる効用があると考えられております。・・・また、この「くちなしの汁」は、本州では静岡県以西、ほかに四国地方や、九州地方、沖縄県などでしか栽培ができないものらしく、江戸時代後期の東日本や北日本の地域では、当然に西方から齎(もたら)される貴重品とされたようでして、“慎重に扱って”との徳川斉昭の声が聞こえてきそうですが・・・もしかすると、もっと化学的な根拠に基づいていたのかも知れません。・・・「くちなしの汁」に含まれる黄色の色素・ゲニピンには、精米が甘い米に残留する米糠に含まれたアミノ酸と化学反応を起こし、これがもし食べられずに時間を置いて発酵してしまうと・・・本能的に人間が持っている食材の色見としては適当ではない・・・青色の着色料になってしまいますので。・・・それ故の「うる上白米」と「餅上白米」という風に、きちんと記述して、念を押すかの如く「はらはらの加減にして」との表現になっていると考えられる訳です。
中巻16【あさいな粽(ちまき)】・・・「あさいな」を漢字で表すと、「朝比奈」となるようでして。・・・この場合には、「い」を「ひ」と発音しています。・・・しかし、もしも「い」を、そのまま「い」と発音するのならば、「浅井菜」など、他にも「呼び名」としての可能性が出てくることになります。・・・いずれにせよ、水戸徳川家(水戸藩)藩士の家系には、「朝比奈」と「浅井」の苗字を、それぞれの家名とする家系がありましたので・・・これら両家にそれぞれ属した家臣達は、それぞれが殿様に、この菓子? もとい、正月やお盆、節分などにおける御馳走的な保存食として、その作り方とともに献上していた可能性が高いと想われます。・・・そうでないと、以下のように、似たような食品の作り方が、何故に併記されているのか? についての説明が苦しくなりますので。
「一、たいとう餅(※この名詞の漢字表記については、二種ほど可能性がありますので後述致します)
上白米水にて洗い(≒上白に精米した うるち米 を水で研いで)
、椿の灰汁(つばきのあく:※アルカリ成分高し)
にて洗いたる米をひたし(=浸し)
、飯に炊き加減(≒米飯にする加熱具合などは)
常の飯ほどにして、桶(おけ)へ取り上げ、又(ま)た椿の灰汁ちとづつ(≒椿の灰汁は少しずつ)
打水(うちみず)に(≒打ち水を)
して、箸(はし)にて捏(こ)ね合わせ候えば、よせ加減に(≒寄せるがままに)
練(ね)れ申し候。さて、一つ一つになりつくり候て、眞菰(まこも) か、熊笹(くまざさ)にて、巻き申し候。その後ゆで(=茹で)
候事。煮え湯へ、さっとつき入れ(≒煮えた湯にサッと突き入れたものを)
、上げ申し候てよく御座候(≒ ~を取り上げれば良いのです)
。」
一、同方(≒上記の たいとう餅 と同じ方法のようだが)
、餅米一升、椿の灰汁二升、まず二番の灰汁にて(≒まずは二番目に記述した椿の灰汁二升を用いて)
、米付き(≒餅米を搗いて)
こわく蒸し候て(≒堅めに蒸らして)
、一番の灰汁を(≒上記にある うるち米を 研いだ際に出た椿の灰汁で)
蒸したる強飯(こわめし)の上に(≒堅めに蒸し上げた米飯の上部より)
、打水(うちみず)にして(≒打ち水して)
柔(やわ)らかに蒸し候て、つき(=搗き)
申し候。」・・・さて、文頭部分にある「たいとう餅」と記述されている名詞で、漢字表記として適うものとしては・・・「鯛頭餅」。縁起の良さそうなネーミングなのです。これが。・・・若しくは、「対等餅」。こちらの意味としては、“原文中にある二項目は、どちらも甲乙着け難い”という『食菜録』の著者・徳川斉昭の評価が、根底にあるような気が致します。・・・いずれにせよ、前段文中にある食材は、「うるち米」のみとなり、料理法の順番としては、「椿の灰汁による炊飯」+「椿の灰汁の打ち水」+「何かしらの葉で巻いた後に煮ることで、一応の出来上がり」となるが・・・+「食べる直前に、再度温める」と。・・・尚、こちらについては、「眞菰や熊笹を巻く」とあるので、「粽(ちまき)」と認定しても大丈夫そうです。分量としても、家庭的な量で記述されているように感じますし、暫らくの期間は保存も効くとの認識もあったかと。・・・すると、以下の記述を、どう解釈すれば良いのか?・・・まず、こちら後段の記述には、“何かしらの葉で包むという描写”がありませんので、「粽(ちまき)」とは云えない気が致します・・・が、一般家庭向けか? 大衆向けなのか? は別にして、この『食菜録』の著者・徳川斉昭としては、これら二種の料理レシピについては、各地の伝統や歴史に深く関係する大変貴重な「食文化」との認識があったのかと想います。・・・また、項目名横にある「朝比奈」と「浅井」の両家それぞれのルーツは、それぞれ東海地方や近畿地方に遡れると想いますが、これら家臣達の先祖やルーツに関する情報も、藩主だった斉昭は知ることができる立場にあった訳です。これらについては、別ページに記載しておりますので、ここでは割愛させて頂きますが。・・・いずれにしても、後段文中にある食材としては、「餅米」のみとなり、料理法の順番としては、「椿の灰汁二升で以って餅米一升を蒸す」+「固めに蒸した餅米に対して椿の灰汁の打ち水」+「アツアツの状態の餅米に対して水のみを打ち水して、蒸らしが完了」するが・・・+「最後に、通常の餅同様に搗く」と。・・・こちらは、上記の一番目料理レシピの作り方とは異なっていて、使用する材料の分量が・・・より大きく具体的に記述されて、より大衆向けになっており・・・これを有事平時の別で云えば、まさしく「平時」の印象を受けますね。
中巻17【ひりうす】・・・「ひりうす」を漢字で表すと、「飛竜頭」と表記します。読み方は、ここにある「ひりうす」の他には、「ひりゃうす」や「ひろうす」、「ひりうず」、「ひりょうず」などがありますが、きっと以下の記述を観れば気付かれると想います。ここにあるのは、“がんもどき(=雁擬き)の類似食品”です。・・・江戸時代の「がんもどき(=雁擬き)」は、“そもそも現代のように豆腐に具材を混ぜ込んで揚げたものではなく、饅頭のように豆腐で具材の餡を包んで揚げたものであった”と云いますが、ここにある「ひりうす」には、「豆腐」どころか「大豆」も出てきません。・・・なので、ここは“甘いだんご菓子”と、ご認識下さい。
「麦の粉か、米の粉にてよし、鍋に水を入れ、にやし粉を入れ(≒鍋に水を張り、それが沸騰したところに、前述の粉を入れたら)
ふかせ(=蒸〔ふ〕かして)
、後に湯をしたみ合わせ(≒後に湯の水分を切ってから)
、卵の黄なる所を入れ(=卵黄部分を入れて)
、摺鉢(すりばち)にて摺(す)り、それを油にて揚げて、但し、うるの粉七合(≒但し、うるち米の粉七合と)
、餅の粉三合、細(こま)かに、はたき(≒叩〔はた〕き落とせば)
、それにてよく御座候。卵、米一升に七つ程入れ(≒卵は米一升に対して七個ほど入れるように致して)
、砂糖の煎じたるに(≒それらと砂糖をともに加熱したものを)
、ひたし置き出し申し候(≒煮浸しとしておいて、それを料理として出すのです)
。右砂糖煎じ様(≒前述した砂糖への加熱方法は)
、砂糖一斤に水一升入れ、七分の内に煎し申し候(≒だいたい三割程度の水分量になるまで加熱するのだ)
。あけ申す時は(≒それを取り上げる時には)
、太匙(ふとさじ)にて、すくい(=漉〔す〕くい)
、鍋に入れ、上げ申し候。なりも(=成りは≒形状は)
匙の内手心次第にて色々になり申し候(≒形状は、料理の腕前次第にて、色々なものが出来上がります)
。」・・・ちなみに「ひりうす」、若しくは「飛竜頭」の、元々の語源は・・・“ポルトガルのフィリョス(filhos:※小麦粉と卵を混ぜ合わせて油で揚げた菓子のこと)に由来する”・・・と謂われております。
中巻18【ごぼうもち】・・・「牛蒡餅」。これに山椒味噌(さんしょうみそ)などを付けて食べても良さそうですね。
「牛蒡(ごぼう)よく煮て、細(こま)かに裂(くだ)き、餅米の粉五合、粳(うるち)の粉五合、さき牛蒡(=裂き牛蒡)
と一つに捏(こ)ね合わせ、同じ加減は常の如く作り候。大栗(おおぐり)ほどにして(≒大きめの栗ぐらいのサイズとし)
、厚さは少し平(ひら)めにして、これを油にてよくあげ申し候後に(≒これを油でよく揚げた後に)
、煎じたる砂糖のみづ(≒一煮立ちさせた砂糖の蜜)
につけ(=漬け)
、二、三日も後に出し申し候。但し、ごぼう(=牛蒡)
は三分一。粉は多め。」
中巻19【さうきう餅】・・・「さうきう」を漢字で表すと「宗及」となり、安土桃山時代の堺の商人で茶人として有名な「津田宗及」の名が使われていますが・・・。
「粳(うるち)の粉七分、餅の粉三分、なまたれの(=生垂の)
色合いにて、いつもの団子の加減に捏(こ)ね合わせ、かまぼこ大いさ程に(≒蒲鉾大のサイズとし)
作り申し候。但し、粉一升に白砂糖六十目程入れ申し候。それをよく捏(こ)ね合わせ、蒸籠(せいろ)にて二時ばかり蒸し申し候(≒蒸籠で四時間程蒸らすのです)
。よく冷まし、切り候て出し申し候。右の内へ(≒良く冷まして切ったものに)
、胡桃(くるみ)剥(は)かして二十程入れ、又(また)一さおには、山の芋の皮を去り、内へ入れたるもよくござ候。」・・・文中にある「生垂の色合いにて」という表現が、現代の関東人からすると? となるのですが、この「生垂」という言葉は、近世の京坂地方で多く用いられた言葉だそうで、“男子が、女々しくて女性的であったり、にやけた様(さま)”に使ったそうです。・・・したがって「生垂の色合い」とは、今風に云えば「グニョグニョしてナヨナヨした状態」を云っており、それ故の「宗及餅」とのネーミングかと想います。
中巻20【はたき餅の仕様】・・・「叩(はた)き餅の仕様」。
「上白米をひきわり(=挽き割って)
、粉にいたしたるを(≒=粉状にしてから)
、篩(ふるい)にてふるい、成程(なるべく)煮え湯にて捏(こ)ね申し候。粉一升ならば、たま四つ(≒玉四つ程作れるが)
、それを五寸まわり程にひしめ(≒それらを五寸程離しつつ纏〔まと〕めながら)
、大鍋にて湯をたたせ、その中へ入れ一時たらず程たき申し候(≒その中へ入れてから二時間弱炊くのです)
。さて、取り上げ見て申し候。その時、取上げ水にてよく洗い、粘りを取り、さていかき(≒さて笊〔ざる〕)
へ上げ水気を取り、臼(うす)もよく水気を取り、そろそろとつき申し候(≒臼も良く水気を切り、慎重且つ繊細に搗〔つ〕くのです)
。これも、一時たらず程(≒これも、二時間弱程)
つき(=搗き)
申し候内に、つや出来申し候(≒艶が出てきます)
。つや出来申し時よく御座候(≒艶が出れば良い仕上がりとなります)
。」・・・この餅には、「あんこ」や「きな粉」の記述がありませんので、上白米が持つ本来の甘味を愉しむ餅のようです。但し、後の事は読み手次第で! との著者・徳川斉昭の声も聞こえてきそうですが・・・。
中巻21【葛(くず)やき仕様】・・・「葛焼き仕様」。
「水汁椀(しるわん)に一盃半分、同じく秤物(はかりもの)に葛(=葛粉)
を半分、白砂糖十三匁、塩茶(しおちゃ)一服程、右の葛餅練(ね)る如くに練り(≒前述した食材全てを葛餅のように練って)
、よく練れ候時取り上げ、葛の取り粉(=葛粉の取り粉)
にて取り入れ、鍋にて、そろそろと焼き申し候。火はなるほど弱く致し申し候。」・・・文中にある「塩茶」とは、塩を加えて焙じた茶葉で淹(い)れた茶のこと。あるいは食塩を少し入れた茶碗に熱い焙じ茶を注いだものでして、酔い覚ましの際などに用いたりもします。
中巻22【あめねり様(よう)】・・・「飴粘(ね)りの様(さま)」。・・・まるで、著者・徳川斉昭が飴粘り現場を実況しているような? ・・・実際に観て実践したのでしょう。
「白砂糖三斤、水二升、
右銅鍋に入れ(≒前述したものを銅鍋に入れて)
、炭火(すみび)の上にて、一あわ煎じ(≒一煮立たせさせ)
、毛篩(けぶるい:※馬の毛で作った篩のこと)
にて漉(こ)し、鍋をよく洗い、右の鍋に入れ半分になる程煎じ、米の酢盃に七分ほど入れ、又(また)一あわ煎じ、汁飴(しるあめ)、飯椀(めしわん)に八分め程入れ、一あわ煎じ、餅米三合五勺よく摺(す)り入れ申し候。右へら(=箆)
にて、二人も三人もより合わせ(≒二人か三人で以って縒〔よ〕り合わせて)
、鍋底につかざるように粘(ね)りつめ、たらたらと、よき加減の時、うどんの粉の上へ(=小麦粉の上へ)
、杓子(しゃくし/しゃもじ)にて移し固まりたる時、切り申し候。」
中巻23【いねもちの方】・・・普通に読めば、「稲餅の取扱い方」。
「餅米上白、水にひたし(=浸し)
、成程(なるべく)細(こま)かにはた(=叩)
き、絹篩(きぬぶるい:※絹布を底に張った、きめ細かな篩のこと)
にて通し申し候。常の団子の如く、丸め申し候。右の粉少し取り上げ、青くや、黄色、黒色などに致し候て、右のたんすへ(≒前述したものを、どこにでもある箪笥に)
少し所々に置き申し候(≒あまり込み過ぎないように所々に保存して置けば宜しい)
、さて餅(≒さて餅として食す際には)
、蒸籠(せいろ)にかき(≒蒸籠に掛けて)
、よく蒸し申し候。」
中巻24【柿いりの法】・・・普通に読めば、「柿入りの法」となりますが、むしろ・・・ここは「柿煎りの法(=柿を加熱する際の方法)」と読むべきかと想います。原文を読めば分かりますが、「米粉を使った干し柿の天ぷら」のことです。当然甘い味なのですが、干し上がって保存が効いていた柿が、加熱することによって軟らかく食べ易くなるという利点があります。特に歯が弱った高齢者や病中の人にとっては。・・・それ故に「方」ではなく、「法」の字を使用していると考えられます。
「串柿(くしがき:※渋柿の皮を剥〔む〕いて、竹串などに刺して干し上げた干し柿のこと)
にても、すり柿(ズリがき:※渋柿の皮を剥〔む〕いて、縄や糸に吊るして干し上げた干し柿のこと)
にても、二つに割り、種をとり候て、粳(うるち)の粉を水にて、とろりと練(ね)り候て、右の柿を打ち入れ、さて、あけ(=揚げ)
油をよくたたせ(≒油を良く加熱して)
、杓子(しゃくし/しゃもじ)にて、柿一勺(しゃく:※尺貫法による容積の単位です)
ずつ(=柿を一勺ずつ)
入れ上げ申し候。」
中巻25【ちよくせんの方】・・・「ちよくせん」とは、おそらくは・・・「千翼扇」と表記すると想われます。その見た目や外見上から、このようにネーミングされていると考えられます。何となく縁起も良さそうですし、山芋を使用する時点で滋養効果も望めます。・・・今風に云えば、シンプルに「揚げ山芋のスティック」、あるいは「山芋ポテトのフライ」とはなるのですが。
「山の芋を、皮をむき(=剥き)
、山葵下ろし(わさびおろし:※専ら山葵を摺り下ろす調理道具であり、その多くは鮫皮を張ったもの)
にて粉におろし(=粉状になるまで)
、箸(はし)にて、よき加減にちぎり(≒箸で良い加減に千切りとし)
、油にて上げ申し候(≒油で揚げるのです)
。焼き塩ふりかけにてよくござ候(≒焼き塩を降り掛けて食せば良いのです)
。」
中巻26【あぶらあげ】・・・普通に読めば、「油揚げ」となりますが・・・現代人の我々が知る「油揚げ」とは別物です。これにも「大豆」や「豆腐」は使用されておりませんので。・・・これは、「甘く味付けされた揚げ煎餅」となります。
「粳(うるち)の米一升、餅米一升
右何(いず)れも粉にして(≒前述した食材全てをそれぞれ粉状にして)
、米によりかたく候わば(≒使う米によって、堅めに仕上げるようとするならば)
、餅の粉を過し(≒餅米の粉の方を多めにして)
、汁過ぎ候わば(≒汁気が多すぎると感じたならば)
、粳(うるち)の粉を過(か)し申し候。右何(いず)れもへ砂糖入れ。砂糖の加減は、食い申し候て、好き次第にて候(≒砂糖の甘さ加減は、実際に食べてみて、お好み次第と云ったところ)
。三種(=前述した固さ加減や甘さ加減を)
よくよく合わせ、垂れみそを(=垂らし味噌を)
薄くして、それにてよき加減に捏(こ)ね合わせ、大佛餅(だいぶつもち:※京都・方広寺周辺の土産用の餅のこと)
ほどにして、中へくるみ(=胡桃)
、山椒(さんしょう)少し(≒中に、胡桃や山椒を少々)
。平目にして(≒魚の鮃の如く平らにして)
、ごまの油(=胡麻油)
にても、かや(※榧〔かや〕の実から搾り採った上等の植物油のこと)
にても、きつね色より少し濃めに上げ申し候(≒狐色よりも少し濃い色になるまで揚げると宜しい)
。」・・・文中にある「榧油」は、食用の他にも、灯用や理髪用にも利用できます。
中巻27【かうらいあめ】・・・「かうらいあめ」を漢字で表すと、「高麗飴」。
「餅米一升、糀(こうじ)八合、水七合にて、甘酒(あまざけ)に作り候て(≒つまりは、これらの甘酒を作るのだが)
、こし候て煮申し候(≒前述した食材全てを漉〔こ〕してから煮詰めると仕上がります)
。」
中巻28【金山寺のあめ】・・・「金山寺の飴」。・・・何故に、このネーミングとなったのか? ・・・これとは別のこととして、「金山寺味噌」という「おかず味噌」が、紀州和歌山に由来していると考えられております。実際には、「金山寺」と呼ばれる寺院が紀州和歌山にある訳では無いのですが、同じく「きんざんじ」と発音する「徑山寺(※中国の寺院)」から、紀州・興国寺(こうこくじ:※現和歌山県日高郡由良町門前)へ、鎌倉時代に伝わったという説が最有力と考えられております。・・・このことからも、この『食菜録』の著者・徳川斉昭が、この飴の作り方を入手出来た背景には、水戸徳川家と親戚関係にある紀州徳川家の存在があった筈です。・・・それ故に「金山寺の飴」とのネーミングがされているのではないでしょうか?
「金山寺の飴十五匁(=金山寺の飴を十五匁作るには)
、餅の粉五十目、うどんの粉(=小麦粉)
二斤、葛(くず)の粉七匁、わらび(=蕨)
の粉五匁、砂糖二斤、水、右何(いず)れも(≒前述したもの全てを)
混ぜ合わせ煮申し候(≒混ぜ合わせて煮詰めるのです)
。うどんの粉にて上げ切り申し候(≒小麦粉を用いて取り上げた後に切っておきます)
。」
下巻1【味噌の方】・・・ズバリ「味噌の作り方」。・・・尚、ここから下巻に入り、暫らく調味料や調味液、様々な食品に関する記述が続いており・・・冒頭にある「パンの法」も、下巻に記述されています。
「大豆一斗(白水〔=米の研ぎ汁〕
に半日程漬け、その後米を加す〔=干す〕
ように仕〔つかまつ〕
り候えば、上の皮とれ〔=取れ〕
申し候。その後よくよく蒸し申し候。)
糀(こうじ)一斗、塩三升三合、餅米五合(ただ中〔≒この中の餅米だけは〕
、白米の時はかり〔≒餅米が白くなる時を見計らいながら〕
、強飯〔こわめし〕
に蒸して〔≒普段食す際よりも堅めに蒸して〕、よく冷ます〔事〕
。)
右の大豆よく蒸(む)せ候時(≒前述した大豆が良く蒸し上がったら)
、とり出し(≒それを取り出して)
、常の如く搗(つ)き(≒いつものように搗いて)
、いまだ暖かなる内に(≒まだ暖かいと感じるうちに)
、一ト握りほど(=一握り程)
ずつに玉にして、一日一夜ほど風に当て、その後刀にて(≒その後に刀や包丁にて)
細(こま)かに切り申し候。次第に乾き申し候わば(≒ようやく乾いたかな? と思った頃に)
、右の糀塩には食を混ぜて(=前述した糀や塩を餅米飯に混ぜて)
、臼(うす)にてよくよくつき申し候(≒臼にて良~く搗くのです)
。いまだ濡れ気ござ候わば(≒未だに水気が多いと感じた場合には)
、薄くさかし(≒それを薄く広げて)
、陰干しにして、少し乾きめに成り候時(≒少しは乾いたかな? と思える状態になった時は)
、桶へ入れ候、桶の内へも下(した)から、よくつき込み申し候(≒味噌桶の内の下側部分には、余計な空気が入り込まないように、良く搗き込むようにするのです)
。上に紙を蓋(ふた)にして置き候(≒味噌桶の上側部分には紙で蓋をすること)
。右の塩の外(ほか)には、一切ふり塩も仕(つかまつ)らず候(≒前述した塩以外には、降り塩など一切不要です)
。同じくは小さき桶にいくつも入れてよし(≒同じ様に小さい味噌桶をいくつか使って、味噌玉を詰め込んでも良い)
。三十日過ぎ候得は熟(う)れ申し候(=三十日も過ぎた頃には熟成しています)
。右の味噌いつにてもこしらえども(≒ここにある味噌を、いつ頃に作ろうか? と思案したとしても)
、同じくは寒の内にいたし(≒同じ様に寒の内に行なうこととし)
、来年の又寒(またかん)までつかい申し候(≒翌年の寒の時期までには、残さずに使い切ってしまうこと)
。」・・・文中にある「さかす」とは、「表にして取り扱うこと」や、「ひけらかす」という意味の古語となります。
下巻2【悪(あ)しき味噌直し様】・・・ズバリ、「失敗した味噌を直す裏技」。
「大豆一石に、糀(こうじ)六斗、塩四斗の味噌は、悪(あ)しき味噌なり(≒前述した割合によって作られた味噌は、出来損ないの味噌であ~る)
。この味噌を直すには、右の味噌一斗の内へ糀(こうじ)三升、常の飯一升五合(を必要とする)
。但し、米のときはかる(≒但し、必ず蒸す前の米の状態で、しっかり計ること)
。
この二色を混ぜ(≒前述した味噌二種類を)
、よくよく搗(つ)き候て、桶へ入れ、冬は五日、七日程過ぎ、使い申し候。夏は三日程にてよく候。又(また)もとの味噌、糀(こうじ)六斗を、より多く後に入れ候。糀(こうじ)を三升よりは控え申し候。塩も四斗より少なく候わば、後の飯(めし)を控え申し候。」
下巻3【早作(はやつくり)味噌の事】・・・現代とは違って、フリーズドライ製法などは存在しなかった訳ですが、発酵の力を利用した「即席味噌」と云えるかも知れません。
「大豆一升(水にて洗い、蒸してなりとも、煮てなりとも仕〔つかまつ〕
り候。よく煮え候時、火をひき〔=退き〕
一夜そのまま置き候。 明日また少し火をたき〔=焚き〕
、取り出しつき〔=搗き〕
申し候。)
糀(こうじ)一升(右の大豆あたたか〔=温か〕
なる内につき〔=搗き〕
混ぜ、物に包みあたたか〔=温か〕
なる所に一夜なりとも、半日なりとも置き、よく冷え候程冷め候て後、塩を混ぜ申し候。)
塩二合五勺(但し、食塩分量なしにも仕〔つかまつ〕
り候〔≒但し、食塩の場合には、分量を計らず、概ねで良い〕
。)
右の塩(≒前述した塩二合五勺くらいのもの)
を混ぜ、そのままつかい候てもよく候。同じく塩を混ぜ、よくつきて桶へ入れ、明日より遣(つか)い候えば、なおなおよく候。二時、三時にてもなれ申し候(≒四時間か六時間程度で、塩が馴染んでまいります)
。二十日三十日も、そこね申さず候(≒傷みません)
。」
下巻4【醤油の事】
「豆一斗(よく煮て)、大麦一斗(よくしらげ〔≒棒などを用いて良く叩いて平らにして〕
、炒りて引きわり〔≒炒った後に挽き割りとする〕
)。小麦三升(炒りて引〔=挽〕
きわり〔=割〕
とす。)
右三食(≒前述した豆と大麦、小麦の三種を)
よくよく混ぜて寝させ申し候(≒暫らく放って置きます)
。
(塩)
水二斗(この塩水の中にて、よくよく揉〔も〕
み砕〔くだ〕
き申し候。)
この塩水をよく煮やし、冷え候ほど二日も三日も、冷まし仕込み申し候。その時糀(こうじ)八升入れ、桶の中にてもみ合わせ(≒醤油桶の中で、揉み合わせ)
、一日に二度ずつ、攪(か)き申し候(≒攪き混ぜるのです)
。五十日の間かくの如く仕(つかまつ)り候(≒これを五十日間隔で繰り返して)
、その後、中白米一升を、水八升にて粥(かゆ)に炊き、この粥(かゆ)を、入れ物いくつもにあけ(=開け)
、腐敗申し候わぬように成るほど早くあおぎ(≒腐敗しないように、なるべく早く扇いで)
、冷まし冷え候時、右の醤油の中へ入れ、よく混ぜ、その後も初めの如く一日に二度ずつ攪(か)き、二十一日過ぎ候てあけ(=開け)
申し候。二番醤油は右の粕(かす)の中へ、水一斗、 塩五升、前の如くせんじ冷まし候て入れ申し候。その時も、糀(こうじ)をも四升入れ、又(ま)た毎日二度ずつ攪(か)き、二十一日過ぎ、又(ま)た中白米一升を水七升にて、粥に炊き前の如く冷まし、仕込み申し候。その以後も、毎日二度ずつ攪(か)き、十五日過ぎて、あぐるなり(≒完成させるのです)
。」・・・お気付きでしょうか? きっと、著者・徳川斉昭は、醤油の中に棲み付く微生物の働きを理解していたのでしょう。それ故の「攪」です。
下巻5【ひしおの方】・・・「醤の方」。つまり「醤の作り方と保存方法」。
「大麦一斗(成程〔なるべく〕
よくつき、皮の白きように搗〔つ〕
き申し候。一夜水に漬け、蒸し申し候。)
大豆三升(炒りて引〔=挽〕
きわり〔=割〕
、皮をとりて蒸し申し候。)
右二色(≒前述した大麦と大豆を)
一つにして、醤油の如く寝(ね)させ、二十四時過ぎて(≒二日ほど経ったら)
、又(ま)た打ち返し(≒また天地替えして)、五日程ねさせ候て取りい出し(≒五日程休ませたら取り出して)
、揉(も)み砕(くだ)き、かみ(=紙)
に入れて一日よく天気に干し申し候。さて、ひしお(=醤)
に入れ申し候時、よくよくあたたまりを冷まし、冷え候時しこみ申し候(≒冷えてきたら仕込むのです)
。水一升に、塩二升二合入れ、水の中にて塩をよく揉(も)み砕(くだ)き候えて、鍋に入れよく煮やし、桶へあけ、よく冷まし置きて、冷え候時仕込み申し候。一日一夜にては冷え申し候ほどに(≒一日一夜ぐらいでは、とてもとても冷めてこないので)
、冷(さ)めかね申し候ものにて候(≒なかなか冷めないものだと思って下さい)
。二日二夜も置き候て、右の寝申し候糀(≒前述した休めていた糀)
を入れ、日に干して、天気悪(あ)しく候わば、二日三日は相(あい)待ち候てなりとも、なるほどよき天気にしこみ申し候(≒なるべく良い天気の時に仕込むのです)
。同じくそのまま日に干し申し候わねば、悪(あ)しくござ候(≒これと同様に、陽によって干せないと、悪い仕込みとなります)
。一日に一度ずつ、手にて上下へ攪(か)き回し候。幾日も一度宛(ずつ)、手に手上下へ攪(か)き廻(まわ)し、干し申し候。雨少しにても入り候得ば悪(あ)しく候(≒雨水が少しでも入ってしまうと、良くないのです)
。よくいでき候わば(≒良く出来た際には)
、壺(つぼ)いくつにも入れ置き、用次第(ようしだい)口をあけ遣(つかわ)し申し候(≒必要の折々で壺の口を開けさせるようにします)
。壺の口如何(いか)にもよくはり(≒壺の口を強く張って塞いでおいて)
、風のひかぬように仕(つかまつ)り候(≒風に当てないようにすることです)
。とかく仕込み候日に半日なりとも日に当て申さず候えば不出来にござ候(≒とにかく、仕込み当日に半日ぐらいも陽を当てられなければ、不出来なものとなってしまいます)
。昼は日に干し、夜は取り入れ申し候。日の強き時は、五日にても出来申し候。兎角(とかく)再々給(たまい)し候て見申し候(≒とにかく、再三に亘って目配りすることが肝要です)
。糀(こうじ)の匂い、のき申し候えばよく候(≒糀特有の匂いが無くなってくれば良いのです)
。」
下巻6【ぬかみその方】・・・ズバリ、「糠味噌の作り方」と云うか? 「ぬかどこ(=糠床)の拵(こしら)え方」?
「小糠(こぬか:※玄米を精米する際に、その表皮部分が細かく砕けてできる粉のこと。粉糠とも)
一斗(少し炒りて成程〔なるべく〕
粉にふるい〔=篩い〕
申し候。)、糀(こうじ)三升(はたき〔=叩き〕
候てふるい〔=篩い〕
申し候。)、塩一升、
右寒の内に仕(つかまつ)り候。水にてよき加減に捏(こ)ね申し候て、臼(うす)にてよくよく搗(つ)き、玉に丸め、藁(わら)にて筒の如くに包み、火をたき(=焚き)
候。脇につり(=吊り)
置き申し候。二年、三年置き候ても苦しからず候(≒二年や三年置いても問題無い)
。遣(つかわ)し候時(≒お遣い物とする際は)
、上を一ぺん(=一返)
削り捨て(≒容器内の上側の部分を一度削り捨てて)
、さて酒にてよき加減に摺(す)り込み申し候。汁へ入れ候時は、水にて延(のば)し申し候。」
下巻7【ぬか味噌の方】・・・「糠味噌の作り方と使い方」。但し、こちらは・・・漬物を漬けるための「ぬかどこ(=糠床)」とするだけではなく、福岡県小倉の郷土料理「ぬか炊き」のように「糠味噌」を味付け調味料として、食してしまうものです。
「小糠(こぬか:※玄米を精米する際に、その表皮部分が細かく砕けてできる粉のこと。粉糠とも)一斗(そのまま細〔こま〕
かにふるい〔=篩い〕
申し候。)、塩一升、
右二色(≒前述した小糠と塩の二種類を)
、食の取湯にて(≒食する際に沸かす湯を用いて)
ばらばらに捏(こ)ね合わせ、蒸籠(せいろ)に掛け、色のつき候ほど蒸し(≒色が変わってくるくらいまで蒸して)
、一日程も冷し、桶に搗(つ)き入れ、三十日過ぎ候て、右の糠味噌(ふかみそ)に、上々の味噌二升、糀(こうじ)三升入れ、またよく搗(つ)き合わせ、桶へ仕込み二十七日程過ぎ、つかい(=使い)
申し候。料理の時摺鉢(すりばち)にて一返(いっぺん)摺(す)り、酒を加え申し候。汁へ入れ候には(≒汁物に使う場合には)
、水にて延(の)ばし申し候。」
下巻8【とうこ味噌の事】・・・「とうこ」を漢字で表すと、おそらく「東湖」となるのでしょう。著者・徳川斉昭のことを、安政2年10月2日に発生した「安政の大地震」で亡くなるまで支えた「藤田東湖(※名は彪〔たけき〕、藤田幽谷の次男)」の名に因んでおります・・・が、何故に「とうこ味噌」と名付けられているのか? についてが判然としません。・・・藤田本人が、自ら「東湖」と号し始めたのは、嘉永5年(1852年)頃とされ、また本人の生家が水戸・千波湖を東に望むことに因むともされておりますので・・・きっと、この味噌が、生前の藤田東湖との思い出などを呼び覚ますほどに強い印象として、著者・徳川斉昭の心に残っていたか? 藤田本人が亡くなる以前に「東湖味噌」と呼ぶこと自体は、さすがに憚(はばか)られると想いますので。・・・あるいは、藤田東湖自らが、彰考館勤務時代の研究の一環として、この味噌の考案や、徳川斉昭が想起して記し始めた『食菜録』そのものを補佐するなど、かなり深く関与していたか? 藤田東湖が亡くなる直前の時期は、徳川斉昭の側用人に復帰していましたので。・・・のどちらか? とは想います。
「大麦三斗(よく搗〔つ〕
きて)、黒大豆(八升少し炒りて二割程に引く。)
右二色(≒前述した大麦と黒大豆を)
一つに合わせ、蒸してねさせ(≒蒸して加熱し)
、醤油の如く糀(こうじ)にねせ(≒醤油を作る際のように糀と混ぜて、暫らく放って置いて)
、一日干して揉(も)み砕(くだ)き、冷まし申し候。
水一斗、塩五升、水中にて汐(=塩)
を揉(も)み砕(くだ)き、こし(=漉し)
候て煎じ、冷え候ほど、一日も二日も冷まし、右の麦、大豆を入れ、よくよく混ぜて合わせ、桶に入れ、時々攪拌(かきまぜ)、風のひかぬようにいたし置き(≒風に当たらぬように置いておき)
、五十日程過ぎて、その後、加薬(かやく:※具材のこと)
を入れ申し候。
黒大豆の粉三升(少し炒りて。)、餅米の粉三升(少し炒る。)、白砂糖一升、生姜(しょうが)一升(小米〔こごめ〕
程に刻みて。)、胡桃(くるみ)二升(渋皮を取り、これも生姜程にして。)、山椒(さんしょう)四升(二割として、但し、つけ山椒〔=漬け山椒〕
ならば汐〔=塩〕
をいだし〔=出し〕
て一粒ずつにし、はかり申し候〔≒予め計っておきます〕
。から皮〔=殻皮〕
を入れ候わんと存じ候時は、山椒〔さんしょう〕
二升、から皮〔=殻皮〕
二升にいたし候。)
陳皮(ちんぴ:※温州みかんの外皮を乾燥させたもの。生薬としても用います)
一升(生姜ほどに刻みて。)、紫蘇(=しその葉)
四升(細〔こま〕
かにきざみて。)、白胡麻二升(炒りて荒く摺〔す〕
りて。)、黒胡麻三升(右に同じ〔≒前述の白胡麻と同様〕
。)
右の粉(≒前述した陳皮と紫蘇、白胡麻、黒胡麻の四種を粉状にして混ぜたもの)
、最前の味噌(≒前述した大麦と黒大豆、糀の三種で作っておいた味噌)
の中へよく搗(つ)き合わせ、桶に押し付けて、入れ置き、風の引き候わぬように仕(つかまつ)り、十日程過ぎて遣(つかわ)し申し候。」・・・この原文の中段にある「小米」とは、籾殻を取り除く際(=籾摺り時)に割れたりして、篩(ふるい)に掛けたときに選別された小さな米のことです。米の生育過程で、気象条件などによって、どうしてもヒビが入ることが良くありますが、それをそのままに籾摺りすると、なおさら割れが発生してしまうため、正常な米粒と割れてしまった不出来米の粒とを分別するのです。
下巻9【南良(なら)の法輪味噌(ほうりんみそ?/ほろみそ?)の方】・・・これも、何故に古都「奈良」と関連付けられているのか? についてが判然としない訳ですが、後半に「法輪」とも名付けられています。この「法輪」とは、明らかに仏教用語でして、「仏の教法」のことを云います・・・が、水戸徳川家そのものの墓制を観れば、歴代藩主達が埋葬される墓所としては儒式の瑞龍山(現茨城県常陸太田市)と定められていますので、水戸徳川家としては仏教に対しては、より中立的? と云うか、より宗教学的な立場にあったとも云えるのです。但し、水戸藩として観れば、藩士達や領民達の家系の多くは、仏教を深く信仰する家ばかりであって、それ故に徳川光圀やこの『食菜録』を著した徳川斉昭に代表される歴代藩主達が、自藩領において様々な寺社改革? を進めてきた訳です。・・・ですから、この『食菜録』の一項目に記述される「南良の法輪」については、むしろ水戸徳川家(水戸藩)が長年に亘り『大日本史』編纂事業の一環として行なった一次史料の発掘調査と、全国各地に広がっていた調査先との協力関係に目を向けるべきかと想います。・・・すると、ここにある項目は、そのまま「南良の法輪(ならのほうりん)」と読んで・・・現存している寺院を調べると、「奈良の法輪寺」が浮かび上がってまいります。通称を「三井寺(みいでら)」と呼ぶ、飛鳥様式の寺院建築として知られる古刹(こさつ)です。所在は、奈良県生駒郡斑鳩町三井。「斑鳩(いかるが)の里」にあって、若い頃に修学旅行などで行った人も多いのではないでしょうか? 私(筆者)も中学生時代に行った記憶がございます・・・が、かの「聖徳太子」との所縁の深い処ですので、水戸徳川家(水戸藩)は『大日本史』編纂のための史料提供などでは、かなり協力して頂いたのではないか? と考えられる訳です。・・・したがって、ここにある「南良の法輪味噌」は、水戸藩から派遣された調査員が現地から持ち帰った“伝統製法による貴重な現物史料”と、云えるのかも知れません。
「黒大豆二斗(同じく細〔こま〕
かなる大豆よし)
右の大豆(≒前述した黒大豆を)
しわのよる程はかし(≒シワがよる位まで沸かして)
、さて桶の(≒さて桶状の)
甑(こしき:※古代中国を発祥とする米などを蒸すための土器のこと。需とも。竹や木などで作られる蒸籠と同様の機能を持つ)
へ入れ、蓋を開けて五時程蒸し候得ば(≒蓋を開けながらて十時間ほど蒸らしてみると)
、食い加減より少し過ぎ候程に成り候(≒そのまま豆にて食すよりも、少し軟らかめになってきます)
。その後三時程(≒その後六時間ほど)
そのまま甑に置き申し候。釜(かま)の下に火蔽(おお)い置き申し候(≒釜下の火には蔽いを被せて火力を弱めて置きます)
。さて甑(こしき)より取り出し、熱気を冷し、糀(こうじ)三升入れ、糀(こうじ)蓋(ふた)へ一升ずつ入れ、攪(か)き冷まし申さず候。室(むろ)へ入れ五時程(≒=十時間ほど)
置き、また取出し、その時攪(か)き冷まし、また室(むろ)へ入れ、二日二夜寝(ね)させ申し候。よく寝候て取出し、臼(うす)にて米二割程はたき(≒臼によって米を二割程摺った後叩いて)
とおしにて篩(ふる)い(≒通しで篩に掛けて)
、蓆(むしろ)の叺(かます:※藁〔わら〕を二つに半折し、両端を縄で閉じて封筒状にした袋のこと。肥料や石炭、塩、穀物などを入れます)
に一斗ずつ入れ、一日一夜また室(むろ)に入れ置き申し候。さて取出し候えば、叺(かます)の中にて堅まり候を、揉(も)み砕(くだ)き、また篩(ふるい)候て、蒸し申し候。その時の蒸し様は、桶こしき(※桶状の甑のこと)
の底に大豆二斗程入れ、その上へ味噌、五度程に入れ申し候。一度に湯気(ゆげ)上へあがり候時(≒湯気が上がってくる時が一度あるので)
、随分押し付からぬように入れ申し候(≒あまり押し付けられることが無いように入れるのです)
。この時も桶蓋(あけぶた)をせずに、蒸し申し候上へ、よく湯気のあがり候て後取出し、又(また)とおし(=通し)
にて篩い物にひろげ(=広げ)
、よく冷め申し候時、味噌一斗に、塩一升か一升五合混ぜ、桶に手も壺(つぼ)にても押付け、蓋(ふた)をいたし置き申し候。夏冬共に同じ加減なり。同じくは冬の内に仕(つかまつ)り候得ば(≒同様にとは云ったが、もし冬季の内に完成できれば)
、来年までも苦しからず候(≒来年までは、まず安心ですし)
、夏は室(むろ)へ入れ申さず候ても寝申し候(≒夏季にわざわざ室へ入れなくても熟成しています)
。」
下巻10【こがしの方】・・・「こがしの取扱い方」。「こがし」を漢字表記すると、「焦がし」や「粉菓子」。・・・いずれにせよ、砂糖を混ぜて粉末のまま食べたり、熱湯や水を注いで練って食べたりするものです。また、香ばしい香りが特徴で、上記の中巻10にある「らくがん(=落雁)」の素材にもなります。
「もろこし(=蜀黍=唐黍)
十両(水に浸け、灰汁〔あく〕
を取り、その後、日によく乾かして焙〔い〕
りて、引き割り〔=挽き割り〕 、篩〔ふる〕
い申し候。)
黒大豆十両(焙りて、引き割りて篩〔ふる〕
う。)
山椒(さんしょう)二両(炊〔あぶ〕
り粉にして。)
陳皮(ちんぴ)四両(右同断〔みぎとどうだん:=前述と同じ〕
。)
黒胡麻五両(焙りて、摺鉢〔すりばち〕
にて摺〔す〕
り篩〔ふる〕
う。)
右ひとつにして湿(しめ)り候わぬようにいたし置き申し候(≒前述した五種の食材を一つにして、湿らぬようにして保存して置くのです)
。」
下巻11【善徳寺(ぜんとくじ)酢の方】・・・いわゆる「米酢(こめず)の作り方」。・・・但し、これを何故に「善徳寺酢」と呼んだのか? についてが、また良く分かりません。“何処かにある善徳寺の関係者から教わったから、あるいは伝わっているからだ”と云われても、説得力に欠けると云いますか、どうしても釈然としない訳です。・・・なので、再び調べてみました・・・が、全国に「善徳寺」という名の寺院は数多くあって、これもなかなか候補を絞り込めません。例えば、水戸徳川家歴代当主達のご先祖となる神君・徳川家康が誕生した三河国(現愛知県)内では、計2カ所ありました。・・・そこで、少し視点を変えて観ようと、水戸藩領内にあった寺院を調べることにしました。・・・すると、有力候補を1件見つけました、其処は寺院として現存はしておりませんが、かつては実在していたことが確認できる石塔が遺されております。このような石塔を「宝篋印塔(ほうきょういんとう)」と呼びますが、これは墓塔や供養塔などに使われる仏塔の一種です。大きなものでは五輪塔(ごりんとう)などがありますが、石造りのものが圧倒的に多いのですが、この石塔も、かなり大きいものです。高さ約3.2m。これに銘として「寛永廿一甲申年五月廿二日」と刻まれており、江戸時代前期の西暦1644年(寛永21年)の建立であることが分かります。・・・肝心の、本項目にある善徳寺があった有力候補地は、茨城県水戸市大串町(旧大串村)となります。ここにあった善徳寺は、“1534年(天文3年)とされ浄土宗寺院として開基されましたが、1616年(元和2年)に水戸城下の藤沢小路(ふじさわこうじ)から同・寺町(てらまち)内へ移され、再び1666年(寛文6年)に現在の有力候補地・現水戸市大串町に移された”とのこと。・・・尚、その石塔の主(ぬし)は、「松平(壱岐守)正朝(まつだいら〔いきのかみ〕まさとも)」と云いまして、戦国時代から江戸時代初期に掛けての戦乱期を生きた人物で、元々は三河十八松平氏の一つとされる三河国額田郡にあった大草郷(現愛知県額田郡幸田町)に盤踞した「大草松平家」の一族なのです・・・が、この「大草松平家」が一時期、三河岡崎城を領して「岡崎松平家」とも呼ばれましたが、後に徳川家康となる松平宗家に対して敵対的な路線に進み・・・徳川家康の祖父に当たる松平清康(まつだいらきよやす)謀反して敗れ、「三河一向一揆」では一揆側に付いて一時追放されたり・・・と、紆余曲折がありまして・・・後に、この石塔の主「松平(壱岐守)正朝」は、1635年(寛永12年)に水戸徳川家(水戸藩)へ出仕し、水戸藩初代藩主・徳川頼房の元で六千石を賜って、中山家に次ぎ水戸藩の次席家老となった人物です。・・・しかし、嫡男の正永(まさなが)には跡継ぎがおらず、また「(壱岐守)正朝」の弟「(志摩守)重成(〔しまのかみ〕しげなり)」も、兄と同時期に水戸徳川家(水戸藩)へ出仕し水戸藩家老・山野辺家の次座家老に列しましたが、同じく3代目の時に「無嗣」となり・・・結果としては、兄弟いずれの家系も「無嗣絶家」となってしまい、「大草松平家」は断絶することになりました。・・・ですから、本項目の「善徳寺酢」には、後の水戸藩主・徳川斉昭が抱いた「大草松平家」に対する鎮魂歌的なメッセージが込められているような気がしてなりません。斉昭にとっては、水戸藩立藩当初の重要な時期を支えた重臣達だった訳ですし、この『食菜録』の著者としても、“この酢の製法を水戸に伝えたであろう重要な役割を担った人々”となる筈ですから。
「うるの中白米一斗
水一斗(この水にて右の米〔=粳米を中程度精米したものの〕
を蒸し、飯〔めし〕
に仕〔つかまつ〕
り候。堅めなる飯〔めし〕
になるなり。)
右の食を人肌(≒体温)
に冷まし、八月中旬に仕込み申し候。又(ま)た九月時分に候わば、人肌(≒体温)よりあつき(=熱き)
加減によし。
水二斗三升、麹(こうじ:=糀)
七升、甕(かめ)に成りとも桶になりとも、仕込み申し候(≒前述の水と麹を、甕であっても桶であっても構わない)
。右七升の麹(こうじ)の内を、壺底(つぼぞこ)へ少し仕込み、その上へ飯を一返も幾へんも段々に、麹(こうじ)と飯と置き如何(いか)にも堅く押付け、糀(こうじ)を一升程残し、一の上に置き、その後鍋蓋(なべぶた)のようになる物を置き、食の動かぬように(≒なるべく米飯を動かさぬように丁寧に扱って)
水を入れ申し候。甕(かめ)の口広きがよく候。紙にて一重(ひとえ)蓋をして、その上に雨の入らぬように覆(おおい)いを仕(つかまつ)り候。三日目に上の覆(おおい)いを取り、紙蓋(かみぶた)に小刀(こがたな)にて幾つも穴を開け、息を出し申し候(≒紙蓋を小刀で幾つもの穴を開けて、ガスを空気中に逃がすのです)
。夜は覆(おおい)いを仕(つかまつ)り、朝は覆(おおい)いを取り、晩まで日に当て申し候。三七日(みなのか)の間、かくの如く仕(つかまつ)り候(≒これを合計三度、七日に1回程度〔※つまりは3×7で21日〕の間隔で、前述した方法で取り扱うのです)
。その内に雨降り候わば、上に桟木(さんぎ)を渡し、板蓋(いたぶた)をして雨の入らぬように仕(つかまつ)り、酢の息を出し申し候(≒酢になった液体から出るガスを外へと放つのです)
。酢の蓋三七日(みなのか)にて沈(しず)み候えば(≒酢の蓋が、二十一日間醸造している間に、容器の底へ沈んでしまったら)
、酢は何日なりとも、右の如くにして外(ほか)に置き申し候。虫等入り候わば(≒もしも虫や塵などが容器内に入ってしまったら)
、細々(こまごま)取り申し候(≒細々と取り上げておくのです)
。
一、三七日(=二十一日)
過ぎ紙蓋(かみぶた)の中を五寸程切り抜きて置くなり。
一、蓋よく沈み候時内へ取り入れ、十日程過ぎて開くるなり。
一、あけ酢樽(たる)へ入れ、年を越させて遣(つか)いたるがよく候。 取掛候樽は悪(わる)くなりたがる故(ゆえ)、当座(とうざ)遣(つかい)い申し候わば別にいたし候てよし。
夏になり候ては火を入れてよし。煮加減は酒同前なり(≒煮るときの火加減については、酒醸造の場合と同然と云える)
。」
下巻12【萬年酢(まんねんず)の方】・・・さすがに「一万年」の保存はできないとは想いますが、長期間は大丈夫!? とのネーミングのようです。
「上々の諸白二年酒(?)
一斗
成程(なるべくは)
気吹き酒(?)
一斗
水一斗
この三色を甕(かめ)へ入れ、日の近き軒(のき)の下へ置き(≒目が届く頃合いの軒下に置いて)
二七日(になのか:=十四日)
過ぎて見候て、酢になり候えば、それより遣(つか)い申し候(≒それから使い始めます)
。まず初めはちと粘り入り申し候(≒最初の頃は、少し粘り気があります)
。粘りの来(き)申し候内は(≒粘り気を感じる内は)
、その時遣(つか)い候てよく候(≒その時々で使っても問題は無いが)
、二升取り出し候わば、その跡へ酒一升、水一升加え申し候(≒酢を二升取り出した際は、酒と水を一升ずつ加えておくと良い)
。三升のもとは何迄(いつまで)も減り申さず候(≒酢を三升取り出してしまうと、いつまでも減ってゆかなくなるため)
、同じくは本(もと)を壺(つぼ)二つにして(≒同様に元とするものを壺二つとして)
、かたみ替り(≒交互に)
に取り出したるがよく候。」・・・「上々の諸白二年酒」とは、おそらく「上等な二年ものの白い酒=上等な透明な日本酒(二年もの) ≒ 今に云う、吟醸とか大吟醸のこと」かな? ・・・と想います。・・・その次にある「気吹き酒」は、“気を吹き切った=気の抜けた=微生物のエサとなる成分が無くなって、ほぼ醸造過程が落ち着いてしまっている、かなり古くなった古酒のことだ”とは想いますが、どうなんでしょうか?
下巻13【早作(はやつくり)醤油の方】・・・上記の下巻3「早作味噌」に続いて「早作醤油」です。但し、この名詞に続くのは「の事」ではなく「の方」となっていますが?
「大豆一斗(焦げぬように焙りて引〔=挽〕
き割り皮を取る。)、麹二斗、水二斗、塩八升五合、
右の塩水(≒前述したもの全てを混ぜた塩水を)
一泡煎じ(≒一煮立ちさせて)
、夏ならばよく冷し、冬ならば、人肌に(≒体温ほどに)
冷まし、大豆、麹(こうじ)を入れ、日に当て一日に四、五度ずつも攪(か)き申し候。二十日程にては醤油になり申し候。色をよくつけ候わんと存じ候得ば(≒色付き具合を、より濃くしたければ)
、三十日程も、右の通りにいたし置き申し候。後は酢を立てくみ申し候(≒その後は、若干の酢を汲み入れると良い)
。」・・・若干の酢を足すことで、醸造をより活性化させるというアイデアですが、当然に関東風の黒く濃い色の醤油がベースとなっております。
下巻14【山もも酒の方】・・・今に云う「果実酒・山もも酒の作り方」ですね。甘い「リキュール」・・・しかし、これも別の意味で要注意項目です。もし実験的に、この項目レシピを“いい加減に再現しよう”とすると、場合によっては“酒税法違反”に問われる立場になるからです。詳細は、上記の上巻42【いり酒の方】をご覧下さい。もし、この項目レシピに挑みたい方は、必ずアルコール度数20度以上のもの(※一旦酒税が課税されている酒を購入したほうが無難です)を、ご利用頂き、お酒を漬ける瓶などの容器は、カビの発生を防ぐため、一度アルコールや熱湯で消毒してから使用しましょう。
「古酒(こしゅ)諸白二年酒八升
山桃(やまもも)一斗(但し、少しも古きは悪しく候〔≒但し、少しでも古くなった山桃は適当ではない〕
。少し前方なるは〔≒少しでも新鮮なものを入手し〕
、よくよく自然水にて洗い候えば、水気無きように日に干し申し候。)
白砂糖二升
塩一合(但し、少し控え目に仕〔つかまつ〕
り候。)
右一つに致し(≒前述したもの全てを一つとし)
壺(つぼ)へ入れ、板にて蓋(ふた)を仕(つかまつ)り口をよく張り、地に埋め、蓋(ふた)の上に土一寸余り有る程に埋め、その上にて藁(わら)二、三束ほど焼き申し候。その火の独(ひと)り消え候程置き、その後壺(つぼ)を堀り、涼(すず)しき所に置き申し候。三七日(みなのか:=二十一日)
過ぎ、酒をよく濾(こ)し、山桃(やまもも)を布にて、漆(うるし)を濾(こ)し候ように搾(しぼ)り候て、糟(かす)を捨て申し候。右の酒、来年までも損(そこ)ね申さず候。」・・・醸造してくれる微生物を助けるために、地熱と藁が燃える熱を利用しています。・・・また、甘みを引き立たせるため、敢えて塩を加えたりしていますが・・・おそらく、この発想は・・・長崎出島辺りか、薩摩藩や長州藩辺りの異国と交流があった地域が、その発信源だったような気が致しますが? どうなんでしょう?・・・と云うのも、「山桃」は、山地の暖地を好み、暑さには強いのですが・・・日本では関東以南(房総半島南部、福井県以西)の本州や、四国、九州、沖縄の低地や山地に自生する果物ですし、北関東・水戸周辺の寒い山間部には、あまり環境適応できなかったと考えられますので。・・・現代は温暖化してますので、自生していても、おかしくはありませんが。
下巻15【当座作(とうざづくり)の忍冬(すいかずら)酒の方】・・・「忍冬」というのは、中国風の表記であり、和名表記では「吸葛」となります。・・・“葉を付けたまま越冬する、その耐え忍ぶ姿”が、この名前の由来とされてもいますが・・・“細長い花筒の奥に蜜があって、古来より子供などが好んで、花の管の細いほうを口に含んで甘い蜜を吸うことが行なわれたことに因む”との説もあります。・・・いずれにせよ、日本列島のほぼ全域に分布する常緑または半常緑のつる性低木のため、古代から新芽や若葉も、「山菜」として食してきました。また、この「つる」の部分から、甘い蜜を抽出することも出来たそうですが、非常に手間や時間が掛かるらしく、大変貴重な糖分だったようです。・・・尚、この「当座作の忍冬酒の方」では、「焼酎」の他、「龍眼肉(りゅうがんにく:※ライチのような果物の果肉のみをドライフルーツにしたもの)」や「肉桂(にっき/にっけい:=シナモン)」など、江戸時代中期に漢方薬として、中国から日本へ渡来したものを使用するなど・・・まるで、「薬用〇〇酒」のようなものなのです。テレビCМなどで良く観かけた。・・・これも、異国と交流のあった地域が情報元だったのでしょう。・・・この項目レシピも、現在の「酒税法」に該当する可能性がありますので注意を要します。詳細は、上記の 上巻42 【いり酒の方】をご覧下さい。
「焼酎(しょうちゅう)二弁
忍冬(すいかずら)一両(但し、干して。)
いばらの花(=薔薇の花)一両(但し、干して。)、
龍眼肉(りゅうがんにく:※ライチのような果物の果肉のみをドライフルーツにしたもの)
百粒
肉桂(にっき/にっけい:※シナモンのこと)
一両(皮を去り刻む。)
右の薬(≒前述した薬の全て)
を焼酎に浸し、二七日(になのか:=十四日)
程過ぎて、口を開け味淋酎(みりんちゅう:※餅米と米麹、焼酎を原料とするリキュールで飲酒用のもの)
を心次第(=お好みで)
さし(=注し)
申し候。」
下巻16【葡萄(ぶどう)酒の方】・・・
【注意喚起】この項目レシピを再現(自家醸造)しようとしてはいけません!! 理由は、上記の上巻42【いり酒の方】をご覧頂ければ分かりますが、「葡萄(ぶどう)」を使用したお酒だからです。
「一、よく熟したる葡萄(ぶどう)一粒ずつにして、押し潰(つぶ)し、汁をく搾(しぼ)り溜(た)め、鑵鍋(かんなべ:※燗鍋。酒を燗にするために使う銅製の鍋で、つると注ぎ口と蓋があるもの)
へ入れ、炭火(すみび)の上にて、一泡煎じ(≒一煮立ちさせて)
その後よく冷し、冷え候時焼酎(しょうちゅう)にても、泡盛(あわもり)にても三分加え申し候。
一、龍眼肉(※ライチのような果物の果肉のみをドライフルーツにしたもの)
、上の皮を焼酎(しょうちゅう)へひたひたに漬け、二七日(になのか:=十四日)
も置き候えば、醤油の如く出(い)で申し候。その時龍眼肉を取上げ、布にて漆(うるし)漉(こ)す如くに搾(しぼ)り(≒漆を漉す際のように)
候て粕(かす)を捨て、右葡萄の汁を混ぜて、焼酎と龍眼肉の焼酎二色を心次第に混ぜ申し候。糂粏(じんだ:※枝豆を茹でて摺り潰して調味して、和え衣として用いるもの)
の如く成り申し候。」・・・文中後段にある「糂粏」には追加説明が必要かと想います。・・・「糂粏」については、本来ならば(=第一義的に)、“米糠に塩を加えて発酵させて、酢や酒を加えて食す糠味噌のことであり、実際の味は、今の塩麹に少し糠味噌を加えたようなもの?”を云ったようですが、この項目では、甘~い葡萄酒の作り方が記述されておりますので、第2義的に云う「枝豆を茹でて摺り潰して調味して、和え衣として用いるもの」の方を採用致しました。この部分の文を読んだだけで分かる人は、きっと東北地方や北関東の一部地域の出身者かと想います。そうです、「糂粏」とは、仙台の伊達政宗が愛していたと謂われる「ずんだ餅」の語源的な食品なのです。・・・この『食菜録』は幕末期に徳川斉昭が記述したものであり、また斉昭の九女「八代姫」が輿入れ先が仙台伊達家であって、さらに“市中に砂糖が出回ることで、甘味のある「ずんだ餅」が史料上確認できるのは、この幕末から”というのが、その理由説明となります。・・・尚、もしかすると・・・この「葡萄酒の方」についても・・・仙台藩の初代藩主・伊達政宗により「慶長遣欧使節団」が派遣されて、実際に帰国した「支倉常長(はせくらつねなが)」の例もありますので、情報としては江戸時代初期頃から仙台伊達家によって秘匿され続けていたという可能性があるのかも知れません。伊達政宗も実践主義者でしたから。
下巻17【豊後(ぶんご)のあさち酒の方】・・・「豊後(=現大分地方)の麻地酒の作り方」。・・・【注意喚起】この項目レシピを再現(自家醸造)しようとしてはいけません!! 理由は、上記の上巻42【いり酒の方】をご覧頂ければ分かりますが、バッチリ「酒税法違反」となります。
「上白米五斗(酒に入れ候一日前に、水に漬け飯に蒸して冷え候程よく冷し。)
麹(こうじ)五斗(一日一夜水に漬け蒸して、麹〔こうじ〕
寝させ申し候。酒に入れさまに一夜、渋紙〔しぶがみ:※張り重ねた和紙に柿渋を塗って乾かしたもの。防寒防水用の衣類や部屋の敷物、荷物の包装などに用いました〕
に拡げ、よく冷し申し候。)
水四斗
右の飯、麹(こうじ)をよく混ぜ合わせ(≒前述した米飯と麹を良く混ぜ合わせて)
、壺(つぼ)へ入れ下からよく押し付けて上まで入れ、少し中高に押付け入れ申し候。水を入れ候時、飯の上に板を置き、その上から水をつぎ(=注ぎ)
込み、飯の動かぬように仕込み申し候。壺(つぼ)平地(ひらち)より七寸程深く埋め、蓋(ふた)をよく仕(つかまつ)り、渋紙(しぶがみ)にてよく包み、その上を土にてよく埋め申し候。人の歩き候わぬ屋根の下の風の吹き抜き候所よく候(≒人が歩かず屋根下の風通しが良い処が最適です)
。寒の内に仕込み、来年六月土用の内に口をあけ(=開け)
申し候。酒の色は琵琶色に(=枇杷色の≒浅い黄褐色で赤みがかった色の)
濁(にご)り酒なり。」
下巻18【肥後(ひご)の麻地酒(あさちざけ)の方】・・・「肥後(=現熊本地方)の麻地酒の作り方」。・・・【注意喚起】この項目レシピを再現(自家醸造)しようとしてはいけません!! 理由は、上記の上巻42【いり酒の方】をご覧頂ければ分かりますが、バッチリ「酒税法違反」となります。
「上白米の餅五斗
上白の糯米(うるちまい)五斗
この二色別々の桶に入れ、寒の中に二返(にへん)水にて洗い、初めの一返(いっぺん)の水を捨て、二返目(にへんめ)の水をそのまま七日置き、八日目に常の如く蒸し食にするなり(≒八日目に普段食す米飯のように蒸らすのです)
。但し、餅米と糯米と甑(こしき:※古代中国を発祥とする米などを蒸すための土器のこと。需とも。竹や木などで作られる蒸籠と同様の機能を持つ)
二つにて、めんめんに(=面面に≒それぞれ一つずつ)
蒸し、同じ蒸し加減にするなり。
上白糀(こうじ)六斗、水六斗、右麹(こうじ)を水とよくあわせ、さて二色の蒸し食(≒さて、これら上白米餅米と上白糯米を蒸らした後には)
、人肌(ひとはだ)に冷め候時、半切に入れ、よく揉(も)み合わせ、一夜置き明日臼(うす)にて搗(つ)き申し候。搗(つ)き加減は、この蒸し食の半分過ぎ潰(つぶ)れ申し候程に搗(つ)き申し候(≒その際の搗き加減は、普段食す米飯程度の固さの、およそ半分強が潰れる位まで搗くのです)
。
七日の内一日に二度、三度は手にて揉(も)み合わせ、上下かきまわし(=掻き回し)
温かなる所に置き申し候。さて八日目に壺(つぼ)に入れ、板にて蓋(ふた)をよくよくして(≒板により蓋を厳重に閉めて)
、その上をかき(=掻き)
、紙にてよく包み、湿気(しめりけ)の入らぬようにして土に埋め候。これも来年の六月土用の内に口を開け候。豊後(ぶんご)のよりは(≒上記の現大分地方のものと比べると)
甘く候。白き濁(にご)り酒なり。」
下巻19【甘酒(あまざけ)の方】・・・「甘酒の作り方」。・・・現在の「酒税法」により、酒類と定義されるのは「アルコール分1.0%(=アルコール度数にして1度)以上」の飲料と決められており、また一般の「甘酒」はアルコール分1%(=アルコール度数にして1度)以下であるため「清涼飲料水」と定義されます・・・が、この項目レシピを再現する場合には注意が必要です。くれぐれも、アルコール分1%(=アルコール度数にして1度)以下に抑えるようにして下さい。・・・と云いながら、人が予め計算してアルコール分1%(=アルコール度数にして1度)以下に抑えることができるのか? を問われると答えに詰まるのですが。作る季節や分量を間違えると、もはや「清涼飲料水」ではなく「お酒」になってしまいますので。この項目レシピも、“仮に知ったところで、むやみやたらに行なえない事柄”となりそうです。
「餅米上白一升(但し、あらりと引割り〔≒存在感が残るように粗目に挽き割って〕
、常の強飯(こわめし)の如くに蒸し申し候。尤〔もっと〕も冷やし申し候。)
麹(こうじ)一升(上白米を麹〔こうじ〕
にするなり。但し、粳米。)
水一升(但し、この内三分の一ほどを加えてよし。また酒五合、水五合、合わせて一升にもするなり。)
右の水の内へ糀(こうじ)をつけ(=着け)
、一夜置いてあくる日(≒一夜を置いて翌日に)
成程(できるだけ)強く揉(も)み候えば、よくよく花(はな:=糀の花部分≒カビ)
落ち申し候。
同じくは糀(こうじ)の米のはだ(=肌)
にある(≒同様に、米粒の表面に糀が付いた)
黴(かび)まで落ち候ほど揉(も)みてよし。さて糀(こうじ)の粕(かす)を濾(こ)して捨て、その中へ強飯(こわめし)を仕込み申し候。この甘酒、寒の内に作りよく出来候時、鍋へ入れよく沸(わか)し壺(つぼへ入れ置き候得ば、来年の夏までも持ち申し候。沸(わか)し候酒は、堅く成り申し候故に食べ申す時、水にて延べ燗(かん)をいたし候。尤(もっと)も、当座々々(とうざとうざ:=一回毎に)
に作りてもよし。又(また)常の甘酒よりは損(そこ)ね申さず候(≒また普段飲む甘酒と比べて多少は傷み難くなります)
。」・・・尚、この『食菜録』の著者・徳川斉昭が、粉状の「こうじ」を「糀」とし、水などの液体と混ぜた後にドロドロと多少液体状になった「こうじ」を「麹」としていることが分かります。・・・いずれにしても、「こうじ菌」の働きによって、餅米はさらに糖化して甘くなり、今に云う「飲む点滴」と成る訳です。
下巻20【芋酒(いもざけ)の方】・・・「山芋酒の作り方」。・・・
この項目レシピについては、現在の「酒税法」を、あまり気にしなくても良いのかな? という感じではあります。但し、素材の「練り酒」が市販されているもので代用が効くのか? については良く分かりませんので、ご注意下さい。
「山の芋の皮を取り、厚さ分中程に刻み、いかき(=笊籬=竹製の籠や笊)
へ入れ、鍋の中に湯を沸かし、いかきながら(=沃懸きながら≒注ぎ掛けながら)
湯に漬け、熱茶三ふく食べ候間(≒熱い茶を三杯ほど頂く位の時間)
ほど置きて、そのままあけ(=開け)
、滴(しずく)を垂し(≒水気を切って)
摺鉢(すりばち)にてよくよく摺(す)り、冷え候ほど冷め候時酒を入れ、練り酒(ねりざけ:※蒸した米を発酵させ、臼で挽き絹布で漉して造った酒のこと。甘酸っぱく滑らかでトロミがあるもの。古代酒の原型を最も留めていると謂われ、筑前〔現福岡県北西部〕博多産が有名です)
のように、のべ徳利(のべとっくり:※延べ徳利か? 酒蔵などに敷き広げて使うもの?)
へ入れ置き、用の度々燗(かん)をいたし候。五日程も耐(こた)え申し候。」・・・これも、山芋を原料としていますので、滋養効果が高そうですね。・・・上記の甘酒もそうですが、何となく「薬用酒」の雰囲気もありますね。
下巻21【豆淋酒(とうりんしゅ)の方】・・・「豆淋酒の作り方」。「淋(りん)」には、“水が滴(したた)り流れる”との意味がありますので、これにより名付けられているかと想います。・・・この項目レシピも、現在の「酒税法」を、あまり気にしなくても良いのかな? という感じではあります。但し、実際に利用する「酒」のアルコール度数については、注意を要します。
「黒大豆三合(炒り申し候。炒りようは焙烙〔ほうろく:※素焼きの土鍋の一種で、別名は炒鍋とも〕
にても、鍋にても、炭火〔すみび〕
の上に置く。事の外あつくして〔≒案外強く加熱しても〕
上へ放〔あ〕
け黒大豆を入れ〔≒蓋などせずに、そのまま黒大豆を入れ放って〕
、炒り申し候。半分は皮切れる程、半分は温まり入たるほどに炒り申し候。火の上に置き炒り候ゆえ、炒り過〔すぎ〕
し申し候故かくの如く候〔≒炒り過ぎたかな? と感じるぐらいで良いのです〕
。)
酒一升(右の大豆冷え候時入れ、七日過ぎて大豆を濾〔こ〕
して取り申し候。)」
下巻22【一夜漬(いちやずけ)香の物(こうのもの)の方】・・・今に云う「大根の味噌一夜漬けの作り方」。・・・私(筆者)の祖母などは、「お新香」などの漬物類を、「お香々(おこうこう)」と呼んでいます。ちなみに旧水戸藩内出身者です。・・・尚、ここから「お酒の供」と云いますか? 「酒の肴(さかな)」のような一品料理が、しばらく続きます。
「小大根(だいこん)茎を(=小さき大根の茎を)
一寸程付け、葉先を切り捨て候。よく洗い、成程(できるだけ)水気を取り、味噌に一夜漬け申し候。二つ割にしてもよし、香の物に色をよく付け度候えば(≒色良い漬物を作りたければ)
、大根(だいこん)に少し熱湯を掛け水にて冷やし、さて水気を取り漬け申し候。」
下巻23【瓜丸漬(うりまるづけ)の方】・・・「酒粕による瓜の丸漬けの作り方」、つまりは「奈良漬の作り方」となります。
「瓜白(但し、唐瓜〔からうり〕
にても青瓜〔あおうり〕
にても白瓜〔しろうり〕
にても漬け申し候。熟〔うみ〕
たるは悪〔あ〕
しく候。)
水五升に塩六升三合、よく揉(も)み砕(くだ)き一淡(ひとあわ)煎じ冷え候ほど冷まし(≒ ~を良く揉み解〔ほぐ〕したものを、一煮立ちさせてから、きちんと冷まして)
、瓜(うり)を先にこの水に漬け申し候。瓜(うり)の後先(あとさき)を少しずつ切り候て、中へ穴を開け申し候。又(また)雨の切り小口(こぐち)より(≒また雨の筋のように細く)
、中こ(なかご:※瓜の種子)
を取っても漬け申し候。又(また)二つ割にしても漬け申し候。百の瓜を桶に並べ重ね、右の塩水を入れて押(おも)しを置き、二日そのままに置き申し候。三日目には押(おも)しを少し緩(ゆる)め申し候。四日目に押(おも)しを取り、漬汁(つけじる)にて洗い、又(また)三日天気に干し申し候。その後又(また)三日陰へ置き、熱気を冷まし粕(かす:=酒粕)
に漬け申し候。酒の粕堅くば酒を加え、しるりといたし(≒汁気たっぷりに)
漬け申し候。瓜(うり)の摺(す)れ合わぬように、粕をたくさん(=沢山)
に入れ申し候。右の塩水にて赤土(あかつち:※鉄分を多く含んだ土のこと)
を堅く捏(こ)ね、南良漬(ならづけ:=奈良漬)
の上に五寸も六寸も、蓋の心に塗り申し候(≒前述した塩水によって赤土を堅く捏ね上げて、それを南良漬となったものに五寸か六寸程の厚さの蓋のように塗り固めておくのです)
。」・・・鉄分を多く含んだ「赤土」を蓋に使用することで、酸化効果が高まり、良い色になるとの助言です。
下巻24【淺漬(あさづけ)の方】・・・「大根の浅漬けの作り方」。
「大根(だいこん)(半分は葉を付け乍〔なが〕
ら、半分は葉を切て一両日干して、少し皺〔しわ〕
の寄り候時分よく候〔≒少し葉が萎れる頃合いで良いのです〕
。)
塩一斗、糀(こうじ)四升、
右の塩、糀(こうじ)をよくよく混ぜ合わせ、桶の下へ一返(いっぺん)振り、大根(だいこん)を置き摺(す)れ合わぬように、間(あいだ)へも上へも塩糀(しおこうじ)を置き、何返(なんべん)も重ね上げ、成る程(できるだけ)強く押(おも)しを掛け、後は少し押(おも)しを緩(ゆる)く申し候。塩の分量は大根(だいこん)の数次第なり。大根(だいこん)何程(どれだけ)の積(つも)りは知れ申すものにて候(≒大根の数など見積りは、既に分かっておりますので)
。」
下巻25【又(また)、あさ漬の方】・・・題して、「また大根の浅漬けの作り方」。・・・上記のものと違う事は、「小糠(こぬか)」が使われている点。・・・味は、下巻70にある「澤庵(たくあん)漬」に、より近づくと想います。
「大根(だいこん)(莖際〔くきぎわ〕
より葉を切り捨て陰干しにして。)
小糠(こぬか:※玄米を精米する際に、その表皮部分が細かく砕けてできる粉のこと。粉糠とも)
一斗、塩二升、糀(こうじ)三升
右三色よく混ぜ合わせ、これも漬けよう右同前なり(≒これについても、漬け方は前述した 淺漬の方 同然である)
。この浅漬(あさづけ)は尚々(なおなお)よく耐へ申し候(≒この浅漬けは、さらに長持ちします)
。大根(だいこん)の嵩(かさ)多くば(≒大根の収穫量が多ければ)
、小糠(こぬか)、塩、糀(こうじ)、その加減に拵(こしら)え、大方(おおかた)この積程(つもり)にては、大きなる大根(だいこん)百本程漬け申し候(≒大体の見積り量で云えば、大きめの大根で百本程を漬けることになるだろう)
。」
下巻26【干瓜(ほしうり)の仕様】・・・この項目名にある「干瓜」のことを、別名「千成瓜(せんなりうり)」とも呼ばれる「隼人瓜(はやとうり)」と混同しやすいのですが、ここの記述では瓜の種類についてを特定している訳ではなく・・・瓜を縦割りにするなどして種を取り、さらに塩漬けして干した食品のことを指しています。
「白瓜(しろうり)にても、青瓜(あおうり)にても、二つに割り候て、中こ(なかご:※瓜の種子)
を取り、その瓜一つに塩三合の加減程(かげんほど)に盛(もり)、日に干し申し候。 二日目、三日目程に又(ま)た打返し、裏から干し候えば(≒二日目や三日目ぐらいに、再びひっくり返して裏から干せば)、青味除(の)き申すものにて候(≒独特な青臭さは抜けてゆくのです)
。その時白水(※米を研ぐ際に出る水のこと)
にて洗い、又(また)水気除き候ように(≒また水気が切れるように)
、一日干し、その後酒樽(さけだる)に入れ置き申し候。又(ま)た壺(つぼ)へ入(いれ)候てもよく候。料理の時は心次第に切り(≒料理として取扱う際には、心のままに切って)
、酒に漬け座敷(ざしき)へ出し申し候。後に味噌に漬け候わんと存じ候えば(≒その後に味噌漬けとしたいと思えば)
、切り申さず、そのまま漬け申し候。」
下巻27【煎酒の方】・・・「煎酒の用い方」。ここも、要注意項目です。上巻42に、これと同じように「いりざけ」と読む項目があります。そちらとの違いは、食材の違いと、「精進もの」と呼ばれた料理に該当するか? 否か? の違いによります。この「煎酒」の場合は、鰹節など動物性食品を利用していませんので、“精進ものの料理”に使用できることになります。「ベジタリアン」や、「ヴィーガン」と自称、または呼ばれる方々でも大丈夫でしょう。・・・そして、ここも上記 上巻42 【いり酒の方】と同様に、現在の「酒税法」を意識せざるを得ません・・・が、こちらの項目には、この『食菜録』の著者・徳川斉昭が水戸藩主として整備した「偕楽園」や「藩校弘道館」で育てた「梅の木々」から収穫し、塩漬けした後に干し上げた「梅干し」を使用しております。・・・しかし、残念ながら・・・「グルタミン酸」や、「イノシン酸」、「グアニル酸」などの「出汁成分=うま味成分」は、あまり多く含まれてはいないとのことでありまして・・・“梅干し特有の酸っぱさや香りなどで、味に深みやコクを与えるためだった”かと想います。
「古酒(こしゅ)一升(少し甘味なる濃き酒よし。)、昆布二本(如何〔いか〕
にも上々。但し、細〔こまか〕
に切る。)
干瓢(かんぴょう)(これも細〔こま〕
かに刻み昆布の嵩〔かさ〕
半分程。但し、勝栗〔かちぐり:※栗を干して臼で搗き、殻と渋皮とを取り除いたもの。縁起物とされた。搗栗とも〕
をも入候〔いれそうろうて〕
打砕〔うちくだく〕
。昆布の嵩〔かさ〕
半分、干瓢〔ほしうり〕
にても勝栗〔かちぐり〕
にても一色よく候〔≒使用する昆布の総量のうち半分は、干瓢でも、勝栗でも、或いはそのうちの一方だけでも良いのです〕
。)
梅干(うめぼし)二十(但し、小さくば二十五も入〔いれ〕
申し候。)
右の内へ水一升入れて、皆々よく掻(か)き混ぜて炭火(すみび)の上にて、そろそろと沸(わか)し、本(もと)の酒一升の嵩程(かさほど)に煎じ詰り候時よく候。塩少なくば、浅き内に入れ申し候。」
下巻28【早煎酒(はやいりざけ)の方】・・・今度は、「さらなる早業テクニック・煎酒の作り方」。・・・これも、上記同様に「酒税法上の取扱い」に充分注意して下さい。
「古酒(こしゅ)四盃(甘めなる酒よく候。)、醤油一盃、酢半分。
右何(いず)れも同秤物(はかりねの)にて秤(はか)り(≒前述した全てを、同様に秤物を用いて計って)
、炭火(すみび)の上にて一泡(ひとあわ)煮(にや)し、そのまま下(おろ)し干し候て、掻(か)き廻し、人肌(ひとはだ)に冷め候時、又(また)煮かけ(=掛け)
煮やし、又(また)右の如く冷し、かくの如く三返(さんべん)煮やし候得ば、煎酒(いりざけ)に成り申し候。」
下巻29【漬柚(つけゆず)の方】・・・「塩漬け柚の作り方」。
「水一斗の中へ塩三升入れよく揉(も)み砕(くだ)き、唐金(からかね:※銅や錫を主体とし、鉛や鉄、ニッケルなどを加えた合金のこと)
か赤銅(あかがね:※銅に、金を3~4%、銀を約1%を加えた合金のこと)
鍋へ入れ煎じ候て、又(ま)た唐金(からかね)か赤銅(あかがね)の鉢へ入れ冷まし申し候。二日も三日も置き冷めきり候程冷し、壺へ入れ柚(ゆず)を漬け申し候。同じくは赤銅(あかがね)より唐金(からかね)の道具よし。
柚(ゆず)百本(葉を付けたるがよし。)、同二十(これは輪切りにして。)
右李(すもも)程の青柚(あおゆず)に候わば、かくの如く候(≒前述した柚が李サイズの青柚だったなら、先ほど述べた方法で宜しい)
。柑子蜜柑(こうじみかん:※ミカン科ミカン属の常緑小高木。別名は薄皮蜜柑とも)
ほどの柚(ゆず)に候わば、百の内を二十切てよし、右の汐(=塩)
水へ入れ、壺(つぼ)を半分程出し、土に埋め置き申し候。尤(もっと)も、壺(つぼ)の口をよく包み申し候。来年まで耐(こた)え申し候。」
下巻30【葡萄漬(ぶどうづけ)の方】・・・こちらは、「甘いシロップで漬け込む葡萄の作り方・保存方」。
「葡萄(ぶどう)のよく熟(うれ)し候時、葡萄(ぶどう)の房(ふさ)共(とも)に漬け候。房(ふさ)を持って振り見申し候。粒の落ち候分は除(の)け申し候。房(ふさ)に二つ、三つずつ付け候て漬け申し候。水にて洗い候わば、水気の乾き候ように日に干し申し候。水気の酒に入れ候得ば、色悪(あ)く成り申し候。
古酒(こしゅ)一斗、白砂糖二升五合、
塩(摺鉢〔すりばち〕
にてよく摺〔す〕
り如何〔いか〕
にも少く入れ候。少し塩気〔しおけ〕
あるかと思え候程の加減なり。)
右壺(つぼ)に入れ葡萄(ぶどう)の擦(こす)り候わぬ加減程に漬け申し候。」
下巻31【梅干砂糖漬の方】・・・今度は、「甘酸っぱい梅干しを、古酒や砂糖で漬け直す方法」です。
「古酒(こしゅ)燗鍋(かんなべ:=鑵鍋。酒を燗にするために使う銅製の鍋で、つると注ぎ口と蓋があるもの)
へ入れ、炭火(すみび)にて沸(わか)し煮え立ち候わぬ先(さ)きに、砂糖を入れ嘗(な)めて見申し候(≒炭火で沸かしますが、一煮立ちする前に砂糖を入れて、味を確かめつつ進めても)
、事の外(ことのほか)甘き程にいたし候(≒思いもよらぬほど、甘~く致します)
。酒粘(ねば)り候はば(≒燗鍋の中の酒に粘り気を感じてきたら)
、酒を加え粘り候わぬように仕(つかまつ)り候(≒酒を加えて粘りを抑えるのです)
。梅干(うめぼし)、水にて洗い一時程も(=二時間ほど)
水に漬け、塩気(しおけ)、酢気(すき)を少くいたし(≒塩気や酸っぱさを減らしてから)
壺(つぼ)に入れ、右の砂糖熱き内に梅干(うめぼし)の上へ掛(か)け、梅干(うめぼし)の隠るる程の加減に酒多く入れ、蓋(ふた)をして、一夜も置き、明日給(たまい)し申し候(≒翌日には食すように致すこと)
。十日程も置き候得ば、酢気(すき)出(い)で候て悪(あ)しく候(≒十日ほど置いたままにしておくと、酸っぱさが出てきて不味くなってしまうので)
。少しずつ細々(こまごま)仕(つかまつ)り候(≒この梅干しは少しずつ、こまめに食してゆくものです)
。」
下巻32【漬松茸(つけまつたけ)の仕様】・・・「塩漬け松茸の仕様」。
「松茸(まつたけ)のつばみたるを(≒松茸がを採れたならば)
、いしづき(=石突き)
を切り捨て、湯煮(ゆに)をして成程(なるべく)よく煮申し候。開きたるは傘(=笠)
と莖(=軸)
と別にして、同じく煮え加減にいたし(≒同じ様な煮え加減にして)
、滴(しずく)をよく垂(たら)し成程(なるべく)よく冷え候程冷まし(≒水気を切ってから、できるだけ良く冷まして)
、いかにも白塩(しらじお)を桶の下へ置き(≒白塩を桶底へ敷き広げるようにしておいて)
、松茸(まつたけ)をその上に摺(す)れ合わぬように並べ、また塩を松茸(まつたけ)の隠(かく)るる程に振り、生松葉(なまのまつば)を間々(まま)に置き(≒生の松葉を、松茸と松茸の間に、そっと挟み込むようにして)
、かくの如く上まで段々(だんだん)に漬け申し候。桶の底に四所も五所も細(こまか)く切揉(きりもみ:※錐で穴を開けること)
をいたし、塩汁(しおじる)を垂(たら)し申し候。塩水溜り申し候えば、松茸(まつたけ)腐り申し候(≒もしも塩水が桶底に溜まるようであれば、そこの松茸は腐ってしまいますので、要注意)
。」
下巻33【駒茸(こまたけ)の漬様(つけよう)】・・・ここにある「駒茸」を「コマタケ」と読み替えると、沖縄から九州地方、四国地方に分布する、非常に珍しいキノコになってしまいます。ちなみに、この非常に珍しいキノコの名には、その見た目からか? 「独楽茸」と云いまして、その別名は「シュッケツマンネンタケ(=出血萬年茸)」と。これは、キノコが傷付いた箇所から赤い汁液が流れるためだそうです。・・・と、いうことなので、この『食菜録』の著者・徳川斉昭が、そんな超レア物のキノコの漬様を記述する必要性も無いので・・・「駒」という字に着目致します。「駒」には、「仔馬」や「若い元気な馬」、「小さいものの呼び名」としての意味がありますので、この項目は・・・我々現代人が日常的に食している「しめじ」や「えのき」などの“”小さいキノコの集合体”と考え、「細(こま)かい茸」と捉えるべきかと想います。・・・著者・徳川斉昭が、「細茸(こまたけ)」と表記しても良かったのですが、彼の洒落のセンスや、雅な精神を尊ぶ心からして、「駒茸」という表記に落ち着いたのではないか? と考える次第です。
「駒茸(こまたけ)の開き切り候わぬばかりを取り、いしづき(=石突き)
を切り捨て、よくよく湯煮(ゆに)をいたし滴(しずく)を垂(たら)し、いかにも白塩(しらじお)にて摺(す)れ合わぬように漬け申し候。桶の底にいくつも切揉(きりもみ:※錐で穴を開けること)
をして塩汁(しおじる)を垂(たら)し申し候。」
下巻34【笋(たけのこ)の漬様】・・・「塩漬け筍の様」。
「笋(たけのこの)先の細(ほそ)き所を除(の)け、漬け申し候。同じくは、やせ竹青く候てよく候(≒同様に、痩せ気味の青み掛かった筍でも漬けることが出来ます)
。二つ割にしても、また輪切りにしても、中のうつ(※筍の節にある区切り部分のことか? 卯立のこと?)
を抜きても漬け申し候。いかにも白き塩にて摺(す)れ合わぬように漬け申し候。輪切りのようを抜きたるには(≒輪切り筍の中側に残る養水を抜き取る際には)
、筒の中へ塩を込め申し候。」
下巻35【猪口(いぐち)の干様(ほしよう)】・・・「猪口の干し方」。・・・この「猪口」とは、イグチ目のキノコの総称であり、「アワタケ」や「ヌメリイグチ」、「ハナイグチ」などがあり、笠は肉質の饅頭形で、裏面に襞(ひだ)は無いが小さな穴がたくさんあって、食用になるものも多いキノコのことです。
「猪口(いぐち)何(いずれ)もほ(=干)
され申し候えども(≒猪口はどれも干されてはいるが)
、同じくは粘液(ぬめり)の少き猪口(いぐち)よく候(≒粘液が少ない猪口が良い猪口と云えるのです)
。白水(はくすい:※米を研ぐ際に出る水のこと)
にて洗い、内の黄なる所の皮をむき(=剥き)
、大きなるは二つ割にして干し申し候。料理の時は、白水(はくすい)にてほど剥がし申し候。塩漬(しおづけ)は悪(あ)しく候(≒猪口を塩漬けしても美味くはない)
。」
下巻36【ろくすの仕様】・・・この項目名に、何故「ろくす」とされているのか? についてが、いまいち分かり難いのですが、原文を深く読むと、「勒(ろく)す」という古語に辿り着きます。この意味としては・・・① おさえる。ひかえる。制御する。② ととのえる。おさめる。③ 彫りつける。刻みつける。または書き留める。録する。④ 詩を作る時、あらかじめ韻字を定める。・・・がありますが、この場合には、イメージとして何となく・・・ ② の意味が、より強いかな? と想います。
「八重生(やえなり:※緑豆のこと。別名に、青小豆〔あおあずき〕や、文豆〔ぶんどう〕とも)
を、寒の内に水にほと(≒水煮するように)
わかし(=沸かし)
、豆腐(とうふ)を仕(つかまつ)り候様に(≒豆腐を作る際のように)
石臼(いしうす)にて挽(ひ)き、いかにも目の詰まりたる布か木綿にて袋をして、その中へ入れ水の中にて揉(も)み出し、二返(にへん)ほどこの如くいたし、皮を捨て、白水(はくすい:※米を研ぐ際に出る水のこと)
をいさせ(=を入れて)
、上澄(うわず)みを捨て日に干し候えば、葛(=葛粉)
の如くになり候。料理の時は葛(くず)の水せんの如くに仕(つかまつ)り候(≒料理する際は、葛を別の容器に移し替え水にくぐらせるようにするのと同様に致します)
。」・・・尚、緑豆を粉状にしてから利用するとの記述になっています。・・・すると、これを、葛切りのような形状にしてしまったら・・・我々現代人が知る「春雨(はるさめ)」と何ら変わらない食品に成るような気が致します。・・・いずれにしても、長期保存には適うものではありますが。
下巻37【氷(こおり)ところてん(=心太)
の仕様】・・・この項目名に、何故「氷」が入っているのか? については、“その透き通った見た目から連想し易い”、との著者・徳川斉昭の判断と云うか? イメージ戦略的なものがあったように感じます。・・・この項目名の食品には、原料や何かを冷やすための「氷」は使われておりません。但し、冬季における自然環境を利用することで「凍(こお)る」という現象を巧みに利用しています。・・・ですから、ここは「凍(し)み・ところてん」や、「凝(こ)り・ところてん」などの命名でも良かったのですが、マルチな才能の持ち主と云える著者・徳川斉昭としては、“そうはしなかった”ということだと想います。・・・尚、旧水戸藩領内の北側の地域は、寒暖差のある地域のため「凍み蒟蒻」や「凍み豆腐」を作りましたし、藩領内の東側の海辺に面した地域では、「ところてん」の原料となる「天草(てんぐさ)」も若干は産出していたので、何とか水戸藩領内の人々が入手可能であったと想われます。
「寒の内に、ところてん(=心太)
の藻(も)の白い処ばかりを、何辺(なんべん)もよく洗い大釜(おおがま)に入れ、白水(はくすい)の三ばん(= 白水の三番:※米を研いで三回目頃に出る、いくらか白さが薄まった水のこと?)
をひたひたより多く入れ煎じ、右の藻(も)の溶け申し候時、水嚢(すいのう:※曲げ物の底部に、馬の尾の毛や銅綱でできた細かい網を張った濾〔こ〕し器・篩〔ふるい〕の一種)
にて濾(こ)し申し候。桶に入れ置き候得ば、固まり申し候。滓(かす)あらば何返(なんべん)も煮申し候。固まり候ところてん(=心太)
を長さ三寸、四方に厚さ二寸程に切り申し候。かんかん申し候夜(≒寒々と冷え込む夜に)
、外へ出し一夜置き候えば、右の如くに凍り申し候。日なたへ出し四日も五日も夜昼、外に置き申し候得ば、後は渋紙(しぶがみ:※張り重ねた和紙に柿渋を塗って乾かしたもの。防寒防水用の衣類や部屋の敷物、荷物の包装などに用いました)
のように、ひしげ(=拉げ:※押し潰すこと)
申し候。凍り候内、細々(こまごま)水を掛けさらし候えば、白く見事(みごと)になり申し候。よく干(ひ)きり、紙の如くに成り申し候時に(≒紙のように薄く成った頃に)
取り入れ申し候。雨少しにてもかかり候得ば、黒く成り悪(あ)しく候。料理の時は、水にて洗い細(こま)かに刻み、煎酒にても酢味噌にてもよく候。又(ま)た汁へ入れ吸物(すいもの)等に仕(つかまつ)り候時は、切り候て成りとも、水にて洗い置き椀(わん)へ入れ、その上へ汁を入れ申し候。鍋へ入れ申し候えば消え申し候(≒鍋など入れて煮立ててしまうと、消えて無くなってしまうので、要注意)
。」
下巻38【大根(おおね)のむし竹(=蒸し竹)
仕様】・・・この項目にある「大根」を、つい「だいこん」と読んでしまいそうになりますが、ここは「おおね」と読みます。ここに「野菜の大根」は出てまいりません。・・・それに、著者・徳川斉昭が、後半に「竹」の字を使用して、「笋」や「筍」の字を使用していないからです。・・・要するに、ここからは、少し「笋」や「筍」の旬の時期を若干過ぎてしまった、完全な青竹になる直前時期の若い竹でも、何とか工夫して食せるようにするぞ!! との著者・徳川斉昭の意気込みを感じる訳です。・・・幕末期は、水戸藩のみならず、飢饉や疫病が重なって、農村が疲弊していましたので、緊急事態用の食材として。
「竹の子、真竹(またけ)なりとも淡竹(はちく)なりとも、いかにも(=如何にも)
新しきを皮をつけながら煮立てて置き、馬の食べ候糠を(≒馬の餌となるような糠で良いから、それを用いて)
釜の中へ入れ、竹の子の転び候わぬように詰め、水を釜(かま)八分目程入れ、釜(かま)の上に桶(おけ)を蓋(ふた)にいたし、息出(いきい)で候わぬようにして二時も三時も(≒勢いづく泡などが釜の外に吹き出ないようにしながら、四時間も六時間も)
火をそろそろと蒸し煮候。煮え申し候釜(かま)の口一ぱい程、竹の子立て候てもなおよく候。五十本百本にても成り申し候。よく蒸せ候時、取出し板の上にて押しひしぎ(=拉ぎ:※潰すこと)
申し候。その後、立て掛けて滴(しずく)を垂(た)らし置き申し候。十日二十日それより日数多くも、悪(あ)しく候上に黴(かび)候ても(≒悪い状態にあって、表面にカビが着いていても)
、中は少しも苦からず候(≒中身は少しも悪くなっていない)
。料理候時はそのまま和(あ)えて、刺身、煮物にも汁にもよく候(≒刺身や煮物、汁物にも良く合います)
。」
下巻39【芥子(からし)の粉乃仕様】・・・「芥子」は、幕末の東日本ではポピュラーな薬味「和からし」として、刺身に付けるなど食しており・・・あちらこちらの野原などに自生する「芥子菜(からしな)」の種子を原料とするため、安価でしたし食中毒などを減らす効果もありました。
「六月中に如何(いか)にも強き日の時分、四日も五日もよく乾し、臼にてはたき(=叩き)
、皮を取り、又(また)よく細(こま)かにはたき(=叩き)
、絹篩(きぬふるい)にて濾(こ)し、紙袋に入れ、火をたく(=焚く)
上に吊り置き申し候。湿(しめ)り候えば苦味(にがみ)出来あしく(=悪しく)
候。料理の時は、一時も前かどに(≒二時間も前に)
如何にも(≒かなり)
暑き湯にて煉(ね)り合わせ、息の出(いで)ざるように紙を蓋(ふた)にして置き(≒発酵し過ぎることが無いように紙で蓋をして置いて)
、物に合わせ候時(≒食べ物と合わせようとする際に)
、取出し遣(つかわ)し申し候(≒取出して使用するのです)
。酢の中などへ入れ候時は、茶せん(=茶筅:※茶道で抹茶を点てる際に掻き回す茶器のこと)
の蒲(ほ)にて振り立て申し候。余り辛過ぎ候程にござ候(≒余りにも辛く感じる程なのです)
。同じくは去年の芥子(からし)を仕(つかまつり)てよし(≒同様に昨年の芥子を用いても良いのです)
。」
下巻40【煮大豆(にだいず)の仕様】
「黒大豆(くろだいず)よく洗い、日に三日も五日も乾して醤油を豆とひたひたに入れ、炭火(すみび)の上にてそろそろと煮申し候。細々(こまごま)杓子(しゃくし/しゃもじ)にてかき(=掻き)
回し、大形豆(≒大きめの豆)
の煮え申し候時、喰(くらい)て見るに醤油辛きものなり(≒食して見ると、醤油の辛さが際立つものとなっています)
。その時白砂糖を少し入れ、甘味を付け申し候。その後も細々(こまごま)かき(=掻き)
回し申し候。砂糖入れ候以後は猶(なお)火の弱きがよく候。醤油の煮詰(につま)り候時、上げ申し候。常のもの煮申し候ように火加減仕(つかまつ)り候得ば(≒常日頃に食す煮物のような火加減で調理してしまうと)
、焦げ付き申し候ものにて候(≒焦げ付いてしまうので、要注意)
。大豆(だいず)余り堅過ぎ候得ば悪(あ)しきと存じ候わば(≒大豆が余ってしまい、また堅過ぎると感じて良くないと思ったら)
、前かど一日程、日に干し申し候(≒前もって一日程、陽に当てて干しておくのです)
。
そうべつ(≒おおよそ)
精進(しょうじん:=精進もの)
の時は味噌汁にも、そのほか淸(すま)しの物、煮物にも、酒塩に味淋酎(みりんちゅう:=餅米と米麹、焼酎を原料とするリキュールで飲酒用のもの)
を差してよし。如何(いか)にも少し差し候て、甘味(あまみ)を付け申す物にて候。常の如くただの(=只の)
酒を差し、その上へ味淋酎を加えてもよく候。精進(しょうじん:=精進もの)
の時は、酢の料理殊(こと)に酢きつく成りたがり申し候(≒酢を用いる料理に使用する際には、案外と酢を強く感じるようになってしまうので、要注意)
。その時は猶(な)お味淋酎を加えたるがよく候。あ(=和)
え物、煉(ね)り味噌の類(たぐい)は古酒(こしゅ)を加え候得ば、事の外(ことのほか)甘味付き候てよく候。味噌を水にて延べ申し候時、その水を半分控え、酒を差して、この口伝(くでん)は魚の時もよく候(≒この口伝は、魚料理の時にも利用できます)
。こく塩(=濃く塩)
あ(=和)
え物に候。味淋酎は甘過ぎ申し候(≒魚料理に味淋酎を使うと、甘過ぎて合いません)
。」
下巻41【葛素麺(くずそうめん)の仕様】
「水三合程の中へ、葛(くず)を盃に半分程入れ、よくとき(≒良く溶いて)
、鍋へ入れ、弱き火の上に掛け、箸(はし)にて、そろそろとふりたて(=振り立てて)
一泡(ひとあわ)煮申し候得ば、葛色光(ひか)り粘り出来申し候(≒葛が光って粘りも出てきます)
。その時開(あ)け人肌(ひとはだ)に冷まし、それをも、こねしるに出(いで)し葛(くず)を捏(こ)ね申し候(≒幾重にも葛を捏ねて、汁を絞り出し切っておくのです)
。捏(こ)ね加減のしるさは(≒その時の捏ね加減の目安としては)
、手の中に捏(こ)ね申し候葛(くず)を一盃入れ、下へ流し見申し候に、素麺(そうめん)の如く、よくすすぎ落し(≒=麦素麺のように、良く濯ぎ)
申し候時、柄杓(ひしゃく)の底に穴を五分廻り程に丸く穴をあけ(=開け)、その中へ右の捏(こ)ね申し候葛(くず)を入れ、鍋に湯をよくたたせ(≒鍋の湯を良く沸騰させて)
、その中へおとし(=落とし)
申し候。鍋の下を油断無く焚(た)き申し候。湯ぬるく(=温く)
なり候えば、素麺(そうめん)切れ申し候(≒湯が温くなってしまうと、素麺が切れてしまいます)
。鍋の中に素麺(そうめん)たまり候わば(≒鍋の中に素麺が煮固まってしまったら)
、せんくり(= 先繰り ≒ 順々に)
に取上げ、そのまま水へ入れ申し候。」
下巻42【ちよよめんの仕様】・・・「ちよよめん」は、「ぢょょめん」のことであり、漢字表記すると「薯蕷麺(じょよめん)」となります。「薯(しょ)」も「蕷(よ)」も、「芋」のことですが、「蕷(よ)」を「山の芋(やまのいも)」と訓じます。・・・尚、この「ちよよめん」の材料を観ると、何だか「山芋入りビーフン」のような麺のように感じます。
「粳(うるち)の上白米は焚(た)き、粉にいたし、絹篩(きぬふるい)にてふるい(=篩い)
、粳(うるち)の粉四盃にうどんの粉(=小麦粉)
一盃混ぜ、山の芋の皮を取り、よく摺(す)りて右の粉を捏(こ)ね、蕎麦切(そばきり)の如くになりとも、うどんの如くになりとも、打ち申し候。茹で様(ゆでざま)は、鍋に湯を立て、その中へ少し混じる程に塩を薄茶二、三服程入れかき(=掻き)
回し、右のちよよめんを入れ、三返(さんべん)あがる程にて(≒麺が三度ほど浮き上がってきたら)
そのまま取り上げ、水へ入れ三返(さんべん)程水を替え申し候。温(あたた)め候てその後湯を差し申し候。尤(もっと)も、鍋の蓋を取り候て煮申し候わんに上水(うわみず)に入れ候ば(≒鍋蓋を取って煮え切る前に、上から水を入れてしまうと)
、ねば切れ申し候(≒麺に粘り気が出て、その結果切れてしまいます)
。世間にちよよめんに糯米(もちごめ)、又(また)は玉子等混ぜ候それは、悪(あ)しく候(≒世間一般では、ちよよめんに糯米や玉子などを混ぜて拵〔こしら〕えようとする者がいるが、それは良くない仕様なので、要注意)
。」
下巻43【麩(ふ)の仕様】・・・「お麩の仕様」と云いつつも、「お麩の作り方」になっています。
「小麦のから粉(※小麦粉を挽〔ひ〕く際に出る衾〔ふすま〕のことで、漢字表記すると、唐粉や殻粉と呼びます)
一斗(但し、二番引までいたし〔≒但し、挽く回数は二度目までとし〕
、うどんの粉〔=小麦粉〕
を取り申したるがよく候。)
塩(夏、秋は一合 但し、八夕〔はちせき〕
にても、春、冬は五夕〔ごせき〕
にても、但し、少し控え候てもよく候。塩過ぎ候えば、塩辛く御座候。)
水(よく捏〔こ〕
ね合わせ申し候。捏〔こ〕
ね加減は手にて押し付け見申し候。指の間より出〔い〕
で申し候程の水加減よく候。)
右よくよく捏(こ)ね候て、臼(うす)へ入れ押付け候て、寝させ申し候。熱き内は一時(≒暑い頃は二時間ほど)
、寒き内は二時ばかりも(≒寒い頃は四時間だけでも)
寝させ置き、その後そろそろと餅を搗(つ)き申し候如く(≒その後に、餅を搗く際のように慎重且つ丁寧に)
搗(つ)き申し候えば、麩(ふ)になり申し候。その後水の中にて何返(なんべん)も、もみ(=揉み)
洗い候えば滓(かす)取れ申し候。少しずつの滓(かす)は薄刀(うすがたな)にて切り除(の)け候て、よきかんにちぎり申し候(≒適当な間隔で千切っておくのです)
。その後、湯煮(ゆに)を仕(つかまつ)り候。湯煮(ゆに)いたし候様(≒その後に、湯を沸かしておいて、麩を茹で上げるようにするのです)
。湯の煮え立たぬように沸(わか)し、その中へ麩(ふ)を入れ、杓子(しゃくし/しゃもじ)にて何返(なんべん)も撹(か)き、湯煮(ゆに)へ立ち候えば幾度も水を差し煮えたたぬように仕(つかまつ)りたるがよく御座候。その後麩(ふ)の煮へ加減は(≒その後の麩の煮加減は)
、何(いずれ)も浮き上りたる時よく御座候。そうべつ(≒おおよそ)
麩(ふ)を捏(こ)ねる時も、揉(も)み候時も同じくは流れ川の水よく候(≒おおよそ麩を捏ねる時も揉み込む時も、同じ様に川の流水を使用すると良い)
。」・・・材料とする塩に関する記述中に「夕(せき)」という単位が出てまいりますが、尺貫法による「勺(しゃく)」と全く同じ分量を表す容積の単位です。「一夕」=「一勺」=「升(しょう)の1/100」=「合(ごう)の1/10」に相当しますので ⇒ ≒「0.018リットル」となります。・・・著者・徳川斉昭の秤(はか)りに対する正確さが良く現れていると想います。・・・尚、記述の最後に、「川の流水を使う」という部分がありますが、まず麩を作る際には相当大量の水が必要となるとの判断があって、きれいな井戸水を汲み上げられない地域も水戸城下には多かったことから、“澱(よど)んでおらず質の良い水を使って欲しい”との水戸藩主・為政者としての気持ちも現れているかと想います。
下巻44【梅ひしおの仕様】・・・「梅醤の仕様」。
「梅干(うめぼし)を水にて洗い、塩の固まりたるを取り、肉(=果肉)
を取り、実を打ち割り、あんにん(=梅仁:※梅の実の中にある種子内の胚や核分のこと)
を取り出し、肉(=果肉)
と一つに摺(す)り申し候。水漬(みずづけ)の生姜(しょうが)細(こま)かに刻み、これも摺(す)り、梅(うめ)の肉と一つに混ぜ、水漬(みずづけ)の品にてよきかん(≒適当な加減で)
に延(の)べ食(く)うてみて、生姜(しょうが)と梅(うめ)との加減は心次第(≒お好み)に加え申し候。」
・・・原文中の「梅仁(あんにん)」に「仁」という字が使われておりますが、別名を「天神様(てんじんさま)」とも云います。この理由は、“学問の神として太宰府天満宮に祀られている菅原道真(すがわらみちざね)が、大の梅好きだったこと”に由来しております。・・・しかし、加工されていない生の状態(=青梅)の「仁」には、「青酸(せいさん)」という毒が含まれていて、大量に食べてしまうと中毒によって目眩(めまい)や呼吸困難などの症状を起こす恐れがあるので注意が必要となります。この事とともに、“梅の種子には天神様が宿っているから食べてはいけない”と信じられ、それが伝えられていることも影響しているようです。・・・いずれにしても、著者・徳川斉昭には、“梅干しの仁には、何らかの薬効がある筈”との考えがあったことが分かりまし・・・この「梅醤」を、“魚を煮付ける際などに、臭み消しや毒消しの意味合いで利用していた”と考えられます。生姜との最強タッグですね。これは。
下巻45【葛切(くずきり)の仕様】
「葛(くず)を粉にいたし、よく振るい、煮え湯の加減に捏(こ)ね、そば切りを打ち候如く丸盆(まるぼん)ほどに打ち延(の)べ、切麦(きりむぎ:※小麦粉を捏ねて、うどんのように細く切った麺のこと。熱くして食べるものを 熱麦〔あつむぎ〕、冷やしたものを冷や麦〔ひやむぎ〕と云います)
など切り候ように細(こま)かく切り申し候。振り粉(ふりこ)にも葛(くず)仕(つかまつ)り候(≒振り粉にも葛粉を使用するのです)
。湯煮(ゆに)も煮え過ぎ候わぬように浮き上がり候と、そのまま取り上げ、水へ入れ、二、三返(さんべん)も替え、切麦(きりむぎ)の如く冷やし候てなりとも、温(あたた)め候得えばその後湯をさし申し候。」
下巻46【いばらきうどんの仕様】・・・キター!!! 「茨城うどん」と思いきや、残念ながら、近畿地方を連想させる「茨木うどん」です。・・・水戸藩領内では、うどん粉の原料となる小麦粉は、ほとんど生産されておらず、むしろ蕎麦生産が盛んでしたので。・・・当時の水戸徳川家(水戸藩)の、うどん粉入手ルートが、大坂・茨木出身の商人だったのでしょうか?
「捏ね様(こねよう)は常のうどんの如くにて、塩加減、春は塩一盃に水四盃。夏は塩一盃に水三盃。秋は塩一盃に水四盃。冬は塩一盃に水五盃入れ申し候。かくの如きにて捏(こ)ね、杉原(=杉原紙:※江戸時代中期には庶民も使えるほど普及し、また需要を賄うため各地で生産されるようになった和紙のこと)
の薄き程に(≒世間で使用されている和紙の薄さぐらいまで)
打ち延(の)べ、平目(ひらめ:≒平たく碁盤目状に)
切り申し候。茹様(ゆでよう)如何(いか)にもさっと茹(ゆ)で、浮き上るとそのまま取り上げ、桶になまぬるき湯を(=桶に生温き湯を)
置き、その湯にてよく洗い、後に熱湯を差し申し候。」
下巻47【くづし、とう婦の仕様】・・・「崩し豆腐の仕様」。・・・「豆腐」を、わざわざ「とう婦」としているのは、著者・徳川斉昭の洒落心なのでしょうか?
「豆腐(とうふ)を田樂(でんがく)の大き目成る程に切り(≒なるべく豆腐を大きめの田楽のように切って)
、手の内にて押し潰(つぶ)し、水気の半分除(の)く程に握り、さて鍋には水、醤油、酢、よきかん(≒適当な加減で)
に煮立て、その中へ入れ一泡(ひとあわ)さっと煮申し候。吸物(すいもの)にも煮物にもよし。」・・・後段部分の「吸物」と「煮物」を除いたら、きっと「湯豆腐」になると思うのですが?・・・但し、あくまでも「仕様」としていますので、これはこれで良いのかも知れません。
下巻48【早作のあまさけの方】・・・上記 下巻19 に続いて、今度は「早作の甘酒の方」。・・・ここも上記 下巻19 同様に、アルコール度数について注意を要します。
「粳(うるち)米七合、餅米三合、
右荒きほし飯程に引き割り(≒前述した粳米と餅米を、干し飯程度に挽き割って)
、粉を篩(ふる)い取り、蒸籠(せいろ)にて、酒飯(さかめし/しゅはん:※酒造米を発酵させる前に、一度蒸して強飯〔こわめし〕状態としたもの)
のかんに蒸し申し候(≒酒飯程度の加減で以って蒸らすのです)
。但し、蒸籠(せいろ)めんめん(=面面に≒それぞれ一つずつ)
にしてよし。
水一升、糀一升五合、
この糀(こうじ)を右の水の中へ入れ、成程(できるだけ)よく揉(も)み出し粕(かす)を濾(こ)し、右のほし飯(=干しいぃ)
を入れ、砂糖桶等の如くに、はけ物(=刷け具)
をいたし、それへ入れ鍋に湯を沸(わか)し、湯煎(ゆせん)にして箸(はし)にて頓物(ひたすら)かき(=掻き)
回し申し候。半時程の内には熱なり申し候(≒一時間程度で発酵し初めて熱を帯びてきます)
。その時甘酒になり申し候。惣別(そうべつ:≒おおよそ)
粳米、糯米(もちごめ)蒸してほし飯にして置き候えば、何時(いつ)にても甘酒にいたし申し候。」・・・要するに、“粳米でも餅米でも一旦干し飯(ほしいい)状態にしておけば、いつでも「甘酒」とすることが可能となる”とのアイデアです。
下巻49【酢の方】・・・ここも、要注意項目です。この下の 下巻68 に、全く同じ項目名となる「酢の方」があります。・・・ここは、「酢醸造の作り方と酢の使用方法」。・・・下記の原文を読むと良く分かりますが、ここにある「酢」や「醤油」は・・・現代社会のように、ただ単に人が消費する商品などではなく・・・“原材料を揃えて、一定のノウハウさえあれば、ある程度永続的に賄(まかな)うことができる重要な醸造調味料なのだ”という、著者・徳川斉昭の哲学や思想が感じられる訳です。「酢」を「醤油」に加えたり、反対に「醤油」を「酢」に加えるなどして。
「黒米(くろまい/くろごめ:※糠部分にはミネラル成分を多く含み、それを摂取することで滋養強壮効果があると謂われ、白米や赤米よりも高い抗酸化機能を持つ米のこと)
一斗(酒飯〔さかめし/しゅはん:※酒造米を発酵させる前に、一度蒸して強飯〔こわめし〕状態としたもの〕
)、糀(こうじ)三升、水三斗(但し、四升程控えてよし。)、
右水を桶に入れ、さて糀(こうじ)を攪(か)き回し、食の熱き内に桶に入れ(≒糀の働きにより熱を帯びている状態のうちに、桶に移し替えて)
、攪(か)き回し、桶の口をよくよく包み、七日目々々々(=七日×四=四週間)
に五度かき(=攪き)
申し候。日数三十七、八日程にてよく御座候。その後酢を立て汲み申し候。二番(≒“下記にある醤油は”)
、右一番の酢(※前述した黒米を使用して作った酢のこと)
を取りて、白水(はくすい:※米を研ぐ際に出る水のこと)
を五升、糀(こうじ)二升入れ、右の如くかき(=攪き)
回し申し候。酢の置き様は、一番の酢(※前述した黒米を使用して作った酢のこと)
を汲み候て桶に入れ候得ば、底に滓(かす)留り申し候。その上澄(うわずみ)をよく汲み、底の滓(かす)は又(ま)た本(もと)へ入れくみ(=汲み)
申し候。少しも酢濁(にご)り候えば替え申し候。その後は樽(たる)に入れ置き申し候。二番同前の事(≒“下記にある醤油を作る場合と同然”です)
。
同(=同様に)
醤油の法 つき麦一斗(炒りてざら引〔=挽〕
こまかなるをさる〔≒炒って粗く挽いて細かなものを取り去るのです〕
。)
大豆一斗(炒りて二つ割に引き〔=挽き〕
、皮を取り、麦の細〔こま〕かなるをかけ〔=掛け〕
、糀〔こうじ〕
に寝させ〔≒糀を着床させる〕
)
塩一斗に水一斗八升入れ、煎じ一夜冷まし、右の糀とかき(=攪き)
合わせ、又(ま)た外(ほか)に米糀(こめこうじ)五升入れ、日数五十日程過ぎて 白米(はくすい:※米を研ぐ際に出る水のこと)一升五合に水一斗三升入れ、粥(かゆ)に煮て一夜程冷まし、前の醤油に入れ、六、七日かき(=攪き)
合わせ口をつつみ(=包み)
、二十日過ぎてあける(=開ける)
なり。
二番 醤油
大麦一斗、大豆一斗(高々〔たかだか:≒せいぜい、この程度なのです〕
)、米糀(こめこうじ)三升、塩一升五合、白米(はくすい:※米を研ぐ際に出る水のこと)一升に、水一斗入れ粥(かゆ)に煮て、冷ましかき(=攪き)
合わせ。
右一番(※前述した黒米を使用して作った酢のこと)
に塩一斗、二番(※この醤油のこと)
に一升一合よし。
一七日(ひとなのか:=七日間)
かき(=攪き)
合わせ、二七日(になのか:=十四日間)
程蓋をいたし置き、その上に酢を立てくみ(=汲み)
て申し候。」
下巻50【菊もとのつくり】・・・この項目レシピに「菊もと」とありますが、出来上がるものは・・・「日本酒(清酒)」ではなく、白濁した「どぶろく」のような「お酒」になっております。したがって、現在の「酒税法」により、これら「濁り酒」の自家醸造は原則として禁じられますので、注意を要します。
「米二升、糀一升四合、水二升、
右の米二升、内二合取り、飯に炊き冷まし申し候て小ざる(=小笊)
に入れ、右の水二升の中へ米を入れ、右の飯をも小ざる(=小笊)
に入れ付け置き申し候。二日程過ぎ候て見候えば、右の飯すえ(=饐〔す〕え:※飲食物が腐って、酸っぱくなること)
申し候。きらら(=雲母:※薄くて剥がれ易い鉱物のこと)
のように浮き候時小ざる(=小笊)
を取り上げ、桶の上に巻き二本おき、その上に小ざる(=小笊)
を置き水をたらし(=垂らし)
申し候。
さて、米を取り上げ、ふかし(=蒸かし)
申し候。人肌(ひとはだ)に冷めたる時分、右のめし(≒前述した蒸かし上げた飯)
、水、糀(こうじ)一つに入れ、かきまわし(=攪き回し)
置き申し候。五、六日過ぎてよく御座候。」
下巻51【葛素麺(くずそうめん)の仕様】・・・要注意項目。上記 下巻41に、同名の【葛素麺の仕様】があります。 その下巻41と異なる点は、下巻41では素麺の形状とするのに、ほぼ一本一本茹で上げていましたが、こちらでは「かいけ」を利用して、一定量を一気に茹で上げて効率化を図っている点です。茹で方に関するバージョンアップ。
「さらし葛(くず)をとろりと溶(と)き、鍋を火上に置き糊(のり)の如くに練(ね)り、同葛(くず)を右の練り汁の冷えたる時捏(こ)ね、湯たぎらかし(≒湯を勢い良く沸騰させて)
、かいけ(=掻い木:※手持ちグリップ部分のある小さめの桶のこと)
底に穴をあけ(=開け)
、煮え鍋の中にたらし(=垂らし)
入れ、浮きたる時すくい(=漉い)
上げ、冷水に入れ申すものなり。」
下巻52【丸山(まるやま)醤油】・・・これも何故に「丸山」と名付けられているのか? についてが、良く分かりません。・・・当時の水戸徳川家(水戸藩)御用商人の屋号なのか? もしくは、水戸藩士(※著者・徳川斉昭の家臣のこと)の「丸山家」の人が殿様に伝えたからなのか?・・・尚、「醤油」を作るのに「大麦」を原材料としている点も興味深いかと想います。・・・そもそも「小麦」と「大麦」では、「含有たんぱく質の量」が違うようでして、これが出来上がる醤油のアミノ酸量を左右させるため、結果として旨味成分の多さでは小麦醤油の方に軍配が上がるとのことです。・・・したがって、著者・徳川斉昭は、元々「含有たんぱく質の量」の少ない大麦、そして小麦よりも安価で入手できる大麦を使って、「醤油」を拵(こしら)える事自体に意義を見出していたのではないか? と考える次第です。
「大麦一斗(よくつき〔=良く搗き〕
上白なり。一日三度ずつ水を替え、三日冷やし申し候。)
大豆一斗(炒り候て皮を取り申し候。二つ割なり。)
右の麦三日目に開け、水をよく取り、二つ割の大豆に合わせ候てふかし(=蒸かし)
申し候。さて常の如く、寝(ねか)せ糀(こうじ)に寝せ糀(ねかせこうじ)に成り(≒よくよく糀を大麦や大豆に着床させて)
、二日天日に乾し、計り申し候。その時分の桝目(ますめ)一斗に、水一斗、塩四升宛(ずつ)入れ、煎じ候て二日程も冷まし、さて右の糀(こうじ)を入れかき(=掻き)
合わせ申し候。二、三日も過ぎ候てより、毎日々々(まいにちにちにち:=三日間)
一、二度ずつかき(=掻き)
合わせ申し候。五十四、 五日もかき(=掻き)
、その上に手を付け申さず七十日程にて、すを(≒酸っぱくなった部分を)
立ち取り申し候。
二番(≒二番目に行なう作業としては)
水右と同前(≒水については前述したものと同然であるが)
、塩水一升に二合宛(≒塩は水一升に二合ずつ)
。糀(こうじ)、水一升に二合宛(≒糀は水一升に二合ずつ)
、三色かき(=掻き)
合わせ、ざくざくかき(=ざくざく掻き)
申し候。」
下巻53【あまひしお】・・・「甘醤」。・・・ここも要注意項目です。特に、原材料の「豆」に着目して下さい。・・・ここの「甘醤」では、「豆」を「豆」として、「大豆」に限ったことではないとしている点が、下記の 下巻74にある、同名の「あまひしお」 が異なっているのです。・・・要するに「小豆(あずき)」でも「えんどう豆」でも、“何でも御座れ”という具合であり・・・「大豆」を原材料とする場合には、“下記の 下巻74 を読んでね”という構成となります。
「大麦(よくつきて〔≒良く搗いて〕
)一斗、
豆(くい加減にいりて〔≒普段食すぐらいの加減で炒って〕
二つ割に成るように引き、皮をむき〔=剥き〕
出し)五升、
塩三升、水八升、
右の麦、水の澄(す)む程洗い米磨(と)ぐようにいたし、右の豆に合わせ、こわめし(=強飯)
のようにふかし(=蒸かし)
、少し干し醤油のように寝(ねか)せ申し候。糀(こうじ)のようになり候時、揉(も)み砕(くだ)き、一夜も置き申し候。右の水塩合わせ、煎じ一夜一日も水の冷え候程よく冷まし、右の大麦を入れ申し候。二日程うちに(≒屋内に)
置き日向(ひなた)へ出し申し候内に、くち(=口)
を開け堀り出すようにして使い申し候。」
下巻54【ひしお】・・・「醤」。・・・この項目レシピも、上記 下巻5 に同名の「ひしおの方」があるので、相違点に注目して下さい。・・・下巻5の方は、原材料に「大麦」を使用して、ここにある「小麦粉」や「餅米」は使っておりません。・・・要するに、同名の「ひしお」ではありますが、中身は別物と云った具合となります。
「小麦(よくつきて〔≒良く搗いて〕
)一斗、大豆四升(いりて〔=炒りて〕
あらあらと引〔=挽〕
き割り、皮をむき〔=剥き〕
出し、粉にして。)
餅米三升(小麦と合わせ一夜浸し、強飯〔こわめし〕
程に蒸し、豆を混ぜ寝せ申し候。)
水八升、塩三升、
右塩水煎じ、冷ましかく(=掻く)
なり。」
下巻55【なつとう】・・・キター!!! 現代茨城県民のソウル・フード「納豆」。しかも「藁(わら)づと(=苞)納豆」か? ・・・と思いきや、私(筆者)の想像とは少し違うものの様です。・・・何やら、予め「塩」で味付けがされており、納豆菌なのか? は定かではありませんが、微生物を着床させるために「炒った小麦粉」を使用し、また稲藁(いなわら)などの外装や容器についての記述もなく・・・。・・・もしかすると、ここにある「なつとう」とは、文字通りの「夏豆(なつとう)」の可能性もありそうです。要するに、“夏の暑い時期に作る大豆の一品料理ということ”なのでしょうか?
「大豆一斗(煮申し候。小麦の粉、衣〔ころも〕
にし寝〔ねかせ〕
せ申し候。)
小麦一斗(よく炒りて引き〔=挽き〕
申し候。)、水一斗、
塩三升、煎じ詰め申し候。」
下巻56【唐(から)納豆】・・・これも、上記に続いて・・・「納豆」とは云うものの、「生姜」を使用したり、「唐皮(からかわ)」を容器にするなど、まさに「一品料理・唐納豆」かと想いますし・・・「唐皮」のような丈夫な容器があれば、「騎馬兵」が自ら食す「軍糧」として、“作りながら(≒発酵させながら)移動や戦闘行動ができる様”が、想像できてしまい・・この『食菜録』が、“やはり幕末期に記されたものなんだな~”という印象を持ちます。尊皇攘夷傾向が強かった「水戸学」の・・・相手方を深く理解するための研究成果だったかと。・・・敵勢力が異国の陸上部隊なら、騎馬兵が相手になるかも知れないな? という・・・。実際に、水戸藩主・徳川斉昭は、「安神車(あんじんしゃ)」と呼ばれる鉄製の牛引き人押し戦車を造らせておりますし。
「大麦(よく搗〔つ〕
きて一斗。よく炒りて二ッ引に引〔=挽〕
きふるい〔=篩い〕
、粉をば別にして置く。)
大豆一斗、
右大豆、馬の食い候加減に煮て(≒馬が食べれる程度に堅めに煮て)
、右の二つ割の麦を煮豆によく合わせ、戸板(※雨戸の板のこと)
の上厚さ五分に広げ、前の大麦の粉を篩(ふるい)に掛け、その上に白膠木(ぬるで:※ウルシ科の落葉小高木のこと)
の葉をかけ(=掛け)
寝(ねか)せ、さて翌日に白膠木の葉に露掛り候はば(≒さて翌日に白膠木の葉に水滴が付くようになったらば)
、そのまま蓋(ふた)を取りて置き、五日程すぎ打返へし(≒五日程過ぎたら裏返して)
、又(また)二日程置き、成程(できるだけ)揉(も)み碎(くだ)き、はな(=糀)
を付け乾して、塩三升七合、水一斗にてよく煮候て濾(こ)して、右の糀(こうじ)を入れ申し候。からかは(= 唐皮:※オランダから渡来した羊または鹿のなめし革のこと)
生姜たくさんに入れ、桶に入れ蓋をして置き、三日過ぎ、上に重(おも)りを少し置き候えば水上(のぼ)り申し候を、又(ま)たかき(=掻き)
合わせ置き、よき時分遣(つか)い申し候。」
下巻57【上々(じょうじょう)納豆】・・・これも、列記とした・・・「大豆」や「生姜」、「茄子(なす)」、「紫蘇(しそ)の実」を使った一品料理です。何となく・・・旨味があって、サッパリした味わいのサラダ的な料理のような気が致します。・・・著者・徳川斉昭が、「上々(じょうじょう)」と名付けていますので、かなり気に入ったレシピだったように感じられます。
「小麦三升(よく炒り六つ割くらいに、ざら〔=ざら目に≒粗めに〕
引く〔=挽く〕
なり。)
大麦一升(生にてざら引〔=挽〕
くなり〔≒生のままで粗めに挽くのです〕
。)
大豆一升(味噌大豆くらい成る程〔≒なるべく味噌を作る際の大豆ぐらいの堅さになるまで〕
よく煮るなり。)
右の大麦小麦、攪(か)き混ぜ、むす(=蒸す)
なり。常の如く糀(こうじ)に寝(ねか)せ、一日天日(てんぴ)に乾かすなり。水八盃、塩二盃半入れ攪(か)き合わせ、押(おも)しを置くなり。三日程押(おもし)を置き、後に蓋(ふた)を取り、それより遣(つか)うものなり。生姜(しょうが)、茄子(なす)、しその実、右三食よく乾して、八合程入れ申し候。」
下巻58【菊本(きくもと)の酒造りやう】・・・「菊本の酒造り様」。・・・これも、上記の 下巻50 にもあるように、白濁した「どぶろく」のような「お酒」になると想います。したがって、現在の「酒税法」により、これら「濁り酒」の自家醸造は原則として禁じられますので、注意を要します。『食菜録』の著者・徳川斉昭が、「上々(じょうじょう)」とまで表現していますので、誠に残念ではありますが。
「米二升、糀(こうじ)一升四合、水二升、
米二升、この内二合取りて、飯(めし)に焚(た)き水二升の内へ飯を入れ置き候得ば、きら浮き(≒鉱物の雲母〔きらら〕のように光りながら、酒に浮遊し)
申し候。その時右の飯を笊(ざる)へ取り上げ、汁気(しるけ)なきよう(=無きように)
に乾かし、天日(てんぴ)に干し申し候。右の米冷し申し候飯を混ぜ、強飯(こわめし)に蒸し申し候。人肌(ひとはだ)に冷め申し候時分、糀(こうじ)一升四合入れ、前の飯浸し候水にて造り申し候。四、五日中に上々(じょうじょう)の酒に成り申し候。」
下巻59【ゆづおき様】・・・「柚の保存方法」。と云いながら、「梅の塩漬け ≒ 梅の保存方法」についても記述されています。「梅干し」ではありませんので、ご注意下さい。・・・また、著者・徳川斉昭が記述する中段部分で、「奇妙にござ候」などと、自らの感想を述べていることも興味深いと想います。
「銅(あかがね)鍋内へ柚(ゆず)一つずつ入れ申し候。ほどへて〆(しめ)切り(≒ほどなくして鍋蓋を閉じ、しっかり密閉状態にしてから)
、塩漬(しおづけ)に置き申し候。
奇妙にござ候(≒奇妙な一致現象とは思うのだが・・・)
。
同(≒同じ様に)
梅漬(うめづけ)の事 竹の筒(≒竹筒に)
節(ふし)を罩(こ)め、塩を入れ、梅(うめ)を入れ、段々(だんだん)にその上へ竹蓋(たけぶた)をよくよく仕(つかまつ)り火の上へ置き候得ば、年を越(こし)へ候えども(≒ ~火の上で加熱し置いておけば、もし年を越してしまっても)
、生(なま)にて居(お)り申し候(≒生のままの状態であるのです)
。小梅(こうめ)ならでは居(お)り申さず由(よし)(≒これは、小さな梅の梅漬けだからといって腐らずに生のままの状態に保たれている訳ではありません)
。」・・・実験家・徳川斉昭が、その本領を発揮しています。ここでは、“空気に曝(さら)しながら、ただ置くことによって、酸化現象が進み、適切な処理や処置をしておかないと、食べ物の保存など適わぬのだ”という考えと理由を述べているのです。
下巻60【うり漬の方】・・・「瓜漬けの方法」。
「きらず(※豆腐を作る時にできる大豆の絞り滓のこと。「おから」や「卯の花」とも)
一升、塩一升、
右能々(よくよく)合わせ、白瓜(しらうり)の内をよくよく攪(か)き、すじ(=筋)
を付け申し候ように、段々(だんだん)に瓜(うり)すり(=摺り)
合わせ申し候様に付け、その後強く重(おも)りを置き申し候えば、暑(しょ)に向う時まで居(お)り申し候(≒暑くなる頃まで、ほぼそのままの状態なのです)
。」
下巻61【茄子(なす)甘漬の方】・・・以下の原文を読めば、「茄子の甘酒漬けの作り方」。
「茄子(なす)百、成る程(できるだけ)傷これ無くを、糀(こうじ)一升、上白(米)一升、攪(か)き混ぜ、甘味(かんみ)出(い)で候時分、塩一升合わせ、茄子(なす)摺(す)れ合い申さず候様に付け(=漬け)
申し候。塩、辛目(からめ)に候わば(≒塩分が強いと感じるならば)
、五、六合も入れ申し候。」
下巻62【醤油の法】
「此の方(≒この醤油の作り方と使用方法については)
四十九の所へ入る(≒本下巻四十九に記述している)
。」・・・となっております。詳しくは、上記の 下巻49の二番 をご覧下さい。
下巻63【小まと納豆】・・・これを漢字表記すると「小的納豆」。この「小的」とは、射場の的で小さなもののことです。概ね直径が一尺二寸(約36.4cm)以下のものを云い、反対に「大的(おおまと)」とは直径が一尺二寸(約36.4cm)以上のものを云います。・・・したがって、ここは文字通り「小さく纏(まと)まった豆料理」を思い浮かべて下さい。「ネバネバ納豆」ではありませんし、「甘納豆」のようなものでもなく、云わば「醤油味の干し大豆を、煮て食べるもの」かな? と想います。
「大豆一斗(みそまめ程に煮てよし。)、大麦五升(よく搗〔つ〕
き晒〔さら〕
し炒〔い〕
りて引〔=挽〕
き割り。)、小麦(同断〔≒前述の大麦と同じため省略する〕
。)
右二色(≒前述した大麦と小麦について)
は豆煮え申し候時(≒大豆の方が煮えた頃に)
、衣(ころも)にかけ(=掛け)(≒衣のように上から掛けて)
、但し、醤油の如くに寝(ねか)せ花(はな)付き申し候時(≒但し、醤油のように熟成させて糀の花が付いてきた頃合いにて)
、天日(てんぴ)にて干し、豆ばりつき候う程(≒豆同士が張り付くぐらいまで)
干し作り込み、塩三升、水七升、右は七升の水にて煎じ、よく冷まし、翌日かき(=掻き)
入れ、但し、醤油作り込み候様にいたし、よくよく堅く作り候故、桶へ入れ、押(おも)し付け重(おも)り強く置き申し候。塩水上へ上る程置き申し候。十月(とつき)まで置き候て(≒そのまま十か月間放っておいて)
、十月(とつき)になり紫蘇(しそ)の葉の入りて、からかわ醤油(= 唐皮を使用して作った醤油 ≒ オランダから渡来した羊または鹿のなめし革を使用して作った醤油)
にて煮申し候。生姜しなしなと干入れるなり(≒生姜は、シナシナの状態まで干してから入れるのです)
。右納豆堅きからかわに申し候(≒この納豆は堅い唐皮を用いて作るものです)
。醤油にてよくよく煮とき(=煮溶き)
合わせ申し候。」
下巻64【五斗(ごと)味噌】・・・“鎌倉時代の頃から作られて来た”と謂われる、いわゆる「五斗味噌」のことのようですが、以下にある原材料と見比べると、配合割合が大きく異なっていると想います。・・・本来の「五斗味噌」の“原材料とその配合”は、「大豆二斗、米糠(こめぬか)二斗、塩一斗」、または“「大豆、米糠(こめぬか)、米麹(こめこうじ)、酒粕(さけかす)、塩を各一斗ずつ、合計五斗を搗(つ)き合わせて作った味噌のこと”なのです・・・が、以下にある「五斗味噌」と比べると、原材料の塩の割合が多く、かなり塩辛いものになるか? とも想います。・・・著者・徳川斉昭は、この『食菜録』で、特に飲食物の保存方法についてを意識し記述しているようですので、さほど矛盾は感じませんが。
「大豆五升、かす(=酒粕)
五升、
塩五升、米糠五升、
細(こま)かにふるい(=篩い)
申し候。味噌煮申し候(≒この味噌は煮て作るのです)
。いき(=意気≒勢い良く)
にて蒸し申し候(≒ 一気に勢い良く蒸らし上げるのです)
。その後つき(=搗き)
合わせ、こが(=古家≒小家?)
へ入れ申し候。」
下巻65 【ぬかみそ】・・・「ぬかみそ」に関しては、上記の 下巻6 や 下巻7 、下記の 下巻69 や 下巻75 にも記述があります。・・・ここの「ぬかみそ」は、“旅に携帯する際や、持ち運ぶ場合の仕様について”のようです。それも、“二つのタイプ”を紹介しております。・・・特に二番目に記述されるタイプの方は、塩分濃度を強めて、より長期間保存に耐えるようにしておりますが、糀(こうじ)や(豆)味噌を同量使うことによって、コクや旨味、甘味など味わい深いものになるようです。・・・とすると、二番目の方は、ちょっとした「お遣い物」などに用いることもできますし、蒸し上がった糠味噌そのものを食すことも、視野に入っているようにも想えます。・・・ただ、これも飢饉対策など緊急事態用食品なのかも知れません。
「餅の米糠(こめぬか)一斗、塩一升、
右入れ、揉(も)み合わせ遣(つか)い申し候。旅(たび)へ持ち申し候。
又(または)
米糠(こめぬか)一斗、塩二升、糀(こうじ)三升、味噌三升
右入れ、搗(つ)き合わせ申し候。糠(ぬか)は豆煮(まめに)へ申し候時蒸し申し候(≒米糠は、味噌の中に残る豆が煮えた頃合いで、蒸し上げるのです)
。」
下巻66【ほう漬】・・・この項目レシピにある「ほう」とは・・・漢字表記すれば、おそらくは「法」になるかと想います。以下の原文中に、「大根」や、山菜「蕨(わらび)」、「きのこ」が記述されており、如何にも「山伏」や「修験者」などの山岳信仰に関わる人々が、里山や山々で入手し易いものを取り扱っているからです。彼ら山岳信仰に関わる人が身に着ける着衣などを「法具(ほうぐ)」と呼んだり、僧侶のことを「法師(ほうし)」と呼びますが、そこから着想して著者・徳川斉昭が名付けたのかな? と想います。・・・いずれにしても、城下町などから遠く離れた自然環境の中でも、しぶとく人々が生き延びるための知恵や手段として書き遺したのではないか? と考えられる訳です。
「大根(だいこん)百本、糀(こうじ)五升、塩三升、
右入れ、重(おも)り置き申し候。水上り候えば重(おも)りゆるめ(=緩め)
申し候。
又(または)
蕨(わらび)百葉に、塩三升、寒の水三升入れ、重(おも)し置き申さず軽く蓋(ふた)おさえ(=押さえ)
置き申し候。強く押し候えばひしげ(=拉げ:※押し潰すこと)
申し候。その他(ほか)きのこ何(いずれ)にてもつけ(=漬け)
申し候によし。」
下巻67【ぬか味噌】・・・ここにある「ぬか味噌」は、著者・徳川斉昭が記述しているように、“糀(こうじ)を贅沢にも三升使うこと”によって、甘く仕上げ・・・おそらくは、それをそのまま食した(=食べ易くした)と考えられます。・・・米糠(こめぬか)には、ビタミンやミネラルが豊富に含まれておりますので、「脚気(かっけ)」や、当時流行した「コレラ」に対して有効なことを理解していたのでしょう。・・・それ故、「砂糖のように御座候」との“キャッチーなフレーズ”を加えたのだと想います。
「糠(ぬか)一升、糀(こうじ)三升、塩二升、
右入れ搗(つ)き合わせ、押し付け置き申し候。砂糖のように御座候(≒まるで砂糖のように甘くなります)
。寒中の米糠(こめぬか)よし(≒寒中の米糠が最適です)
。」
下巻68【酢の方】・・・上記の 下巻49 にも【酢の方】がありました。ここにあるのも、原材料の種類や分量については変更ありません・・・が、以下原文の後半部分をお読み頂ければ違いに気付かれると思います。・・・これは、著者・徳川斉昭が、追加補足的に加えた記述内容になっております。つまり、“発酵や醸造が活性化し過ぎて、熱を感じるほどになったらば、床(とこ)替えしなければいけません”との、「酢のメンテナンスに関する情報」なのです。
「黑米(くろまい/くろごめ:※糠部分にはミネラル成分を多く含み、それを摂取することで滋養強壮効果があると謂われ、白米や赤米よりも高い抗酸化機能を持つ米のこと)
一斗、糀(こうじ)三升、水三斗、
右入れかき(=掻き)
回し候えば、よく酢になり申し候。温(あたた)み出(い)で候えば、とこ(=床)
替え申し候。」
下巻69【糠(ぬか)味噌】・・・ここにある「糠味噌」は、原材料の配合割合を変え、製法も若干変更したバージョンとなります。・・・上記様々な種類? の「ぬかみそ」が記述されておりましたが、現代人の我々が良く知る「糠味噌」となっており、より保存についてが意識されているかと想います。
「糠(ぬか)一斗(細〔こま〕
かに篩〔ふる〕
い、蒸して、よく冷まして。)、糀(こうじ)五升、塩三升、
右よくよくつき(=搗き)
合わせ申し候。」
下巻70【沢庵(たくあん)漬】・・・ようやく、来ました「たくあん/たくわん」が。・・・著者・徳川斉昭が原文末尾に記述しているように、幕末と云うか? 西暦1700年代には、この大根の漬物が、「大江戸」だけでなく京都や九州地方でも食されていたようです。・・・この「たくあん/たくわん」の名の由来としては、江戸時代前期頃の臨済宗の高僧・沢庵和尚(※正しくは、澤庵宗彭〔たくあんそうほう〕)が考案して食していたという説が最も有力です。この説は・・・贅沢な食生活に飽きていた、時の将軍・徳川家光が懇意にする沢庵和尚の元を訪れた際に、沢庵和尚が大根の糠漬け「貯(たくわ)え漬け」をお出したところ、その美味しさに徳川家光が感動し、改めて「沢庵漬け」と名付けたと謂うものです。
「糠(ぬか)一斗、糀(こうじ)三升、塩一升五合、
右よくつき(=搗き)
合わせ申し候。大根(だいこん)百本、五七(ごなのか:=三十五)
日も、よく干し漬け申し候。たくわん漬なり。」
下巻71【百本(ひゃっぽん)漬の法】・・・「大根の塩漬け」のことですが、著者・徳川斉昭は、これを「法」としており、原則的な掟(おきて)の如く記述しております。
「大根(だいこん)百本、
右五、六日干して、塩一升にて漬け申し候上へ、梅雨(つゆ)上り候えば重(おも)り緩(ゆる)め申し候。」
下巻72【同(≒上記 下巻71 と同じく)百本漬の法】・・・こちらも「大根の漬物」であり、上記の 下巻70 「沢庵漬」と似ていますが、「糀(こうじ)」を加えないタイプです。
「糠(ぬか)一斗五升、塩一升五合
右へ大根百本 五七(ごなのか:=三十五)
日干して漬け申し候。」
下巻73【味噌納豆】・・・これも、立派な・・・黒豆の一品料理です。単に味噌で味付けするのではなく、“発酵させて食す”というもの。「黒豆」を使用して、滋養効果も高そうです・・・が、甘くない甘納豆? 塩辛い黒豆味噌? ・・・粘りも出そうなので、やはり・・・味付けしてある黒豆納豆?
「黒豆(くろまめ)一斗(よく煮て。)、小麦一斗(炒りて引〔=挽〕
割り。)
この小麦すいのう(=水嚢:※曲げ物の底部に、馬の尾の毛や銅綱でできた細かい網を張った濾〔こ〕し器・篩〔ふるい〕の一種)
にて篩(ふる)い、荒(あら)き所を(≒篩で残った粗目の小麦を)
蒸し、黒豆(くろまめ)と一つにして天日(てんぴ)に干し、よき加減に寝(ねか)せ申し候時分、小麦に振り掛け衣(ふりかけごろも)に掛け申し候(≒小麦へ天日干しした黒豆を、衣の如く上から掛けるようにするのです)
。花付き(≒黒豆に黴〔かび〕が着いたら)
天日に干し、揉(も)み砕き、塩三升に水七升入れ、煮かえし(※既に一度煮たものを、もう一度煮ること)
成る程(できるだけ)冷し、右の引(=挽)
粉、右の汁にてこね(=捏ね)
申し候。桶に押し付け置き、七日々々に(= 七日×三に ≒ 三週間ほど)
上下へこね(=捏ね)
替へし(≒天地替えして)
、七度右の通りにいたし候。その後は押付け置き申し候。六十日程にて給(たま)し加減になり申し候(≒六十日程経つと食せるようになります)
。」
下巻74【あまひしお】・・・下巻53 にある【あまひしお】と異なる点は・・・「大豆」を使用することと、「塩」を使用せずに自然発酵に任せることで、“大豆や大麦本来の甘味を引き出すこと”か? と想います。
「大麦一斗(成る程〔できるだけ〕
上白に搗〔つ〕
き、一日に三度ずつ水を替〔か〕
へ冷し申し候。)
大豆(だいず)五升(よく炒りて、六つ割にざら引〔=挽〕
き皮を取るなり。)
三日目に、右の麦をあけ(=浸しておいた水から上げて)
つゆ(=露)
を取り、大豆(だいず)に合わせ蒸(むら)すなり。そのまま釜(かま)より取り出し、天日(てんぴ)に干し、糀(こうじ)に寝(ねか)せ申し候。花付け取り出して(≒大豆に黴〔かび〕が着いたら取り出して)
干し申し候。」
下巻75【糠(ぬか)味噌】・・・この「糠味噌」も、“食すための糠味噌”のようです。・・・ただの駄洒落(ダジャレ)ではないと信じます。
「こぬか(=小糠)
七八升、味噌の下へ置き候えば、糠味噌(ぬかみそ)に成り、酒にて溶(と)き給(たま)し申し候(≒小糠七八升も味噌の下に置いておけば、文字通りの糠味噌と成るので、酒で溶いて食すのです)
。」
下巻76【百一漬(ひゃくいちづけ)の方】・・・「百一漬」とは、“大根(だいこん)の間に茄子(なす)の塩漬けを挟んで漬けた沢庵漬け”のことであり・・・“百一物(ひゃくいちもつ)に因んだ重宝な漬物の意味がある”とも、“百日後には食べられるから”とも謂います。・・・原文の後半、但し書き部分には、“即席仕様の百一漬の作り方”まで記述されています。
「茄子(なす)百一へ、塩二升(但し、塩五合水一升、煮替え〔※既に一度煮たものを、もう一度煮ること〕
し、水の如く相〔あい〕
成り候節〔≒塩が溶けて、ただの水のようになる頃合いを観て〕
、右の茄子〔なす〕
塩二升入れ候て、押して〔≒重しをして〕
、その夜の内に水上り候様〔≒その夜の内に水が上がってくる様に〕
押し〔=重し〕
を置き、そのままにて指置〔さしおく〕
。)
当秋沢庵(たくあん/たくわん)御付け(=御漬け)
遊(あそ)ばされ候節(≒その年の秋に沢庵漬けが出来上がる頃合いに)
、大根(だいこん)一同(=大根とともに)
御漬け遊ばさるべく候(但し、沢庵来年五月御出〔おんいで〕
で遊ばされ候わば〔≒沢庵漬けが翌年五月には市中に出回るので、それを待って沢庵漬けを予め用意してから〕
、塩五升、糠〔ぬか〕
七升、御入り遊ばさるべく候〔≒ ~塩五升と糠七升を加えても、同様のものが出来上がります〕
。)」
下巻77【芥子漬傳方(からしづけでんほう)】・・・この項目レシピは、「小茄子(こなす)の漬け汁を活用した芥子酢の使用方法」となります。また「伝方」とされているため、“何処からか伝来したもの”とのことであり、これ自体も「発酵調味料」と呼べるものとなります。
「八、九月の小茄子(こなす)(へた〔=蔕〕
を取り、花落の所を去リ〔≒茄子の花が落ちたらば〕
。)山に一升(≒笊〔ざる〕一山に対して凡〔およ〕そ一升)
、塩一合五勺、
右押(=重)
しを強く致し、一夜漬ける。糀(こうじ)七合、粉芥子(こながらし:※芥子菜の種子を摺って粉末状にして干したもの)
四合五勺、酢一合、右漬茄子(つけなす)の汁をよく濾(こ)し、外(ほか)の品(しな)に練り合わせ(≒塩漬け茄子の水気を良く切り、下に滴〔したた〕った汁に、前述の糀や粉芥子、酢を練り合わせて)
、壺(つぼ)へ入れ、気の泄(も)れぬように(≒外気に触れないように)
目張(めばり)をいたし、三十日過ぎて取り出す。(但し、来年茄子出る時まで〔≒但し、これで翌年に茄子が収穫出来る頃まで〕
貯〔まかな:=賄〕
う。)」
下巻78【糀漬(こうじづけ)】・・・ここにある項目レシピは、「茄子(なす)の糀(こうじ)漬け」と云うよりも、“塩漬け茄子を干したものの糀付け”が適当かと想います。・・・肝心な茄子(なす)の食感は、半生状態で、ある程度歯応えのあるものになるのではないでしょうか?
「糀(こうじ)一升、味醂(みりん)、酒(本〔もと:=元〕
のまま二本、にかえし〔≒味醂と酒は、それぞれ別々に一度煮て、再度煮ておきます〕
。)
茄子(なす)を塩にて押し(≒茄子を塩漬けにして)
、よく干し揚げ(≒良く干し上げ)
、夫(それ)に順じ候(≒塩漬け茄子を良く干し上げておいて、糀、味醂、酒の順番で以って付けて食します)
。(大は切り、小は切らず〔≒大きな茄子は切っておき、小さなものは切る必要はありません〕
。)」
下巻79【三ッ輪(みつわ)漬】・・・これも「漬物」と云いながら、“油分のないサラダのような一品”であり、「大根に青柚を効かせた酢の物」と呼んでも良いのではないか? と想います。尚、食材の分量までのシンプルな記述となっています。・・・「三ッ輪」とのネーミングは、このレシピを食べる際に、生大根や青柚を輪切りにしたからか? と想います。つまりは、“その観た目”から。
「生大根(なまだいこん)三本(薄く切り。)、青柚(あおゆず)三つ、味醂酢(一合にかえし申さず〔≒味醂酢一合を一度煮るだけで良いのです〕
。)、醤油一合、酢八勺。」
下巻80【あちゃら漬】・・・これも「漬物」と云いながら、“油分のないサラダのような一品”であり、「茄子に柚を効かせた酢の物」と呼んでも良いのではないか? と想います。これもまた、食材の分量までのシンプルな記述となっています。・・・この「あちゃら漬」を、漢字表記すると「阿茶羅漬」。何でも、ポルトガル語で野菜・果物の漬物を意味する「achar」が、その語源とされるとか。
「生茄子(なまなす)三十、柚(ゆず)五つ(何〔いず〕
れも薄く切〔る〕
。)
酢二合、味醂酢二合(にかえし申さず〔≒味醂酢二合を一度煮るだけで良いのです〕
。)
醤油一合五勺。」
下巻81【玉子酒(たまござけ)下戸口(げこのくち)】・・・要注意項目です。「玉子酒」そのものは、現代でも病気養生の際などに飲まれるものではあります。・・・この項目レシピと原文の前半部分では、著者・徳川斉昭が「下戸口(げこのくち)」と云っており、かなりアルコール度数も低いものに成るのでしょうから、「酒税法」の問題は無い筈ですが・・・後半部分には「上戸口(じょうごのくち)」と、“ちゃっかり”と加えられておりますので。それも「(酒)強き婦人」を読者ターゲットとして。・・・現代社会では、何とか・ハラスメントと云われかねないような?
「一、玉子八つ、砂糖小茶碗(こじゃわん)に三つ、
酒小茶碗(こじゃわん)に二つ半、水小茶碗(こじゃわん)に十斗、又(また)玉子四つ、砂糖猪(=猪口=ちょこ)
に二つ、水同(=ちょこにして)
四つ、酒同(=ちょこにして)
一つ半、
右土鍋へ、水と砂糖と玉子と入れて、火に掛けよく攪(か)き回し、煮え立ぬ前に下(おろ)す。甚(はなは)だしく煮え立つ時は、玉子は堅(かた)まりて、ふわふわの如く水と別々に成るなり。(泡の消えぬ内に、下すを〔口〕
伝とする。又〔ま〕
た早く下す時は、玉子生〔なま〕
にて悪〔あ〕
しく候。この加減口伝なり。 )
同(=玉子酒)
上戸口(じょうごのくち)
一、玉子七つ、砂糖二つ、水五つ、酒三つ。(但し、強き婦人は酒の分量を増すのみなり。)」
下巻82【早甘酒(はやあまざけ)】・・・ここには、じっくり「甘酒」を作るのではなくて、何かと忙しい時に作れる方法が記述されています。・・・特に原文末尾には「但し書き」で、“熟成させるための時間が一夜も無いような緊急時に使える早業”を紹介しているようです。
「糀(こうじ)五升、米二升三合程、飯(めし)に炊(た)き候て混ぜ置き、湯を煮返し(≒一度湯を沸かして、ある程度冷めたら、再び沸騰させて)
候て良い加減に跡(=後)
より入れ候て、よく搗(つ)き混ぜ一夜置き候て、それにて宜しき候。(但し、召席〔しょうせき?:≒正式な会食などを設ける際〕
には道明寺〔=水に浸し蒸した餅米を乾燥させて粗めに挽いたもの〕
干飯〔ほしいぃ〕
、又〔また〕
は只〔ただ〕
の干飯〔=粳米の干飯〕
にてもよし。砂糖一同に鍋へ入れ、湯をよき程にいれ煮替〔にかえ〕
し用〔もち〕
ゆ。)」
下巻83【鴨味噌(かもみそ)の法】・・・ここで、著者・徳川斉昭は、「方」を用いず、「法」として、ほぼ断定的に“鴨味噌を拵(こしら)える際はコレ以外の方法は無い”としています。・・・「赤味噌(あかみそ)」を用いることで、野鳥である「鴨」を食す際の臭みを軽減すべきとの考えです。・・・こればっかりは、「合鴨(あいがも:※野生の真鴨〔まがも〕と家鴨〔あひる〕との交雑交配種のこと)肉」に慣れ親しむ現代人には、もはや想像しか出来ませんが。
「赤味噌(あかみそ:※熟成期間が長く、色の濃い味噌のこと)
をよく摺(す)り、味醂五合ばかりにて延ばし、水嚢(すいのう:※曲げ物の底部に、馬の尾の毛や銅綱でできた細かい網を張った濾〔こ〕し器・篩〔ふるい〕の一種)
にて濾(こ)し置き、味淋五合別に煮立て置き、その内へ鴨(かも)の作り身(=鴨肉のすり身)
を入れ、煎じよく煮えたる時下(おろ)し、肉の細末(さいまつ)に刻み(≒鴨肉を細かく刻んで)
、前の味噌も一同(≒前述した味噌と全ての鴨肉を一つにして)
摺鉢(すりばち)にて摺(す)り、鴨(かも)を煮たる味淋も一同にして(≒鴨肉を煮立てた味醂も加えて)
、鍋にて煎じよく煮えたる時、鴨(かも)の皮の細(こま)かに切りたるのと油とを入れ、文火(とろび:=弱火)
にて、へたへたに成る程(なるよう)に練り詰めて粉山椒(こなざんしょう)を入れ交ぜる。」
下巻84【煮鳥(にとり)の法】・・・上記の 下巻83 に続いて、これも「鴨肉の臭みを軽減して食す方法」となります。・・・著者・徳川斉昭の鴨肉に対する情熱が伝わってまいります。相当な肉好きであることは間違いないかと。・・・ここでは、「赤味噌」が入手できない場合でも、“何とか白味噌や葱(ねぎ)を用いて鴨肉を食す、または当時の西日本に居住していた人々にも食してもらいたい”との熱い想いも感じられます。
「白味噌(しろみそ:※米麹の比率が高く甘さが特徴的な味噌のこと。但し、塩の含有比率が低いため他地域の味噌よりも日持ちしない傾向あり。京都だけではなく関西全域や香川県と徳島県の一部で食されます)
一升五合、葱(ねぎ)水嚢(すいのう:※曲げ物の底部に、馬の尾の毛や銅綱でできた細かい網を張った濾〔こ〕し器・篩〔ふるい〕の一種)
に一盃、
味淋(みりん)杓子(しゃくし/しゃもじ)に七つ、白砂糖杓子(しゃくし/しゃもじ)に五つ、醤油同(=杓子にて)
一つ、鴨(かも)一羽、
右味淋、砂糖、醤油を一同煮立て(≒=味淋、砂糖、醤油を一つにし煮立てて)
、その内へ鳥を入れ、鳥煮えたる時、味噌を入れ煮え立つ時、煎じ置たる葱(ねぎ)を入れ(≒予め炒っておいた葱を入れて)
よくかき(=掻き)
回し。(但し、火鉢〔ひばち〕
にて文火〔とろび:=弱火〕
にて交ぜ合わす。)」
下巻85【鴨てんぷら】・・・この項目レシピに「てんぷら」とあります・・・が、「鴨肉」を何かしらの粉で衣状に包み込み、ふっくらと油で蒸し揚げる料理ではありません。・・・上記の 下巻84 で、既に「煮鳥」と命名してしまったからだと想います。原文を読めば、これは「鴨肉を使った煮物」であると分かりますが・・・これも、「牛蒡(ごぼう)」や「椎茸(しいたけ)」を用いて、“鴨肉の臭みを軽減する事”に苦心する著者・徳川斉昭の姿が目に浮かびます。・・・尚、この料理は、おそらく・・・上巻69【正宗流 生かい(せいかい)の料理】をバージョンアップさせた料理です。使用する食材の全てが、旧水戸藩領内で調達出来ますし、現在でも茨城県北部地域で良く食されてる、具だくさんの「けんちん蕎麦」にそっくりだからです。「けんちん汁」と云えば、禅宗寺院などで食される「精進料理」ですから、本来は「鳥肉」は使ってはダメとされるのでしょうが、何故か「鶏肉」が入っているのです。鶏の出汁(だし)が出て、とても美味です。・・・ここにある「煮物料理」に、あと「里芋」、「人参」、「大根」、「蓮根(れんこん)」などの野菜と「蕎麦」を加えて、「砂糖」の分量を減らせば、まさに北茨城地方の郷土料理「けんちん蕎麦」の出来上がりとなりますので。
「鴨(かも)二羽、牛蒡(ごぼう)(大十五本、中ならば三十本、右四分斗の厚さに輪切りにし、又〔また〕
は二寸ばかりの長さにせん〔≒線状〕
にす。)、味淋四分、醤油二合五勺、砂糖半斤、椎茸(しいたけ)五十、氷こんにゃく(=凍み蒟蒻)
五十、
先(ま)ず初めに醤油、味淋、煮立(にたて)、直(じか)に鳥を入れる。鳥煮え上げ候節に出し、油皮(※鳥皮部分など油分を多く含む部位のこと)
は鍋に残し置き、直(じか)に生(なま)の牛蒡(ごぼう)を入れ候。その時水一升入れ、余程の内煮る程(≒ちょうど良い頃合いまで)
よく煮え候処(ところ)へ、氷こん(=凍み蒟蒻)
、椎茸(しいたけ)を入れ、半日程煮て煮あけ候事。(但し、出し候前に鳥をよく攪〔か〕
き混ぜて出す。)」
下巻86【早吸物(はやすいもの)】・・・ここも、“旨いお吸い物を早業で作る方法と、その効用について”が記述されています。以下の原文には、当時の京都辺りで「菓子(かし)昆布」と呼ばれていた「山出し昆布」との重要証言もあり、また「梅干し入りの昆布茶(こぶちゃ)」と云えるものの記述もありますが・・・特に、原文後半部分には、「昆布」を薬として観た場合の薬効や、髪の毛など増毛効果まで記述されています。・・・著者・徳川斉昭は武士ですので、当然に髷(まげ)を結(ゆ)っておりましたが、自身の頭髪量を気にしていたのでしょうか? ・・・人の男性ホルモンと、昆布など海藻類に含まれるミネラル成分には、一定の関係性が観られるのは、ほぼ確実と云えるのでしょうが・・・。“計37人の子を儲けた徳川斉昭”ですので・・・。
「山出し昆布(やまだしこんぶ:※北海道南部の函館を中心とした地域で収穫された真昆布〔まこんぶ〕のこと)
(京にて菓子昆布といふもの。)巾(=幅)
四寸ばかりの品なれば長さ五寸ばかりを一寸ずつ手にて引き裂き、鋏(はさみ)にて一寸四方に成る位に切り、茶碗(ちゃわん)へ入れ、梅干(うめぼし)一つ入れ、熱湯を茶碗(ちゃわん)一盃、つぎ蓋(ぶた)をして少しの内置けばよき加減に成る。人により一滴(ひとたらし)醤油を入れてもよし。(但し、なるだけ鋏〔はさみ〕
、小刀等用いざる程風味よし。又〔また〕
昆布を水にて洗いては風味悪しくそのままがよろし。又〔また〕
土瓶〔どびん〕
にて湯を沸〔わか〕
し昆布を入れてもよろし。梅〔うめ〕
は入れず、茶の如く色出る程に多く入れ、気根〔きこん:※一つの物事にじっと耐える精神力のことで、「根気」や「気力」とも〕
の薬、又〔ま〕
た通利〔つうり:※排便のこと〕
によし。胸のやけるにもよし。常に用〔もち〕
ふる時は髪をふやす。)」
下巻87【早雜煮(はやぞうに)】・・・これも、“早く作って早く食すこと”に軸足を置いたシンプルな料理です。・・・どうしても、非常事態や戦時下の軍糧を思い浮かべてしまうのですが。
「餅をよき程に切り、燒きて茶碗(ちゃわん)に入れ、醤油を少々入れ、熱湯を掛け海苔(のり)と鰹節をかける(=掛ける)
。」
下巻88【からみ餅】・・・この項目レシピを漢字表記すれば、「絡(から)み餅」、あるいは「辛味(からみ)餅」とも呼べるかな? と想います。・・・いずれにしても、正月などに良く食べる「大根おろし餅」のことです。但し、「焼き上げた餅」ではなく「煮上げた餅」を使用し・・・また、当時の「大根」は、現在の「大根」ほど「糖度」が高くはありませんので、より辛かった筈なので・・・そのため、このレシピを「からみ餅」と名付けた上で、「砂糖」を加えて、大根おろし特有の辛味を軽減しているのだと想います。・・・尚、原文の末尾部分には、まず大根おろしを作って、時間を置くことで辛味を飛ばし、さほど辛くはない大根おろしを餅に絡める「絡み餅」となっています。・・・まるで「言葉遊び」のようではありますが。
「餅を煮し上げ、大根(だいこん)おろしへ砂糖を交ぜたるのをかけ(=掛け)
又(また)にかえし置きたる(≒煮返して置いた餅に、予め用意した大根おろしを合わせて)
醤油をかける(=掛ける)
。」
下巻89【汁味噌(しるみそ)の法】・・・要注意項目です。「味噌汁」ではなく「汁味噌」となります。・・・つまり、「味噌玉(みそだま)」を予め用意しておいて、後から水を加えて、火に掛けて「汁物」とする方法が記述されているのです。・・・これもまた、非常事態や戦時下の軍糧を思い浮かべてしまうのですが。しかも「尾張流兵法」です。コレは。・・・但し、“より美味しく食べたい/食べさせたい”との著者・徳川斉昭の熱い想いを、どうか理解してやって下さいませ。・・・時代が時代なら、間違いなく重罪が課せられることになりますので。・・・と云うか、この『食菜録』そのものが、長らく水戸彰考館で大切に秘匿されてきたように感じられ・・・また、元水戸藩主・徳川斉昭の業績自体が、当時の江戸幕府(=徳川幕府)によって問題視され、同時に結果責任を問われて、「水戸永蟄居(みと・えいちっきょ)」とされた一因ではあるのですが・・・。
「水七合につき尾張味噌(おわりみそ)摺(す)りて丸め、大抵(たいてい)柿の大きさ位(ぐらい)小き方はよし(≒大抵の場合、柿の大きさよりは小さい大きさのものの方が良い)
。(重さにして)
五十目(め:=匁=文目≒3.75グラム)
位、
日向(=日向産)
干椎茸(ほししいたけ)大抵の大きさ七つ多い方はよし(≒日向産干椎茸は、その大きさにして七つ分よりは多めが良い)
。山出し昆布(やまだしこんぶ:※北海道南部の函館を中心とした地域で収穫された真昆布〔まこんぶ〕のこと)
十七匁(もんめ:=文目)
多い方はよし(≒山出し昆布は、十七匁よりは多い方が良い)
、
鰹節(かつおぶし)かきて(=掻きて)
中皿(ちゅうざら)に一つ多い方はよし(≒鰹節を掻く際には、中皿に一つ分よりは多い方が良い)
。右椎茸(しいたけ)、昆布(こんぶ)を洗い、昆布(こんぶ)はさっと洗いよき程に切り、土鍋(どなべ)にて取り、七合の水の中に入れ、一時ばかり漬け置き(≒二時間ほど漬け置いて)
、右の中へ味噌と鰹節(かつおぶし)と入れ、こんろ(=焜炉=コンロ)
にかけ(=掛け)
、よく煎じ昆布(こんぶ)のよく煮えたる時、昆布(こんぶ)を取出し用(もち)ゆ。昆布(こんぶ)を好(す)く人は、昆布(こんぶ)のままにてもよし。」
下巻90【早漬大根(はやづけだいこん)、香の物、蕪(かぶ)も同斷(=前述の大根同様)
】・・・これも、おそらくは「尾張流」かと想います。わざわざ「赤味噌」を利用していますので。・・・ここは「赤味噌と醤油で漬けた大根と蕪の香の物」。
「赤味噌(あかみそ:※熟成期間が長く、色の濃い味噌のこと)
を醤油にてとき(=溶き)
、大根(だいこん)を一分(てちぶ)位の厚さに輪切りにいたし五、六日漬ける。」
下巻91【早吸物(はやすいもの)の法】・・・云わば「即席のお吸い物」。・・・そして、これも・・・カルシウムなどミネラルが豊富で安価で入手できた「縮緬雜魚」を用いて、水戸藩士や領民だけでなく、一般庶民の目線で記述された料理レシピかと想います。
「縮緬雜魚(ちりめんじゃこ)、五、七分ばかりの雑魚(ざこ)を塩漬(しおづけ)にして、白く干したるものなり。
右雑魚(ざこ)をよき程茶碗(ちゃわん)へ入れ、塩、油を少々垂(た)らし、その上へ浅草海苔(あさくさのり:※江戸浅草産の海苔のこと)
を燒き、もみかけ(=揉み掛け)
熱湯をつぎて(=注ぎて)
よし。又(また)醤油無き時は塩を入れてもよろし。」
下巻92【みしお】・・・この「みしお」を漢字表記すれば、「味塩」になるかと想います。この「味塩」とは、“塩水に昆布を入れたもののこと”だそうです。つまりは「塩昆布出汁」なのですが、ここでは一品料理として記述されております。
「大根(だいこん)おろしの中へ右雜魚(ざこ:※上記91中の縮緬雜魚のこと)
を入れ、みしお(=味塩)
かけて(=掛けて)
もよし。」
下巻93【熬酒(いりざけ)の法】・・・ここも「いりざけ」と訓じるのですが、元の「味淋酒」から、加熱することによってアルコール成分を飛ばしてしまうため、「酒税法」の問題は出ないかと想います。また、例により「法」とされております。
「味淋酒を鍋へ入れ煎じ、付木(つけぎ:※火を他の物に移す際に用いた木片のこと)
より火を移し、又(ま)た蓋(ふた)を取り移し、三、四度もする時は(≒または、鍋蓋を三、四度も取り移すした際には)
、酒の匂(にお)い失(うしな)い申し候を度といたし(≒酒の匂いが失なわれる頃合いにて)
、おろし(≒火から下ろし)
申し候事。」
下巻94【時雨餅(しぐれもち)拵方(こしらえかた)】・・・これは・・・「高級な和菓子」と云えるかと想います。著者・徳川斉昭が考案したものなのでしょうか? ・・・まさに「時雨(しぐれ)」のような衣を纏(まと)った、美しい造形になるかと。
「一、小豆(あずき)一升、白砂糖一斤余、
こし餡(=漉し餡)
にいたし、固くしぼり、うる米(=粳米)
三合程粉に挽(ひ)き、右の品よくよく揉(も)み合わせ、蒸籠(せいろ)へ木綿(もめん)切れ一重(ひとえ)敷き、その上へ金篩(かなふるい)にて裏より、うぐいす(※茶筅〔ちゃせん〕を立てるための道具のこと)
、又(また)は杓子(しゃくし/しゃもじ)にてよく撫(な)で候得ば、細(こま)
かによれ候ようになり、残らず落ち申し候(≒細かく縒〔よ〕れて、全てが金篩の下に落ちてゆきます)
。それを、そっと撫(な)で平(たいら)にいたし、その上へ(小)
豆一つ乗せ、ふかし(=蒸かし)
その(小)
豆軟(やわ)らかに成り候得ばふけ(=蒸け)
候事。
又(また)の法(≒また別の方法としては)
一、小豆(あずき)一升、白砂糖一斤半、粳米(うるちまい)二合半、右にてもよろしく(≒この項で最初の方法に則っても良いのだが)
、尤(もっと)も小豆杯(あずきのさかずき)は、その時に出来かけにて多少もござ候事。故(ゆえに)砂糖、米もその時の様子(ようす)にて入れ候事。」
下巻95【求肥(ぎゅうひ)昆布(是〔これ〕
は少々昆布旧〔ふる:=古〕
くなりたる品にてもよろし。)】・・・この当たりから、祭祀などに用いられる伝統的な食品や、珍味と考えられていたもの、民間療法的に用いられる健康食品の類いが記述されております。・・・ここにある「求肥」とは、白玉粉または餅粉に砂糖や水飴を加えて練り上げたもののことです。「牛皮」や「牛肥」とも表記します。・・・ここにある項目レシピは、どうやら「祝い事」に用いる料理で・・・いわゆる「おせち料理」の一つかと想います。
「山出し昆布(やまだしこんぶ:※北海道南部の函館を中心とした地域で収穫された真昆布〔まこんぶ〕のこと)
なり。さて、酢の中へ白砂糖を少々交ぜ、一枚ごとに表裏へ、みご箒(みごぼうき:=稭箒=藁〔わら〕の外側の葉や葉鞘〔はざや〕を取り除いた茎の部分で作った箒)
にて総体(そうたい:≒山出し昆布の葉の部分全体)
へ摺(す)り付け、何枚にても三十日程蓋物(ふたもの)へ入れ置く節に 、酢の乾(かわ)き候処を、みご箒(=稭箒=藁〔わら〕の外側の葉や葉鞘〔はざや〕を取り除いた茎の部分で作った箒)
にて、よくよく摺(す)り付け仕舞(しまい)置くなり。それより蒸籠(せいろ)へかけ(=掛け)
、極(ご)く軟(やわ)らかに成り候まで蒸し、その上にて塩、砂糖と交ぜ、摺(す)り付け 、又(ま)た一度蒸し候て冷(さま)し、蓋物(ふたもの)へ入れ、寝(ね)かし置き候えば、求肥昆布(ぎゅうひこんぶ)のように出来るなり。(但し、砂糖、塩、分量は見計いよき程入れ申すべきなり〔≒但し、砂糖と塩の分量については、ちょうど良い加減になるように計ってから入れるべきです〕
。)」
下巻96【こはく饅頭(まんじゅう)の法】・・・この項目レシピは、かなりの長文となります。これはこれで、読み下すのにも、少々忍耐力が必要になります。・・・また、「饅頭」と云いながら、我々が良く知るものとは、かなり違います。どちらかと云えば「砂糖菓子」や「飴の類い」? ・・・これも、病中病後などに栄養補給を促進させるための飴のようなものとして記述されており、また原材料の「中三盆砂糖(なかさんぼんさとう)」や「唐三盆砂糖(からさんぼんさとう)」は、江戸時代後半でも相当な高級品とされていましたので、滅多には口にすることはできなかったのではないか? と想う訳です。・・・原文後半部分にある「灰汁取り法」の前の文章を読むと、「わた飴」のようにも想えますし。
「一、中三盆砂糖(なかさんぼんさとう:※日本の中国地方産砂糖のことか? あるいは上等な砂糖して有名な和三盆〔わさんぼん〕のことか?)
二百五十目、水三合入れ、煮立ちたる所を下し、灰汁(あく)を寄せ取り、又(ま)た煮立ちたる処を下し、灰汁(あく)を寄せ取る。かくの如く三、四度し、灰汁(あく)寄せかね候位少くなり候節(≒灰汁が出てこなくなった頃合いで)
、煮立ち下し少々の灰汁中(あくのなか)へ掻(か)き寄せ、その処へ玉子二つの白味(=白身)
を入れ、又(ま)た一寸火に掛け玉子堅まり候節、右にて寄せたる灰汁(あく)も玉子と一同にすくい(=漉くい)
上げる。
一、外(ほか)に寒天(かんてん)二本、水四合にてよくとき(=溶き)
置き、右を前文の砂糖水と一同にして濾(こ)し、又(また)煮たて緩(ゆる)き水飴(みずあめ)の如くなるまで火に掛け、焦げぬように掻(か)き回し、飴(あめ)の如く成りたる時、小猪口(=小さい猪口)
へ匙(さじ)にて七分目ばかり入れ、右の中へ団子(だんご)に拵(こしら)え置きたる餡(あめ)を入れ、又(また)少々前文の如く飴(あめ)に成りたる品を入れ、猪口(ちょこ)のまま水へつけ(=浸け)
堅まりたる所を抜くなり。(但し、琥珀〔こはく:※砂糖や寒天を煮詰めて水飴状になり、また琥珀色になったもののこと〕
やわらかく〔=軟らかく〕
するには寒天〔かんてん〕少なく、堅くするには寒天〔かんてん〕多く入れるまでなり。)
白砂糖、白寒天(しろかんてん)なれば白く、黄の寒天なれば黄に、紅なれば紅に出来る。砂糖の白からざれば琥珀(こはく)の如し。
又法(≒また別の製法としては)
琥珀饅頭(こはくまんじゅう) 一名 金玉饅頭(きんぎょくまんじゅう)とも云う〔≒別名を金玉饅頭とも云う〕
。)
一、唐三盆砂糖(からさんぼんさとう:※中国から輸入した砂糖のこと)二百五十匁、水に煎じ上げ、右の水煮詰め、但し、箸(はし)にて回し糸の引(ひく)ようになるまで、右の所へ寒天(かんてん)一本、水五合程冷やし、その水共(=その水とともに)
煮溶(にとか)し、水の中へ濾(こ)し込み、尚(な)お又(ま)た煮詰め、やはり右の如く糸引く程にてよろしき、(図略す。)図の如く、猪口(ちょこ)を多く入れる時は、水、湯に成る故(ゆえ)に栓(せん)を抜き、度々(たびたび)水を替える。
図の如く型(かた)の中へ水をつぎ(=注ぎ)
、少々堅く成り候所へ、餡(あめ)を丸め入れ、その上へ又(ま)た口まで注(そそ)ぎ込むなり。「みつ」とは、煮詰り密(=蜜)
の如くなるをいう。
中三盆砂糖(なかさんぼんさとう:※日本の中国地方産砂糖のことか? あるいは上等な砂糖して有名な和三盆〔わさんぼん〕のことか?)
二百五十匁、右へ水二百合程入れ煎じ煮立ちたる所へ、長芋(ながいも)二、三寸摺(す)り込み、段々(だんだん)に煎じ候えば泡(あわ)の様なる灰汁(あく)浮上(うきあが)る。右を掬(すく)い取り、段々(だんだん)に煮詰るに従い、少々ずつ水を入れる。度々(たびたび)泡様なる灰汁(あく)浮き上る。右を度々(たびたび)掬(すく)ひ取り、惣体(そうたい:≒全体として)
水は七、八合程入れ砂糖澄(す)むまで灰汁(あく)を取るなり。右の密(=蜜)
糸の引く程に煮詰め候処へ、寒天(かんてん)一本に水五合程入れ煮溶(にとか)し、密(=蜜)
の中へ濾(こ)し込み、又(ま)た煮詰め、やはり糸の引く程に相(あ)い成り候処にて茶碗(ちゃわん)に入れる。
灰汁(あく)取り法(≒これら上記のものに共通する事項として、灰汁を取り除く方法)
砂糖一斤、水二合程入れ、煎じ亦(また)長芋(ながいも)を二、三寸程摺(す)り込み、段々(だんだん)煎じ、灰汁(あく)を掬(すく)ふなり。段々(だんだん)に煎じ詰るに従い、少しずつ水を入れ、あく(=灰汁)
取るなり。 惣体(そうたい:≒全体として)
に水は七、八合程入れ、砂糖澄(す)むまで、あく(=灰汁)
を取るなり。」
下巻97【痰(たん)の薬法】・・・ここで、「痰(たん)が出る人に対する薬法」が出てまいります。・・・以下で「花梨(かりん)」を使用していますが、「花梨酒」や「花梨の砂糖漬け」、「花梨の喉飴(のどあめ)」として、風邪の予防などのために利用する人も多いのではないでしょうか? ・・・尚、以下原文を読む限り・・・砂糖と醤油で煮付けたとは云え、“あの堅~い花梨を食したよう”であります。昔の人は、顎(あご)や咀嚼(そしゃく)する力が強かったのですね。やっぱり。
「一、花梨(かりん:※中国から日本へ渡来した薬用にもされる落葉高木・果樹のこと)
を薄く切り湯煎(ゆせん)にして湯をしたみ、湯を少し入れ、砂糖、醤油にて煮付ける。(但し、したむ〔湑む=滴る〕
湯も、痰〔たん〕
の薬、右食の薬とする。)
一、花梨(かりん:※中国から日本へ渡来した薬用にもされる落葉高木・果樹のこと)
を薄く切り、日にてからからに干し、砂糖へ漬ける。一年置て用(もち)ゆ(≒砂糖漬けにしてから一年後に用いるのです)
。」
下巻98【燒饂飩(やきうどん)】・・・ここでは「焼きうどん」となっていますが・・・これは、“少し甘めで膨らまないホット・ケーキ”となっています。何かしらの具材を包み込んだら、「プレーンタイプのクレープ」ですね。完全に。
「饂飩粉(うどんこ)二十匁、砂糖十五匁、玉子二つ、水三勺位、
右鉢(はち)へ入れよく摺(す)り、玉子、焼鍋(やきなべ)へ薄く垂(た)らして焼き、少し堅く成りたる時、又(また)裏返し焼くなり。鍋へは垂(たら)す度(たび)ごとに胡麻(ごま)の油をよく引くなり。」
下巻99【ふな燒 (六月朔日〔ついたち〕
を「むけ〔=無卦の〕
朔日〔ついたち〕
」と云ひ、うんどん粉〔=饂飩粉〕
食するもののよし〔=由〕
。)】・・・この項目レシピの「ふな」、若しくは「うな」については不明なのですが、「六月」のことを「むつき」⇒「むけ」と云った具合に訛(なま)らせると、「無卦(むけ)」という漢字表記が脳裏に浮かびます。この「無卦」は、平安時代の陰陽師として有名な安倍晴明(あべのせいめい)が携(たずさ)わった「陰陽道(おんみょうどう)」において、“する事なす事みな凶方へ向かう縁起の悪い年廻りのこととされ、これが後の五年間続く”と考えられるそうです。ちなみに、この「無卦」の対義語を「有卦(うけ)」と云います。・・・要するに、ここにある「ふな燒」とは、元々は「神へ捧げる伝統的且つ重要な神饌(しんせん/みけ)」だったのではないでしょうか? いつしか、それが厄払い的な意味を持つ食べ物とされていたのではないでしょうか? ・・・とは云え、この『食菜録』の著者・徳川斉昭も、あまり詳しくは説明せずに、サラッとした表現に留めておりますので、斉昭夫人の「吉子女王(※正式には、登美宮吉子女王。有栖川宮織仁親王の第12王女のこと)」などにより伝えられた宮中行事の一つだったのかも知れません。
「うんどん粉(=饂飩粉)
一升、上大白(じょうだいはく:≒大きな杯で上等なもので)
一斤、水は見計(みはか)らいて入れる。焼方(やきかた)右に同断(≒この焼き方は、上記の燒饂飩同様である)
。」
下巻100【茄子(なす)のへた(=蔕)
】・・・ここで、再び・・・「気根(きこん)」を良くして、髪の増毛を促進させると考えていた? ような一品が記述されております。以下の原文をご覧下さい。
「茄子(なす)のへた(=蔕)
切りて捨てる所なり。右心(しん:=芯)
を去り、四つに割り干して貯(たくわ)う。味淋、醤油にて煮、用(もち)ゆ。煮豆杯(にまめのさかずき)の中へ入れても用(もち)ゆ。気根(きこん:※一つの物事にじっと耐える精神力のことで、根気や気力とも)
をよくし、髮を増(ふ)やす。」
下巻101【ふくたみ】・・・ここにある項目レシピは、著者・徳川斉昭が「珍味」と考えていたもののようです。・・・「ふくたみ」を漢字表記すると「福多味(ふくだみ)」となります。・・・尚、原文中では「鮑(あわび)」とされますが、本来は「常節(とこぶし)」と呼ばれる“鮑よりも小型の巻き貝を使用する”とのことです。・・・そういう些細な事は、気に為されない著者・徳川斉昭なのであります。
「鮑(あわび)、貝のまま少々煮、わた(=腸)
と身を離し、わた(=腸)
の砂を取り、わた(=腸)
をよく摺(す)り潰し、味淋にて程よくとき(=溶き)
、焼き塩(やきじお)にて加減いたし漬(つけ)込む。鮑(あわび)十、わた(=腸)
十入れ候事。(小さきのは丸のまま漬ける。大きなるは切りて漬ける。又〔また〕
新らしき貝をはがし〔=剥がし〕
塩と交ぜ漬ける。これは身堅く出来る。)」
下巻102【鱚(きす)すり流汁 (鱚を摺〔す〕
り漉〔こ〕
して置き。)】・・・“江戸前の鱚”の登場です。いわゆる「椀物(わんもの)」ですね。・・・尚、これも「赤味噌」を使用していますね。・・・
「赤味噌焼き、よく煮出し冷(ひや)し候て、金摺鉢(かねすりばち)に魚摺(す)り、段々に摺(す)り混ぜ薄くし煮たてる(=煮立てる)
。蕪(かぶ)、薄大根、生椎茸、しめじ茸、こうづ茸(こうづだけ:※和紙の原料・楮〔こうぞ〕の根本に生えるキノコのことか?)
、うちわ茄(うちわな?:※団扇〔うちわ〕の姿のように平たく縦に切った茄子のことか?)
等、何(いずれ)にてもよし。」
下巻103【尾州(びしゅう)味噌摺(す)り流し】・・・上記の項目レシピに続いて・・・やはり、“尾張流の料理のよう”です。使われる「尾州味噌」は、以下原文を読むと・・・おそらくは「赤味噌」で、大豆の含有率が高かったもののようです。・・・以下原文の情報元は「尾張徳川家」であり・・・著者・徳川斉昭が、この情報を入手した場所は、おそらくは・・・“江戸城内の大名控えの間”ですね。・・・会話の相手は、時代背景や時期的なことを考慮すれば・・・「中務大輔様」こと「慶勝(よしかつ)」と改名する前の「尾張徳川家(尾張藩)・第14代藩主の徳川慶恕(とくがわよしくみ)」ですね。・・・彼の実母は、水戸徳川家・徳川治紀(とくがわはるとし/とくがわはるのり)の五女「規姫(※後の真証院)」なので。つまり、この『食菜録』の著者・徳川斉昭と徳川慶恕は、伯父と甥の関係になりますので。
「一、松魚節(しょうぎょぶし:=鰹節)
煮出しを取り候て、よくよく冷まし置き、その露(つゆ)にて味噌をすり(=摺り)
煮立て、なお又(ま)た冷まし置き、魚の肉を右汁にて段々摺り流し、その上にて又(ま)た煮出ち候まで掻(か)き廻し候事。(但し、最初より、よくよく掻〔か〕
き廻し候わねば焦げ付き申し候事。)
一人前に(≒一人前を作るのに)
尾州味噌七十匁程、鮎(あゆ)並尺(なみのしゃく)くらいの品二本入れ。(但し、石臼〔いしうす〕
にて搗〔つ〕
き、蒲鉾濾〔かまぼここし〕
にて、よくよく越す〔=漉す〕
事。)
一、魚肉いらず(≒魚肉は炒らずに)
、尾州味噌御仕上げの節は煮立て候節、泡(あわ)をよくよく取り候事。
右(≒前述した内容のもの)
は、中務大輔様(※尾張徳川家当主の徳川慶恕のこと)
御出(おんい)で、茶の節御持成されたる候(≒茶事の際に持参為されたのです)
。尾州味噌摺(す)り流し出来(でき)風味(ふうみ)殊(こと)の外(ほか)よろしき候処(≒尾州味噌の摺り流しが出来上がったので、その風味を確かめると、とても良い風味でしたのに)
、この御味噌は江戸表(えどおもて)にて為御製(ぎょせい)に相(あ)成り御味噌にて(≒この御味噌は江戸表で拵〔こしら〕えさせた味噌なので)
、本渡(ほんわた)り尾州の味噌にはござ無く(≒本来の尾州味噌とは云えないものであって)
、江戸表(えどおもて)にて為御製(ぎょせい)に相(あい)成り候味噌にて尾州様(びしゅうさま)御上(おのぼ)りに相(あい)成り候よし(≒尾州様〔※徳川慶恕のこと〕自らが、拵〔こしら〕えさせた御味噌を京都上京の際に持ち込まれたとの事)
。本渡(ほんわたり)尾州味噌にては、渋き御座候由(≒本来の尾州味噌とは、さらに渋い風味だとの事)
。中務大輔様御直話にござ候事(≒中務大輔様が直接お話になった事なのです)
。(但し、御汁の仕立方は〔≒但し、尾州味噌を使用した摺り流し汁の作り方は〕
前に認め候通りにござ候〔≒以前に、中務大輔様がお認め為さった通りであろう〕
。)」
下巻104【砂糖漬の梅の法】・・・上記の 下巻31 には、「梅干の砂糖漬」がありましたが、ここは「入梅前の青梅の砂糖漬け」となります。・・・但し、疵(きず)のある青梅(あおうめ)には毒があり、注意を要すため、以下原文に「無疵(むきず)の~」と記述されております。・・・尚、原文但し書きにある「出島砂糖」という名称により、長崎出島を貿易窓口としてオランダや中国から輸入された砂糖のことを、一般的に「出島砂糖」と呼んでいたことも分かります。
「入梅(にゅうばい)十日前、無疵(むきず)の大きなる実を取りて、砂糖に漬(つけ)るなり。(但し、出島砂糖〔でじまさとう〕
よろしき。)」
下巻105【御台所(みだいどころ)亦味噌(またみそ)汁 梅印(うめじるし)】・・・この項目レシピにある「亦」を「赤」と読み間違えると意味不明な文書になりますので、注意を要します。・・・この項目レシピを、今風に訳すと・・・「毎度、奥方様(おくがたさま)が作る味噌汁。 ですが、水戸徳川家のお墨付きあり!!!」・・・になるだろうと想います。原文には「梅」は出てきませんので・・・「梅印」には、このような意味しかありません。・・・どうして、このような具合になるのかと申しますと・・・大消費地・江戸で暮らす「江戸定府」とされていた水戸徳川家(水戸藩)の者達は、藩主から末端の藩士まで、恒常的に物価高に難儀しておりました。それでも、それぞれ一家としての格式は保たなければなりませんし、“旬とされる土佐産・上り鰹”などは、半分江戸っ子に成り掛けている水戸っぽ(水戸人)としては、何が何でも入手し食したいものだったからです。本来は、“生の鰹のお刺身を芥子醤油で食したい”ところではあったのでしょうが、現実には時代劇の大店(おおだな)の商人(あきんど)のようにはいきません。・・・以下原文では、そんな「大江戸」に暮らす人々に対する徳川斉昭なりの配慮が感じられる訳です。
「味噌百四十五匁、水一升五合、
右の水へ、上土佐鰹魚節(≒上物の土佐産鰹で作った鰹節を)
沢山(たくさん)に入れ、煮出し申し候。味噌は摺(す)りながら少々ずつ、右の出し水にてのべ(=延べ)
申さず候ては御加減(おかげん)よろしからず候(≒味噌を少しずつ丁寧に摺りながら水で溶かさないと、家族の者達の機嫌を損なってしまうので、注意を要します)
。(又〔また〕
右鰹魚節、椎茸〔しいたけ〕
をよく煮出し置き、煮え立ち候節、味噌を入れ掻〔か〕
き回し候もよろしく候。)」
下巻106【魚味噌(うおみそ) (魚は干鯛〔ほしだい〕
、同甘鯛〔あまだい〕
、同平目〔ひらめ:=鮃〕
、同きす〔=鱚〕
等、生臭〔なまぐさ〕
き魚にこれ無き品を用〔もち〕
ゆ〔≒魚は干鯛、甘鯛、平目、鱚などの生臭くない魚を用います〕
。)】・・・題して「魚味噌」なり。
「味噌、赤白当分にて(≒味噌は赤味噌と白味噌を等分にして)
七十匁。
魚、塩出し極(ご)く細(こま)かにたたき(=敲き)
入れる。四十五匁。
味淋、猪口(ちょこ)に一つ。
鰹節、少々入れる。
右にて煮詰(につめ)る。」
下巻107【鯛味噌(たいみそ)】・・・ここで、上記の 下巻105 にある「亦味噌(またみそ)」が出てまいります。
「八寸鯛(たい)(≒八寸大の鯛を)
一枚(ふくめ魚〔ふくめうお:=含め魚≒内臓など不要部分を除いた後の魚丸ごと〕
となし〔=為す〕
。)
梅印亦味噌(うめじるしのまたみそ:※上記の 下巻105 にある亦味噌を)
二合五勺、砂糖二十匁、味淋酒二合、
右の割合にて、程(ほど)よく煮詰る。
仕法(しほう:≒仕上げる方法)
鯛(たい)を三枚におろし、よく小骨を去り、皮を引き、塩にくるみ(=包み)
、湯煮(ゆに)をいたし、布に包(くる)み、水気を委(よ)くよく搾(しぼ)り揉(も)みて、含め魚(≒内臓など不要部分を除いた後の魚丸ごと)
にいたし置き、亦味噌(またみそ)をよく摺(す)り、表をいたし、右魚と摺(す)り交ぜ(≒前述の魚と良く擦り合わせて)
、大抵(たいてい)交り候得ども、味淋酒と砂糖を煎じ、味淋の匂(にお)い抜け候処へ、魚と味噌とを交ぜ候を、乗せ(=載せ)
入れ段々(だんだん)に煎じ詰める。」
下巻108【くらげ(=海月=水母=水月)
の塩漬】・・・ここでは、「塩漬けクラゲの食し方」が記述されていますが、観た目の奇妙さ故なのでしょうか? ・・・著者・徳川斉昭の味覚には適わなかったようであります。
「くらげ(=海月=水母=水月)
の塩漬の椎茸(しいたけ)の如く黒く成る物(※くらげの笠に似た部分のことか?)
を、茶殻(ちゃがら)にてよく洗い、細(こまか)く切り、酢を掛けて食す。酒肴杯には成る(≒酒の肴の杯には成るが)
、美味には非ず(≒美味くはない)
。塩に漬けたる物は、右の如くしても、白くは相(あ)い成らざるなり(≒塩漬けしたクラゲは、前述した方法で調理しても、一向に白くはなりません)
。」
下巻109【らっきょう〔=薤=辣韮〕
煮付け (精神絶し〔≒精神的に絶好調となり〕
、邪気〔じゃき〕
をさけ〔≒避け〕
、寒暑を凌〔しの〕
くに〔≒暑さ寒さを凌ぐにも〕
尤〔もっと〕
もよし〔≒最も良い〕
。)】・・・ここは、「らっきょうの煮付け」であり、「酢漬け」ではありません。・・・「らっきょう(=薤=辣韮)」は、日本に9世紀頃渡来し、当初は薬用として用いられました。その頃は独特な辛味と匂いが敬遠されていましたが、身体を温める効果があるとされ、“江戸時代には食用として広まり、漬物だけでなく煮物などにして親しまれるようになった”とのこと。・・・尚、“この煮付け”は、現代人ほど虫歯を患っている人は多くはなかった時代のことですので、当時高齢となった人々を意識した記述だと想われます。
「らっきょう(=薤=辣韮)
、よく湯煎(ゆせん)し、軟(やわ)らか成りたる時、味淋、醤油、砂糖を入れ、又(ま)たよく煮詰める。(但し、臭〔にお〕
いを好まざる人は、二、三度も湯煮〔ゆに〕
をして流すなり。されども煎したる湯を流さず方、薬によろし〔≒それでも、煮た湯を流し捨てたくなければ、薬とする方法もありますよ〕
。歯悪しき人は、箸〔はし〕
にて押す時は潰〔つけ〕
るる程に軟〔やわら〕
かにし、歯無き人は溶ける位にも煮るなり〔≒歯が悪い人は、箸で潰せる程に軟らかくして、全く歯が無い人は、らっきょうが溶けてしまう程煮たら良い〕
。)」
下巻110【漬薤(つけらっきょう:=漬薤=漬辣韮)
】・・・現代人も、よく食べる「らっきょう(=薤=辣韮)の甘酢漬けの漬け方」です・・・が、これより下の 下巻167 に【漬ラッキョウ(=薤=漬辣韮)の法】もあります。
「らっきょう(=薤=辣韮)
生(なま)一升に付、味淋酒三合、醤油三合、酢三合、らっきょう(=薤=辣韮)
は少々にても、水気これありては悪(あ)しく、よくよく水気を拭(ふ)き取(とる)なり。(但し、外三味〔ほかさんみ:※らっきょう(=薤=辣韮)のこと〕
は煮申さず右露〔≒味淋酒、醤油、酢から成る調味漬け汁〕
へ潰〔つけ〕
る。)」
下巻111【蓮の実(はすのみ)料理仕法(つかまつりほう) (気魂〔きこん:=魂=精神≒気根〕
の薬によし。)】・・・つくづく想います。好きなんだな~と。もとい、重要視していたんだな~と。「気根」や「気魂」を。・・・著者・徳川斉昭は、かなりエネルギッシュな人だったんですね。・・・真面目に「蓮の実」を語ると、タンパク質やビタミンB群、食物性ミネラルなどが豊富に含まれておりますし、仏教では象徴的なものですよね。「蓮(はす)」自体が。・・・ちなみに、別ページの『常陸風土記』の中にも「蓮(はす)」の記述が見られますので、“旧常陸人にとっては、馴染み深い植物”とは云えますし。
「先(ま)ず外の皮をよくむき(=剥き)
、油にてよき程に揚げ、焼塩(やきじお:※焙烙などで煎った塩のこと)
を掛け、食す。(但し、八月頃色の着〔つき〕
たる実なり。実の中なる芽は、食せずして取り捨てる〔≒実の中に成る芽は、取り除いて食しません〕
。)
又(ま)たは油にて揚げず、うま煮にしても用(もち)ゆ。」
下巻112【塩山椒(しおざんしょう)の法】・・・ここには、「調味料」としての「塩山椒の作り方と保管方法」が記述されています。・・・原文中にある「朝倉山椒(あさくらさんしょう)」は、江戸時代初期頃から旧但馬国の地域ブランドとして有名でした。
「朝倉山椒(あさくらさんしょう:※現兵庫県養父市八鹿町朝倉発祥とされる粒が大きい山椒のこと)
の実、赤くなりたるを白水(※米を研ぐ際に出る水のこと)
に付け置き、一粒ずつ内白皮をむき(≒内側の白い皮を一粒ずつ剥いて)
、焼塩(やきじお:※焙烙などで煎った塩のこと)
の末の内へ入れ(但し、塩へも水を廻す。)摺(す)り混ぜ、天日(てんぴ)又(ま)たはジヨタン(=助暖:※小さな火鉢のこと)
にて干し、揉(も)む時は外へ付きたる塩落ち、内へ入れたる塩のみ残るを、硝子(がらす)又(また)は徳利(とっくり)等へ入れ貯(たくわ)える。」
下巻113【蒲鉾(かまぼこ)つくり】・・・ここは、「鮫肉(さめにく)の蒲鉾製法」。・・・原文中にある「星鮫(ほしざめ)」は、良く近海で釣れたり、網に掛かったりしますが・・・その肉は美味とされ、食用となります。おそらくは、現代で市販される蒲鉾や竹輪(ちくわ)にも使われているのではないでしょうか?
「一、星鮫(ほしざめ:※日本では北海道以南に分布し、体長約1.5m、背中に斑点模様を持つ鮫のこと)
(水戸にも多く有り。)二尺ばかり迄なるを骨を去り、よくよく叩き(=敲き)
、(摺)
鉢(はち)にて摺(す)り、味淋酒、砂糖を入れ、又(また)よく摺(す)り、濾板(こしいた)へ付けて蒸す。(但し、鯛〔たい〕
その外〔ほか〕
の魚を交ぜても製〔つく〕
る。味淋酒、砂糖入れる時は甘味有りて風味よろし。)
同(≒同じく星鮫の)
一、端(はじ:≒星鮫の端っこと)
、白きす(≒白鱚を)
当分(≒等分にして)
摺身(すりみ)にして煎(=炒り)
、味淋酒、玉子白身ばかり入れ、蒸し上げる。白砂糖入れてもよし。
同上々(≒同じく星鮫で最も良いのは)
一、星鮫二尺位までの、鯛(たい)八寸位までの品(鯛大きく成る時は油強く宜しからず。いずれも新しきを上とす。)製方煎に同断(≒炒るという製法は前述に同じである)
。七、八寸位の鯛(たい)二枚余りは(星)
鮫(さめ)。(七寸四方深さ二寸箱に入れる割合〔也〕
。)」
下巻114【鶏卵四角(しかく)、三角(さんかく)に拵(こしら)える法】・・・ここでは、いわゆる「ボイル・エッグの成形テクニック」が記述されております。・・・著者・徳川斉昭が特に強調しているのは、“まずは美濃紙の入手が不可欠である”と。・・・いずれにしても、鶏卵そのものが滅多に食せなかった物なので、病中病後などで養生が必要とされる人々への助言かと想います。
「美濃(みの:※美濃地方〔現岐阜県南部〕で作られる美濃和紙のこと。江戸時代には最上の和紙と評されていました)
にて一寸五分四方位に袋を拵(こしら)え、右の口より玉子を入れ、口を二つ程折って手の平(ひら)に乗せ、指にて袋の上より袋の角にまで行き及ぶ様やわらかに(≒丁寧に)
押し、煮え湯の中へ入れ堅まりたる時、湯より出し紙を取る。(但し、紙は美濃に限る。鶏卵を猪口〔ちょこ〕
に入れ、それより袋へ入るべし。三角は袋を三角に作るなり。)」
下巻115【蒸し平目(=鮃≒蒸し鰈〔かれい〕)
製法】・・・この項目レシピでは、食材選びに注意する必要があるかと想います。・・・左記の項目内に注釈部分を加えましたが・・・元々、「平目(=鮃)」と「鰈(かれい)」を見分けるのは、素人ではなかなか難しい事ですよね。魚に詳しい人に言わせると、その魚の口部分の構造的な違いで分かるそうですが。・・・いずれにしても、この『食菜録』が著わされた江戸時代末期には、「ムシカレイ/ムシガレイ」と呼ばれる魚のことを、「蒸し平目」と呼んでいたらしいので、左記のような注釈となった訳です。・・・味や食感的には、若干変わるかな? という程度? ・・・なのでしょうか? ・・・口の構造で見分けられる位なら、魚の食性も違うでしょうし・・・。尚、この『食菜録』には、この他にも「蒸し物」が多く取り上げられております・・・が、これら「蒸し物」は、“まずは料理の下拵(したごしら)え作業の一つ”として認識されていたようであります。
「取り立て(=採りたて)
の蒸し平目(=鮃≒蒸し鰈〔かれい〕)
を、塩にて半日ばかり押し、水にてさっと洗い、尾の処を糸にて結び、竹にかけて(=掛けて)
天日(てんぴ)にて三、四日干す。(但し、上々の天気なれば二日にてもよし。干し過ぐる時は風味悪し〔≒干し過ぎた場合には風味が落ちています〕
。)
水にさっと洗わず、押したるまま干す時は、干魚(ほしうお)の如く成って、つや(=艶)もなく見所よろしからず、風味も悪(わる)し。又(ま)た塩にて押す前、庖丁(ほうちょう)にてよく、のろ(=ノロ:※粘り気があり、ドロッとした感触の液体状の部分)
を扱(あつ)くべし(≒ノロの部分は取り除くべきです)
。(但し、よく水にて洗い、のろ〔=ノロ:※粘り気があり、ドロッとした感触の液体状の部分〕
を取つてもよし。)
焼き立ての蒸し平目(=鮃≒蒸し鰈〔かれい〕)
に、白酒(しろざけ:※餅米や米麹を蒸して、味醂や焼酎と混ぜて仕込み、一カ月程度熟成させた醪〔もろみ〕を軽く摺り潰して造った、白い濁り酒のこと)
を掛けて尤(もっと)も美味なり(≒焼き立ての蒸し平目に白酒を掛けて食すのが、本当に美味い食べ方です)
。又(また)生(なま)のは、煮浸(にびた)しにするも美味なり(≒また、活きの良い蒸し平目なら、煮浸しとするのも良いでしょう)
。」
下巻116【川越味噌(かわごえみそ)の法】・・・現在も「小江戸(こえど)」と呼ばれ、かつての武蔵国川越(現埼玉県川越市)の城下町で、“醤油造り”や“味噌造り”が活発だったことを連想させるネーミングとなっております。・・・尚、この項目レシピも、著者・徳川斉昭の八男「八郎麿(はちろうまろ:※七郎麿こと、後の徳川慶喜の一つ下の弟。母は水戸藩家老・山野辺義質の娘の直)」が、武蔵川越藩第5代藩主の松平典則(まつだいらつねのり)の養子となって、西暦1854年(嘉永7年)8月に川越藩第6代藩主「松平直侯(まつだいらなおよし)」となったことが、深く関係していると想われます。
「大豆二斗、麦糀(むぎこうじ)八升、塩一斗六升、
右十ヶ年余り置き候えども、風味別(わ)けてよろし(≒風味が別格と云える程良いのです)
。」
下巻117【赤味噌(あかみそ)製法 (是迄〔これまで〕
御上〔おのぼ〕
りの分〔≒これまでの上京に付帯させた分〕
。)】・・・この項目内にある「御上り」の相手方と云いますか? 届け先と云うのか? 良く分かりませんが、京都内に居た誰だったのでしょうか? ・・・誰であれ、ここにある「赤味噌製法」を携えた人や、届けられた人は喜んだのでしょうから・・・著者・徳川斉昭の御簾中(=正室)・吉子女王(※正式には、登美宮吉子女王)の実家「有栖川宮」である可能性は低いでしょうし。「赤味噌」なので。・・・と、すると・・・残る可能性としては、京都へ上った息子・徳川慶喜本人や、慶喜の兄で水戸藩主の徳川慶篤とともに京都本圀寺に駐屯した尊皇攘夷派の水戸藩士達(=本圀寺勢/本圀寺党)ぐらいしか思い当たらないのですが・・・。・・・尚、以下原文中の分量を見ると、ある程度の集団に向けた内容になっているようにも感じますが・・・?
「一樽(ひとたる)に付き、大豆二斗、糀(こうじ)二斗、塩八升(但し、豆を煎る時、極〔ご〕
く古き味噌を入れる時は出来上り候て、早く〔=既に〕
数年を経たる如く赤く見ゆるなり。)」
下巻118【紅赤味噌(くれないあかみそ)製法】・・・上記の「赤味噌製法」に続いて、今度は「紅赤味噌の製法」です。・・・何やら「赤味噌製法」では、「短期間で赤く見える味噌を造る方法」が記述されており・・・こちらの「紅赤味噌の製法」では、最低限熟成させる期間が記述されているようです。・・・また、こちらの方が塩分濃度がより高くなり・・・「赤」と「紅赤」ほど、若干の色味の違いが生じるようであります。
「大豆二斗、糀(こうじ)二斗、塩一斗二升、
右割合にて二ヶ年寝かし置き候えば、色つき申し候事。」
下巻119【鎌倉製味噌の法】・・・ここにある項目レシピを「鎌倉味噌」とは呼ばずに、「鎌倉製味噌」とし「法」と組み合わせて、使い分けしているように感じます。・・・「古都」と呼ばれ「武士の都」とされる故地。しかも・・・著者・徳川斉昭が尊敬する、ご先祖・水戸光圀が実際に行った旧都・・・そんなことが、表現の違いを生じさせているのかな? とも想います。
「一樽(ひとたる)に付、大豆二斗、並糀(なみのこうじ)一斗五升、塩八升、
右割合にて製法。二ヶ年の間製(つく)り置き、三ヶ年目相(あ)い用(もち)い候。」
下巻120【信州松代城下並近在(しんしゅうまつしろじょうかなみきんざい)にて味噌仕入方】・・・「信州松代城下の周辺で観られる味噌の仕込み方法」。・・・ここにある項目は、著者・徳川斉昭が、水戸徳川家(水戸藩)の家臣らの家々で、代々伝えられていた味噌製法を調査し、それを纏(まと)めたものだと想います。・・・別ページでも触れておりますが、水戸藩には甲斐武田家の遺臣らの家系も多いですから。
「一、大豆よく洗い大桶(おおおけ)に入れ、大豆の上に至り候程水を張り、その水引き候得ば掻(か)き回し、よく冷かし候ようにいたし置き、翌朝大釜(おおがま)へ入れ、釜(かま)の八分目に水入れ候て焚(た)き申し候。和(やわ)らか(=柔らか)
に相(あ)い成り候得へば、木綿切れに大豆一粒包み、指にて押し出し出候得ばよろしく御座候。その節臼(うす)にても半入桶(はんいりおけ:※通常の桶よりも小さく、俵と桶の間などで用いる桶のこと)
へなりとも入れ候て搗(つ)き潰(つぶ)し、一升玉位の玉にいたし、菰(こも:※水辺に生えるイネ科の多年性植物を乾かして、粗く編んだむしろのこと)
の上に干並置き(≒大豆を菰の上に千粒程広げて)
、七日ばかり過ぎ候て玉返しいたし候(≒七日ほど経過したら、大豆の粒を反転させるのです)
。二十日ばかりにて仕入れ候。その節右の玉を大桶(おおおけ)に入れ、水に半日程漬け置き、よく洗い候上にて、莚(むしろ)の上に積み重ね、その上へ莚(むしろ)をかけ(=掛け)
、一夜置き翌朝に相(あ)い成り庖丁(ほうちょう)にて細(こま)かに切り、莚(むしろ)の上にて塩、糀(こうじ)一同、よくよく交ぜ合わせ、桶(おけ)に詰め入れ、よくよく押し付け、その上に振り塩いたし置き、風の入らぬように蓋(ふた)をいたし置き、右糀(こうじ)一升に付、米二、三升飯に焚(た)き、交ぜ合わせ、一夜造りにいたし候て、入れ候もよろしく御座候。
大豆一升に付き並塩(≒並の塩)
三合、糀(こうじ)三合、割合(≒割合にして)
、上糀(≒上質な糀を)
三合、
右焚(た)き候時節、雪(ゆき)、白水(※米を研ぐ際に出る水のこと)
にて焚(た)き候もよろしく、又(ま)た二、三、四月中までも焚(た)き申し候。二月上旬ならば二十五日ばかり差し置き(≒二月上旬ならば二十五日ばかりを放置し)
、三月ならば二十日ばかり、四月ならば十四、五日にて仕入れる(≒三月ならば二十日ばかりを放置し、四月ならば十四、五日放置して、仕込むのです)
。」
下巻121【山中方(やまなかのほう)竹生村(たけぶむら)辺にて仕入方】・・・この項目も、上記同様に・・・水戸藩には甲斐武田家の遺臣らの家系が多かったため、藩主・徳川斉昭により調査・記録されたものです。・・・この項目内にある「山中方(やまなかのほう)」とは、上記の 下巻120 の項目にある“信州松代城下並近在より、もっと山の中の地域の”という意味であり、これに続く「竹生村(たけぶむら)」とは、かつて信濃松代藩の領内にあった「竹生村(たけぶむら)」のことです。現在の長野県上水内(かみみのち)郡小川村高府となります。残念ながら「竹生(たけぶ)」という地名は遺っていないようであります。
「焚(た)き方は右同様(≒大豆の焚き方は、上記にある信州松代城下並近在と同様です)
。日数は(≒掛かる日数は)
、正月、二月頃まで四、五十日も置き候よし。四月は十五日程にて仕入れ候よし。玉も一升を三玉にもいたし候(≒味噌玉一升分を三つに分けて造るのです)
。」
下巻122【田舎味噌(いなかみそ)の法】・・・以下の原文を読むと・・・著者・徳川斉昭が、ここまで遜(へりくだ)りながらも、何故に「田舎味噌」の記録を遺したのか? についてのほうに、興味が湧くのですが・・・。・・・もしかすると、コレは・・・全国諸藩へ味噌など食材の調査協力を依頼する際の・・・決まり文句? 定型文? 泣き落とし口頭戦術? ・・・いずれにしても、山間部では、安価で入手し易い「大麦」から「大麦糀(おおむぎこうじ)」を造り「田舎味噌」にしたとの記録なのです。・・・でも、「味噌」の他にも、これまで沢山の発酵食品や醸造調味液などが『食菜録』に記述されていましたし、それらにも多く「大麦」が原料として記録されていましたが? ・・・結局のところ、「大麦糀(おおむぎこうじ)」なるものの有用性を、広く一般に普及させたかったのではないか? とも想えるのです。
「大豆一升に付、塩二合五勺と為(な)し、糀(こうじ)の代(かわ)りに麦割飯(むぎわりめし:※麦飯のこと)
等入れ申し候。(但し、〔米糀が絶対的に〕
分量不足〔也〕
。)
味噌製法口伝(くでん)、左に申し上げ奉(たてまつ)り候(≒この味噌製法は口伝であって、以下で申し上げる通りとなります)
。
本文は、幣邑(へいゆう:※自国〔自藩〕のことを遜〔へりくだ〕って云う場合に使う言葉です)
辺皆(へんぴ)な、此(か)くの如く製(つく)りし仕(つかまつ)り候(≒この本文は、かなり辺鄙な処と云える水戸藩領内における話であり、以下のように田舎味噌を造ってきたと述べておるのです)
。
極(ご)く山中(やまなか)にては糀(こうじ)を入れ申さざるなり(≒里山から離れた山奥の地域では、なかなか米糀を調達できないので)
、大麦の時分糀(こうじ)を造り、入れ申し候(≒大麦が収穫出来た後に、大麦糀を造ってから、味噌に入れていました)
。大麦糀(おおむぎこうじ)は大麦を飯(めし)に仕(つかまつ)り候て、平目なる箱(=平たい箱)
の蓋(ふた)の如き物へ、薄く飯を入れ、糀(こうじ)の元と唱(とな)へ、並方の米の糀(こうじ)を少々上へ振り播(ま)き申し、莚(むしろ)にて覆(おお)い置き候得ば糀(こうじ)の元より麦へ移り、十分(じゅうぶん)にはこれ無く候得ども花付き候を用(もち)い申し候由(よし)に御座候(≒それでも充分な量とは云えないのだが、大豆の発酵具合が進んできた頃から使用しているとの事なのです)
。」
下巻123【海雲(もずく)製(づくり)】・・・この項目も、珍しいものと云えるでしょう。「海雲(もずく)製法」としては。・・・現代人は「海雲(もずく)」と云えば「沖縄産海雲(もずく)」を思い浮かべますが・・・日本列島の本州から沖縄に掛けて分布しているようであり、本州太平洋側では千葉県以南にも育つそうです。昨今の海洋水温の上昇や温暖化現象下では、さらに厳しさが増しているとは想いますが。・・・幕末頃は、江戸湾以南の海域でも採れたのではないか? とも想います。
「海雲(もずく)を取り、そのまま置く時は、直(すぐ)に悪(あ)しく相(あ)い成るなり。依(よっ)て海雲(もずく)一升へ、塩一升交ぜ、桶へ入れ置く時は、二、三年置いても悪(あ)しく相(あ)い成らず、製(つく)る時は摺鉢(すりばち)の中へ入れ、砂にて何遍(なんべん)も、よくよく揉(も)み、又(また)水を何遍(なんべん)も掛けて洗い、いささかも砂の残らざるようにいたし、水をよく切り布にて搾(しぼ)り、いささかも水気無きようにいたし、一、二寸位に切り、三塩かけて(=掛けて)
相(あ)い用(もち)い候(≒ ~ 一、二寸位に切り、三度塩を掛けて、料理に用いるのです)
。」
下巻124【白味噌(しろみそ)製法方(せいほうのほう) (但し、一樽〔ひとたる〕
へ上味淋酒一升の割〔合也〕
。)】・・・やはり、と云うべきか? 著者・徳川斉昭の御簾中〔=正室〕・登美宮吉子女王は、「白味噌」がお好みだったようです。・・・“積極的に、水戸徳川家(水戸藩)の味噌御用商人・伊勢屋喜太郎(いせやきたろう)なる店主に会って、いろいろとお尋ねになった”と。・・・有栖川宮織仁親王の第12王女なのに。武家に嫁いだのだとしても、「内助の功」が半端じゃありません。この方の行動力。・・・尚、水戸徳川家(水戸藩)からの諸藩大名家などへの贈答品に「白味噌」を用いていたことも分かりますね。
「大豆二斗、糀(こうじ)二斗九升、塩五升五合、
右の通り製(つく)りし指し上げ(=差し上げ)
候旨、味噌(みそ)御用達(ごようたし:=御用商人)
伊勢屋喜太郎(いせやきたろう)相(あ:=会)
い尋(たず)ね申し出(い)で候旨、御台所(※著者・徳川斉昭の御簾中〔=正室〕・登美宮吉子女王のこと)
より申し出(い)で候。
右割合を以(もっ)て製(つく)りし、極上(ごくじょうの)味淋酒にて練り交ぜ、四、五月の頃は、三日目には指し上げ(=差し上げ)
、暑気(しょき)の節は前日仕込み、翌日指し上げ(=差し上げ)
候旨、日数過ぎ候ては御用(ごよう)に相(あ)い成らず(≒暑い季節の白味噌は長持ちしないため、仕込みから二日目には御用の品としては役に立たなくなるとの事)
。冬気(とうき)に至り候えば(≒冬となり、冷たい空気になってくれば)
六日、七日目位にて指し上げ(=差し上げ)
候旨、申し出(い)で候。」
下巻125【鎌倉味噌(かまくらみそ)の製法】・・・ここで、上記の 下巻119【鎌倉製味噌の法】とは、若干表現が変更された「鎌倉味噌(かまくらみそ)の製法」が記述されておりますが・・・その内容を比べると、大きく異なるものとなっており・・・下巻119のほうは、“鎌倉辺りの一般的な味噌の作り方”であって、ここにあるのは、云わば「鎌倉味噌と呼ばれるブランド味噌製造現場視察後の報告書」のようになっております。・・・これにもまた「御用」という語句がありますので、おそらくは水戸徳川家(水戸藩)からの諸藩大名家などに対する贈答品候補の一つとされたのでしょう。
「大豆二斗へ、糀(こうじ)一斗五升、塩八升(但し、売買(ばいばい)の板付き糀(こうじ)を〔≒市販されている板付き糀を〕
、揉みふぐし〔≒揉み解し〕
一斗五升まで。)
右仕込み候月より、十二、三ヶ月目にて用(もち)ゆ。豆は蒸籠(せいろ)にて、ふかし(=蒸かし)
仕込み申し候所、味噌の色、薄きと濃きとは鎌倉にて製(つく)り候節、一度に八樽位仕込み候に付、豆ふかし加減に寄り(≒大豆の蒸かし加減によって)
、下の方に相製(あいつくり)申し候処(≒下記に記述したような方法で造ってはみたものの)
、又(また)は一度に八樽仕込み候故(ゆえ)、順々(じゅんじゅん)に御用(ごよう)に相(あ)い成り候故(ゆえ)(≒予め決められた手順に従うことで、役立つ品に成るのであって)
、取廻りに相(あ)い成り候方は(≒樽の外周内側部分の発酵状態は)
色濃く相(あ)い成り候儀にござ候よし(≒色が徐々に濃くなってきているようであり、良い兆候と云えるそうです)
。糀(こうじ)は麦糀(むぎこうじ)にはござなく候(≒ちなみに、糀は麦糀を使用しておりません)
。並糀(なみのこうじ)に候えども、糀(こうじ)も鎌倉にて出来(でき)候事(≒通常使われる糀とは云え、鎌倉で出来た糀であります)
。故(ゆえに)、江戸町方(えどまちかた)にて出來候(できそうろう)糀(こうじ)とは相(あ)い違(たが)うに御座候(≒従いまして、江戸町方で出来た糀を使用した場合と比べると、結果が異なってくるのは仕方のないことなのです)
。かの様(さま)鎌倉より申し来(きた)り候(≒そのような状況報告が鎌倉より伝えられて来ております)
。(但し、鎌倉町方〔かまくらまちかた〕
にて出来〔でき〕
候〔≒但し、鎌倉の町方衆の手により、この鎌倉味噌は既に出来上がっておりますので〕
。)」
下巻126【玉味噌(たまみそ)の製法】・・・ここには、水戸徳川家(水戸藩)領内で造られて来ていた地域ごとの味噌製法・・・通称「玉味噌製法」が、当時の役所内で使用されていた報告書から抜粋したような形式で記述されております。計4方式です。一番最初に記述されているのは、著者・徳川斉昭の家、つまりは「水戸徳川家内における玉味噌製法」になっています。・・・これらを見比べると、地域により少しずつ製法が異なっていたようであります。これらの事は、“水戸藩領内という限られた領域の中でも、それぞれ風土特性が少しづつ異なり、酵母菌など微生物の働き具合に影響するのだ”と、著者・徳川斉昭が云っているように感じます。
「一、大豆一升、塩四合、糀(こうじ)六合、大豆を常法(じょうほう:≒普段の方法により)
煎(いり)て突き、土瓶(どびん)の大(おおき)さに丸め、藁(わら)を此(これ)の如く敷き、その上へ乗せ包み、台所の梁(はり)につるし(=吊るし)
置き黴(かび)るまで置き、小口(こぐち)切りに切りしを、塩、糀(こうじ)、突きまぜ(=混ぜ)
、桶(おけ)へ入れ置き、勝手成る者は(≒台所仕事を心得た者や料理番の者は)
一年位置きて用(もち)ゆなり。(但し、右は上方手代杯〔かみがたてだいのさかずき〕
へ出し候分〔≒但し、前述した造り方は、上方へ遣いを出す際など正式な場合の分量である〕
。手前遣(てまえづか)いは〔≒家の者達などの私用遣いとする場合には〕
、塩四合、糀〔こうじ〕
四合〔也〕
。)
又(また)法(≒また別の方法として・・・)
一、御領内(ごりょうない:=水戸藩領内)
入郷筋(いりごうすじ:※水戸藩庁〔水戸城〕から現栃木県芳賀郡茂木町方面へ向かう街道辺りのこと)
にて出來候(できそうろう)、玉味噌製法の儀、常の味噌の如く豆を煮て搗(つ)き候て、その豆一升位ずつ丸め玉にいたし候を、そのまま藁(わら)等にて縛(ゆわ)い、日数、四、五十日つるし(=吊るし)
置き、その後、塵(ちり)を温湯(おんとう:=温かい湯)
にて洗い落し、乾(かわか)し置き、細(こま)かき割のまま糀(こうじ)を、堅作り甘酒(≒いくらか硬めの甘酒)
にいたし置き候を入れ、搗(つ)き交ぜ拵(こしら)え候趣(そうろうおもむき)、尤(もっと)も豆一升へは糀(こうじ)三合、塩四合位の分量に拵(こしら)え候趣(そうろうおもむき)に候えども、糀(こうじ)四合入れ候得えば、尚以て(なおもって)宜(よろ)しき趣(おもむき)、製する時節は(≒造る時期は)
十月より二月頃まで宜しき。夏を越し申さず候ては風味出(い)で申さず趣(おもむき)に御座候(ござそうろう)。
右玉味噌製法の儀、承(う)けさせ候処(そうろうところ)、前書の通りにござ候。
四月 東(ひがし)御郡方(おんこおりかた)玉味噌製法(≒四月 東御郡方という水戸藩の部署管轄内における玉味噌製法は・・・)
一、大豆一斗積り(≒大豆は一斗ほど用いて)
、塩五升、
右煮方、常の味噌の通り、よく舂(つ:=搗)
き、茶碗(ちゃわん)位の大(おおき)さに丸め、板の上へ並べ、五日程過ぎて堅く成り候を二つ縄(なわ)に結び、竈(かまど)上などへ火気の上へつるし(=吊るし)
、四、五カ月指し置き(=差し置き)
、殕(やぶれ:※腐った部分は)
を去り(=取り除き)
、細(こま)かく刻み、樽(たる)へ春込み(=搗き込み)
、四、五カ月過ぎ候て用(もち)い申し候由(そうろうよし)に御座候(ござそうろう)。
同(≒同じく、四月の東御郡方という水戸藩の部署管轄内における玉味噌製法として)
河津楠内(かわつくない?:※水戸藩士)(の)
拵(こしらえ)(は)
下(したに・・・)
一、大豆を常の如く煮、搗(つ)き候て一升位の分量、玉にいたし、家の内へ吊(つる)し、日数二十日も過ぎ、湯にて洗い刻み、塩五合、糀(こうじ)五合の割に入れ、搗(つ)き混ぜ、一ケ年も置き候て用(もち)い候えば、極上品に出来(でき)候由(そうろうよし)。」
下巻127【きす(=鱚)
ほりほり製法】・・・「ホリホリ製法」とは何ぞや? ということになると想うのですが、私(筆者)は以下のように解釈致します。
「新しききす(=鱚)
をひしぎ(=拉ぎ:※潰すこと)
、骨、頭、尾を去り、よく蒸し日にて干し、助暖(じょだん:※小さな火鉢のこと)
へかけ(=掛け)
置き候と、ほりりほりり(≒鱚のように小さく、白身で柔らかい魚は、丁寧且つ慎重に、箸で彫りり彫りりと、身を解〔ほぐ〕すように)
いたし候様に相(あ)い成り申し候。」
下巻128【鶏卵(けいらん)湯の製法】・・・これは、「甘~いボイル・スクランブル・エッグ」ですね。・・・これも病中病後を考慮した「養生料理」かと想います。
「玉子十、上白砂糖三合、水四合、酒三合、
右を一同にし、よく掻(か)き混ぜ、火に掛け、煮え立つまで手を放さず掻(か)き回す。一度に泡立つと雖(いえど)も、煮え立つ時は泡消えるなり。」
下巻129【味噌漬(みそづけ)香物(こうのもの)】・・・これは、「大根の沢庵漬けのリメイク味噌漬け」ですね。・・・「奈良漬」のように甘くはないのでしょうが、香りが良い漬物に成るかと想います。・・・また、元々コリコリとした歯応えが魅力の沢庵漬けを、如何にして美味い味噌漬けにするか? という難題にも取り組んでいた様子が窺えます。
「一、沢庵(たくあん/たくわん)の香物(こうのもの)に一ヶ年いたし、それにより味噌に漬(つけ)る。(但し、寒前〔かんまえ/かんまい〕
二十日もよく干して澤庵〔たくあん/たくわん〕
に漬〔つけ〕
る。寒に入る時は大根〔だいこん〕
に水を持ち、沢庵〔たくあん/たくわん〕
相〔あい〕
成らず〔≒寒に入る時期の大根は、水分量が多いので沢庵漬けには向かないため、要注意〕
。)
又(また)法(≒また別の方法として・・・)
一、沢庵(たくあん/たくわん)に漬ける如く大根(だいこん)を、十月三日(とつきみっか)も干し、直(ただ)ちに味噌に漬ける。三月(みつき)も立て(=経って)
用(もち)ゆる時は、柔(やわらか)にして風味も至極(しごく)に宜しき。」
下巻130【味噌漬大根(だいこん)の方】・・・以下の原文では、上記の 下巻118 にある「紅赤味噌(くれないあかみそ)」を使用していますが、通常の「赤味噌」でも大丈夫かと想います。・・・いずれにしても、食品の長期保存と、食す際の美味しさを追求した一品かと。
「冬大根(ふゆだいこん)、極(ご)く生分よろしき品(≒できるだけ新鮮なもの)を選び、大振(おおぶり)の所(≒大きく育った大根は)
、生(なま)のまま極(ご)く辛塩(からじお)にいたし漬け込み、五ヶ月座(ざ)し置き(≒五ヶ月ほど漬け込み置いて)
、その後水にて洗い上げ、日に干し上げ、それより酒粕(さけかす)へ漬け込み置き、四、五十日指し置き(=差し置き)
、なお又(ま)た水にて洗い上げ、日に干し上げ、先前の通り(≒前述した通りに)
酒粕(さけかす)へ漬け込み、なお日柄(ひがら)相(あ)い立ち候得えば、右仕法(みぎのつかまつりほう:≒前述の方法)
にて三度まで、酒粕(さけかす)へ取り、塩も抜け候えば紅赤味噌(くれないあかみそ:※上記の下巻118)
へ漬け込み、日数十五日も相(あ)い立ち候得ば用(もち)いて宜し。
(但し、暑気〔しょき〕
に至り候えば、漬け込み候分、穴藏〔あなぐら:※土地に穴を掘って物を蓄えるようにした場所のこと〕
の様〔に〕
成る冷気〔れいき〕
の場所へ、指し置き〔=差し置き〕
申さず候ては風味変わり候事。)」
下巻131【芋干葉(いもほしば)の方 京人傳】・・この項目中にある「芋干葉」とは、里芋の茎や葉の部分のことでありまして、「芋がら」とか「芋茎(ずいき)」と呼ばれる食材のことです。「里芋」そのものは、古くから旧常陸国では栽培されていましたし、「芋がら」を現代でも良く食しますので。・・・また、項目中に「京人傳」とあるのも、“然(さ)もありなん”とは想いますが・・・原文末尾の但し書き部分は、“完全な勘違い記事”となります。元々「芋がら」や「芋茎(ずいき)」は、食物繊維の豊富な食材ではありますが、基本的に出産後云々(うんぬん)という話とは別の事柄なので。
「芋の出来葉を取り捨て候節、よく葉を選(えら)み赤く成りたるを用いず、青葉のみ細(こま)かに刻み、日にて干し上げ、貯(たくわ)い置きて用(もち)ゆる節は、さっと煎じ、汁を流し、松魚節(=鰹節)
を入れ、味淋酒、醤油にて煮つける。(但し、産後用る時〔≒婦人が出産後に用いる時には〕
、悪血〔あくち/おけつ〕
を下〔くだ〕
し宜しきよし〔≒悪血を下すと云うので良いのだそうだ〕
。産後用〔もち〕
ゆるには味醂酒を入れず。)」
下巻132【鯛(たい)濱焼(はまやき)用方(ようほう)仕法(つかまつりほう)】・・・この項目レシピを今風に云えば、「美味い!!! 鯛の浜焼き」になるかと想います。・・・そして、これも・・・どうやら、著者・徳川斉昭の甥で、徳川慶喜の従兄弟に当たる尾張藩主・徳川慶恕から「御書(=書状)」が届いて・・・それに従って「鯛の浜焼き」を作って、実際に食したところ・・・原文末尾の但し書き部分には「とても美味かった」という感想まで記述されております。・・・尚、鯛の鱗を取り除くために浜焼きにして、後に蒸していますので・・・何か「ポン酢」や「柚酢」みたいな、アクセントがある調味液を掛けたのかな? と想像しております。近海で獲れた鯛は、脂がのっていたでしょうし。
「鯛(たい)を浜にて焼き、鱗(うろこ)焦げて真黒になりたるを、左の通り(≒以下のように)
製(せい)す。
水に漬け置き、塩を出し、鱗等(うろこなど)を洗い取り、薄下(うすした:※塩加減が薄い塩水のこと)
ばかりにて煮立て、又(また)は蒸立(むしたて)にて、掛塩(かけじお)、大根おろし、又(また)は煮え湯を掛け候得ば、この黒く焼き候所きれいに取れ鱗(うろこ)も取れ候得ば白く相(あ)い成り、夫(それ)より塩を出し蒸(むら)し、かけ塩(=掛け塩)
にいたし候てもよろしく。(但し、尾州様御国許〔=尾張藩主・徳川慶恕の国許〕
にて浜焼〔はまやき〕
にいたし候まま、この御書付◇〈?原文一字不明部分とされるが、「図」か? 「録」か?〉
進めなされ〔=薦め為され〕
候に付き、御書付の通り、鱗等〔うろこなど〕
洗いとり蒸立〔むした〕
て、かけ塩〔=掛け塩〕
、大根下し〔だいこんおろし〕
掛け御製〔ぎょせい〕
に相〔あ〕
い成り候処、魚新しき〔に〕
至って味わいよろしき候。)」
下巻133【水府(すいふ)浜焼鯛(はまやきだい)製法】・・・この項目内にある「水府(すいふ)」とは「水戸」のことですので、「水府流(=水戸流)の浜焼鯛製法」となります。地元に伝わる浜焼鯛製法も、しっかりと忘れずに記述されております。
「さて焼立方の儀は(≒さて水府浜焼鯛の焼き方は)
、舟より帰るや否や(≒鯛が水揚げされたら直ぐに)
、腹を抜き(=腹わたを抜き)
、背へ刀(かたな)を入れ、その所へ塩を詰め、又(また)大鯛(おおだい)一枚へ、塩二合、中へ(=鯛の腹の中へ)
一合五勺に一合位の割(合)
を以(もっ)て、立塩(たてしお:※魚介類を洗ったり材料に塩味を付ける場合に、予め塩水を使用する方法のこと)
にいたし、一夜漬(つ)け置き、囲爐裡(いろり)を構え、渡し鉄いたし、鉄網へ載せ、焼き立て、片面焼け候後、又(ま)た外(ほか)の鉄網を当て、打ち返し(≒裏返して)
、堅炭火(かたすみび:≒備長炭〔びんちょうたん〕のように金属音がするような堅い木炭で、ゆっくりと遠火で以って焼くこと)
にて焼き立て申す儀に御座候(ござそうろう)。」
下巻134【パンの法 中浜万次郎咄(なかはままんじろうばなし)】・・・ようやく来ました! 「パンの法」。しかも、「ジョン・万次郎」こと「中濱萬次郎」が話したという「咄(はなし)」です。・・・いわゆる「捕鯨船」の中における、アメリカ人など船員達の船上生活の一部も語られております。・・・この「咄(はなし)」は・・・幕末期の幕府大老・井伊直弼や、後に将軍となる徳川慶喜、実際に太平洋を横断した小栗(上野介)忠順(おぐり〔こうづけのすけ〕ただまさ:※幕臣で勘定奉行や江戸町奉行、外国奉行を歴任した)や、本ページ中の勝安芳(※通称は麟太郎、安房守とも、号は海舟)、脱藩土佐藩士で幕末志士の坂本龍馬などが、当然に接していた情報だった訳です。・・・確か、薩摩藩の島津斉彬(しまづなりあきら)は、直接「中濱萬次郎」と会っていたような気が致しますので、薩摩の殿様から水戸の殿様に、この「咄(はなし)」が伝わったと想うのですが。当時としては、珍しい舶来の技術「写真術」などとともに。
「饂飩の粉(=うどん粉)
二升(麦粉なり。)、
豚(ぶた)の油(=豚脂=ラード)
一斤の四つ一つ(≒一斤を四等分にし、その一つを)
、牛乳搾(しぼ)りたるままなり、水よき程に入れる。焼酎(しょうちゅう)盃に(≒焼酎用の盃にして)
二、三盃。右は四年より十年余り保つべし(≒前述した豚の油などは、四年から十年余りは保存すべきである)
。器物(うつわもの)に入れ、目張(めばり)をし、風当たらざるようにして、貯(たくわ)うれば其(そ)の余りも保つべし(≒器物に入れ、密閉状態に致し、風に当たらぬようにして保存しておいて、十年以上は保てるように努めねばならない)
。航海の糧(≒外洋航海をする場合の糧〔かて〕としては)
三、四年〔分〕
を用意す 。一人にてパン一斤を三度に食す。牛豚肉を菜とす。肉は塩にて煮る。パン、平生食し候には、砂糖加う。三、四年も貯(たくわ)え候には砂糖は入れず。(但し、案ずるに牛乳少なき時は、水多く入〔いれ〕
るべし。乳多き時は水無くてよし。手にて漸〔ようや〕
くこね〔=捏ね〕
候位に堅くいたし、そば〔=蕎麦〕
打ち候棒の短〔みじか〕
き物にて、板の上にて平らに延べ、厚さ四、五分渡り四寸位ずつに、右を玉子焼の中へ入れ〔≒パンの生地を玉子焼き器のような鉄器の中に入れて〕
、上下より火にて焼く〔≒上下から熱を通して焼くのです〕
。)」
下巻135【齢(レイ)なし餅の法 (老人用〔もち〕ゆるによろし。)】・・・ここは、シンプルに「歯無し餅の法」でも良かったのですが、「齢梨(れいなし)餅」と掛けているのかも知れません。砂糖で甘く味付けしているので。・・・それに著者・徳川斉昭は、江戸で生まれ育った「江戸っ子」とも云えますので。洒落心があったのでしょう。・・・また、いわゆる「(お)かき」のことを、当時一般的に「かちん」とも呼んでいたようなのですが、現代では聞いたこともないので「死語」に当たるのかな? と思い、調べたところ・・・「かちん」は、「かちいぃ(=搗ち飯)」が音変化・訛(なま)りを起こした単語と考えられ、「餅もち」を言う女房詞(にょうぼうことば)らしく、「おかちん」とも呼んだそうです。・・・いずれにしても、ここの項目内にあるように、“高齢者など歯が無かったり、歯並びが悪くなった人向けの餅菓子”です。
「薄く切って干したる餅、俗に「かき」、「かちん」とも云うを、胡麻(ごま)の油にてよく揚げ、直(ただ)ちに熱き所、砂糖、醤油の中へ入れ、よく浸(しず)ませ、出(いで)し用(もち)ゆ。至って柔らかにして美味なり。又(ま)た油嫌う者は右餅を焼き直し、茶碗(ちゃわん)に入れ熱湯を掛け、蓋(ふた)をなし(=為し)
暫(しばら)く置き、湯をしたみ(=その湯の水気を切って)
、砂糖、醤油をかけ(=掛け)
用(もち)ゆ。又(また)大根下し(だいこんおろし)へ醤油をかけたる(=掛けたる)
を付けて用(もち)ゆ。何(いず)れも美味なり。」
下巻136【牛乳酒】・・・ここも、もし作ってみる場合には、アルコール度数に注意して下さい。これも病中病後などを考慮した「養生酒」になります。・・・水戸藩では、牧場経営も行なって「牛乳」を搾乳できましたので。
「牛乳茶碗(ちゃわん)に二盃、酒二盃、水三盃、砂糖一盃、右一同鍋へ入れ、掻(か)き回し、煮え立ち候節用(もち)ゆ。(但し、只の砂糖湯の如く牛乳は堅まりて、おり〔=澱〕
の如く沈殿〔おどみ〕
残る者〔=物〕
なり。全く養生〔ようじょう〕
に用〔もち〕
ゆ迄なれば〔≒養生のために栄養補給が必要となる者達には〕
沈殿〔おどみ〕
たる牛乳を口に入れ、右汁にて呑〔の〕
むなり。 酒好〔す〕
く人なれば酒三、四、五盃入れて然〔しか〕
るべし。)」
下巻137【蛸(たこ)みしお】・・・この項目レシピにある「みしお」は、漢字表記すると「味塩」となり、上記の 下巻92 にある「塩昆布出汁」のことです。・・・つまり、「味付け蛸(たこ)の保存方法」が記述されているのです。「蛸の酢漬け」ではありません。
「蛸(たこ)みしお、蛸(たこ)を茹(ゆ)で冷まし、みしお(≒塩昆布出汁を)
煎じ冷まし置き、蛸(たこ)の頭を二つ三つに切り、八本の足をも切り放す。前文の冷えたるみしお(≒前文の冷えた塩昆布出汁を)
へ漬(つ)けるなり。直(すぐ)に壺(つぼ)に入れ、目張(めばり)をす(≒すぐに壺に入れて保存するのです)
。(但し、冬は三月〔みつき〕
位持つなり。用〔もち〕
ゆる時に薄く切るなり。)」
下巻138【鳥の刺身】・・・「酢漬け野鳥肉の刺身」。・・・原文には、漬け込む容器について記述されておりませんが、やはり蓋のある壺が良いのか? と想う・・・と同時に、何故に・・・上記や下記に 「酢漬け蛸」、若しくは「酢蛸(すだこ)」が記述されていないのか? が気になります。・・・「酢漬け蛸」、若しくは「酢蛸(すだこ)」は、関東以北の地域でポピュラーな「おせち料理の一品」なのですが、歴史的に観ると、案外新しい食品なのかも知れません。「蛸の刺身」や「焼き蛸」、「蛸飯」などは、古来から日本列島人が食べて来たことが、ほぼ考古学的にも明らかなのに・・・。・・・著者・徳川斉昭は、「くらげ(=海月=水母=水月)」や「蛸(たこ)」などの軟体生物がお嫌いだったのでしょうか?
「鳩(はと)にても、鴨(かも)にても、薄く刺身に作り、醤油一盃、酢一盃、味淋酒半盃、白砂糖小雀(こがら/こすずめ)卵大是(こ)れ程入れ(≒白砂糖は、小雀の卵大のサイズ程入れて)
、よく掻(か)き回したる中へ漬けて用(もち)ゆ。」
下巻139【鴨(かも)の製作】・・・これは、「鴨肉のつみれの作製方法」、若しくは「鴨肉団子の作製方法」ですね。
「鴨(かも)を、肉も骨も一同に細(こま)かに叩き(但し、皮も、ともに叩き入〔いれ〕
る。)、別に皮を鍋に入れ、火に掛け油を取り、右油を手につけて、前文の叩きたる肉を丸め、煮付にするなり。汁すましにも入れるなり。格別に風味美なり。又(また)丸めざれば、肉へ油を引いてもよし。」
下巻140【パン製法】・・・上記の 【パンの法 中浜万次郎咄】を知った実験家・徳川斉昭が、再び実験的な試みをして、実際に食し・・・いろいろと想像を膨らませ・・・もしかすると、自身の下っ腹辺りを膨らませ? ・・・いずれにせよ、一定の結果を得た後に、自身の感想を述べています。ご本人は、至って真面目です。
「うどんの粉茶碗(ちゃわん)に十、生牛乳同(=茶碗に)
一つ、焼酎(しょうちゅう)(盃か?)
一つ、右を木鉢(きばち)に入れ、手にてよく捏(こ)ね、但し、漸(ようや)くに捏(こ)ねらるる程に堅き加減よろし。何(いず)れも同じ位に丸め、板の上にて棒にて蕎麦(そば)を打つ如く、厚さ四、五分、渡り五寸ばかりに丸く平(たいら)に延べ、玉子焼の如き者(=物)
へ入れ(≒パン生地を玉子焼き器のような鉄器の中に入れて)
、但し胡麻(ごま)の油引き、上下より文火(とろび:=弱火)
にて焼き(但し、箸にて穴を開ける時は気漏れ、早く焼けるなり。)、程よく色付たる時、落し(≒加熱するのを止めて)
冷ます。食する時熱き湯に入れば、柔らかに成る。 壺(つぼ)に入れ、目張(めば)りいたし置く時は、六、七年、十年も貯(たくわえ)に成る。軍用貯(ぐんようのたくわえ:≒軍糧や備蓄食料)
、船中などにて用(もち)い候には、しかるべく(=然るべく)
候得ども、永く日本人常に用(もち)い候得ば、大便の通じなどに如何(いか)これあるべきか(≒もしも、日本人が長きに亘ってパンなる食べ物を用いていたならば、人の排便にどんな影響を齎〔もたら〕したのだろうか?)
。試〔ため〕
さざれば知らず〔≒試さなければ分からなかった〕
。」
下巻141【奥州守山(おうしゅうもりやまの)糒(ほしいぃ)製法 (寒中製すべし〔≒寒中には作るべし〕
。)】・・・奥州守山藩は、陸奥国南部(磐城国)田村郡(現福島県郡山市)に存在した藩であり、また水戸藩の「御連枝(ごれんし)」と呼ばれた「支藩」に当たります。そのため常陸国内にも所領を有して「松川陣屋」を置いてはいましたが、歴代の守山藩主達は、江戸・小石川藩邸に定住し参勤交代を行なうことは無く、その藩政も親藩たる水戸藩の監督を受ける立場にありました。・・・なので、この項目レシピが記述された時期は、6代目藩主・松平頼升(まつだいらよりのり)の頃に、著者・徳川斉昭が、調べて纏(まと)めた情報かと想います。・・・尚、原文後半部分には、糒(ほしいぃ)を用いた菓子の材料についてが記述されており・・・これが、まるで・・・アイヌ北方民族の言語か? 古い大和言葉か? とにかく「山伏」や「虚無僧」が発する言葉に想えるような表現が為されており、意味があまり掴めないのですが、できるだけ頑張って部分訳してみました。・・・いずれにしても、当時の税収の基軸とも云える「米」に関するものであり、しかも「米の保存方法」に関わっておりまして、非常に細かい表現になっております。
「一、糒仕立(ほしいぃのしたて)、上白(米)一石蒸し(但し、乾欠〔※乾いていて欠けた部分のある上白米のこと〕
一斗五升減、正在〔※欠損部分の無い上白米のこと〕
八斗五升位。)
右欠米(みぎのかけまい:≒乾欠を含んだ上白米を)
大数試(こころ)み置き候所に御座候(≒ ~ を試みとして大量に備蓄しております)
。糒上(ほしいぃののぼ)りよろしくば(≒糒の収穫高が良ければ)
、米生(こめなま)により、度(と)るごとに甲乙(こうおつ)御座候(≒米は生き物なので、その年ごとの収穫高や米の出来栄えについては、甲乙様々あるかと存じます)
。米の儀、前日磨(みが)ぎ候(≒米とは本来、食す前日に磨くものです)
。数度掛け水仕(つかまつ)り濁(にごり)よく抜き(≒何度か水にて研ぎ洗いして、濁りを良く抜いて)
、附桶(つけおけ:=浸け桶)
へ入れ(この桶は下に水抜きの穴あり。)、一夜指置き(=一夜差し置き)
一両度も水入れ替え(≒一、二度きれいな水を入れ替えて)
、濁り(にごり)を抜きて、翌日一斗入れ位の蒸籠(せいろ)へ、三つ重ねて蒸し候方よろしく候(≒蒸籠を三段重ねて蒸らす方が良いのです)
。桶こしき(=桶状の甑)
にて蒸し候ては、桶肌付きて相(あ)い成り候処(≒桶の内側に炊いた米がくっ付いてしまうので)
、柔(やわら)かに相(あ)い成り候てよろしからず候(≒あまり軟らかくなるまで蒸してしまうのは良くない事なのです)
。蒸籠(せいろ)念入れ、よく蒸(むら)し筵(むしろ)へ取り薄く仕(つかまつ)り候て(≒良く飯を蒸らしてから、筵に薄く広げて)
、息を抜き度々(たびたび)返し手入れいたし(≒空気を含むように、度々飯を天地替えして)
、その後中干(ちゅうぼし:※昇る蒸気が半減して飯の余熱がほどほど)
に相(あい)成り候砌(そうろうみぎり)(≒飯が中干状態になった頃合いにて)
、板揉み(いたも)と申し候て、幅一尺、長さ三尺位の板を敷きて、その上へ飯を載せ、六、七寸位の小さき板にてよく揉(も)み候えば、一粒ずつに相(あい)成り申し候。その後よく干し上げ、唐箕(とうみ:※臼などで籾殻を外した後に、風力を起こして穀物を籾殻や玄米、塵などに選別するための農具のこと)
に掛け筵塵(むしろのちり)等を取り、桝目(ますめ)相(あい)改め申し候(≒桝目で以って、改めて量るのです)
。
一、粳米(うるちまい)は蒸し候ても、糯米(もちごめ)より欠米(かけまい)が粳米相立(あいたち)申さず候ように相(あ)い考(かんが)へ申し候(≒粳米を蒸らすにしても、餅米と比べて欠米の量を目立たなくするため、事前に良く考えて調整しなければなりません)
。粳糒(うるちのほしいぃ)しかと試(こころ)み仕(つかまつ)らず候(≒但し、粳糒については、しっかりと試して確認する訳ではありません)
。さりながら糯米より粳米の方干上り、よろしくこれあるべき候と存じ奉り候(≒しかしながら、餅米よりも粳米の干し上がり方が良い事が重要かと存じます)
。尤(もっと)も粳糯仕法(≒もっとも、粳米と餅米の取扱い方法は)
、前書の通り蒸籠(せいろ)にて念入りに蒸(むら)し、右飯莚(むしろ)取り、一通り息を抜き(≒一通り、蒸気と熱を逃がしてから)
手揉(ても)みと申し候て、熱き内揉(も)み候得ば、早速(さっそく)に一粒ずつに相(あい)成り申し候。よく干上げ申し候。右糯糒(もちほしいぃ)と違い製方面倒(めんどう)に御座無く候(≒前述した餅糒の場合とは異なって、この製法は面倒ではありません)
。右を御貯(おんたくわえ)に極(きわ)められ候には、叺(かます:※藁〔わら〕を二つに半折し、両端を縄で閉じて封筒状にした袋のこと。肥料や石炭、塩、穀物などを入れます)
へ詰め置き、翌春入梅前、御手入れ日干しに極(き)められ候得ば、湿(しめり)請(う:=受)
け申さず候。右成(みぎのなり)は(≒湿気を含まないで適切に保存できた粳糒の品質は)
、二、三年御手遊ばされ候えば丈夫に之有り候。日干(ひぼし)仕(つかまつ)り候節、一通り日、息を抜き、入れ物へ御詰め遊ばさるべき候(≒入れ物へお詰め為さるべきと存じます)
。(但し、右糒〔みぎのほしいぃの〕
菓子種〔かしのたねの〕
製法、仕立挽臼加減〔したてひきうすかげん〕
、なおまた御鹿訳ヶ仕法〔おがわけわけ? ≒大鋸訳ヶ? つかまつりほう:※下記の菓子に使われる糒の篩による分別方法を表現しているか?〕
の儀は、甚〔はなは〕
だ面倒〔めんどう〕
にこれあり候。巨細〔こさい/きょさい:≒詳細〕
の儀は、紙の上にては申しかね候えども、大意〔たいい〕
のみ、右の通りに御座候。)
一、糒(ほしいぃ)石臼(いしうす)にて挽(ひ)き候て、荒(あら)き所をすぐり取り(=漉くい取り)
、又々(またまた)石臼(いしうす)へ掛け申し候。右、最初篩(ふるい)へ留(とどま)り候を、伊羅(いら)と相(あ)い唱(とな)え申し候。「伊羅(いら)」、篩(ふるい)より降(ふ)り候を「上伊羅(かみいら)」と唱(とな)え、その次を「荒(あら)」と唱(とな)え、それよりだんだん篩(ふる)い候て、「仙台(せんだい)」、「真引(しんびき)」、「細真引(さいしんびき)」、「微塵(みじん)」と、七段に相(あ)い分け申し候。右訳(わ)け方は、荒き篩(ふるい)より追々(ついづい)細(こまか)の篩(ふるい)に移し仕上げ申し候、右の通りにござ候。」
下巻142【道明寺(どうみょうじの)糒(ほしいぃ)製法】・・・今度は「道明寺粉の糒(ほしいぃ:=干飯)」です。上記の中巻10 【らくがんの仕様】や、下巻82 【早甘酒(はやあまざけ)】 の材料として、水に浸し蒸した餅米を乾燥させて粗めに挽いた「道明寺粉」がありました。・・・尚、おそらくは・・・水戸徳川家(水戸藩)藩邸内の台所付近の勝手役人(=料理担当者)が、水戸藩の御菓子御用達商人から予め与かっていた、当時の説明書き(=商品パンフレット)を読んで、殿様へお知らせしたのかな? と想える内容になっております。商人の実名も出ており、リアルな感じが致します。デフォルメしたり、偽名にしたりする必要はありませんので。・・・また、殿様の徳川斉昭から、この勝手役人(=料理担当者)に対して・・・今度、御菓子御用達商人が来たならば、詳細を知らせるように!!”・・・との、暗黙のお達しがあったようにも感じます。
「御達(おたっし)御座候(ござそうろう)間(≒そちらから、新たな指令があるのを待っている間に)
、御菓子御用達(おかしごようたし)真志屋五郎兵衛(ましやごろぅべえ)◇◇〈?原文二字欠落部分とされるが、おそらくは「名前」か? と思いきや、下記の 下巻83 を読むと「心得」か?〉
製法書(かき)し候処(≒御菓子御用達・真志屋五郎兵衛◇◇が説明する道明寺糒の製法に関する書面を読むと)
、寒製に限り候儀には御座無く候(≒冬場に限って行なっているものではないとの事でした)
。市中商物(しちゅうあきないもの)の分は(下総・)
行徳(ぎょうとく:※現千葉県市川市南部のこと)
の辺りにて寒暖の差別なく出来候由(≒これら道明寺糒の内で市中に出回る品は、寒暖差のあまりない下総・行徳辺りで製造されているとの事です)
。拵(こしら)え様は極上の餅米を前日、水に漬(つ:=浸)
け置き、翌日蒸しあげて干飯に仕(つかまつ)り、目荒き臼にて挽(ひ)き篩(ふるい)の目、中荒に、又(また)細末(さいまつ)の篩(ふるい)にて一扁(いっぺん)篩(≒一度篩に掛け)
、二扁(にへん)篩(ふる)い段々(だんだん)と篩抜き(≒二度、三度と、段々に篩を繰り返して)
、微塵粉(みじんこ)に相(あ)い成り候分は◇〈?原文一字不明部分とされるが、おそらくは「仕(つかまつ:≒そのままで利用)」か?〉
り、一扇篩候分(ひとおおぎふるいそうろうぶん)は荒く候間、篩い抜き留(たま)り候文(=分)
幾度も挽(ひ)き(≒とにかく幾度となく篩と挽きを繰り返して)
、一扁篩目(≒一度篩の目)
へ留(たまり)り候分、道明寺(どうみょうじ)と相(あ)い唱(とな)え候由。右に付けて出来難き儀は御座無く候(≒前述したように行なってみても、最後まで微塵粉が出来ないという理由はないでしょう)
。」
下巻143【醒井(さめがい)餅】・・・「醒井(さめがい)」とは、近江国坂田郡南部(現滋賀県米原市醒井)にあった宿駅のことであり、古くから「清水」が有名で、“日本武尊(やまとたけるのみこと)が伊吹山で熱病に罹(かか)った際に、この清水で体を冷やした”という伝説もあります。東山道と中山道の街道沿いに位置したため、宿駅として繁栄し、その宿駅の名物として、ここにある「醒井餅」の名が残っています。また、この宿駅を管轄した彦根藩は、諸大名から贈られた特産品のお返しとして、「鮒鮨」や「松原海老」、「漬松茸」、「鴨」、「醒井餅」、「近江牛の味噌漬け」などを贈答品にしていました。・・・と、そんな話もありますが、ここにある記述内容は、幕末の「安政の大獄」が始められる直前時期のものであることが明らかなので、水戸徳川家と井伊家の関係が、ある程度順調な頃だったも云えるため、非常に興味深いものになっております。とは云っても、以下原文は水戸藩内で交わされた内部文書でもありますし、また水戸藩内で「醒井餅の製法」を明らかにしようと試行錯誤を重ねていた様子なども分かる記述になっております。・・・とにかく、この「醒井餅」は、当時全国的に名を馳せた名産品となっていたようでして、当時の書物のいくつかにも見られるのですが、作り方や形状については、地方の名物料理を纏(まと)めた江戸時代中頃の『料理山海郷(りょうりさんかいきょう)』に、「極上の米で餅を作り、薄く切って、藁(わら)で編んで、陰干にしたもの。」と記され・・・また、同時期の地誌『近江輿地志略(おうみよちしりゃく)』には、「紅黄白の片餅大さ堅四、五寸、幅四、五分厚さ一分に及ばず甚(はなは)だ薄し。」とか、「今短冊餅(たんざくもち)とて幅一寸六分許(ばかり)、長五寸許(ばかり)、黄白赤の三色にして、これを売る。専(もっぱ)ら醒井餅という。これ百年以来の事也。」とも記されているので・・・それだけ、著者・徳川斉昭が「醒井餅の製法」を知りたかったという事かと想います。
「一、井(伊)
家にて製(つく)りし進物(しんもつ)等に相(あ)い成り候所、何(いず)れも何時(いつ)まで御貯(おんたくわ)えに相(あ)い成り候ても、黴出(かびい)で申さず候処(也)
。試(こころ)みに製(つく)り候様醒井餅(さめがいもち)御下(おさ)げ御達(おたっし)の趣(おもむき)御座候所、製法方心得(こころえ)居(お)り候御座無く候間、是(こ)れ又(ま)た、真志屋五郎兵衛(ましやごろぅべえ)心得(こころえ)居(お)り候えば、御菓子の御用(ごよう)も相(あ)い勤(つと)め居(お)り候間、申し出候様(もうしでそうろうよう)御達(おたっし)に相(あ)い成り候所、更(さら)に相(あ)い心得(こころえ)申さざる趣(おもむき)に付、御国表(おくにおもて:※水戸藩の本領のこと)
同役共(どうやくとも)へも御下(おさ)げの御品(おしな)指し下し(=差し下し)
申し遣(つかわ)し候所、是(これ)を以(もっ)て製方工風もこれ無き旨(むね)申し来たる。御筆(※徳川斉昭からの書状のこと)
にもあらせられ候通り、餅米を寒晒(かんざらし)に致し、粉となり候。餅搗(もちつ)き候には相違(そうい)これあるまじきか、寒中餅米を七日、水に漬(つ)け置き、右を干上げ、粉と成り候。餅搗 (もちつ)き候。尤(もっと)も、取粉(とりこ)を用(もち)い候えば、黴出(かびい)で候間相(あ)い用(もち)いず、よき程に固き候篩(ふるい)、御雛形(おんひながた)の通り断ち切る。
一、板の上へ一枚ずつ並べ置き候分は、風に当たり反(そ)り、又(また)は割れ出(い)で申し候。
一、板の上へ一枚ずづ並べ、風に当たり候ては、よろしからずと存じ候。長持(ながもち:※衣類や寝具の収納に使用された長方形の木箱のこと)
の内へ入れ置き、日々手返し(≒日々裏返して)
いたし候処、自然と干割れに相(あ)い成り申し候(≒自然に粉々となってしまいました)
。
一、箱の内へ一枚ずつ並べ置き、又(ま)た反(そ)り出(い)で申さず候様、十四、五枚ずつ重ね置き、長持(※衣類や寝具の収納に使用された長方形の木箱のこと)
の内へ入れ置き候分は黴出(かびい)で申し候。
一、葦簀(よしず:※葦の茎部分を編んで作られた簾〔すだれ〕のこと)
の上へ並べ、長持(※衣類や寝具の収納に使用された長方形の木箱のこと)
の内へ入れ置き候分は、干割れ相成(あいな)り申し候。右の通り試(こころ)み候処、何(いずれ)にも御用(ごよう)相(あ)い立たず、若(も)し混ぜ物等にも、これあるべく候か相(あ)い分(わか)りかね候処、江州(=近江国)醒井(さめがい)
の儀は、寒地の場所とも承(うけたまわ)り候間、餅に搗(つ)き断ち切り候を、直(じか)に箱に入れ重ね置き候ても黴(かび)も出(い)で申さず、日割れ等もこれなき儀にこれあるべきか、又(また)は混ぜ物などの類(たぐい)御座候(ござそうろう)か、さて又(ま)た暖気を催(もよお)し候砌(そうろうみぎり)に候えば、干割れ等は之(これ)有り候まじきと、又々(またまた)試(ためし)に寒中餅米を十日程、水に漬(つ)け置き候を粉と成し差し置き(≒水に浸けて置いた寒中餅米を、粉にしてから放置し)
、三月始めに至り搗(つ)き立て前の如く取り、粉(こな)更(さら)に相(あ)い用(もち)いざる程よく固まり候を断ち切り、琉球表(りゅうきゅうおもて:※麻糸を縦に、七島〔しちとう〕の茎を横に織った筵〔むしろ〕のこと)〕
の上へ一枚ずつ並べ置き、日日(ひび)手返し干上げ候処、風当たり候ても干割等少なく、試(ためし)に製(つく)りし候品(そうろうしな)、御覧(ごらん)に入れ奉(たてまつ)り候えども、醒井餅(さめがいもち)通り出来るとは申し上げかね候。若(も)し、よろしき御工風(おんくふう:≒御工夫)
も御座候えば、御達次第(おたっししだい)に製候様(つくりしそうろうよう)仕(つかまつ)るべく候えども、先(ま)ずこの儀申し上げ候。
以上 御番屋(ごばんや)懸(かか)り(≒御番屋係よりお伝え致します)
五月 吟味役(ぎんみやく)共(=吟味役とともに)
」
下巻144【芥子漬(からしづけ)の法 (水戸三◇〔?原文に一字抜け部分あり。おそらくは「反[たん]」か?〕
田の茄子〔なす〕
は、皮厚くして味よし。尤〔もっと〕
も、此〔こ〕
の茄子〔なす〕
を漬けるなり。)】・・・「水戸三◇田茄子の芥子漬の作り方」。・・・唐突なのですが・・・私(筆者)は、この項目レシピ内にある「水戸」に続く地名には、おそらくは「反(たん)」という字が入るのだろうと考えます。・・・旧水戸藩領内の水戸には、「三田(みた)」という旧町や旧村は無く、現在まで続く「大字(おおあざ)」や「小字(こあざ)」を調べてみても、その存在が確認出来ません。・・・しかし、江戸時代後期の水戸藩の「郡奉行(こおりぶぎょう)」で儒学者の小宮山楓軒(こみやまふうけん)が編纂した『水府志料(すいふしりょう)』には、“古くから、常陸国那珂郡内に「三多田(みただ)村」とされていた地域が在ったが、元禄年間頃に「三反田(みたんだ)村」に改称された”とあり・・・また、水戸藩の地誌学者・高倉胤明(たかくらたねあき)が著した水戸城下の地誌『水府地理温故録(すいふちりおんころく)』にも、“この「三反田(みたんだ)村」が、「瓜」や「茄子」などを多く産する所となって、大変大きく育ったものが採れた”とあり、さらには“元禄年間中に、「中丸瓜(なかまるうり)」や「茄子」、「ほおずき(=酸漿=鬼灯=鬼燈)」の産地として知られるようになった”とも。・・・これらの理由により、「水戸・三反田(村)」が、一番自然かな? と想う訳です。・・・この推測が正しければ、この「三反田(みたんだ)村」とは、現在の茨城県ひたちなか市美田多(みただ)町と、同ひたちなか市大字三反田(みたんだ)に跨(またが)る地域となります。
「小茄子(こなす)山盛一升、塩一合五勺、右一夜塩押(しおおし)にいたし置き、芥子(からし)七合、糀(こうじ)四合、酢一合、右茄子の塩も一つに入れ漬(つけ)る。三十日程立てば(=経てば)
用(もち)いてよろし。(但し、初めに茄子〔なす〕
の漬様肝要なり〔≒但し、初めて漬ける茄子の状態が重要なのです〕
。汐〔=塩〕
よく行き渡り〔≒塩が良く馴染んで〕
、茄子〔なす〕
の色よく漬〔つかる〕
時は、芥子へ漬〔つ〕
けて永く保つなり。右の割合にて多く漬〔つ〕
ける程よろしき事。)」
下巻145【塩の製法】・・・ここにもまた、「ジョン・万次郎」こと「中濱萬次郎」が登場しており・・・捕鯨船などの「異国船」が遠洋航海するのに必要となる、貴重な物資「塩」を、如何にして調達し、また精製しているのか? についてが記述されています。・・・おそらくは、塩は塩でも「岩塩の抽出方法」が記述されているのではないか? と想います。・・・相手方のことを良く知ることも「水戸学」では重視していましたので・・・著者・徳川斉昭が、直接? 中濱萬次郎に尋ねたようでもあります。
「一、先年(=昨年)
長崎より、「ボウトル」(牛の乳の事。〔=オランダ語のboter=バター〕
)の桶を塩にて詰め来たり候事之(こ)れ有り候。右の塩、氷砂糖(こおりざとう)の如く堅く相(あ)い成り居(お)る故(ゆえ)、その事を中浜万次郎へ尋(たず)ね候処、拵方(こしらえかた)左の如く(≒以下に述べるように)
、一間半或(あるい)は三間位、深さ一尺程の箱、地上より四尺斗高くいたし、右箱へ海水を汲み入れ、雨露(あめつゆ)ふせぐ(=防ぐ)
ばかり取り離しなる様の屋根いたし、海岸へ数多く拵(こしら)え置く。汐干(しおひ)付けたる時取るなり。常の塩より荒く、氷砂糖の細(こまか)き品の如くなる様なり。何ケ月にて出来候か覚え申さず候処、十月頃取り、その跡へ又(ま)た海水汲み入れ候様、相(あ)い覚(おぼ)え定めて一ヶ年にて取り候事に、之(こ)れ有り候かと申す。土地、土数(どすう?つちかず?:※土の嵩〔かさ〕のこと)
にもより、申すべく候如何(いかが)之(こ)れ有るべきか、北アメリカ四十一度(=緯度四十一度)
半位の地に候由なり。北アメリカにも常の焼きたる塩も之(こ)れ有るよし。
一、在国中、我工風(わがくふう)にて生塩を水にて溶き、硝石(しょうせき)を寄るようにして試(こころ)み候なり。◇〈?原文一字不明とされるが、「岩(いわ)」、あるいは「晶(しょう)」か?〉
此位(このぐらい)にあられの如くに堅まり、又(また)は◆〈?原文一字不明とされるが、「山(やま)」、あるいは「岳」、「嶽」、「峯」か?〉
かくの如く屋根の如き塩出来るなり。又(また)塩を焼き抜く時は、陶器の如く相(あ)い成る物なり。」
下巻146【川越味噌の法】・・・ほとんど同じ内容で、上記 下巻116 に 【川越味噌の法】がありました。・・・ここは「法」は「法」でも、念を押すかの如く「川越味噌とは塩味が強いものである」としているようです。・・・著者・徳川斉昭による注意喚起?
「大豆二斗、麦糀(むぎこうじ)八升、塩一斗六升、右は何(いずれ)にも塩からし(≒前述した分量で川越味噌を造ると、塩辛いものになります)
。」
下巻147【鎌倉味噌の法 (同所〔どうしょに〕
御附〔おつき〕
相〔あ〕
い勤め候、川村角介申し上げ候事。)】・・・「鎌倉味噌」については、上記の 下巻119 や 下巻125 にもありました。この 下巻147 の「鎌倉味噌」に関する記述は、これらの「続報」と呼べるものだと想います。・・・ちなみに、この項目中にあって個人名が分かる二名については、『水府系纂(すいふけいさん)』によって「水戸藩士」であることが確認できます。また「御附(おつき)」という役職がありますので、著者であり藩主? 前藩主? の徳川斉昭の側に勤めていた人達であり、さらには一定期間「鎌倉」に出張していた事も分かります。・・・まず、「川村角介」とは「川村角介正直(かわむらかくすけただなお?/まさなお?)」と云い・・・次にある「石川清衛門(いしかわきよえもん)」には、二名ほど候補者があるのですが、「石川富衞門清愼」、あるいは「石川清閑久富」のうち、どちらかの人だとは想うのですが? 人名の読み方や呼び方については、いろいろとありますので、ご容赦下さい。・・・いずれにしても、以下原文の中段部分が、「石川清衛門」による報告であり、冒頭部分と後半部分が「川村角介」による報告となります。
「大豆二斗、糀(こうじ)二斗、塩一斗。
同製法(=同じく鎌倉味噌の製法)
(同所に御附〔おつき〕
相〔あ〕
い勤め候、石川清衛門申し上げ候事。)
大豆一斗、糀(こうじ)二斗或(あるいは)一斗、塩三升程。
同製法(=同じく鎌倉味噌の製法)
大豆一斗、糀(こうじ)五、六升位、塩四升程、右何(いず)れも転役(てんやく:=転任)
覚(おぼ)え置き候処を咄(はな)し候なり。」
下巻148【鮒柔煮(ふなやわらかに)の法】・・・いわゆる「鮒(ふな)の甘露煮」となります・・・が、鮒(ふな)を焼く際の、嫌な匂いを軽減させる料理テクニックも記述しています。
「鮒(ふな)を自(みずか)ら焼(やき)にす。焼く時(自らの)
の先へ胡麻油(ごまあぶら)を付けて焼くもよし。
右自(みずか)ら焼きにしたる鮒(ふな)を、早朝より湯煎(ゆせん)にし、夜五つ時頃まで(≒午後八時頃まで)
二日程煎じ、又(また)味淋酒を入れ一日煎ず。その後、醤油、砂糖を入れ、又(ま)た一日程煮立てる時は、骨までも喰(く)わるる程に柔(やわら)かになるなり。
味淋五合、醤油二合、砂糖半斤程なり。(但し、湯詰る時は追〔おっ〕
て湯を入れて煎ず。湯を捨てる時は味悪〔あじわる〕
し。是〔これ〕
も、早朝より夜五つ時まで〔≒午後八時頃まで〕
煎るなり、湯は一切捨てざる様致すべく候。)」
下巻149【高野(こうや)の氷豆腐(こおりどうふ:=凍み豆腐)
似たるは】・・・「高野の氷豆腐」とは、かの「高野山」で製法が完成されたと云われる凍り豆腐の「高野豆腐」のことです。北関東や東北では「凍み豆腐」とも呼ばれますが、「高野豆腐」と呼ばれるようになったのは、江戸時代に「高野山」の土産物として珍重されたからとも謂われます。・・・ここの項目名に「似たるは」とありますが、“製法から食し方や保存方法まで、水戸藩領内で作られて食されている「凍み豆腐」と何ら変わるところが見出せない”という著者・徳川斉昭の気持ちが伝わってまいります。
「おぼろ豆腐(※豆乳に苦汁〔にがり〕を加え、完全に固まらないうちに、漉くい上げた柔らかな豆腐のこと)
にて至(いたっ)て柔(やわ)らなる品あり。右を極寒(ごっかん)の節、凍(こう)する時は高野(こうや)の風(ふう)に出来て、目細(めこまか)きなり。」
下巻150【辛味(からみ:≒絡み)
餅 (歯なき〔=歯無き〕
老人等によし。)】・・・「歯の無い高齢者向けの大根おろし絡み(≒辛味)餅」。・・・原文末尾では、あまりにも辛すぎると感じるならば、「白砂糖」を加えても良いとの配慮もされております。
「水餅(みずもち)(水へ漬〔=浸〕
け置きたるを言う。)を煎じ、あつき(=熱き)
所を茶碗(ちゃわん)に入れ、大根おろし醤油を少しかけて(=掛けて)
用(もち)ふるなり。(但し、白砂糖加えかけ〔=掛け〕
たるもよし。)」
下巻151【海苔(のり)餅】・・・私(筆者)としては、“醤油と海苔と餅をいっしょに食す”のが、もはや当たり前のことになっているので、「今更感(いまさらかん)」があるのですが・・・江戸時代末期頃の山間部や地方に暮らす人々は、海苔の生産地や乾物屋さんとは縁遠く、そうでもなかったようであります。当時の流通システムの限界と云うものがあったのかも知れません。上記の 下巻91 に、有名な「浅草海苔」が出ていましたが、現代ではポピュラーな「板海苔(いたのり)」とするまでに、漁師さんや職人さん、海産物を取扱う商人達の手間などが掛かりますので。
「餅長さ二、三寸ばかり、巾(はば:=幅)
五、六分位に切り、焼(やき)て醤油へ一寸と入れ、直(ただ)ちに海苔(のり)を巻きて、あつき(=熱き)
所を用(もち)ゆなり。」
下巻152【鹿(しか)を製(つく)る法】・・・お肉大好き著者・徳川斉昭による「ジビエ料理」です。ここにある「鹿肉」は、味噌漬け肉を使用しております。・・・地方では特に、野生の「猪」や「鹿」などが畑や収穫物を食い荒らす害獣とされたため、厳格な戒律が課される「お坊さん」などを除いて、案外食用にされていたようであります。・・・尚、既にこの頃には薩摩藩の江戸藩邸で黒豚が飼育され、それを食していたとのこと。・・・“その薩摩藩飼育の黒豚肉を著者・徳川斉昭の息子である徳川慶喜がエラく気に入って、何度も所望するようになり、「豚一様」と呼ばれるようになった”との逸話もあります。ちなみに、“「豚一」の中の「一」は、その時の慶喜が徳川御三卿・一橋家に養子に入っていたため”とも云います。尚、親子であっても、獣肉の好みは少々違っていたようでありまして・・・父の好みは「牛」や「鹿」で、息子は「豚」や「鹿」だったようです。「鳥」は獣ではありませんので別物と云えます。・・・もしかすると、以下原文末尾部分は、息子・徳川慶喜への助言だったのかも知れません。
「鹿(しか)を刺し身の如く薄くし、大根おろしの中へ入れ、よく揉(も)み、身(=鹿肉)
を取り出し、水にてよく洗い堅く絞(しぼ)り、汁(しる)になり、煮付(につけ)になりするなり、右様(みぎのよう)にする時は(≒前述した様に食す際には)
、鹿臭(しかくさ)き事なし(≒鹿肉特有の臭さがあってはならない)
。味噌などへ漬(つ)け置き、鹿臭(しかくさ)きも右の如くすれば臭(くささ)去(さ)るなり。(但し、獣肉類〔けものにくのたぐい〕
には蕎麦〔そば〕
は忌〔い〕
み申すべきかに候〔≒但し、獣肉類には蕎麦と合わせて食すのは止[よ]した方が良いだろう。なぜなら、蕎麦の香りや風味が台無しとなるのだから〕
。)豚(ぶた)食い候節は(≒例えば、豚肉を食す際は)
、そば(=蕎麦)
、生荷(しょうが:=生姜)
入湯を忌〔い〕
むなり。」
下巻153【梨(なし)に熊胆(ゆうたん/くまのい:※熊の胆嚢〔たんのう〕のこと)
禁物之法(きんもつのほう)】・・・ショッキングな項目名 and ショッキングな記述内容です。・・・以下原文を読むと、著者・徳川斉昭が、実際に経験し? 抱いた危機感も分からなくも無いのですが・・・。・・・ここにある「熊胆」とは、別名「熊の胆(くまのい)」とも呼ばれる動物性の生薬です。古くから万病の薬として知られ、「鎮痛(ちんつう)」、「鎮痙(ちんけい)」、「消炎(しょうえん)」、「鎮静(ちんせい)」、「解毒(げどく)」などの目的で利用されて来ました。当時も非常に高価な漢方薬でしたが、いわゆる「胃薬」として著者・徳川斉昭が服用したのでしょう。うっかり「梨」と食べ合わせてしまったのかも知れません。・・・「熊胆」の主成分は、「ウルソデオキシコール酸」と云う“胆汁酸代謝物の一種”であり、元々雑食性の熊の胆嚢(たんのう)ですから、“強い酸性成分を含んだもの”とも云えます。・・・もしも、これと・・・当時は、小さくて硬く消化され難(にく)い、そして特に酸っぱい「梨(※アルカリ性の果実)」を食べ合わせたなら・・・おそらくは、多くの人が「便秘」や「下痢」を引き起こし・・・現代医学ならば、適切に医療的な処置が為されるのでしょうが・・・幕末期では、そうもいきませんよね。どんどん体力が衰弱してしまい・・・という具合になるかと。・・・まさに七転八倒の苦しみだったかと想います。
「梨(なし)食し候前後、熊胆(ゆうたん/くまのい:※熊の胆嚢〔たんのう〕のこと)
は一切用(もち)ゆべからず(≒梨を食す前後に熊胆を用いる事は一切認めない!!!)
。ことによる時は即(すなわち)死するなり(≒事によると即、死に至るぞ)
。」
下巻154【たまご永貯法(えいちょほう)】・・・「玉子を長く貯える方法」とありますが、絶対に真似して実験しないで下さい。・・・それでも我慢できずに実験してしまった場合、もしも長い期間卵の形状に変化が観られなかったとしても、絶対にその卵を食してはいけません。・・・と云う以前に、これが記述された頃は、おそらくは「有精卵」だった筈でして・・・本当に壁土の中を真空状態に出来たならば、鶏卵の成長を止められて鶏卵を半ば休眠させているような状態になるのでしょうが、それが完全に行なえないと、一定期間経てば鶏卵が「ひよこ」になっているか? 鶏卵が死んでしまって腐ってしまうか? のどちらかだとは想うのです。・・・原文末尾部分に、「油気(あぶらけ)は少々抜けてしまったが」とあり、“実際に食して確かめて見た”と「読み手」に連想させてはおりますが・・・元々鶏卵の殻は多孔質で、鶏卵の中身は呼吸している筈なのです。したがって本当に、壁土の中を無菌状態且つ真空状態に出来れば、細菌の影響は無くなるので結果腐敗しないことにはなるのです・・・が、著者・徳川斉昭は、その鶏卵をどのようにして食したのか? までを記述してはおりません。結局のところは、“偶然且つ奇跡的なお話”として聞き流した方が無難だと想います。まさか「生玉子」では食さなかった筈ですよね。そして、“昔の人は現代人よりも胃腸が強かっただけ”とも云えるのではないでしょうか?・・・尚、もしも「油気」を「ゆげ」として読んだ場合には、意味としては「少々熱気が抜けるなり」となるので、もはや「一玉でアウト!!!」と云える状態かと想います。この場合の「熱気」は、鶏卵が吐き出す「炭酸ガス」のことですから、“壁土の中が真空状態に至っていなかった”という証拠になりますので。・・・それに、そもそもの話として・・・通常の「壁土」は、家屋などの土壁(つちかべ)に利用しますが、主に「耐火性」や「防水性」、「吸湿性」を期待して、柱や梁などの木造躯体(もくぞうくたい)を守るという目的がありますので、空気を通さない完全な粘土を調達出来ないと、「真空状態」を作るのに向いておりません。
「玉子を永く貯(たくわ)うるには(船中などなり。)玉子を壁土(かべつち:※壁を塗るのに使う粘り気のある土のこと)
にて一つずつ包み、幾つも寄せて箱へ詰(つめ)るなり。(箱の内、隙〔すきま〕
之〔こ〕
れ無き様に土をつめる〔=詰める〕
。)一ヶ年置き出し試(こころ)みるに、少しも悪(あ)しく相(あ)い成らず。(少々油気〔あぶらけ〕
は抜けるなり。)」
下巻155【鮑(あわび)を永(なが)く置(おく)法】・・・上記 下巻154 に続き、これも要注意項目です。「永」の字が使用されており、どうしても・・・現代人は「永久」とか「永遠」という単語を連想してしまいますので。ここは「長めに」と置き換えて読んで下さい。・・・また、著者・徳川斉昭は、「鮑(あわび)」と「常節(とこぶし)」と呼ばれる“鮑よりも小型の巻き貝”を区別してはおりませんので、ご注意願います。
「鮑(あわび)を初夏の日など、三日位貯(たくわ)え置くには椿(つばき)の葉を多く敷き、その上へ伏(ふ)せて置く時は三日、四日は死なずして持つなり。(但し、道中〔どうちゅう:=旅路〕
ならば籠〔かご〕
へ入〔いれ〕
るべし。)」
下巻156【時鳥(ほととぎす)羽根の法】・・・もはや、これは「料理」とは云えず、単なる「科学実験」のような気が致しますよね。この項目名を見る限り。・・・でも、これは・・・“野鳥のホトトギスのこと”を云っている訳ではなく・・・以下原文を読めば、何となく想像出来ると思うのですが・・・「山菜の時鳥(ほととぎす)」のことです。いくら野鳥を食していた著者・徳川斉昭でも、古来から珍重され和歌などで詠まれて来ていた「野鳥の時鳥(ほととぎす)」は食べませんし、その徳川斉昭に「野鳥の時鳥(ほととぎす)を食す」と、わざわざ伝える罰当たりな人もおりません。・・・この「山菜の時鳥(ほととぎす)」が、“野鳥の時鳥(ほととぎす)に似ている様から命名されている事”から生じる誤解なのであります。・・・この「山菜の時鳥(ほととぎす)」は、日本固有種であり、本州や四国地方、九州地方の低山から亜高山まで分布し、湿気の多い土地を好み、丘陵や山麓の沢沿いや湿った林内、原野などに見られ、水気のある場所に群生する植物のことでして・・・その若芽は、山菜として食用とされ、採取時期は5月~6月頃で、寒冷地や高山では7月頃が適期とされます。食味は瓜(うり)のような仄(ほの)かな香りと爽やかな食感、サッパリとした味わいに特徴があります。現代でも、採取した若芽を茹でて、「芥子との胡麻和え」や、「白和え」などの「和え物」の他、「酢の物」や「生(なま)」のままでも食べられますし、「天ぷら」や「汁物」などの具材にもなります。また、“一部の地域では、民間薬として止血の際に使われる”とも云います。・・・左記の項目中や以下原文にある「羽根」や「尾羽」という単語が、なおさら誤解に拍車を掛けるような事になっていますが、「時鳥(ほととぎす)の羽根」とは、“葉部分のこと”であり・・・また、「時鳥(ほととぎす)の尾羽」とは、“若芽部分、若しくは根の部分”のことかと想います。「時鳥(ほととぎす)」は「ユリ科の植物」なので。つまりは「ユリ根」に近いかと。・・・ですから、以下原文で「酒など変(へん)じたる時入れ置く時は、本(もと)の如くなると言う」とあるのは・・・いわゆる「マムシ酒」のように酒に漬け込んで薬効あるものを保存する、云わば「時鳥(ほととぎす)漬けの薬用酒」になると云う訳です。・・・以下原文からも分かるように、著者・徳川斉昭が「山菜の時鳥(ほととぎす)」を知らず、食していなかったために、あくまでも「伝聞」として記事とした故か? と考える次第です。
「時鳥(ほととぎす)の尾羽(おばね)を味噌へ入れ置く時は変わらず。酒など変(へん)じたる時入れ置く時は、本(もと)の如くなると言う。(但し、試〔ため〕
さず〔≒但し、実際に試してみた訳ではありません〕
。)」
下巻157【生海鼠(なまなまこ)貯置法(たくわえおくほう)】・・・“海から離れた山間部に暮らす人々でも、「生海鼠(なまなまこ)」を食せるように”との著者・徳川斉昭の配慮が感じられますね。
「生海鼠(なまなまこ)を寒中四、五日余りも持たするには、柚(ゆず)を丸切りにして桶へなり、竹の筒へなり一同に(≒いっしょに)
入れる時は、四、五日かかる(=掛かる)
里数にても(≒四、五日掛かってしまう距離があったとしても)
遣(つかわ)すに寒中は変わらざるなり。」
下巻158【酒造る法】・・・ここも非常に興味深い項目です。「地名」も出てまいりますが、酒造りの上で重要な、「米と水の関係についての話」です。それも、“水戸藩領内や隣接藩では、せっかく美味い米が収穫出来るのだから、あとは造り方次第とのご指導”であります。きっと「酒豪」だったに違いありません。著者・徳川斉昭さん。
「酒は、世上(せじょう:=世間)
にて水よりても善(よ)くも悪(あ)しくも出来ると雖(いえど)も、水は二の次なり。米を吟味するなり。米の宜しき品第一なり。水戸にては小沢郷(※現茨城県常陸太田市小沢町)
の米、他領にては小田(※現茨城県つくば市小田のこと。ここは土浦藩領であり第11代藩主・土屋挙直〔つちやしげなお〕は、著者・徳川斉昭の第十七男です)
辺りの米をよしとす。左様の性合よき米をよしとす。左様の整合よき米を念入れて春(ま)き、又(また)よく念を入れて磨(みが)ぎて造る時は、上方(かみがた)の酒にても水戸の酒にても相違(そうい)は之(こ)れ無く候なり。上方(かみがた)は酒の直(じか:=値)
よければ念を入(いれ)て造るなり。常州(じょうしゅう:=常陸国)
辺りは酒の直(じか:=値)
よろしからずは米を撰(えら)ばずして、造り方も手間(てま)省(はぶ)く故(ゆえ)、酒宜しからずというは尤(もっと)もなり 。案ずるに、伊丹(いたみ:※現兵庫県南東部地域で尼崎藩領)
にて酒を造る水の目方(めかた)を以(もっ)て、右同様の水にて上米にて念入れ造るときは必ず同じからん(≒前述したように酒を造る水の目方を、きちんと見極め、且つ上米を用いて丁寧に酒を造れば、必ず伊丹の酒と同じ様なものに出来るのだろう)
。(但し、ホクトメートル〔※液体の比重を計るための浮き秤のこと〕
などにても水の目方〔めかた〕
は知れるなれども、それまでもなく茶碗へ入れても分〔わけ〕
るべし。)」
下巻159【きす(=鱚)
ほりほり製法】・・・上記の 下巻127 に全く同名の【きすほりほり製法】がありました・・・が、以下原文に「取肴(とりざかな)」という単語がありますので、より高齢の賓客などを意識したものか? と想います。
「新しき鱚(きす)を開き、骨、頭、尾を去り、よく蒸し(但し、塩水にて洗い候てもまた、然〔しかり〕
しかるべきか、汐気〔しおけ:=塩気〕
ある時はしめる〔≒絞める〕
。)、天日(てんぴ)にて干し(何日も干し、よく干し上るなり。)助暖(じょだん:※小さな火鉢のこと)
へかけ(=掛け)
置く時は、ほりほり〔≒箸で彫り彫りと〕
いたし軽く相(あ)い成り、取肴(とりざかな:※正式な日本料理の饗膳の際、三度目に出す酒に添えて勧める酒の肴のこと。 饗応する主人自らが漁猟したものや遠来の珍品など、心尽しの物を取って勧めたため、この名が付いています)
などによろし。(汐水〔=塩水〕
にて洗わざる方よろし。)」
下巻160【餅の事】・・・ここはまず、以下原文中で語られている「羽二重餅(はぶたえもち)」から説明致します。「羽二重餅(はぶたえもち)」とは、餅粉を蒸し砂糖と水飴を加えて練り上げた和菓子であり、江戸時代末期頃から越前国(現福井県)辺りで親しまれていたものです。そもそも、江戸時代から繊維業が主力産業とされた越前国(現福井県)辺りでは、「羽二重(はぶたえ)」が最高級の絹織物とされており、その色合いや風合いに似せた和菓子として誕生したのが「羽二重餅(はぶたえもち)」です。・・・そして、水戸藩など太平洋側の地域の人々は、越前国や越中国、越後国から山々を越えてやって来る物産品を「越え物(こえもの)」や「越し物(こしもの)」として認識し、それらがまた商人らにより宣伝されていたようであります。「富山の薬売り」などは、特に有名でした。・・・したがって、以下に「水戸の如く羽二重越(はぶたいごん/はぶたいごえ)のように相(あ)い成らず」とありますが、これらを単純に読めば・・・“水戸では、きめ細かな羽二重越(はぶたいごん/はぶたいごえ)が食せるのに、江戸では製法の違いによって羽二重越、若しくは羽二重餅のように、きめ細かな食感には至らず、悲しいことだ”・・・との著者・徳川斉昭の不平不満ですね。コレは。「水」と「湯」を使い分けると、そんなにも和菓子の食感が変わるものなのでしょうか? ・・・私(筆者)は、単純に「水の硬度の違いや、ミネラル成分の違い」に因るものだと想うのですが。“水戸など山々に囲まれた地域から流れて来た水”と、“玉川上水を経由として流れて来た水”の違いかと。
「江戸にては、捏(こ)ね取りを水にてする故(ゆえ)に、水戸の如く羽二重越(はぶたいごん/はぶたいごえ)のように相(あ)い成らず、水戸にては捏(こ)ね取りを湯にていたし候故(そうろうゆえ)、羽二重(はぶたえ)にて越(こ:≒漉)
したる如く目もこまか(=細か)
に成るなり。」
下巻161【鯛昆布(たいこう)秀吉(ひでよし)】・・・この項目名は、「たいこう・ひでよし」と読む、呼ぶそうです。・・・しかし、何故に「秀吉」と名付けられているのか? についてが、良く分かりません。・・・水戸徳川家が水戸に入る以前から、このように呼ばれていたのでしょうか? ・・・それとも、著者・徳川斉昭が名付けただけなのでしょうか?
「新しき鯛(たい)を指身(さしみ:=刺身)
の如く薄く切り、一夜酢に漬(つ)け昆布(こんぶ)の上へ並べながら、だんだん巻き、渦巻(うずまき)の如くし軽く押(おもし:≒重し)
を置き、右昆布(こんぶ)を開きながら切身を食すなり。昆布(こんぶ)も食すなり。又(また)重箱(じゅうばこ)へ昆布(こんぶ)を敷き、その上へ切身を並べ、又(また)昆布(こんぶ)を置き、切身を並べ、だんだんと右様にしても同断なり。昆布(こんぶ)は菓子昆布(=山出し昆布:※北海道南部の函館を中心とした地域で収穫された真昆布〔まこんぶ〕のこと)
よし。鯛(たい)の油は昆布(こんぶ)に染み、昆布(こんぶ)の塩は切身に染み、双方甚(はなは)だ美味なり。」
下巻162【近江蕪(おうみかぶ/おうみかぶら)煎様(いりよう) (京地より申し来〔きた〕
る。)】・・・この項目にある「近江蕪(おうみかぶ/おうみかぶら)」とは、現在の滋賀県大津市付近で生産される蕪(かぶ)のことでして、扁平な形状の白い蕪です。肉質は緻密で食味良好。京都の聖護院蕪(しょうごいんかぶ)の原種とされます。・・・著者・徳川斉昭は、以下原文の後半部分で、わざわざ各個書きを重ねて感想を述べております。
「かぶら(=かぶ)
を一寸四方ばかり切り、皮を去り、昆布(こんぶ)、鰹節だし(=鰹節出汁)
にて湑(こし)ため(≒昆布と鰹出汁を染み込ませて)
、よくよく柔(やわら)かに煮たる所へ醤油をさし、薄葛(うすくず:※トロミを付けた葛粉のこと)
引き候て用(もち)ゆなり。(さりながら、近江蕪〔おうみかぶ/おうみかぶら〕
は白味噌の汁にて用〔もち〕
いたる方、我等〔われら〕
は風味よく覚〔おぼ〕
ゆ〔≒しかしながら、近江蕪は白味噌の汁で用いるほうが、我々は風味が良いと感じます〕
。)
(但し、聖護院〔しょうごいん:※聖護院蕪のこと〕
を上品とす。第一大なり〔≒第一、聖護院蕪は大きいものなのです〕
。大なるは渡り七、八寸有るべし〔≒大きなものは、廻り尺が七、八寸も有ろうかと云う程に〕
。)」
下巻163【青柚(あおゆず)を貯(たくわえ)る法】・・・「青柚(あおゆず)の保存方法」です。・・・「お粥」を使用し、「生もの」を「生もの」のままで、多少発酵させながら保存するようであります。・・・しかし、どの程度の期間まで保存できるのか? についてが記述されておりません。
「粥(かゆ)へ塩を交ぜ、(三つ一つも交ぜる〔≒粥三杯に対して塩一杯の割合で混ぜるのです〕
。)、冷やし置き壺(つぼ)へ入れ、漬け込み、目張(めば)りして置く時は貯(たくわえ)に成るなり。(但し、インゲン〔=隠元豆〕
、ササゲ〔=大角豆〕
等も同断なり〔≒但し、隠元豆や大角豆なども、前述した同様の方法によって保存することが出来ます〕
。) 」
下巻164【鰹(かつお)を貯(たくわえ)る法】・・・この項目にある「鰹」は、上記や以下原文にもあるように、「松魚(しょうぎょ)」とか、「堅魚(かたな)」と呼んでおりました。そもそも「かつお」という魚に「鰹」という字を当てるようになったのは、江戸時代に入ってからなのですが、それ以前は「堅魚(かたな)」とされておりました。煮たり干したりすると身が硬くなることから来ているようであります。・・・別称の「松魚(しょうぎょ)」は、云わば「勝魚(かつうぉ)」からの“縁起担ぎ”です。「長寿」や「不変」、「守節」の象徴として貴ばれた「松」を、“目出度(めでた)い樹木”に見立てて、「松魚」という漢字が当てられたものかと想います。
「松魚(しょうぎょ:=鰹)
を正月頃まで貯(たくわえ)るには、なまり節(=生利節:※生の鰹を解体し、蒸す、茹でるなどの処理を施した一次加工食品のこと。特に関西では生節〔なまぶし〕と呼びます)
を製(つく)る如く四つにおろし(≒四枚に下ろし)
、カラシ(=芥子)
を摺(す)り、壺(つぼ)の下へ敷き、その上へ前文おろしたる鰹魚を並べ(≒ ~ その上に前述したように下ろした鰹を並べて)
、又(また)カラシ(=芥子)
をあつく(=厚く)
置き、何べんも右の如くし、その上より醤油をつぐ(=注ぐ)
なり。(但し、醤油は、カラシ〔=芥子〕
の半分位なり。用〔もち〕
ゆる時はよく洗い、刺身に切るなり。)尤(もっと)も、取立(とりたて:=獲りたて)
の新しき堅魚(かたな:=鰹)
貯(たくわえ)とすべし。(常の堅魚〔かたな:=鰹〕
よりも少々柔〔やわら〕
きようなれども隨分風味よろし。)」
下巻165【うなぎ(=鰻)
蒲燒(かばやき)の法】・・・江戸で生まれ育った「江戸っ子」の著者・徳川斉昭としては、“書かない訳にはいかない項目レシピ”だったかと想います。・・・もちろん、鰻の開き方は「背開き」だった筈ですね。・・・武士が多く暮らした「大江戸」や、東日本では、“切腹を連想させる腹開きは縁起が悪い”とされて来ましたので。
「うなぎ(=鰻)
白焼(しらやき)にして熱湯をかけ(=掛け)
幾つも重ね置きて、少しの中、軽きおし(≒重し)
を置き、湯気をしたみ(=湯気を湑み≒蒸して)
少し焼きて醤油を付け、又(ま)た燒くなり。その上にて重箱(じゅうばこ)又(ま)はうなぎ(=鰻)
入れ(※「鰻入れ」と云う容器のこと。鰻を運ぶ蓋付きの木桶のことか?)
に入れ置くなり(但し、うなぎ入れ〔=鰻入れ〕
は冬は周りへ湯を入れ置く故〔ゆえ〕
、うなぎ〔=鰻〕
冷めず。)。但し、醤油、味淋何(いず)れも上々の品等分に合わせ、右を半ば煮詰めて用(もち)ゆ。」
下巻166【蕎麦(そば)の法】・・・ここには、「田螺(たにし)蕎麦」や「雉(きじ)蕎麦」などが紹介されています。これらの“温かい蕎麦が、山間部が多い水戸藩領内で食されていたこと”を物語る記述だと想います。・・・「雉(きじ)蕎麦」は、クセの強い鳥蕎麦のような味かな? と想像できますが、「田螺(たにし)蕎麦」は・・・かなりの高齢者でないと食べたことの無いものかも知れませんね。田んぼの中などの淡水環境に暮らす貝ではあるので、「泥出し」をきちんとすれば食べられたのでしょうが・・・今でも、「毒タニシ」という言葉も聞きますので、止めておいたほうが無難ですね。きっと。
「くるみ(=胡桃)
、飴(あめ)、柿(かき)、右は蕎麦(そば)の毒消しなり(≒胡桃や飴、柿は、蕎麦を食す際に、毒消し効果があり、消化を助けるものなのです)
。飴は蕎麦をはやく(=早く)
解(とか)す物なり。水飴も同断(≒水飴も同じなので割愛する)
。毒は田螺(たにし)、雉子(きぎす:※鳥の雉の古語表現です)
なり。」
下巻167【漬ラッキョウ(=漬薤=漬辣韮)
の法】・・・下巻110 に【漬薤(つけらっきょう:=漬辣韮)】がありましたが、今度は・・・「甘酢漬けラッキョウ(=薤=辣韮)の食べ頃」に関する記述となります。・・・この内容を 下巻110 に記述しなかったのは、おそらくは・・・この『食菜録』が時系列的に纏(まと)められたからだと想います。“こちらが、甘酢漬けラッキョウ(=薤=辣韮)の続報(第二報)”になるかと。・・・また、“この記述のために、約一年~三、四年を要した”ということでもあります。
「ラッキョウ(=薤=辣韮)
五升、酢、醤油、味淋各一升、よく交ぜ(=混ぜ)
たる中へラッキョウ(=薤=辣韮)
を漬(つけ)る。三、四年も立ち(=経ち)
用いてよろし。(但し、一年も過ぎる時は食べる事相〔あ〕
い成るなり〔≒但し、漬け込んでから一年も過ぎれば、食べ頃に成るのです〕
。)」
下巻168【韮(にら)、にんにく味噌の法】・・・見るからにスタミナが付きそうな項目レシピが続きます。・・・以下原文の上段部分は、にんにくを味噌に摺り混ぜた、いわゆる「にんにく味噌」となり・・・下段部分は、「にんにくの使用量を減らす代わりに、韮の若葉を用いた、にんにく味噌」のようであります。・・・また当時は「にんにく」と「韮(にら)」は、どちらも香りの強い「葱(ねぎ)」のようなものと考えられていたのか? と想えるような記述になっております。・・・尚、現代日本人が中華料理などで食べるようになった「にんにくの芽」は、この頃はまだ食さなかった筈です。
「一、にんにくをよく摺(す)り、味噌と摺(す)り混ぜる。但し、味淋、砂糖程よく入れ摺(す)り交ぜる(=混ぜる)
。
同法(≒同じ様な方法として)
一、にんにく生(なま)のまま、味噌と摺(す)り混ぜ、三年も置き用(もち)ゆるという(但し、味噌は格別摺〔す〕
り混ぜては、味噌腐るべきか〔≒但し、にんにくを味噌に極端に多く摺り混ぜてしまうと、発酵が進み過ぎて、味噌そのものが腐ってしまうかも知れない〕
)。又(ま)た若葉(※韮〔にら〕のこと)
を葱(ねぎ)の如く平(たいら)などにしても用(もち)ゆ。」
下巻169【あさづき(=浅葱)
】・・・ここにも、下巻92 の「みしお」が使用されております。・・・尚、「蛤(はまぐり)」が使用されてはおりますが、あくまでも“メインの食材はあさづき(=浅葱)”だった筈です。
「蒸(むら)し、みしお(≒塩昆布出汁を)
をかけて(=掛けて)
用(もち)ゆ。蛤(はまぐり)のむき身等煎じたるを入れる。」
下巻170【野びる(=野蒜)
】・・・「野びる(=野蒜)」は、ヒガンバナ科ネギ亜科ネギ属の多年草で、日当たりの良い土手や道端に生える野草です。全体の姿や臭いは、「小葱(こねぎ:=浅葱)」や「韮(にら)」に似ています。葉と地下にある球根部分が食用となり、シャキシャキした食感の鱗茎は生でも食べられ、味は「葱(ねぎ)」や「らっきょう(=漬薤=漬辣韮)」に似ていて、多少の苦味と鮮烈な辛味があるもので、古代から食べられている野草です。日当たりの良い場所では、2月~3月頃、その他の環境では4月~5月頃が収穫適期になるかと想います。・・・私(筆者)の祖母などは、「野々蒜(ののひろ)」と呼んでおります。・・・いずれにしても、これも「スタミナ食材」と云えるでしょう。
「のびる(=野蒜)
を煎し、白味噌和(あ)えにして用(もち)ゆ。(但し、白味噌は味淋、砂糖を加〔くわ〕
う。)」
下巻171【葱(ねぎ)、白ねぎ(=白葱)
】・・・立て続けに、「スタミナ食材」が登場しています。
「種(たね)を蒔(ま)き、のびる(=野蒜)
の如く出たるを、汁、平枕(ひらまくら:≒寝床の枕を、平らに連ねたような状態に並べて、焼く? 蒸す? 茹でる?)
などにして用(もち)ゆ。冬より春大きく成りたるは(≒冬から春に掛けて大きく育ったものは)
、白き所を用(もち)ゆ。青き所は臭気(しゅうき:=臭み)
有りて宜しからず。汁、平枕(ひらまくら:≒寝床の枕を、平らに連ねたような状態に並べて、焼く? 蒸す? 茹でる?)
など、又(また)は砂糖、味噌を付け田楽(でんがく)にもして用(もち)ゆ。」
下巻172【仙台(せんだい)氷豆腐(こおりどうふ:=凍み豆腐) (黄ばみあり。)】・・・ここにあるように、「仙台氷豆腐」は、“極寒の中で急速に凍らせたため、黄ばみが出る程だった”という事だと想います。決して、「江戸」や「水戸」で食す際に、黴(かび)が発生していた訳ではありません。・・・それだけ、湯で戻して食した際の食感が、相当肉々しいものだったので、著者・徳川斉昭が驚いたのでは? と考えられます。
「仙台(せんだい)の氷豆腐(=凍み豆腐)
は、煮立ちたる湯に入れ両度洗い、しぼり(=絞り)
、油ぬける(=抜ける)
なり。その上にて茹で、湑(し)たむるなり(≒その上で茹でて、水分を滴らせるのです)
。」
下巻173【鷺(さぎ)しらす】・・・この項目レシピ内にある「鷺(さぎ)しらす」とは、“野鳥の鷺の如くに白く細長いシラス”という意味であり、商品名やブランドに近いものだと考えられます。この料理にも、食材として「野鳥の鷺(さぎ)」は使用されておりません。・・・尚、以下原文からも分かりますが・・・著者・徳川斉昭でさえ、「鷺しらす」と呼ばれるものが、何という魚種であるのか? についてを予想を交えて記述していますので・・・私(筆者)が補足説明するのも変かな? とは想うのですが・・・ここにある商品・ブランド名にある「シラス」は、おそらくは「鮎(あゆ)の稚魚」を主体にしたもののことだろうと想います。冒頭部分に、「京(きょう)鴨川」とありますので。
「京(きょう)鴨川(かもがわ)にて出来る鷺(さぎ)しらすというは、いかり(=どんこ=鈍甲〔※スズキ目ドンコ科の魚のこと。白身肉で美味です〕)
、雑魚(ざこ:※前述した魚種の他という意味です)
等の五分位より六、七分位の大きなるを、生姜(しょうが)を毛の如くに細(ほそ)くし、醤油にて煎じ、火より下(おろ)す前に、朝倉山椒(あさくらさんしょう:※現兵庫県養父市八鹿町朝倉発祥とされる粒が大きい山椒のこと)
を粒のまま入れて、からりと煮上げたる物なり。茶漬(ちゃづけ)の飯等にはよく飯を進ましむ。又(また)右の品を茶碗(ちゃわん)へ入れ置き、極(ご)く熱き湯を入れる時は酒の時の吸い物にもなれり。」
下巻174【九年母(くねんぼ) 煮方(にかた)の法】・・・「九年母(くねんぼ)」とは、東南アジア原産と謂われる、ミカン科の常緑低木のことです。その実は、香りが良く甘みがあって、外皮も食べられるものですので・・・ここにある項目レシピは、「九年母(くねんぼ)のマーマレード」になります。
「九年母(くねんぼ)の皮二十五、内の方の白き所をすき(=漉き)
取り捨て、皮ばかり細(こま)かに庖丁にて叩き、五、六度煮出し、白砂糖二十三匁程、焼塩(やきじお:※焙烙などで煎った塩のこと)
五分入れ、煮て露(つゆ)なき程にす。」
下巻175【氷豆腐(こおりどうふ:=凍み豆腐)
の法】・・・いわゆる「美味しい凍み豆腐の作り方」になります。
「寒中、寒強き夜に氷(こお)らせ、明日又(ま)た水へ漬けて引き上げ、以前の如く氷(こおら)する事、此(これ)の如く五、六日する時は高野(こうや:=高野豆腐)
の如く目細(めこまか)に出来るなり。右は仙台の氷豆腐(※上記の 下巻172 にあるもののこと)
の如くして用(もち)ゆべし。」
下巻176【鮎(あゆ)、骨拔(ほねぬき)の事】・・・「鮎(あゆ)の骨の抜き方」。・・・尚、“鮎(あゆ)は塩焼きに限る”という人は別になるのでしょうが、水戸藩領内で大量に獲れた鮎(あゆ)を飽きずに食す方法としてなのか? 「山椒(さんしょう)」と「醤油」が出てまいります。
「五月頃に相(あ)い成る時は、鮎(あゆ)の骨堅く相(あ)い成る故(ゆえ)、骨を抜きて用(もち)ゆるなり。右は取り立て(=採りたて)
の新しき鮎(あゆ)(図解有るも略す。)図の如く尾の上にて焼きて、あつき(=熱き)
所を紙の上へとり(=取り)
、手にて焼(やき)たる餅を押す如く、背と腹とより指にて押しひしぎ(=拉ぎ:※潰すこと)
、その後頭(かしら)の方、皮と身とを切り、首をつまみ(=摘まみ)
引く時は、小骨(こぼね)まで残らず抜けるなり、その後ひれ等の骨は、その所を裂きて去るなり。(はらわた有りの儘〔まま〕
、左様する時は、わた〔=腸〕
共に取るなり。)
又(ま)た八、九、十月頃に子(=魚卵)
の多く有るは、前の如くする時は、子(=魚卵)
まで皆(み)な出る故(ゆえ)、是(これ)はよく焼いて前の如く、背、腹より押して、さて頭(かしら)の方を切って捨て、尾の方切るべき所の皮と肉を切り、又(ま)た少し背の方と腹の方とを裂き置きて、尾を持ってさか(=逆)
に引くなり。(但し、背の方と腹の方と少々切置く。これは骨出〔いで〕
ぬ故〔ゆえ〕
なり。)左様して山椒(さんしょう)、醤油のつけ(=付け)
焼きとするなり。」
下巻177【冬瓜(とうがん)白煎(しらいり)】・・・この項目レシピも、良~く柔らかくしてから砂糖等で味付けしていますので、「デザート」、若しくは“病中病後の人向けの一品”かと想います。
「冬瓜(とうがん)極々(ごくごく)よく煎じ、砂糖を入れ焼塩(やきじお:※焙烙などで煎った塩のこと)
少々入れ煎ず。」
下巻178【ようかん(=羊羹)
昆布(こんぶ)製法】・・・この項目レシピは、“干し昆布(こんぶ)を酢に漬け込んで柔らかくしてから、くるくると巻き棒状にして羊羹(ようかん)のようにして長期保存する”という方法です。現代の菓子「昆布羊羹」とは別物です。
「昆布(こんぶ)へ酢を引き、日々引く時は、自然柔(やわ)らかに成りて、羊羹(ようかん)の如く成る。右を巻いて箱に入れ置く時は、三、五十日(≒三十日から五十日)
は貯(たくわえ)に成るなり。」
下巻179【ソツプ製法】・・・いきなり「ソツプ」とは何ぞや? ということになるとは想うのですが、以下原文を読むと・・・雌(めす)の鶏肉を柔らかく煮込んだ、日本料理で云う汁物(しるもの)や椀物(わんもの)のようでありまして・・・西洋料理の「スープ」だと想います。珍しい「香草」や、「ハーブ」などは加えられておりませんが、“病中病後の人向けの一品”かと。・・・「ソツプ」の語源は、おそらく・・・オランダ語の「soep」かな? と。
「かしわ雌鶏(めすどり)を、一羽毛を去り、嘴(くちばし)並びに足は股より下を去り、どり(※鶏の肺のこと)
、ひゃくひろ(※鶏の小腸のこと)
を去り、かん袋(※鶏の砂肝か?)
、糞袋(くそぶくろ:※鶏の大腸)
を去り、肝(きも:※鶏の肝臓)
、ひらきも(※鶏の平肝部分のこと)
等は肝要なる故(ゆえ)去らず。水三升入れ煎煮し、半(なか)ば煮、煮詰まりたる時、鰹節(かつおぶし)一本削りて、味淋三合入れ煮る事。暫時(ざんじ) にして、滓(かす)を麻(あさ)の袋にて絞りて、醤油五合を加え、再び煎し詰め、すべて一升ばかりにして、硝子瓶(がらすびん)の中に入れ、水に浸し置き、今日の食用の品を 、この汁にて加(くわ)い供(きょう)し、滋養(じよう)の大効(たいこう)これある事。
右を貯(たくわ)え置き、大根(だいこん)にても、牛蒡(ごぼう)にても、何(いずれ)にても煎る時しかるべき程、右ばかりを入れ、魚肉など煎るにも、右を用(もち)ゆ時は夜中暖めてよきなり。疝癪(せんしゃく:※胸や腹、腰などが急に差し込んで痛む病気。「さしこみ」とも)
持ちなどは、寒三十日、日々用(もち)いてよし。」
下巻180【味淋酒(みりんしゅ)の製法】・・・【注意喚起】この項目レシピも、「料理酒の一つ」として侮(あなど)って、再現(自家醸造)しようとしてはいけません!! 理由は、上記の上巻42【いり酒の方】をご覧頂ければ分かりますが、バッチリ「酒税法違反」となります。
「餅米一升、もみ(=揉み)
糀(こうじ)五合、焼酎(しょうちゅう)一升、(但し、餅米五合、糀〔こうじ〕
三合にてもよし。是〔これ〕
は松花酒〔しょうかしゅ:※松の花粉から造られた中国酒のこと〕
より甘みこれ無く出來る。) 右餅米をよくよく磨(と)ぎ、一夜水へ冷たし、蒸籠(せいろ)にてふかし(=蒸かし)
人肌にさまし(=冷まし)
、糀(こうじ)をもみ(=揉み)
交ぜ、焼酎(しょうちゅう)に入れ目張(めばり)をして置く。目張(めばり)はよくよくすべし。悪(あ)しき時は酒気ぬけて(=抜けて)
馬鹿(ばか)に成るなり。甘く出来候ても、早く悪(あ)しく相(あ)い成り、七日目毎にかき(=掻き)
回し(但し、五十日の間に二、三度かき〔=掻き〕
回してもよし。) 日数五十日(但し、冬は七十日ばかり。)にて出来申し候。餅米、糀(こうじ)の多き方甘み有るべし。(此処〔ここ〕
に図解あれども略す。)
右の通りにても宜しく候処、焼酎(しょうちゅう)多く米糀(こめこうじ)少々故(しょうしょうゆえ)、甘味薄く出来申し候。右を濾(こ)し笊(ざる)の如き物へ新しく麻布(あさぬの)を敷き候て、もろみ(=醪)
の儘(まま)入れ候えば、押し(=重し)
なで(=撫で)
仕(つかまつ)り候にも及ばず、直(ただ)ちに濾(こ)し、酒に相(あ)い成り申し候。余り絞り過ぎ候得ば、滓(かす)の味悪(あ)しく相(あ)い成り申し候。滓(かす)も目張(めばり)を致し置き候方宜しき。(但し、一度濾〔こ〕
し候て半日も置き候えば、澱〔おり〕
は下へ沈み候間、上澄〔うわず〕
みを取りて、貯〔たくわ〕
え置き沈澱をば当座に用〔もち〕
い候方宜しく候。)」
下巻181【天蓼(またたび)酒】・・・ここにある項目レシピは、いわゆる「薬用酒」となりますが、実際に使用する酒の種類やアルコール度数によっては、「酒税法違反」となる場合があるので注意しましょう!・・・この項目名にある「天蓼(またたび)」とは、マタタビ科の落葉性蔓(つる)植物で、山地に自生しているものです。その実は長楕円形で先が尖(とが)り、黄色に熟しますが、その実に付着した虫の影響で出来た、コブ付きの実を「木天蓼(もくてんりょう)」と呼び、これが滋養強壮に良いとされ、古くより生薬(しょうやく)として用いられてきました。また、猫が好む興奮効果を齎(もたら)す「マタタビラクトン」と云う成分を含有していることも知られているかな? と想います。
「木天蓼(もくてんりょう:※天蓼のコブ付きの実部分)
一斤、粗皮(あらかわ)を去り、細(こま)かに刻み、生糸(きいと)の袋に入れ、好酒(このみのさけ)三斗の中へ漬(つ)ける。春夏は一七日(ひとなのか:=七日間)
、秋冬は二七日(になのか:=十四日間)
、毎日昼と夜と燗(かん)をして、一盃ずつ飲む。風気(かぜけ:※風邪をひいている状態)
を治(ち)する事、立ちどころに(≒たちまち)
奇効(きこう)あり。老幼(ろうよう)は臨時加減す。常腹(じょうばら)には一度(≒妊娠していない女性には一度で良い)
。」
下巻182【木天蓼(もくてんりょう:※天蓼のコブ付きの実部分)
のひたし物】・・・この項目レシピには「木天蓼(もくてんりょう:※天蓼のコブ付きの実部分)」とありますが、以下原文を読むと、使用するのは「天蓼(またたび)の若葉部分」であります。・・・著者・徳川斉昭が「木天蓼」とした方が、薬効も期待できるし、且つ読み手に分かり易いのではないか? と考えたためだと想います。・・・いずれにしても、「天蓼(またたび)若葉部分のお浸し」です。
「木天蓼(=天蓼)
の若葉を煮て醤油をかけ(=掛け)
用(もち)ゆ。(み塩〔=塩昆布出汁〕
をかけて〔=掛けて〕
もよし。)又(また)細(こま)かに刻み、酒醸〔さけかも〕
して〔≒天蓼若葉のお浸しを酒の肴として〕
飲むもよし。癥結〔ちょうけつ:※腹の内部に出来たシコリのこと〕
、積聚〔しゃくじゅ:※お腹付近で起こる異状のこと〕
、虚冷の證〔きょれいのあかし:※衰弱して体が冷え易くなる兆候が現れて来た際のこと〕
に妙なり。」
下巻183【蛤(はまぐり)はんぺん】・・・「蛤(はまぐり)の摺(す)り身と大根(だいこん)を使った、はんぺん」です。
「蛤(はまぐり)のわた(=腸)
のかた(=堅:※堅い部分のこと)
を去り、堅き所(=蛤の身の堅い部分)
を細(こま)かに刻み、大根(だいこん)を摺子木(すりこぎ)にして(但し、大根の折り申さずくらい。) かき(=掻き)
回し、その後、銅摺鉢(どうすりばち)に入れ、摺子木(すりこぎ)にてよく摺(す)り、生塩を入れて、なおよく摺(す)り、その後湯煎(ゆせん)にするなり。」
下巻184【蚫(あわび:=鮑)
しんじょ】・・・「しんじょ」とは、日本料理の一つで・・・「真薯」や「糝薯」、「真蒸」、「真丈」、「新丈」といった漢字表記もあります。「海老(えび)」や、「蟹(かに)」、“魚の白身など”を摺り潰したものに、山芋や卵白、出汁などを加えて味を付けて、蒸したり、茹でたり、揚げたりして調理したものです。
「蚫(あわび:=鮑)
を大根おろしにておろし(=下ろし)
、銅摺鉢(どうすりばち)にてよく摺(す)り(但し、貝をはがし〔=剥がし〕
、身を取り、又〔また〕
上の平なる所の赤色を薄くへぎ〔=剥ぎ〕
取るなり。) 生塩(きじお)、玉子白身、酒、水にて然(しか)るべく延(の)べる。湯煮(ゆせん)をして葛(くず)かけにして(≒葛粉を利用したトロミのある調味液を掛けて)
用(もち)ゆ。」
下巻185【生海鼠(なまなまこ)の法】・・・以下原文を読むと、「生海鼠(なまなまこ)の保存方法」です。上記の 下巻157 にもありました。・・・江戸時代は、「生(なま)」であっても「干(ほし)」であっても、「海鼠(なまこ)」が広く利用される食材とされ、人々の重大関心事だったことが分かります。
「一、生海鼠(なまなまこ)は赤、青、黄あり。赤色のは肉厚き故(ゆえ)上品とす。次は黄、次は青なり。赤はわた(=腸)
に砂なし。黄は右に次ぎ、青は砂のなきは稀(まれ)なり。右生海鼠(なまなまこ)取りたて(=採りたて)
の品は、何(いず)れも堅く肉しまり(=締まり)
、日数を経(たち)たるは肉柔らかなり。(但し、塗物〔ぬりもの:※漆器のこと〕
へ入れる時は、新しき品も柔らかになるなり。陶物〔すえもの:※陶器のこと〕
へ入れ置く時は堅く成るなり。わら〔=藁〕
を入る時は、とける〔=溶ける〕
なり。わら〔=藁〕
は大禁物〔だいきんもつ〕
なり。)遠路(えんろ)へ遣(つかわ)すには、取りたて(=採りたて)
の堅き品へ、生柚(きゆず)の皮をむき(=剥き)
、一同に桶(おけ)へ入れ遣(つかわ)す時は、冬の日にて十日位は持つなり。柚(ゆず)は丸の儘(まま)入れても、二つ切位にしてもよし。生海鼠(なまなまこ)の多少により柚(ゆず)を入れるも多少あり。生海鼠(なまなまこ)は首尾(しゅび)を切りたち(=絶ち)、
割り小口(わりこぐち)より、よく切れる包丁を以(もっ)て、極(ご)く薄く皮をむき(=剥き)
捨てる時は、烏賊(いか)の如き真白(まっしろ)に成り、格別見た所もよく柔(やわ)らかに成りて、歯悪(あ)しき人にても喰(く)えるなり。細(こまか)に切り、みしほかけて(=塩昆布出汁を掛けて)
用(もち)ゆ。生姜(しょうが)おろしより、大根おろし(≒生姜よりも大根おろしが合う)
。わさび(=山葵)
おろしより、人参(にんじん)好み候者は、おろし人参(※いわゆる「紅葉おろし」のこと。大根と人参を摺り下ろしたものと唐辛子の粉末を混ぜたもの)
を用(もち)ゆるもよし(≒山葵よりも人参おろしを好む人は、紅葉おろしを用いるのも良い)
。(但し、細〔こま〕
かに切りたる生海鼠〔なまなまこ〕
を堅くするには塗重〔ぬりじゅう:※漆器の重箱のこと〕
へ入れ、生塩(きじお)少々入れて振る時は堅く成るなり。その時水にて洗う。但し、熟〔う〕
れたる品は堅く相〔あ〕
い成らず、なまこ〔=生海鼠〕
は、塗物〔ぬりもの〕
へ入れれば熟〔う〕
れ、陶器〔とうき〕
へ入れれば堅く成る所、切りたるは塗重箱〔ぬりじゅうばこ〕
へ塩と一同入れ振る時は堅くなるなり。)
又(また)法(≒また別の製法としては)
一、取りたて(=採りたて)
の生海鼠(なまなまこ)のわた(=腸)
へ醤油をたらして(=垂らして)
用(もち)ゆるもよし。干(ほし)たるは、藁灰(わらばい)あく水(=藁を燃やした後に残る灰と水とを混ぜたもの)
へ一夜漬(つけ)る時は柔(やわらか)になるなり。」
下巻186【かき(=牡蠣)
製(つくり:≒お造り)
】・・・ここにあるのは「生牡蠣(なまがき)の御造り」なのですが・・・昔の人は、現代人よりも胃腸が強かったのでしょうか? 食中毒の心配は無かったのでしょうか? ・・・とにかく、珍しい「生牡蠣(なまがき)」を使った一品です。
「取たて(=採りたて)
のかき(=牡蠣)
へ、みしほ(=塩昆布出汁)
かけ(=掛け)
、海苔(のり)をもみかけて(=揉み掛けて)
用(もち)ゆ。」
下巻187【甘酒(あまざけ)製法造方(せいほうつくりかた)】・・・これも・・・現在の「酒税法」により、酒類と定義されるのは「アルコール分1.0%(=アルコール度数にして1度)以上」の飲料と決められており、また一般の「甘酒」はアルコール分1%(=アルコール度数にして1度)以下であるため「清涼飲料水」と定義されます・・・が、この項目レシピを再現する場合には注意が必要です。くれぐれも、アルコール分1%(=アルコール度数にして1度)以下に抑えるようにして下さい。・・・と云いながら、人が予め計算してアルコール分1%(=アルコール度数にして1度)以下に抑えることができるのか? を問われると答えに詰まるのですが。作る季節や分量を間違えると、もはや「清涼飲料水」ではなく「お酒」になってしまいますので。この項目レシピも、“仮に知ったところで、むやみやたらに行なえない事柄”となりそうなのですが・・・著者・徳川斉昭としても、一般の個人に向けてと云うよりは、“この甘酒製法を広める意欲のある人々に向けた書きっぷり”になっております。
「餅米一升、糀(こうじ)三合、右二味まず糀(こうじ)を水にて洗い上げ、粉を去り、水気を滴(たら)し尽くし、餅米を常通の飯の如く炊(た)き、別器に移し冷(さま)して後、二味を器に納(い)れ混和し、甘味の中、少しく酸味生ずるを度とす(≒甘味の中に、少し酸味が生じる頃合いを限度とします)
。尤(もっと)も、朝、蒸餅(むしもち/じょうべい:※饅頭などの蒸した餠のこと=蒸し菓子の別称≒パン)
の母(もと)を製(せい)せんと欲(ほっ)するときは、前夕に甘酒を製(せい)するなり。冬日は早く製(つく)りし、火辺(かへん:≒火の側)
に置き少し暖気(だんき)を得るを好(よ)しとす。夏は二更頃に(にこうごろに:≒夜九時から十一時頃の間に)
製(せい)す、極暑(こくしょ)の節は昼後用(たも)ゆるを忌(い)む。(甘酒酸味過ぎればなり〔≒甘酒の酸味が生じてくれば既に成っている〕
。)故に昼後用(もちう)るには、早朝製(せい)し、太陽に照(てら)し、器物(うつわもの)熱するときには、昼後に至って漸(しばら)く適度の源醅(げんばい:※発酵する酵母菌のこと)
と成るなり。
初発(しょはつ/しょほつ:≒物事を起こす初めの段階で)
新たに製(つくる)時は、別に甘醅(かんばい:※甘酒の種となる酵母菌)
を求め(但し、饅頭屋〔まんじゅうや〕
にて求〔もと〕
むるなり。)、混(ま)ずる時は、上好の甘醅(かんばい:※甘酒の種となる酵母菌)
と成るなり。その後は少しずつ残し置き、これを源醅(げんばい:※発酵する酵母菌のこと)
とし次第(しだい)に加え用(もち)ゆべし。米一升に醅(ばい/もろみ)、およそ二合ほど納(い)れるなり。 」
下巻188【蒸餅(むしもち/じょうべい:=パン)
製法(せいほう)】・・・以下原文を読めば、「パン製法」で間違はいないと想うのですが・・・どこか中央アジア風、中東風に想えてならないのです。・・・「パンの発祥地」は、これらの地域と考えられるので、歴史に忠実と云えば忠実なのですが、日本列島に暮らす人に伝えたのは、何処の国の何人だったのでしょうか? 遠く昔の飛鳥時代にも、日本列島に渡来人達が来てはいるので・・・?・・・尚、ちょうど、この後の頃・・・明治初期には「あんぱん」が、世に現れて来ますので・・・?・・・長崎出島に出入りしていた中国清王朝時代の商人だったのか? オランダ人だったのか?
「小麦粉四百八十目、食塩三戔(せん)、甘酒(あまざけ)二合、冬日極寒(ごっかん)の節は二合五勺ばかり入れるなり。四季(しき)寒暖(かんだん)により少し斟酌(しんしゃく:=微調整)
すべし。右三味、水にて捏(こ)ね揉(こ)み軟(やわ)らかにして、稍(ようや)く丸(まるく)す可(べ)きに至るを、八箇(=八個)
に分(わか)ち(半斤パンの割合なり。)図の如く口径凡(およ)そ六寸、深さ凡(およ)そ三寸程の土鍋(どなべ)の裏面に、豚油(=豚脂=ラード)
若(もし)くは麻油(マァゆ:※胡麻油のこと)
を塗り、パンの地を納(い)れ、これを助暖(じょだん:※小さな火鉢のこと)
に納(い)れ莞莚(かんえん:※藺草〔いぐさ〕で編んだ莚のこと)
を覆い、又(ま)た蓋(ふた)を覆う。下火(したび)は極めて弱劣(じゃくれつ)にして熱灰中(≒熱き灰の中に)
、所々(ところどころ)細火(ほそび)ありて(≒ところどころに、か細い火が見えて)
、人膚(ひとはだ:=人肌)
の如き暖かさを以(もっ)て漸々(ぜんぜん:=徐々に)
あたたむる(≒温める)
時は、土鍋(どなべ)中のパン次第(しだい)に膨張(ぼうちょう)するに至(いた)りて、上面乾燥(かんそう)せざるが為(ため)に、二、三度指を以(もっ)て、少しく水を振り掛け、既に膨張すること十分なゐる時に当たりて、まず塗(ぬり)、釜中(かまのなか)におよそ二十斤より三十斤までの薪(まき)を焼き尽す時は炉中(いろりのなかの)石面(せきめんが)白色となるを度とし、図の如く藁(わら)を以(もっ)て作りたる長柄(ながえ)の箒(ほうき)を水に浸(ひた)し置き、これにて火を掻(か)き出し、中に埋め置くところの壺(つぼ)中に納(い)れ、滅(めっ:≒火を消)
し、残余(ざんよ)の細火(ほそび)を炉中(いろりのなか)の四方(しほう)に寄せ、箒(ほうき)にまた水を注ぎ、下面を掃(は)き、さて箸(はし)の大(おおき)さにして、まず少しく尖(とが)りたる木を水にて湿(しめら)し、パンの上面数ヶ所を突き、図の如き刺扠(ささ:※パンを釜に出入させるためのフォーク状の器具か?)
に土鍋(どなべ)の底をかけ(=掛け)
、爐中(いろりのなか:=炉中)
に納(い)れ、蓋(ふた)を覆い、少間にして視る時(≒少しの間をおいてから視る時に)
、パンを上面焦(こげ)黄色となるに及んで、初めの如く刺扠(ささ:※パンを釜に出入させるためのフォーク状の器具か?)
にて取出し、土鍋(どなべ)を反覆し(≒土鍋をひっくり返して)
、パンを土鍋(どなべ)より出し、前に上面なる所を下面となし(=為し)
、 杓子(しゃくし/しゃもじ)の如きものに乗せ(=載せ)
、また炉中(いろりのなか)に納(い)れ蓋(ふた)を覆い、半(なか)ば焼けるをうかがい(=窺い)
、杓子(しゃくし/しゃもじ)を以(もっ)て回し前面を後面となす(=為す)
。又(また)蓋(ふた)を覆い前面焦(こ)げ、黄色となるを度とし炉出す(≒黄色に色付く頃合いで以って炉〔いろり〕を出すのです)
。」
下巻189【ヒスコイト方】・・・上記の 中巻12 にも【かすてらほうろ】と云う似たようなものがありましたが、こちらは「直径三寸大のビスケットの作り方」になります。
「小麦粉、食塩少しばかり。右二薬(=前述の小麦粉と食塩を)
混和し、パン(≒上記にある 下巻188 のもの)
よりやや強く捏(こ)ね、長さ一尺五六寸ばかりの丸き木を以(もっ)て延べ、厚さ凡(およ)そ三歩、円径凡ひ(=おしなべて)
三寸程になし(=為し)
、銅の板にて造りたる円径一寸程の器(※銅製フライパンのこと)
にて、正中(せいちゅう:※小麦粉と食塩を捏ねたものの、ちょうど真ん中辺りのこと)
を押し切り、円孔(=円き穴)
を穿(うが)ち(≒小麦粉と食塩を捏ねたものを輪切りにした際に、蛇の目模様になるようにして)
、上面をパンの如く数ヶ所突き (焼け易〔やす〕
きが為〔ため〕
なり。)、火度(かど:※物を焼き上げる際の窯の温度のこと)
、パンに比(ひ)すれば少し劣(おと)れり。焦(こげ)黒(くろく)ならずして全面黄色なるを良(りょう)とする故(ゆえ)なり。(図解あれども略す。)」
下巻190【甘酒(あまざけ)造り方】・・・幾度も「甘酒の造り方」が出てまいります。・・・今度は、“元甘酒(もとあまざけ)なるものの重要性”を記述しているようであります。・・・試しに造る際には、くれぐれもアルコール度数にご注意願います。
「餅米一升、糀(こうじ)三合、
右二品の内、まず糀(こうじ)を水にて洗い上げ、粉を去り水気をしたみ(=湑み)
ぬき(=抜き)(≒米糀中の余分な粉末部分を取り除いてから、水気をよく抜いて)
、餅米を常の通りの飯の如く焚(た)き、別の入れ物へ移し、よく冷まして、後二味を桶へ入れ、よく交ぜ(=混ぜ)
合わせ、あまみ(=甘味)
の中、少し酸(す)き出(いず)るころ(=頃)
、蓋(ふた)をいたし、冬の日は朝早く仕込み、火辺(かへん:≒火の側)
に置き、少々あたためてよし(≒少々温めると良い)
。夏の日は夜五つ時(=夜七時から九時)
ころ(=頃)
造り込み、翌日昼前に用(もち)ゆべし。昼後になれば、酢味(すのあじ)出(いず)るなり。故(ゆえ)に昼後用(もち)ゆるには朝早く造り 、日の当たる所へ出し置き、入れ物あつく(=熱く)
なる頃、昼後になりて甘味出(いず)るなり。これを元甘酒(もとあまざけ)として宜(せん)し、初めて造るには別に甘酒を求むるがよし。(饅頭屋〔まんじゅうや〕
にて求むべし。)元甘酒(もとあまざけ)を入れて造れば、味わいよく出来るなり。餅米一升に付き元甘酒(もとあまざけ)二合程入れてよし、その後は少しずつ残し置き、順々に元甘酒(もとあまざけ)といたし造りてよし。」
下巻191【唐豆腐(からどうふ)製法】・・・「唐豆腐(からどうふ)」と名付けられてはいますが、何やら「灰」の香りを付着させた「燻製風味の豆腐」のようですね。・・・味付けなどは、どうやって食すのでしょうか? ・・・ゆはり、醤油を掛けて食すと乳製チーズのような味になるのでしょうか?
「常の豆腐一丁を紙二、三枚にてよく包み、灰へくるみ(=包み)
置き、それより紙を取り、湯にて煎じるなり。」
下巻192【寒元(かんもと)の方】・・・この項目レシピは、“「どぶろく」などの濁り酒の造り方 ⇒ 「清酒」の仕込み方まで”を記述したものであり、特に専門知識と専門技術を要しますし・・・【注意喚起】この項目レシピを再現(自家醸造)しようとしてはいけません!! また、「どぶろく」などの濁り酒までだったとしても、再現するのには「経済特区」などの指定や認可が無いと困難を極めますので。・・・なのに、さらに「清酒」までを、実験という目的であったとしても、絶対に造ろうとはしてはいけません!!!・・・完全に「酒税法違反」となります。・・・この項目レシピも、知識に留め置くだけにしましょう。
「一、極上白米一石、白米四斗、糀(こうじ)に寝(ねか)せ、(但し、十月より冬至位までを良き節とす。但し、大飯切〔おおはんぎり:※大きな寿司桶のこと〕
十枚へ仕込み置、つぶつぶ致し候。桶〔おけ〕
二本へ寄せ、これを元一組〔もとひとくみ〕
と云う。)右は白米よくよく洗い、二夜水へひたし(=浸し)
、ふかし(=蒸かし)
、 莚(むしろ)十枚へ取り、よくよく冷まし、糀(こうじ)四升ずつ割合、飯切(はんぎり:※寿司桶のこと)
一枚へ水一斗二升ずつよく合わせ、一夜置いて、翌日(図あれども略す。)此(これ)の如く山をあげ(=上げ)
一夜置く。右強飯(こわめし)等、どろどろとなるまでよくよく揉(も)み潰(つぶ)し置き、それより昼夜に五、六度ずつ、(図解あれども略す。)此(これ)の如くなる箆(へら)にて、掻(か)き回し、掻(か)き回し置き(十日或いは十七、八日位。)にて、箆(へら)当たり軽く成るなり。右に随(したが)い甘味出で候節、右の桶(おけ)二本へ寄せ、桶(おけ)を菰(こも:※水辺に生えるイネ科の多年性植物を乾かして、粗く編んだむしろのこと)
にて巻き、又(ま)た莚(むしろ)をかけ(=掛け)
念入りに包み置き、暖気(だんき)樽(たる)へ(図解あれども略す。)此(これ)の如き樽(たる)なり。煮え湯を入れ、一昼夜に一本ずつ入れ熱を出すなり。暖気(だんき)入れ候、最初はせわしく(=忙しく)
所々へ回し、段々(だんだん)に湯の冷めるに従い遠く回し、(但し、蓋〔ふた〕
をして上へ莚〔むしろ〕
等を置くなり。)一夜過ぎてまた樽(たる)の湯を替えるなり。右の如くいたし候事しばらく。尤(もっと)も湯気(ゆげ)随(したが)い四度、五度、六度位の内に大泡(おおあわ)出(いず)る。(これを蟹泡〔かにあわ〕
という〔=云う〕
なり。) わき(=沸き)
上り、又(また)さらさらいう音いたし、泡こまか(=細か)
に成りわき(=沸き)
沈み候を見てにがからみ(=苦辛味)
出(いず)る、しぶく(=渋く)
酢(すっぱ)き味出(いで)て、甘味少し有る頃をよしとし、暖気(だんき)を抜き、楫(かじ/かい:※舟の後ろに付けて、舟の方向を定める船具のこと)
を入れ、せわしく(=忙しく)
冷まし申し候なり。(図解あれども略す。) (但し、冷め次第にふた〔=蓋〕
成り候程、かわのはり〔※樽の上側に出来上がるもののこと〕
候を上元〔じょうもと〕
という〔=云う〕
。)
右造込み方(=前述されるものの造り込み方法は)
一、上白米一石二斗、(但し、是〔これ〕
を◇〈?原文一字不明部分とされるが、おそらくは「元」か?〉
米と申し候。)白米三斗六升、糀(こうじ)に寝(ねか)せて入(いれ)るべし。水九斗、或いは一石から一石二斗入れ(但し、水つまり〔=詰まり〕
候程に酒よろしく〔=宜しく〕
出来る。又〔ま〕
た水は霄日〔よいのひ:≒日暮れから夜中までの間に掛けて〕
汲〔く〕
み置き遣〔つか〕
うべし。)右を三尺七寸の桶、前日よりよく洗い清(きよ)め置き、莚(むしろ)にて包み、右の元半組(もとのはんくみ)水、右の割合にて舛目(ますめ)改め、糀(こうじ)を入れ白米よく砥(と)ぎ、二夜水にひたし(=浸し)
置き候をふかし(=蒸かし)
(尤〔もっと〕
もふかし〔=蒸かし〕
飯、手の平〔ひら〕
にてもみ〔=揉み〕
潰〔つぶ〕
し芯〔しん〕
のなき〔=無き〕
程にふかし〔=蒸かし〕
。)、莚(むしろ)十二枚位へ取り少し冷まし、右の元水(もとのみず)、糀(こうじ)よくよく櫂(かい:※水を掻いて舟を進める道具。棒の一端を幅広く平らに削ったもののこと)
にて合わせ、強飯(こわめし)あつき(=熱き)
を仕込み蓋(ふた)を締め、莚(むしろ)にて包み、一夜置いて蓋(ふた)を取り、さっと櫂(かい:※水を掻いて舟を進める道具。棒の一端を幅広く平らに削ったもののこと)
を入れ、又(ま)た白米二石、白米六升を糀(こうじ)に寝(ねか)せ、右同様にいたし仕込み候日より二夜過ぎて造り込み候なり。(但し、強飯〔こわめし〕
はよく冷まし造り込むべし。尤〔もっと〕
も暖寒見計口伝あり〔≒もっとも、暖かさと寒さを見計らうとの口伝がある〕
。)右の仕込み、一日過ぎて蓋(ふた)を取り櫂(かい:※水を掻いて舟を進める道具。棒の一端を幅広く平らに削ったもののこと)
を入れ、元の如くし蓋(ふた)を締め置き(但し、酒のわき方〔=沸き方〕
悪〔あし〕
き時は莚菰〔むしろ、こも〕
をかけ〔=掛け〕
暖〔あたた〕
め申し候。)、五日目位にて蓋(ふた)を取りもろみ(=醪)
沈み候て、沸(わ)き止み候櫂(かい:※水を掻いて舟を進める道具。棒の一端を幅広く平らに削ったもののこと)
を入れ、折々(おりおり)さます(=冷ます)
なり。その後木綿袋へ入れ、舟にかけ(=掛け)
、桶へあけ(=開け)
置き、澱(おり)を引き清酒にいたすなり。」
下巻193【寒鶏卵酒(かんどりたまござけ)の法】・・・ここも要注意項目です。上記の 下巻81 にも【玉子酒(たまござけ)下戸口(げこのくち)】がありました・・・が、こちらのものは、著者・徳川斉昭も、「下戸口(げこのくち)」とも云っておりませんので。・・・アルコール度数によっては、「薬用酒」であったとしても「アウト」となります。
「冬至の日、卵鶏(らんけい:=鶏卵)
十五、酒一升、白砂糖一斤、右摺鉢(すりばち)にてよく摺(す)り徳利(とっくり)へ入れ、口をよく封じ、土中へ埋め置き、(但し、一切雨水入らざるよう摺鉢〔すりばち〕
様のものかぶせ〔=被せ〕
埋めるなり。)入寒の日(※冬至から15日が入寒の日。「寒の入り」とも)
に取り出し、寒三十日用(もち)ゆ。(大方〔おおかた〕
一日に三勺位ずつの割、毎夜呑〔の〕
む〔=飲む〕
べし。)右気根(きこん:※一つの物事にじっと耐える精神力のことで、根気や気力とも)
の薬、疝癪(せんしゃく:※胸や腹、腰などが急に差し込んで痛む病気。「さしこみ」とも)
の薬、しびれ(=痺れ)
の薬等に成るなり。」
下巻194【鮒(ふな)製法】・・・この項目レシピは、以下原文を読むと・・・著者・徳川斉昭が実際に料理したと云うよりは、明らかに人から伝えられたものを、纏(まと)めて記述しております。・・・尚、この「鮒料理」が、現茨城県霞ケ浦地域の郷土料理に類似しているとの指摘もありますので・・・土浦藩土屋家など水戸藩の隣接藩からの情報提供があったのかも知れません。・・・いずれにしても、“淡水魚・鮒(ふな)を様々工夫して食している”との紹介記事になります。
「遠火(とおび)にてあぶり(=炙り)
、水の出(い)でざる位にまでにあぶり(=炙り)
、煮浸(にびたし)にいたし候事に御座候。煮法は大根(だいこん)の輪切りを下へ敷き、その上へ鮒(ふな)を乗せ(=載せ)
、煮浸(にびたし)候わばよく煮え候程宜しき事。半日或いは一日大根(だいこん)煮え過ぎ候を厭(いと)わず候得ば(≒半日あるいは一日も煮ると、大根が煮崩れしてしまうので)
、二時(ふたとき)間程(≒約四時間程)
一旦冷(ひや)し大根(だいこん)を取り替え、右の鮒(ふな)を又(ま)た再び入れ替え煮え候事。前の如く開(ひら)き候て串(くし)にさし(=刺し)
、照焼(てりやき)、又(ま)た塩焼(しおやき)にいたし候事も御座候。(但し、なます〔=膾〕
、ぬた〔=饅=饅膾:※一般的には酢と味噌の合わせ調味料で和えた料理のこと〕
等に製〔つく〕
りし候事も候。)」
以上で、著者・徳川斉昭が遺した『食菜録』は全300項目で終わっております。・・・と云うか、徳川斉昭の「水戸永蟄居」と「死去」が無ければ、おそらくは・・・“もっと項目レシピが増えたり、加筆など修正が加えられていたのだろう”・・・とも想います。
この『食菜録』からも分かるように・・・探求心が強く、またグルメであった父・斉昭が、徳川御三卿・一橋家へ養子へ出すこととなる徳川慶喜に送った書状は、数多く遺されていて・・・『父より慶喜殿へ---水戸斉昭一橋徳川慶喜宛書簡集』大庭邦彦編には・・・
「黒豆(くろまめ)は日に二百粒づつ召し上がり、牛乳も上がり申し候良し。」・・・と。
・・・牛乳はともかく、黒豆(くろまめ)を一日に二百粒という相当な量を云われていると想うのですが、息子・慶喜はこの薦めを実践していたのでしょうか?
・・・この他にも、父・斉昭は息子・慶喜へ、彼の故郷とも云える水戸藩や近郊の特産品をまめまめしく送っており、「鱒(ます)」、「海老(えび)」、「鯛(たい)」、「鮟鱇(あんこう)」、「鮒(ふな)」・・・。そしてやはり、その食べ方まで書状に細かく記しており・・・
「鯛は三、四分ぐらひの厚さに御切らせ、焼き立てのあつきところ、御風味成さるべく候。」とか、「このかまぼこ、微小ながら御好み故。」・・・などと。
これらの書状の内容からすれば、息子・慶喜は「かまぼこ(=蒲鉾)」も好きで、それを父・斉昭も分かっており・・・父子ともに、「食通・グルメ」であり・・・「食」や「人の健康」に対する探求心は、思想哲学的な「水戸学」から大きな影響を受けていたことも分かります。
尚、江戸時代は表向き・・・まだ仏教的な戒律規範に準じるべきとする考えが主流だったため、牛や豚など獣肉類を食すこと自体が敬遠、若しくは禁止する社会通念が存在していたとのこと。上記の『食菜録』の中にある「鳥類の肉」は「獣肉」に該当しないので「セーフ」と云えますが、この忌避通念からすれば「豚の油(=豚脂=ラード)」などを使用した食品を口に入れること自体、世の中的には敬遠されていたとは想います。
しかし、討幕(倒幕)運動が本格化する、しばらく前の時期・・・近江彦根藩主に井伊直弼が就く以前の頃までは、彦根藩だけは牛肉生産が許可され、この「近江牛の味噌漬け」が水戸徳川家(水戸藩)などの諸藩への「贈答品」となっていたのです。この「近江牛の味噌漬け」を食した水戸藩主であった父・徳川斉昭は、「稀代の肉好き人間」として知られるようになりました・・・が、この後彦根藩藩主となった井伊直弼が、仏教の教えに傾倒して、それまでの慣習を改め「獣肉類を食すことを国禁」として・・・贈答品の一つ「近江牛の味噌漬け」を諸藩へ贈らなくなったのでした。
・・・そんなこんながあって、世の中が変化を見せても・・・肉好きの傾向は、水戸徳川家で養育された息子の慶喜に遺伝? 継承されており・・・
江戸幕府(徳川幕府)の15代将軍職に就いた頃の徳川慶喜は、まだ討幕(倒幕)運動が本格化する以前の話となりますが・・・薩摩藩家老・小松清廉(こまつきよかど:※通称は帯刀〔たてわき〕)に、“黒豚の肉を送るよう度々要求した”というエピソードもあり・・・
また、「豚一(ぶたいち)様」という通称で以って幕臣達から呼ばれるほど、“豚肉を好んだ”ようであります。・・・「豚一(ぶたいち)」の中の「一(いち)」は、慶喜が徳川御三卿・一橋家の出身者だったからであり・・・つまりは「豚肉がお好きな一橋様」という訳です。
残念ながら・・・「豚一(ぶたいち)様」こと徳川慶喜が、どんな料理法で献上された豚肉を食べたのか? については不明なのですが、上記の『食菜録』を観れば・・・「焼く(炒る)」、「煮る」、「蒸す」のいずれか? 若しくは、これらの組み合わせ料理だったのではないか? とは想います。
将軍職に就いた後の徳川慶喜は、西洋各国の公使達と「洋食」や「コーヒー」をともにしており・・・また、「豚肉」のほかにも「羊肉」を食した可能性も高いとのこと。徳川慶喜の曾孫に当たる徳川慶朝氏の著書『徳川慶喜家の食卓』には・・・“イギリス公使から慶喜宛に、羊の脛肉(すねにく)とハムが献上された”という記録があったとのこと。
将軍職を退いて明治期を迎えた徳川慶喜の好物の一つに、「べったら漬」があったと云います。・・・「べったら漬」とは、塩で下漬けした大根を米麹(こめこうじ)と砂糖で漬けこんだ漬物であり、江戸時代のえびす講(※年中行事として「えびす様」を祀る庶民信仰のこと)で売られていた「大根の浅漬け」が、「べったら漬け」の発祥とされますが・・・実父・徳川斉昭の『食菜録』の中の、 下巻24【淺漬(あさづけ)の方】や、下巻25【又(また)、あさ漬の方】、下巻66【ほう漬】にあるものと、ほぼ同じものだったか? とも想います。・・・いずれにしても、大根を甘口の粕漬けにした、この庶民的な食べ物を、“たっぷり厚めに切って食べるのが慶喜の好みだった”とか。
徳川慶喜の曾孫に当たる徳川慶朝氏は、その著書『徳川慶喜家の食卓』の中で・・・「ハマヤのふき豆」や「木村屋のあんぱん」も好きだったとしています。・・・残念ながら、「富貴豆(ふきまめ:※そら豆を清酒や醤油、味醂、砂糖で炊いたもの)」を製造販売されていた東京都中央区日本橋人形町の老舗「ハマヤ」さんは、近年閉店されたとのことです・・・が、本ページにあるように、“旧幕臣・山岡高歩(※通称は鐵太郎、号は一楽斎、居士号は鉄舟、一刀正伝無刀流の開祖となる人物で禅や書の達人)も毎日のように食べた”と云われ、また「明治天皇」など皇室の方々に献上された「木村屋の(酒種)あんぱん」は健在であります。
明治時代の徳川慶喜は、隠居暮らし中や名誉回復した後も、様々な趣味に取り組んでいますが・・・その大元にある考えには、自らの健康を維持する「食」を基本原則とするという水戸徳川家の家訓や、実父・徳川斉昭、「水戸学」の思想哲学による影響が大きかったのではないか? と想います。
本ページにもあるように、「写真」や「絵画」、「書道」、「工芸」、「乗馬」、「サイクリング」、「旅行」、「狩猟」、「将棋」はもちろん「囲碁」など数えきれない程の趣味を持つ徳川慶喜は、「豚一(ぶたいち)様」という通称で語られるように、“とことん極める”との性格的な傾向が強く、かなりの凝り性だったとも云えるかと。
そんな凝り性人・徳川慶喜らしい逸話も残っております。
・・・ある日、砲兵工廠(工場)を見学中、飯盒(はんごう)を目にして、たまらなく欲しくなった徳川慶喜公。其処で目出度く飯盒(はんごう)一つを貰い受け・・・早速、帰宅してから試しに、米を炊いたところ、その炊き上がった状態を観て、とても気に入ったという。
・・・ところが、この飯盒(はんごう)がアルミニウム製だったことが気にいらない慶喜公。・・・アルミニウムの成分が、炊きあがった、ご飯に染み出て、身体に悪いのではないか? と心配し・・・
・・・砲兵工廠(工場)へ、「銀を送るから、その銀で飯盒(はんごう)を作ってくれ」と依頼します。・・・伝統的な西洋銀食器への拘(こだわ)りがあったのか? 新素材のアルミニウムに抵抗感があったのか? ・・・いずれにしても、銀製の飯盒(はんごう)を入手した慶喜公は、“生涯その飯盒(はんごう)で毎食のご飯を炊いて貰っていた”と云います。
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その壱へ 【はじめに:人類の起源と進化 & 旧石器時代から縄文時代へ・日本列島内の様相】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その弐へ 【縄文時代~弥生時代中期の後半頃:日本列島内の渡来系の人々・農耕・金属・言語・古代人の身体的特徴・文字としての漢字の歴史や倭、倭人など】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その参へ 【古墳時代~飛鳥時代:倭国(ヤマト王権)と倭の五王時代・東アジア情勢・鉄生産・乙巳の変】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その四へ 【飛鳥時代:7世紀初頭頃~653年内まで・東アジア情勢】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その伍へ 【飛鳥時代:大化の改新以後:659年内まで・東アジア情勢】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その六へ 【飛鳥時代:白村江の戦い直前まで・東アジア情勢】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その七へ 【飛鳥時代:白村江の戦い・東アジア情勢】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その八へ 【飛鳥時代:白村江の戦い以後・東アジア情勢】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その九へ 【飛鳥時代:天智天皇即位~670年内まで・東アジア情勢】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その壱拾へ 【飛鳥時代:天智天皇期と壬申の乱まで・東アジア情勢】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その壱拾壱へ 【飛鳥時代:壬申の乱と、天武天皇期及び持統天皇期頃・東アジア情勢・日本の国号など】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その壱拾弐へ 【奈良時代編纂の『常陸風土記』関連・其の一】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その壱拾参へ 【奈良時代編纂の『常陸風土記』関連・其の二】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その壱拾四へ 【《第一部》茨城のプロフィール & 《第二部》茨城の歴史を中心に・旧石器時代~中世頃】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その壱拾伍へ 【中世:室町時代1435年(永享7年)6月下旬頃の家紋(=幕紋)などについて、『長倉追罰記』を読み解く・其の一】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その壱拾六へ 【概ねの部分については、『長倉追罰記』を読み解く・其の二 & 《第二部》茨城の歴史を中心に・中世頃】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その壱拾七へ 【《第二部》茨城の歴史を中心に・近世Ⅰ・関ヶ原合戦の直前頃まで】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その壱拾八へ 【近世Ⅱ・西笑承兌による詰問状・直江状・佐竹義宣による軍法十一箇条・会津征伐(=上杉討伐)・内府ちかひ(=違い)の条々・関ヶ原合戦の直前期】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その壱拾九へ 【近世Ⅱ・小山評定・西軍方(≒石田方)による備えの人数書・関ヶ原合戦の諸戦・関ヶ原合戦の本戦直前期】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その弐拾へ 【近世Ⅱ・関ヶ原合戦の諸戦・関ヶ原合戦の本戦・関ヶ原合戦後の論功行賞・諸大名と佐竹家の処遇問題・佐竹家への出羽転封決定通知及び佐竹義宣からの指令内容】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その弐拾壱へ 【近世Ⅱ・出羽転封時の世相・定書三カ条・水戸城奪還計画・領地判物・久保田藩の家系調査と藩を支えた収入源・転封決定が遅れた理由・佐竹家に関係する人々・大名配置施策と飛び領地など】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その弐拾弐へ 【近世Ⅲ・幕末期の混乱・水戸学・日本の国防問題・将軍継嗣問題・ペリー提督来航や日本の開国及び通商問題・将軍継嗣問題の決着と戊午の密勅問題・安政の大獄・水戸藩士民らによる小金屯集】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その弐拾参へ 【近世Ⅲ・安政の大獄・水戸藩士民らによる第二次小金屯集・水戸藩士民らによる長岡屯集・桜田門外の変・桜田門外の変の関与者及び事変に関連して亡くなった人達】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その弐拾四へ 【近世Ⅲ・丙辰丸の盟約・徳川斉昭(烈公)の急逝・露国軍艦の対馬占領事件・異国人襲撃事件と第1次東禅寺事件の詳細・坂下門外の変・元治甲子の乱(天狗党の乱、筑波山挙兵事件とも)の勃発】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その弐拾伍へ 【近世Ⅲ・1864年(元治元年)4月から同年6月内までの約3カ月間・水戸藩(水戸徳川家)や元治甲子の乱(天狗党の乱、筑波山挙兵事件とも)を中心に】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その弐拾六へ 【近世Ⅲ・1864年(元治元年)7月から同年8月内までの約2カ月間・水戸藩(水戸徳川家)や元治甲子の乱(天狗党の乱、筑波山挙兵事件とも)を中心に】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その弐拾七へ 【近世Ⅲ・1864年(元治元年)9月から同年10月内までの約2カ月間・水戸藩(水戸徳川家)や元治甲子の乱(天狗党の乱、筑波山挙兵事件とも)を中心に】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その弐拾八へ 【近世Ⅲ・1864年(元治元年)11月から同年12月内までの約2カ月間・水戸藩(水戸徳川家)や元治甲子の乱(天狗党の乱、筑波山挙兵事件とも)を中心に】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その弐拾九へ 【近世Ⅲ・1865年(元治2年)1月から同1865年(慶應元年)11月内までの約1年間・水戸藩(水戸徳川家)を中心に・元治甲子の乱(天狗党の乱、筑波山挙兵事件とも)の終結と戦後処理・慶應への改元・英仏蘭米四カ国による兵庫開港要求事件(四カ国艦隊摂海侵入事件とも)・幕府による(第2次)長州征討命令】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その参拾へ 【近世Ⅲ・1865年(慶應元年)12月から翌年12月内まで・元治甲子の乱の終結と戦後処理・水戸藩の動向・第2次長州征討の行方・徳川慶喜の将軍宣下・孝明天皇の崩御・世直し一揆の発生】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その参拾壱へ 【近世Ⅲ・1867年(慶應3年)1月から12月内までの約1年間・パリ万博と遣欧使節団・明治天皇即位・長州征討軍の解兵・水戸藩の動向・大政奉還・王政復古の大号令・新政体側と旧幕府】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その参拾弐へ 【近代・1868年(慶應4年)1月から同年4月内までの約4カ月間・討薩表・鳥羽伏見の戦い・征討大号令・神戸事件・錦旗紛失事件・五箇条の御誓文・江戸無血開城・除奸反正と水戸藩の動向】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その参拾参へ 【近代・1868年(慶應4年)閏4月から同年7月内までの約4カ月間・戊辰戦争・白石列藩会議・白河口の戦い・鯨波合戦・北越戦争・上野戦争・越後長岡藩庁攻防戦・除奸反正と水戸藩の動向】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その参拾四へ 【近代・1868年(慶應4年)8月から同年(明治元年)内までの約5カ月間・明治帝即位の礼・会津戦争の終結・水戸藩の動向・弘道館の戦い・松山戦争・東京奠都・徳川昭武帰朝と水戸藩の襲封】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その参拾伍へ 【[小まとめ]水戸学と水戸藩内抗争の結末・小野崎〈彦三郎〉昭通宛伊達政宗書状・『額田城陥没之記』・『根本文書』*近代・西暦1869年(明治2年)2月から概ね同年5月内までの約4カ月間・水戸諸生党勢の最期・生き残った水戸諸生党勢や諸生派と呼ばれた人々・徳川昭武の箱館出兵・「箱館戦争」と「戊辰戦争」の終結・旧幕府軍を率いた幹部達のその後】
ある不動産業者の地名由来雑学研究~その参拾七へ 【近代・1876年(明治9年)2月から1893年(明治26年)内までの約17年間・水戸徳川家の欧州留学・宝刀「児手柏包永」とその関係者達・[総まとめ]「水戸学」とは、いったい何だったのか? 水戸学の一端・徳川斉昭の正室「吉子女王」とは】

